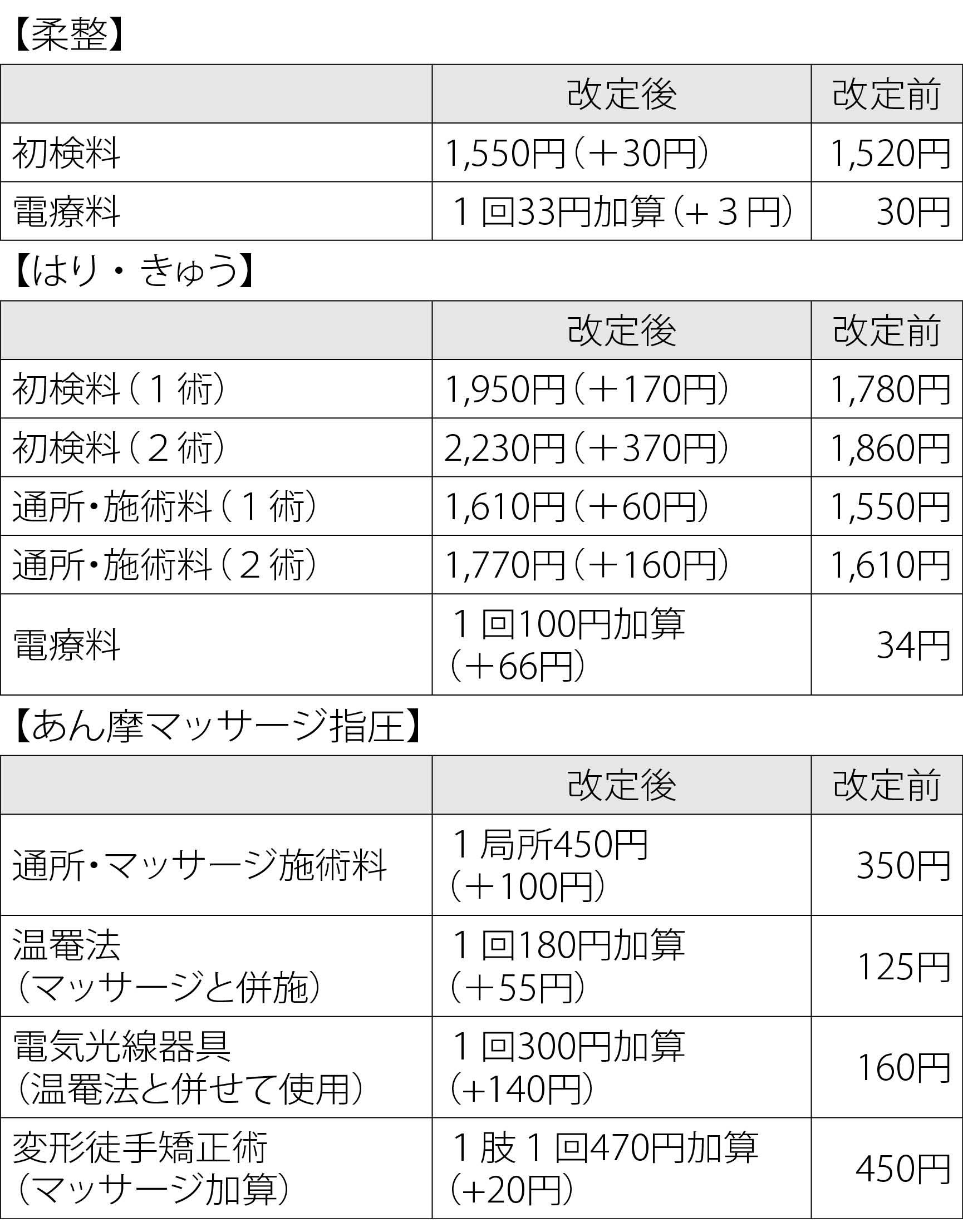日整と全整協が初となる会合開く
2024.07.10
「柔整業界がまとまる」機運高まる
6月19日、日本柔道整復師会(日整)と全国柔道整復師統合協議会(全整協)が都内で会合を開いたことが分かった。当日は、それぞれの役員・幹部らが集まり、意見交換を行ったようだ。両会とも柔整療養費検討専門委員会に委員を輩出し、一定数の会員を有する業界を代表する団体同士の初となる話し合いということで、大きな転換点と言ってもいい。業界全体の協調、団結に向けた端緒を開く動きとしても注目だ。
これまで日整とその他の個人柔整師団体では、「協定」と「契約」といった属性上の違いから考え方に隔たりがみられていたが、今後、柔整療養費で導入が予定されているオンライン請求において、復委任の問題を中心に団体の垣根を超えた形で対処せざるを得ない状況となることも予想され、今回の会合を開くに至ったという。
(さらに…)