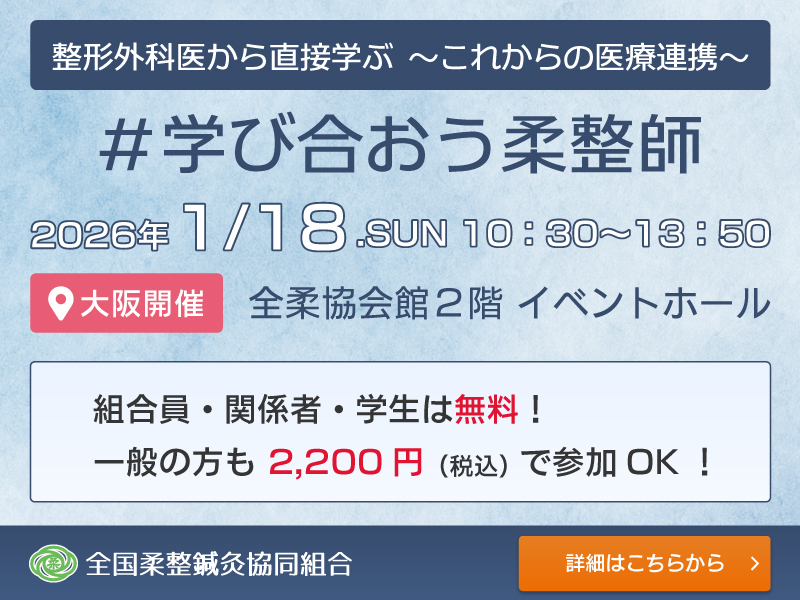『医療は国民のために』250 ついに「保発32号」が廃止されるが、はたして鍼灸療養費は救われる?
2018.06.25
あはき療養費の平成30年度料金改定について、5月24日付の厚労省通知でその内容が示された。施術料金が引き上げられたことで、業界全体が喜んでいる向きもあろうが、私が注目したのは全く別のところだ。それは、この通知文中の「なお書き」部分である。以下、その内容だ。
「なお、『はり、きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて』(昭和42年9月18日付保発第32号)は、平成30年10月1日をもって廃止する」
現在まで鍼灸療養費は、同意書の義務付けや医科との併給・併用を認めない等、手かせ足かせの多くの条件で縛られている。その療養費支給申請の提出がしづらい諸悪の根源の一つが「保発第32号局長通知」である。この32号通知には、「鍼灸療養費の支給対象となる疾病は医師による適当な治療手段のないもの」との記載があり、医科の「療養の給付」が行われたなら療養費は請求できないとする「医科との併給・併用の禁止」の根拠とされてきた。また、保険者が同意医師に照会する際、「医師による適当な治療手段がなかったのでしょうか?」などとふざけた質問をさせる元凶にもなっている。その32号通知が、今回の通知で廃止されることとなったのだ。保険を取り扱う鍼灸師にとっては長年の願いであり、大変喜ばしいことである。
ただ、この32号通知が論拠となっている「医科との併給・併用の禁止」も併せて10月1日より廃止されなければ、32号廃止との整合性が取れない。この点は非常に気になる。また、なぜ32号廃止が、料金改定に合わせた6月1日ではなく、10月1日であるのだろうか。まさか、これから9月までに32号通知に代わるような新たな通知が発出されるのか? 再び、療養費の支給対象に「枠」をはめるような愚策を繰り返すのではないかと心配になる。
私の経験上、行政では、今後影響の生じる通知を先に廃止した上、該当箇所のみを修正し、残りはそのままの記載で「復活」させるというケースが往々にして見受けられる。このケースに当てはめれば、同意書の添付を要しない「再同意」において、今後は全てに同意書の添付を求める運用変更を予定していることから、32号通知内の再同意に係る記載である「第2回目以降その添付を省略して差し支えないものとすること」を変える必要性が出てきた。つまり、そのためだけに32号通知を廃止するのであって、今後発出される新通知の中には「鍼灸療養費の支給対象となる疾病は医師による適当な治療手段のないもの」の文言が再び復活してくるのではないだろうか。
私はたぶんそうなるのではないかと危惧している。業界の交渉担当者は、医科との併給・併用の禁止も併せて廃止されなければ、鍼灸療養費は救われないと理解すべきだ。
【連載執筆者】
上田孝之(うえだ・たかゆき)
全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長
柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。