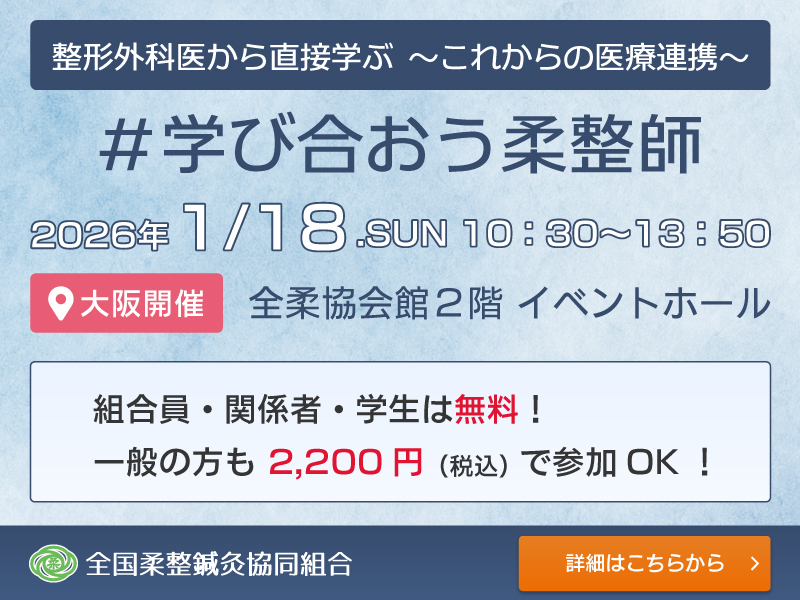連載『未来の鍼灸師のために今やるべきこと』19 地方創生としての養生場構想~雇用と社会復帰~
2018.08.10
「養生場構想」の仕組みについてもう少し詳しく解説したいと思います。
我々が実施している養生場では、守るべきいくつかの決まり事があります。その一つが、「地域の人々を活用する」ということです。
治療やそこから派生したセルフケアには、とかく医療的な要素が含まれています。そのため、セルフケアを学習する場合、医療関係者が中心となって企画しがちです。しかし、養生は一般の人々が日々行う健康法であることから、専門的な視点だけでなく、一般の人たちの視点が必要不可欠です。実際、スタンフォード大学で行われた研究では、「専門家の指導は知識の幅を広げるが、モチベーションが続かない。しかし、同じ境遇の参加者(一般の参加者)がいれば、参加者のモチベーションを高めることができる」と結論付けられています。地域住民にその地の季節ごとの生活習慣や伝統習慣を教えてもらうことによって、参加者は実体験をすることができ、その上で専門家が意味付けを行い、体験を習慣に変えるという取り組みをしています。
地域の人を参加させる意味は、それだけではありません。一つは「養生場」を単なる健康教室としてではなく、地域の人々の健康維持のために必要不可欠な財産として捉えてほしいという視点です。地域の人たちにとっては何でもない生活習慣や伝統習慣に着目し、それに意味付けをすることで自分たちの地域や生活に誇りを持ってもらい、その知的・人的財産を地域のブランドとして育てていく。地域の財産で地方創生するという狙いがあります。
さらに、今まで経験してきた何気ないことが人の健康の役に立ち、その知識が周りの人たちのためになるという経験は、その人が健康でいなければならない原動力となり、健康の連鎖を作り上げます。言い換えれば、自分の経験を知的財産にすることで、自分の人生を肯定的に捉えることができるのです。そして、教えるという行為には少なからず講師料が発生することから、住民の雇用にもつながります。その意味で、地域の人的資源を活用した養生場は、地域の雇用対策にもなるのです。さらには、養生場では病気を克服した人を積極的に活用しています。病気を克服した経験を話すことで人の役に立つという経験を通じて、ネガティブだった病気体験に新たな意味を付け加えられる可能性があります。病気を克服した人は必ずと言っていいほど、病気体験に自分なりの意味付けをしています。養生場がそんな意味付けの場になれば、病気の人たちの社会復帰の場、生きがいの場として役立つことになるのです。
「養生場構想」は、健康を伝えるだけでなく、地域になくてはならない存在となり、地域の人々に生きがいを与えていく、そんな狙いを見据えた構想なのです。
【連載執筆者】
伊藤和憲(いとう・かずのり)
明治国際医療大学鍼灸学部長
鍼灸師
2002年に明治鍼灸大学大学院博士課程を修了後、同大学鍼灸学部で准教授などのほか、大阪大学医学部生体機能補完医学講座特任助手、University of Toronto,Research Fellowを経て現職。専門領域は筋骨格系の痛みに対する鍼灸治療で、「痛みの専門家」として知られ、多くの論文を発表する一方、近年は予防中心の新たな医療体系の構築を目指し活動を続けている。