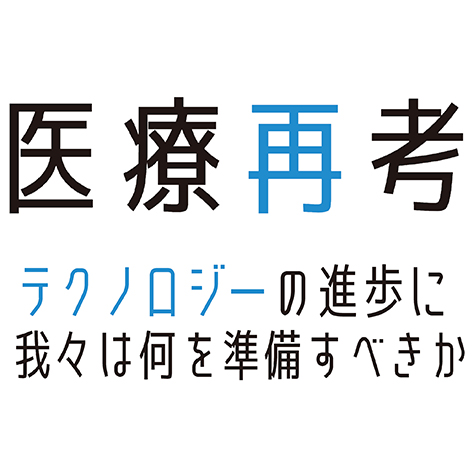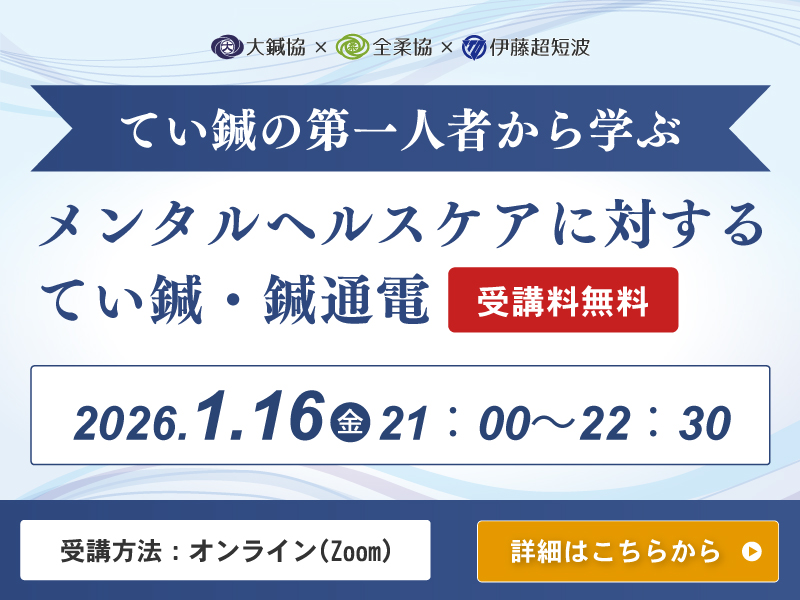Q&A『上田がお答えいたします』 柔整の受領委任は健保組合の判断で契約解除できるの?
2020.07.22
Q.
健保組合が柔整療養費の受領委任取扱いを廃止して償還払いに移行するとの話が出ているそうですが、各都道府県社団の会長との三者協定で成り立っている「協定」があるかぎり、その他の施術者団体との「契約」も、保険者の独自判断で解除できるようには思えませんが……。
A.
健保組合の受領委任に当たっての委任行為の規程を見ると、協定は「本協定の締結を行うに当たっては、甲(地方厚生<支>局長)は健康保険組合連合会会長から受領委任の契約に係る委任を受けること」、個人契約は「本規程に基づく契約の締結を行うに当たっては、地方厚生(支)局長は、健康保険組合連合会会長から受領委任の契約に係る委任を受けること」とあります。 (さらに…)