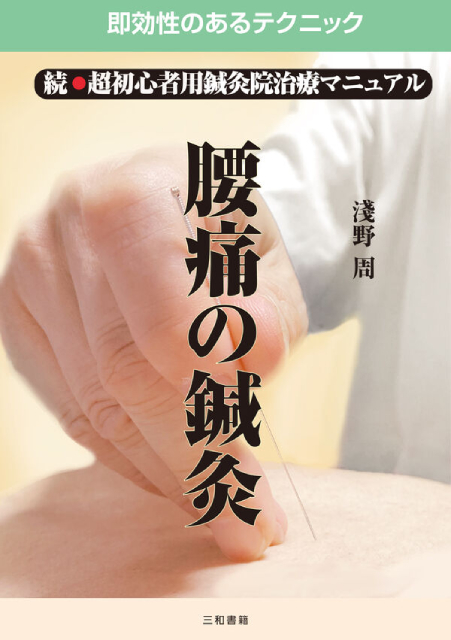連載『食養生の物語』87 免疫力を育ててみる
2020.08.25
「免疫力を上げるために何を食べればいいですか」――新型コロナウイルス感染症の広がりとともに、こう尋ねられる機会が増えました。しかし、これさえ食べておけば大丈夫という決め手となるような食物などありません。そんな魔法のような食物があれば、皆がそれを食べて元気になり、とっくの昔に病気はなくなっているはずですね。
古代ギリシャの医聖ヒポクラテスの残した言葉に「身体にとって良いことをするか、できなければ少なくとも悪いことをするな」とあります。あれこれやり過ぎ、食べ過ぎの現代人は、むしろ何も食べずに断食するほうが手っ取り早く免疫力が上がるかもしれません。まず過食を止めること。胃腸の疲れは自然治癒力を弱める原因の一つです。
その上で強いて言うのなら、大根を上手に摂り入れてみてはいかがでしょうか。 (さらに…)