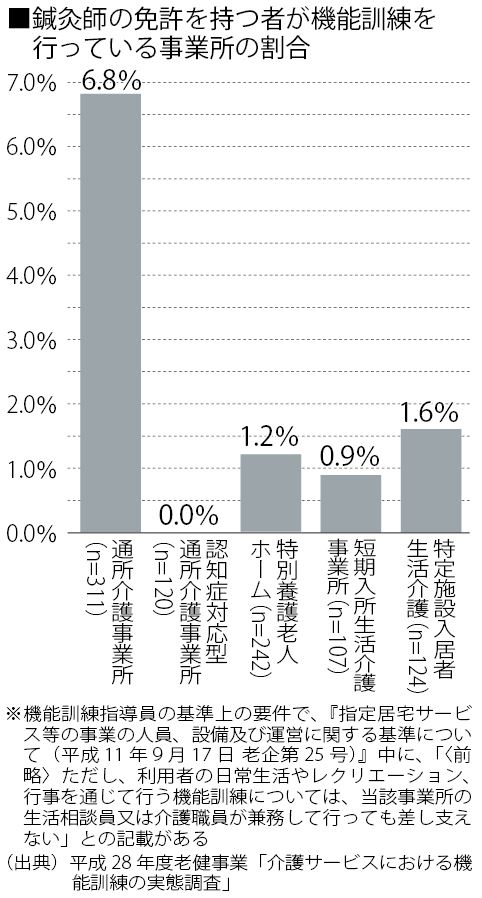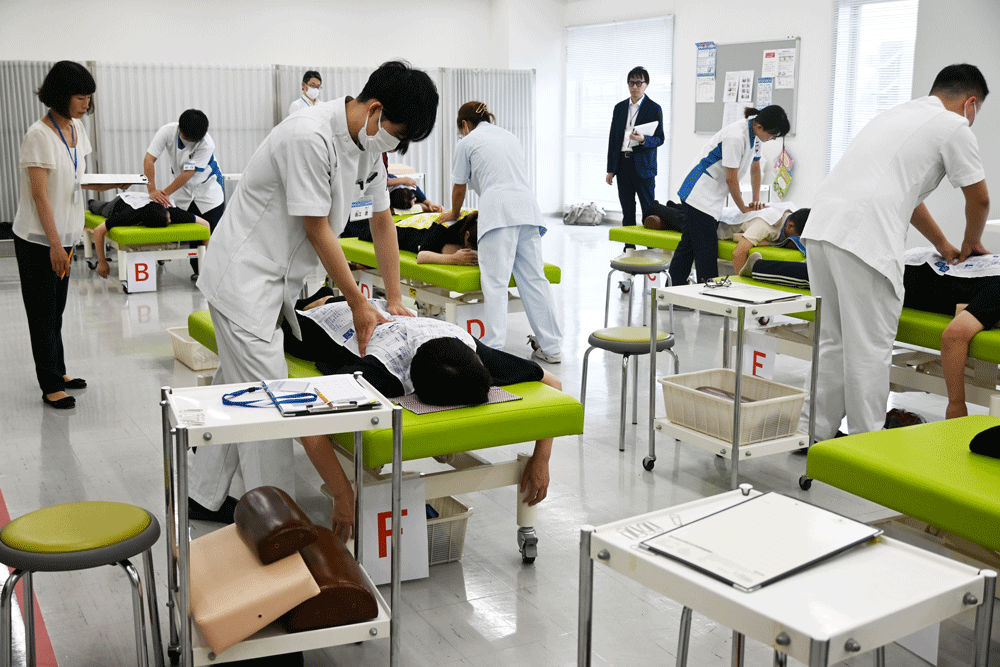連載『食養生の物語』55 ハクサイで芯から温まる
2017.12.25
鍋物の美味しい季節です。鍋物といえばハクサイですね。ハクサイは英語ではChinese Cabbage(中国のキャベツ)と呼ばれています。「西洋のキャベツ、東洋のハクサイ」と並び称されることもあり、使い道が幅広く栄養も豊富な野菜です。
ハクサイは、実は元々野生植物ではありません。カブと漬け菜(つけな:しろな・チンゲン菜のような葉物)類が自然交雑して生まれたもので、栽培種としてのハクサイの原形は中国北部で生まれたものだと推定されています。日本に入ってきたのは明治時代になってからで、広く普及したのは大正時代と言われています。成長するにつれて根に近い白い部分が太く伸びていくことから、「白菜」と呼ばれるようになったとか。朝鮮半島にハクサイが持ち込まれたのもこの頃で、それから栽培法が確立され、朝鮮総督府によって朝鮮半島全土に普及し、白菜キムチの誕生につながったようです。
旬は、11月下旬から2月ごろにかけて。葉の周囲がちりめん状に縮れて互いに抱き合うように重なり合い、冬の冷え込みとともに巻きが強くなっていきます。寒さという陰性の中で求心力という陽性の力が強まる様子には、自然界のバランスが現れています。霜が降りるころには繊維質が柔らかくなり甘みも増して、食べ頃を迎えます。ハクサイは良質な植物性タンパク質、食物繊維が豊富で、精進料理では白菜と豆腐、大根と合わせて「養生三宝」と呼ばれるほどです。冬場には不足しがちなビタミンCやカルシウム、カリウムなどが豊富なほか、食物繊維が多く含まれているために整腸・緩下作用もあります。そのことから、肉料理であるすき焼きなどに用いられるようになったのでしょう。また、キムチを見かけることも今や珍しくなくなりましたが、日本でハクサイの漬物と言えば、やはりぬか漬けですね。ぬか漬けは、ハクサイに豊富に含まれる食物繊維、ビタミンCを保つだけでなく、発酵により乳酸菌が増え、ぬかから溶け出したビタミンB?、B?も多く含んでおり、整腸作用を強化し、肌の調子を整えてくれます。
繊維が柔らかく、味はクセがないので、どんな料理にも合う野菜です。生のシャキッとした食感もさることながら、火を通した時に出るトロッとしたのも美味しくいただけます。外側の葉は生のままでサラダにするか、煮物、お浸し、漬物などに。中ほどの葉は鍋物などでゆっくりと火を入れると柔らかくなるほか、八宝菜などの炒め物にも合います。炒め物にする時は、水気が出て料理が水っぽくなりやすいので強火で一気に炒めましょう。芯には旨味があるので、スープや出汁に使うのがオススメです。ハクサイの芯から水分に溶け出した栄養分を丸ごといただいて、身体の芯から温まりましょう。
【連載執筆者】
西下圭一(にしした・けいいち)
圭鍼灸院(兵庫県明石市)院長
鍼灸師
半世紀以上マクロビオティックの普及を続ける正食協会で自然医術講座の講師を務める。