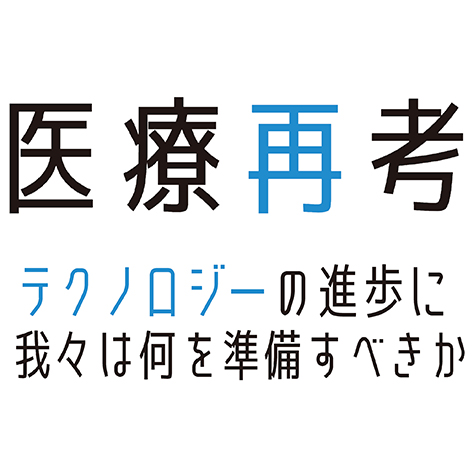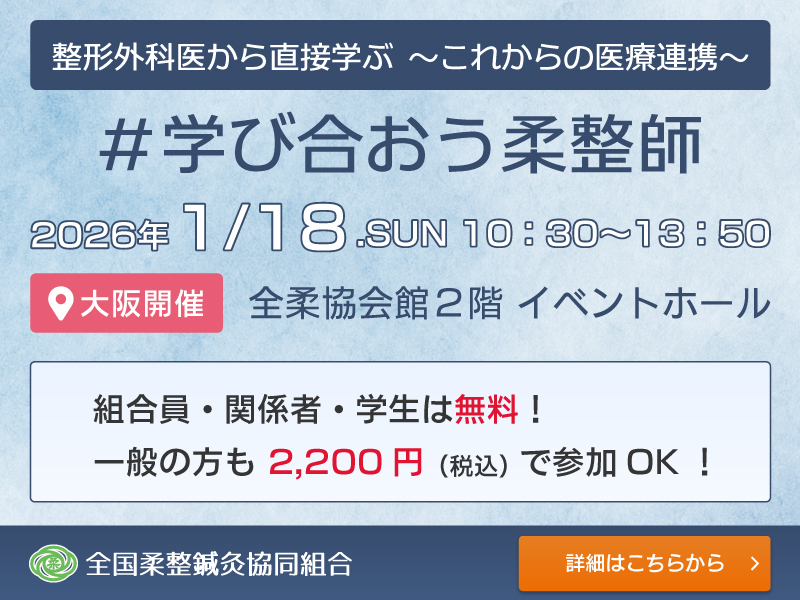Q&A『上田がお答えいたします』 医師が同意書交付料を算定しなければどうなるか?
2021.02.10
Q.
はり・きゅう療養費の同意医師は同意書交付料を診療報酬明細書で算定できますよね。その医師が鍼灸師の友人や知人である場合、交付料を算定しないように頼めば、医科との併給として療養費が不支給になることを回避できるのではないでしょうか?
A.
厚労省の通知で示された留意事項の「第5章 施術料2」に、「療養費は、同一疾病にかかる療養の給付(診察・検査及び療養費同意書交付を除く)との併用は認められないこと。なお、診療報酬明細書において併用が疑われても、実際に治療を受けていない場合もあることに留意すること」と明記されています。つまり、同意医師が自分のレセプトの傷病名欄に同意書に記載した病名を書いた上で同意書交付料を算定しても、薬剤の処方や処置、手術や指導などの「治療」をしていなければ医科との併用とはなりません。同意書交付料は、同意書を作成した医師に対し報酬を出すことで同意書が円滑かつ積極的に交付されるよう、算定できるようにしたものです。 (さらに…)