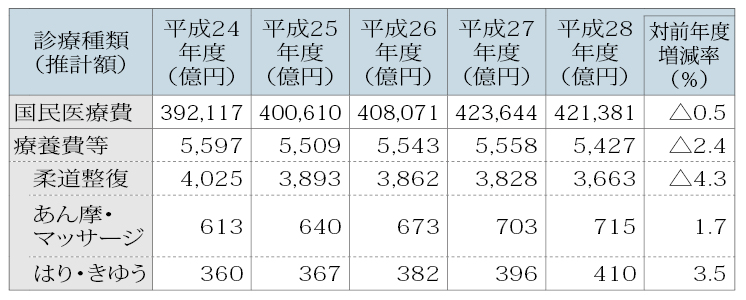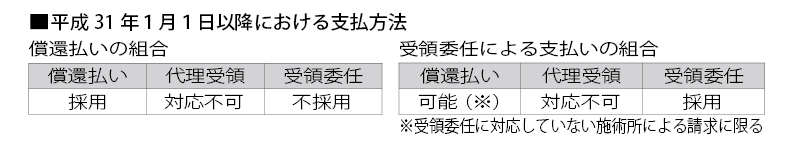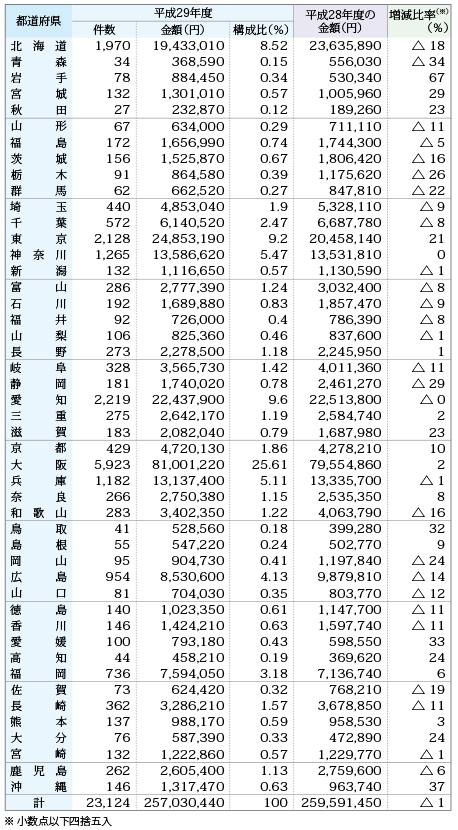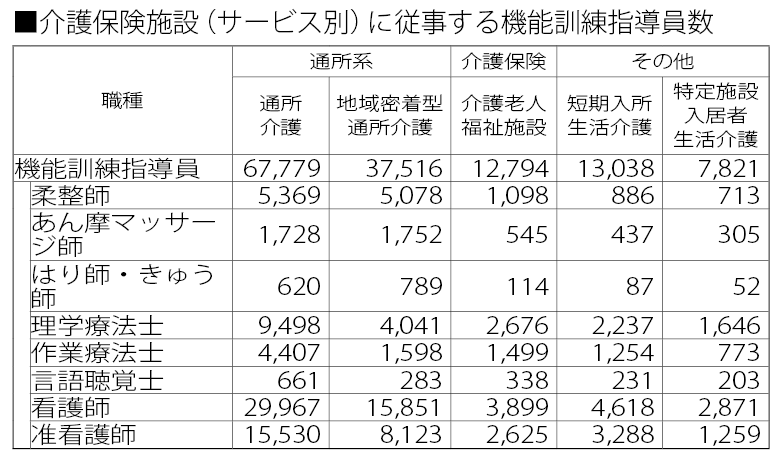病鍼連携連絡協議会が基礎講座 予防や健康増進での連携を模索
2018.11.10
病鍼連携連絡協議会(長谷川尚哉世話人代表)が今秋より3回シリーズの基礎講座をスタートさせた。同会は、病院等の医療機関と開業鍼灸マッサージ施術所の連携の構築を目指して2015年に発足。現在、NPO法人日本HIS研究センターと提携しており、全3講座を受講後に入会した施術者には、全国の同センター加盟病院との連携を含めた支援に取り組むとしている。
9月29日に開かれた1回目の講座では、長谷川氏が登壇し、約4年半の病院勤務と医療法人運営のサテライト治療院での経験を踏まえ、病院との連携の取り方等を解説した。病院では何事も医師のオーダー(指示)から始まるとし、それへの対応が不可欠だと強調。チームで働く力などの「社会人基礎力」はもちろん、検体検査や画像診断の知識も一定程度求められ、また、病院内では患者の投薬情報が電子カルテで全職種に共有されているとの「常識」があり、連携を図ろうと思えば、開業鍼灸マッサージ師も患者の「お薬手帳」のコピーは取っているのが当たり前の時代だと説いた。ただ同会では、エビデンスレベルが高い治療を実践できる鍼灸マッサージ師の養成のみに目的を置いておらず、予防や健康増進にも寄与できる連携の形も模索していると話した。現在、プライマリ・ケアの医師は高リスク群の患者に忙殺され、中・低リスク群には手が回らないのが実態で、この部分に関わっていけると説明。そのためにも、家庭医の藤沼康樹医師が今後の医療で必須と位置付ける「社会的処方」や、故・五十嵐正紘医師が提唱した総合医療の基本要素『五十嵐の10の軸』などの考え方も取り入れ、アプローチを進めていくとした。また、高齢化に伴って増えると見込まれる患者の癌への対処(検診の勧めや徴候のみられる患者の紹介など)にも取り組みたいとも語った。
今後は『治療院でであうかもしれないレッドフラグの知識』、『病歴聴取とマルチモビディティを視野に入れた面接技法とご高診願いの実例、記載法』をテーマに講座が開催される。