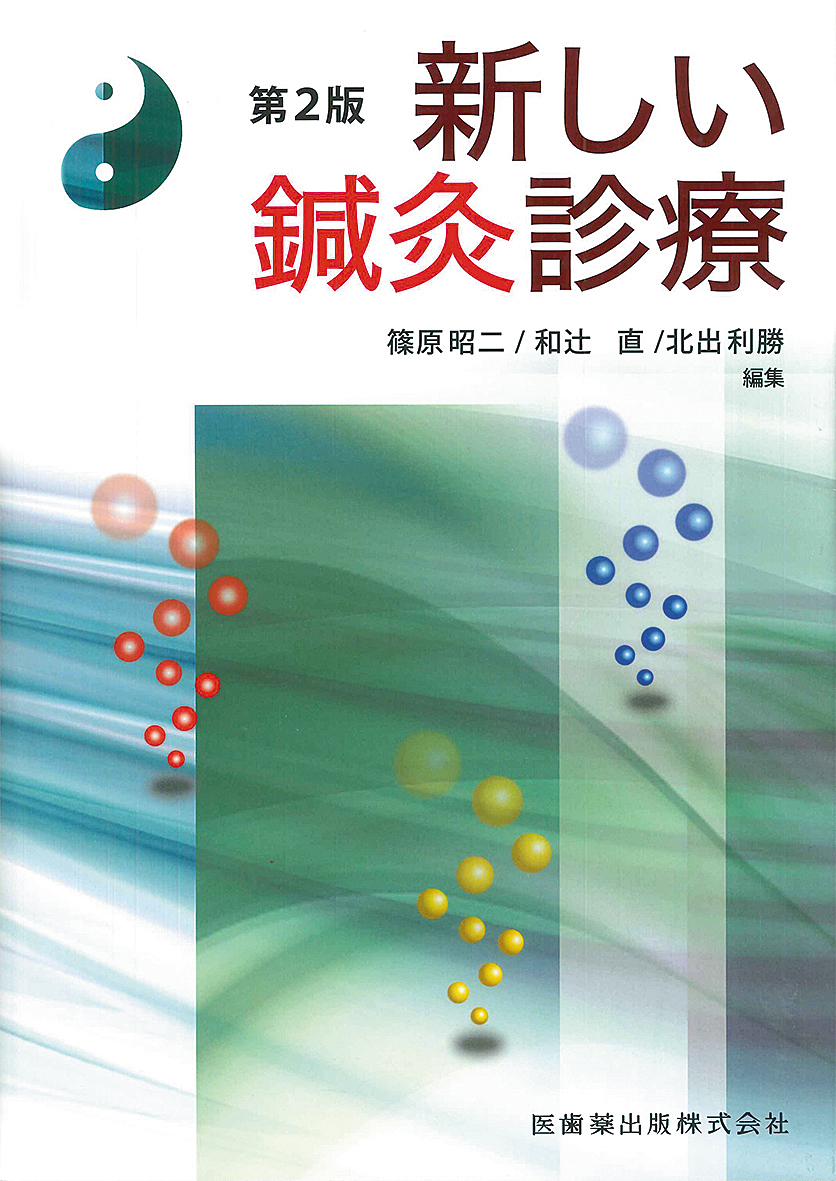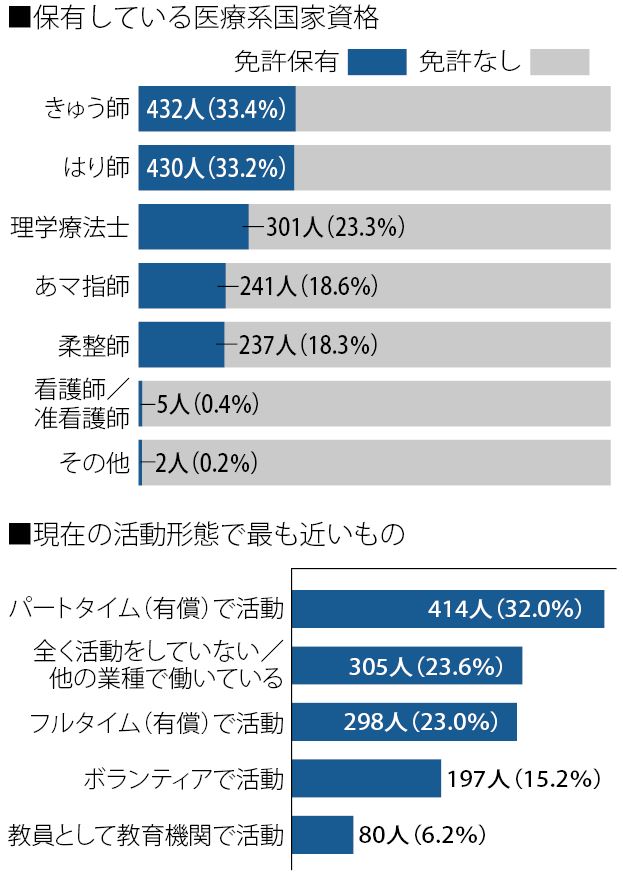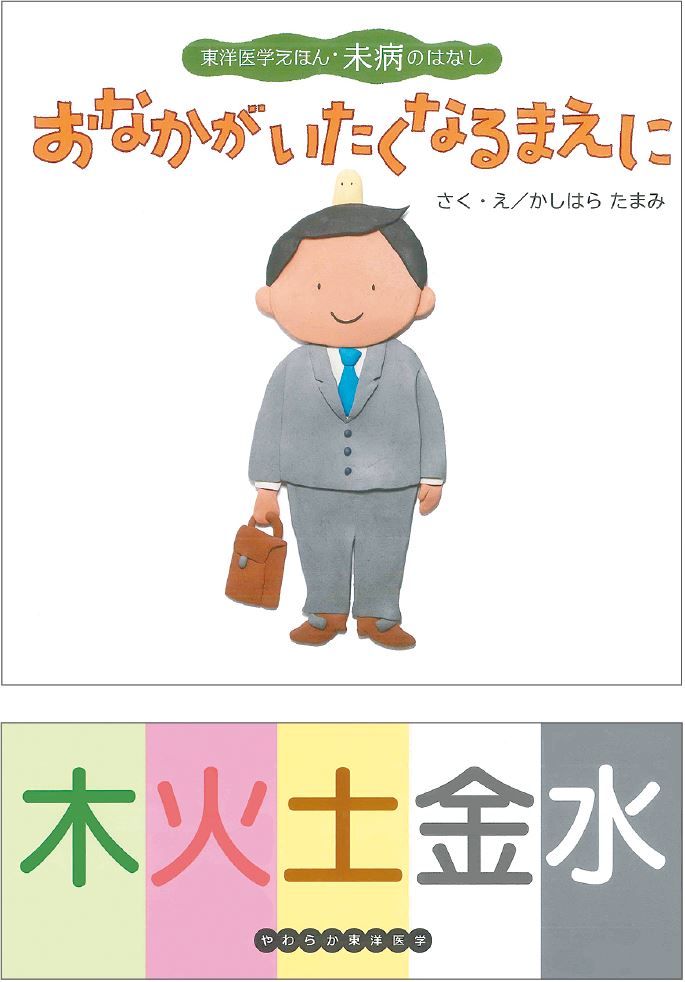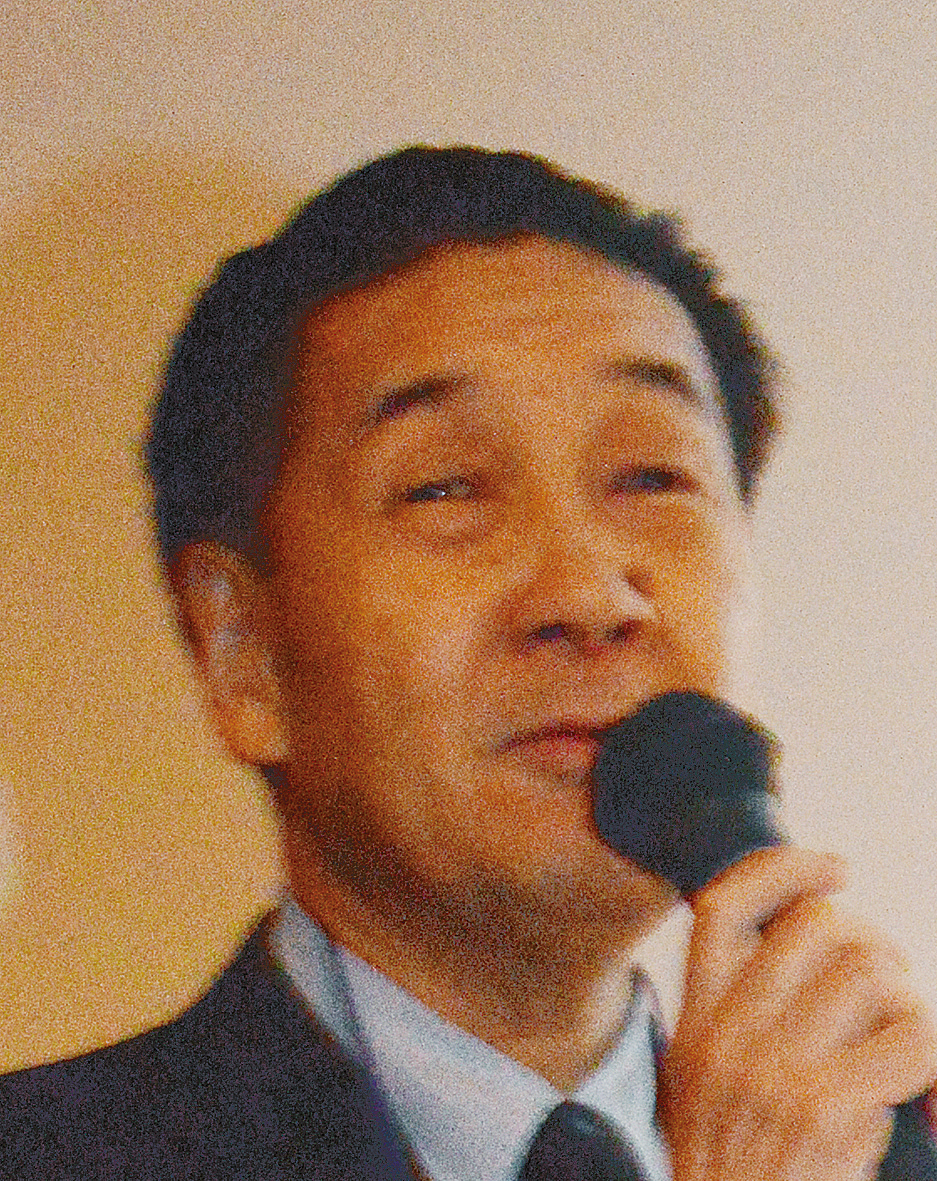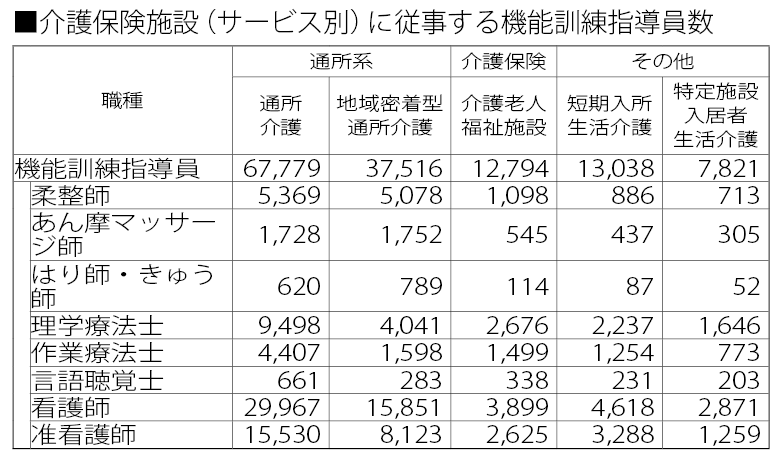日本東洋医学会の第70回学術総会 慢性腰痛ガイドライン、鍼灸「推奨なし」に言及
2019.07.25
検証内容に多数の誤り?
日本東洋医学会の第70回学術総会が6月28日から30日、東京都内で開かれた。
シンポジウム『現代医療における鍼灸のこれからの役割』では、山下仁氏(森ノ宮医療大学鍼灸情報センター)が、60年代の木下晴都らによる臨床試験に端を発する鍼灸のエビデンス構築の歴史に触れた。近年では、線維筋痛症の疼痛・こわばり(線維筋痛症診療ガイドライン2017)、一次性疼痛(慢性疼痛診療ガイドライン2013)などで推奨度B(推奨する)に設定されたと説明。一方で、今年5月に改定された腰痛診療ガイドラインでは、2012年には慢性腰痛について鍼灸をBとしていたところを「推奨なし」に引き下げたとした。ただ、改定に当たって、全く別の評価方式であり、数値が小さい方が改善を示すVASと大きい方が改善を示すNRSの結果を混同する誤りや、「本邦からは、鍼治療と偽鍼の間に有意差はないというメタアナリシスが1編あるのみ」といった記載の誤りなど多くの問題があり、同センターのホームページを通じて指摘と訂正を行っているとした。その上で、海外に比べて国内における大規模で質の高い臨床試験が不足しており、対照群の設定方法に結論が左右されていることも事実であり、継続的に検証を行う体制の確立が必要だと呼びかけた。
ISOのバンコク会議報告も
用語及び病名分類委員会・JLOM報告会では、6月3日から6日にかけてタイ・バンコクで開催されたISOの第10回TC249全体会議を踏まえた現状報告が行われた。生薬の分野では、柴胡のように日本と中国で同じ呼称だが異なる植物を用いるものなどの語彙を整理した上で幾つかの規格が成立し、今後優先的に議論する対象を100に絞るといった整理が行われたほか、鍼灸領域では会議に先駆けた5月末、「通電に用いる鍼の試験方法」や「無煙灸」の規格が成立したとされた。また、WHOの国際疾病分類第11版(ICD-11)についても解説された。
このほか、鍼灸師・医師対象の鍼灸セミナー、生薬・歴史・制度に関するシンポジウムなどが開催。展示コーナー『五感で楽しむ東洋医学』では、各種生薬を手に取って確かめることができたほか、鍼や灸の展示も用意され、水に浮かべた野菜に鍼を刺入する体験コーナーに並ぶ医師の参加者の姿もみられた。