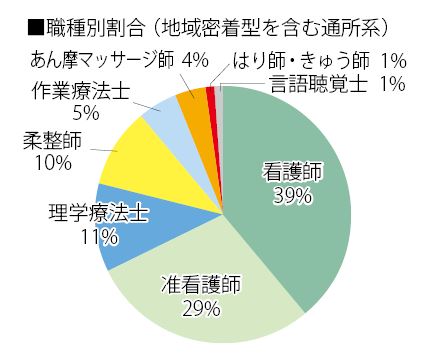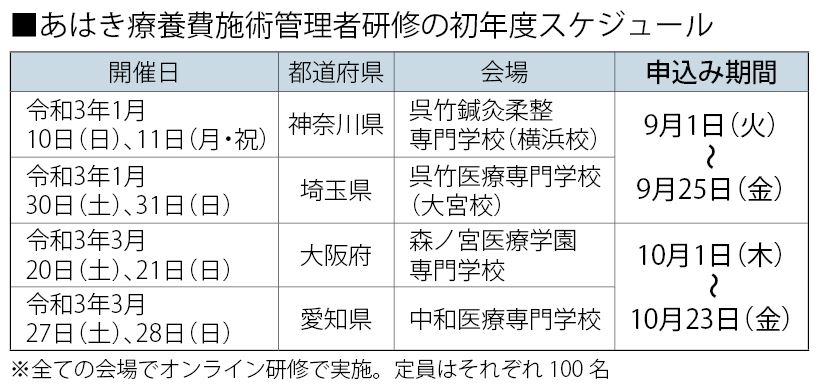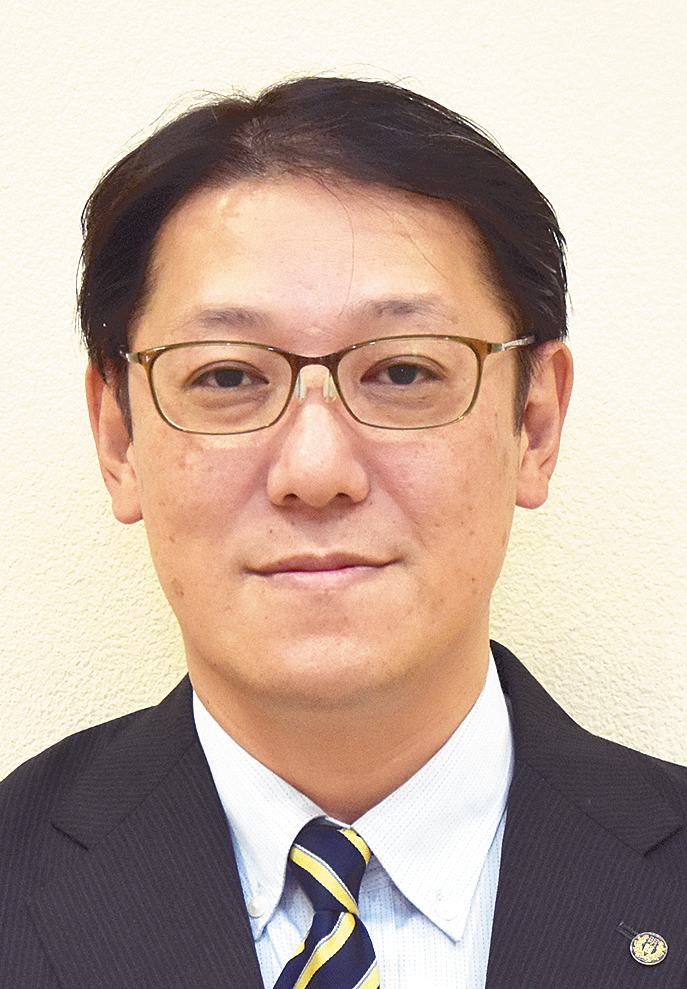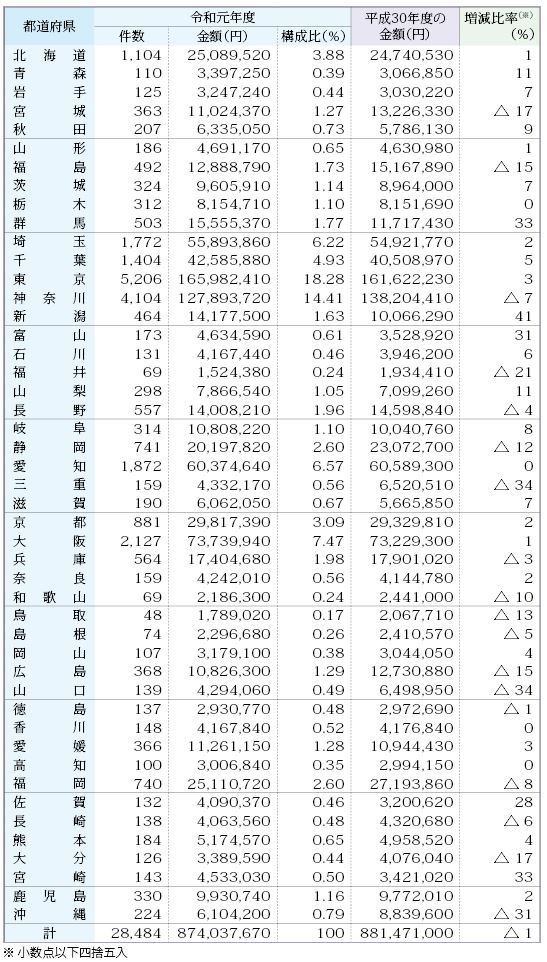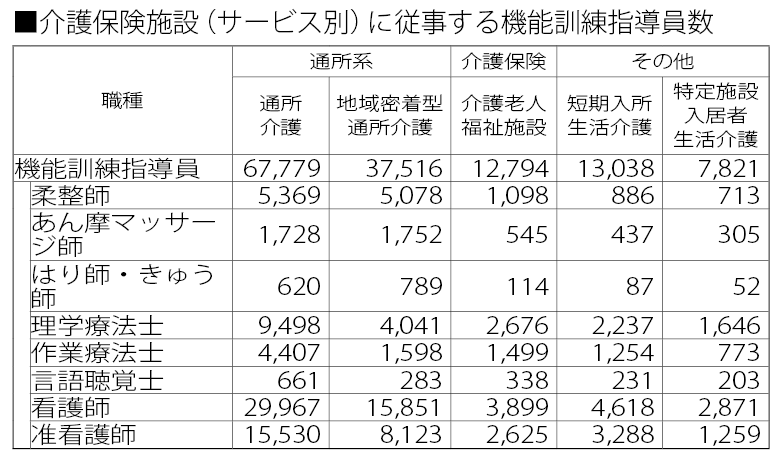あマ指師課程新設をめぐる裁判・東京控訴審 いきなり結審、判決12月8日に
2020.10.09
学園側、1審判決の誤り指摘
あはき法19条の規定が「職業選択の自由」(憲法22条)に違反しているとして、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を認めなかった国に対し、処分取消を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が10月1日、東京高裁で開かれた。原告側の平成医療学園が、請求が棄却された1審・東京地裁判決の破棄を求めた。当日、口頭弁論の初回でありながら結審し、12月8日に判決が言い渡されることが決まった。
晴眼者のあマ指師養成課程新設をめぐっては、東京以外にも、大阪、仙台の2地域でも係争されており、1審判決は原告の請求が全て棄却された。各地裁とも判決内容はほぼ似通っており、昨年12月の東京地裁判決(以下、原判決)は、「19条は視覚障害者の生計維持の保護を図る措置として、今なお必要性があり、憲法に違反しない」旨の判断が下されている。
原告の学園側は控訴理由書で、被告である国側の主張を多数採用した原判決に誤りが散見されるとして、 (さらに…)