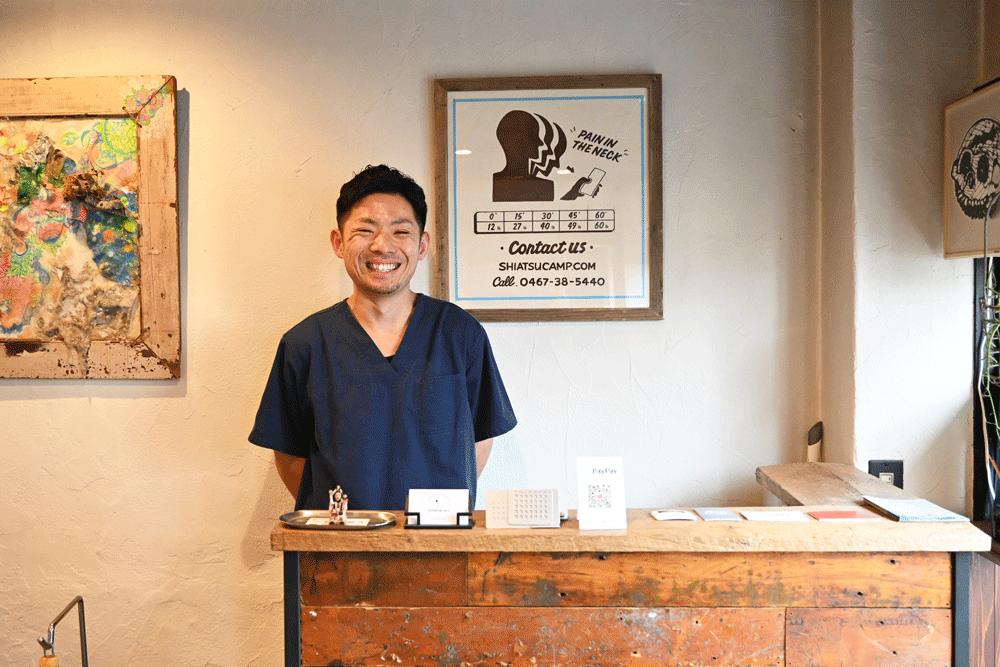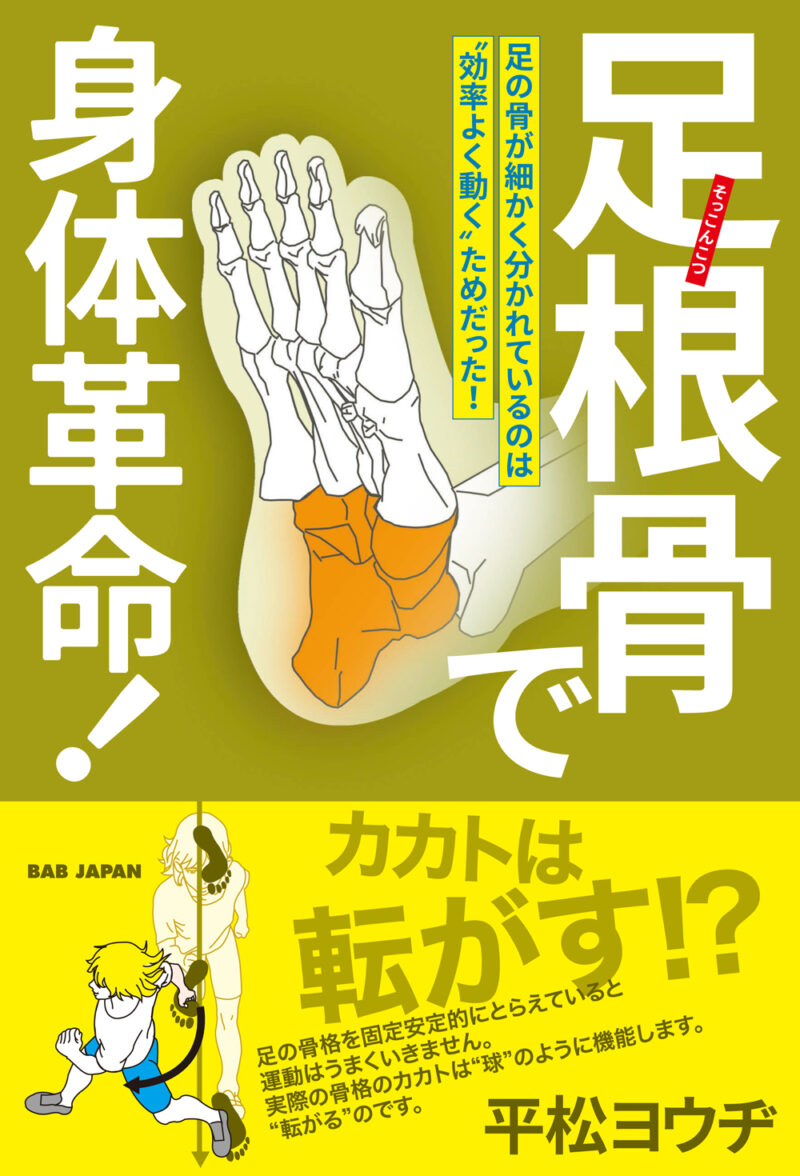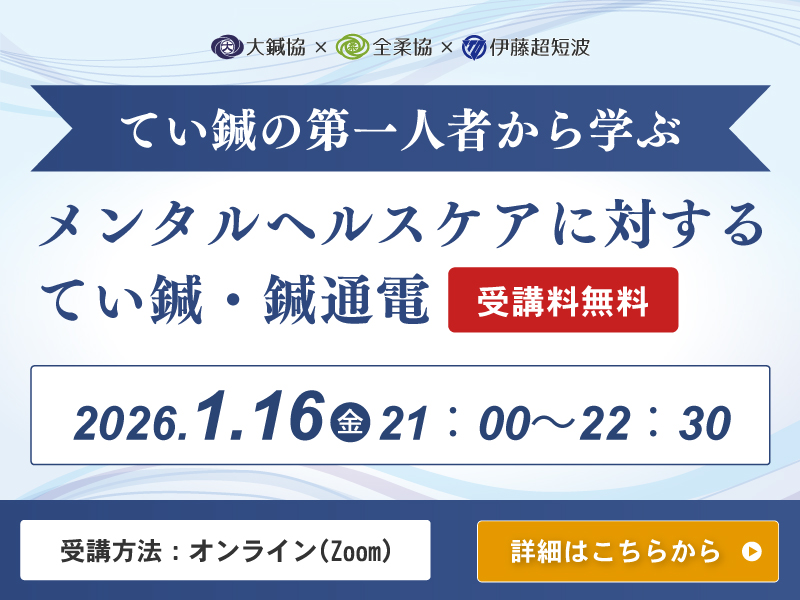Q&A『上田がお答えいたします』 1部位目からの負傷原因記載が義務化されると請求代行団体は潰れる?
2019.12.25
1111号(2019年12月25日号)、上田がお答えいたします、紙面記事、
Q.
今後の柔整療養費検討専門委員会での議論で1部位目からの負傷原因の記載が義務化されたら、療養費の請求代行団体は少なからず潰れていくのではないでしょうか。
A.
昨年の療養費検討専門委員会での議論を経て「亜急性の負傷」としての捻挫は一掃されてしまいました。亜急性が削除されたことから、これをもって捻挫の定義は柔道整復と外科・整形外科との認識が同一とされましたから、3部位以上請求する場合には、支給申請書に関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態であるということを明記しなければなりません。従来まで発生機序としての亜急性の負傷が原因と認知されていたからこそ、反復継続した微々たる外力によるものやオーバーユースも全て支給対象となっていたところを、健保組合等の保険者は「通知にこれらを支給してよいと書いていない」と不備返戻してきています。亜急性を削除した当時の厚労省の担当室長が「支給対象は今まで通り変わらない」と言っていても、「療養費の支給対象の範囲の変更はない」との事務連絡があっても意味をなさず、審査会からも大量に返戻されています。
インフラや国民の栄養状態、自動車の安全性向上などから、明確な急性で新鮮性の捻挫は減っているはずです。保険者に言わせれば「そんなに皆さんあちこち捻挫などしない」のです。一方で、不正請求をしていた一部の柔整師にも自粛の動きが見られます。ただ、患者さんの保護の見地から、実際に急性の外傷性であれば療養費で取り扱うべきですから、「全部が全部自費施術」というのは施術者側の身勝手であるとは言えますが。いずれにせよ、今後は2部位でも1部位だけでも患者照会が実施され、患者さんの回答に「自然に痛くなった」「1年以上前から調子が悪い」「ちょっと揉んでもらった」との記載があれば、これを理由に不備返戻されます。さらに部位数に関係なく負傷原因の記載を義務付けられたなら、多くの柔整師は療養費の請求を諦めることになるでしょう。そうすると、会員からの療養費支給申請の大幅減に耐えられなくなる団体が出てきます。あくまでも私見ですが、最終的には「2部位目から」で議論は決着するでしょう。それでも療養費の申請は激減し、そしていずれは本当に1部位目からとなってしまい、申請そのものの「消滅」に至るということになるとすれば、あなたのご指摘通りですね。
今後を見据えて、各施術者団体には、開業から店舗展開・物品販売に至るまで施術所をトータルパックで支援する、自費メニューの指導と導入を手がける、フランチャイズ事業展開のノウハウを提供するなどして、単なる「療養費請求代行団体」からいち早く脱却していくことが求められるでしょう。
【連載執筆者】
上田孝之(うえだ・たかゆき)
全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長
柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。