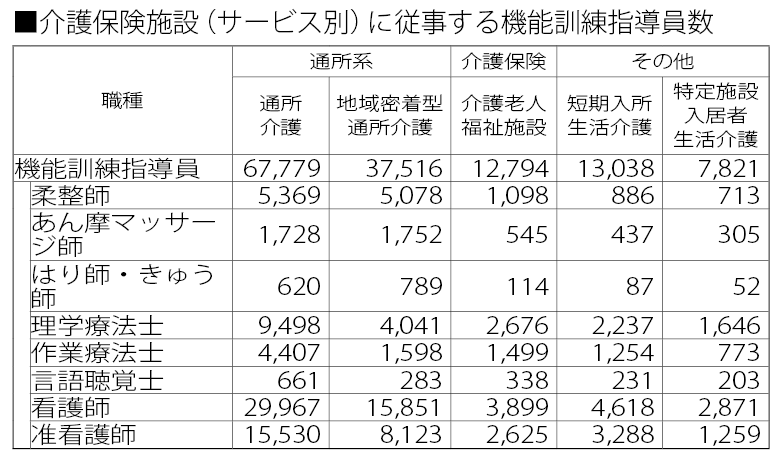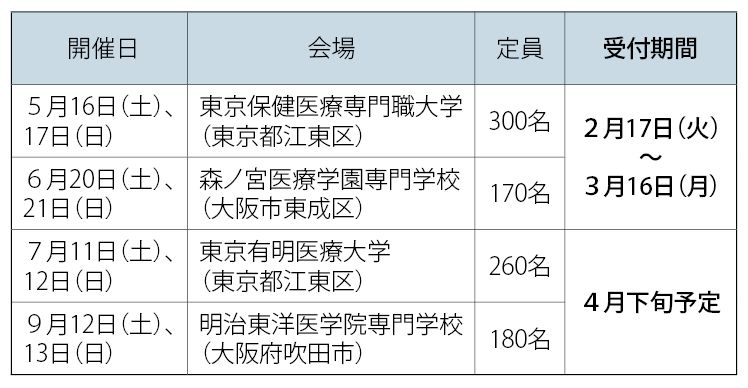連載『食養生の物語』67 平成最後のお節に
2018.12.25
もうすぐ、平成最後の年末年始ですね。来年2019年にはラグビーワールドカップ、2020年には東京オリンピック・パラリンピック。2021年にはワールドマスターズゲームズin関西、そして2025年には大阪での万国博覧会と、多くの国際イベントが予定されています。こうした中で、今後ますます日本文化が注目されていき、歴史上でも転換点を迎えることとなりそうです。
アメリカの生物学者ジャレド・ダイアモンドは『文明崩壊』(草思社文庫)の中で、文明が崩壊する原因は、歴史のターニングポイントで「引き継ぐべき価値観」と「捨て去るべき価値観」の見極めにあると述べています。まさに今の日本は価値観の見極めを問われているとも言えそうです。
2013年にユネスコ無形文化遺産に「和食―日本人の伝統的な食文化」が登録された理由の一つに「正月などの年中行事との密接な関わり」があります。食の時間を共にすることで家族や地域の絆を深めてきたことが評価に影響したのです。季節の行事と食の関わりについて、私たち一人ひとりがきちんと理解しておくことが大切です。知識として知っているだけなのか、経験としてやったことがあるのか、日常的にやっていることなのか、私たちが食文化をどのくらい大事にしてきたかどうかも問われるところでしょう。
関西では、里芋の煮物のことを「小芋のたいたん」と言います。里芋のことを小芋(子芋)と呼ぶのには意味があります。里芋は種子を蒔くのではなく〝子芋〟を植えて栽培し、それが〝親芋〟となって周囲に〝子芋〟〝孫芋〟と育っていく。その姿が親・子・孫と世代間を越えて仲良くする様子に見えるという意味や、子宝に恵まれる象徴として子孫繁栄を願う意味もあって、お節料理に「小芋のたいたん」が定番になってきたようです。
他にも、お節料理には様々な意味が込められています。黒豆は、厄払いに「魔」を「滅」するという語呂遊びに加えて、真っ黒に日焼けするほどマメに働けるようにという健康祈願。昆布は関西弁で「こぶ」と発音されることから、「よろこぶ」につながる縁起物。田作りは「ごまめ」と呼ばれ、「五万米」に通じて五穀豊穣を願うもの。数の子はそのまま子孫繁栄。鰤は魚偏に師と書くほどに賢い魚といわれ、出世魚でもあることから立身出世を願うとか。海老は長いひげを生やし腰が曲がるまで長生きすることを願って。鯛は「めでたい」の語呂合わせで、恵比寿様が持っているようにハレの日の食卓に上るものです。そしてお重に詰めるのは「めでたさを重ねる」意味があります。
こうした文化は、世代の壁を越えて受け継がれてきたもの。こうした一つひとつの意味を語り合うことも、受け継ぐ価値観になるでしょう。平成最後の年末、おばあちゃんから教わりながらお節料理を一緒に作ってみるのもいいかもしれませんね。
【連載執筆者】
西下圭一(にしした・けいいち)
圭鍼灸院(兵庫県明石市)院長
鍼灸師
半世紀以上マクロビオティックの普及を続ける正食協会で自然医術講座の講師を務める。