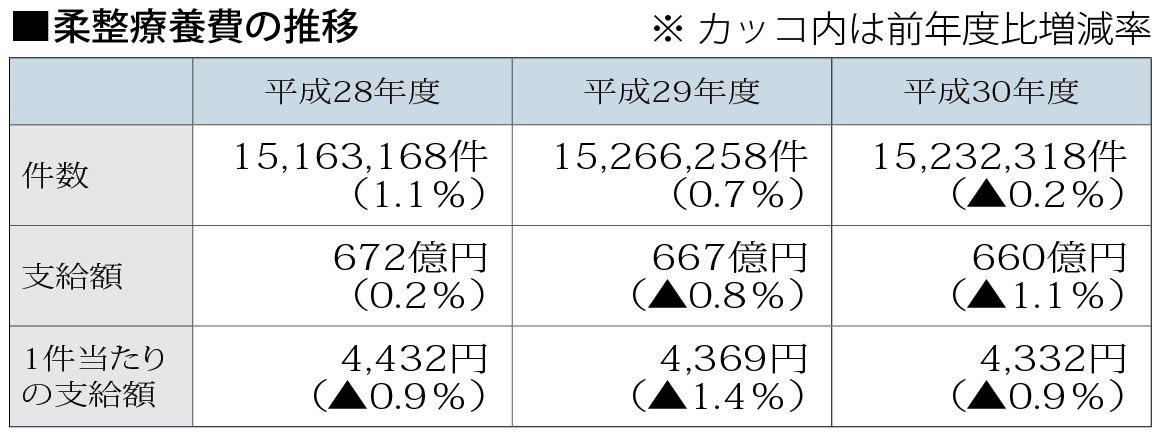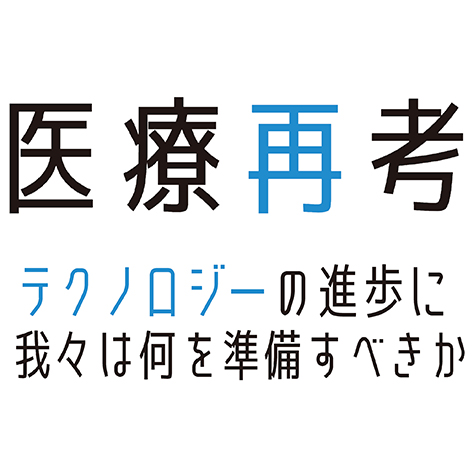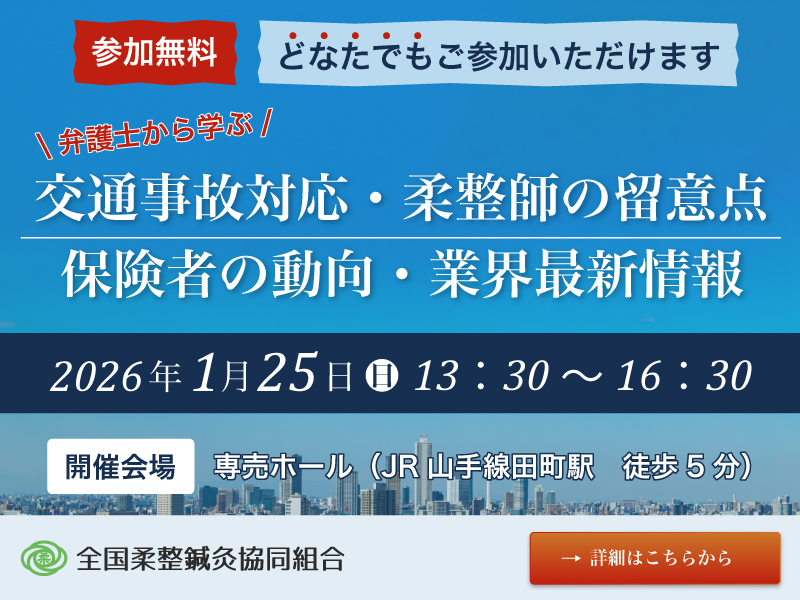今日の一冊 9つの脳の不思議な物語
2019.09.25
9つの脳の不思議な物語
ヘレン・トムスン 著
文藝春秋 2,106円
これまでの人生の全ての日を覚えていて、生後9カ月の時の記憶があるというボブ。自宅のトイレからキッチンへ行こうとして迷子になるシャロン。怒りと攻撃性を抑えられずドラッグにも耽溺していたが、一夜にして虫も殺せない穏やかな性格になったというトミー。彼らの脳内では何が起こっているのか、あるいは何が起きたのか。大学で脳を研究し、科学ジャーナリストとなった著者が、「人とは違う脳を持つ人々」について書かれた論文を読み漁るうちに彼らの「人となり」に関心を持ち、訪ね歩いた旅の記録。