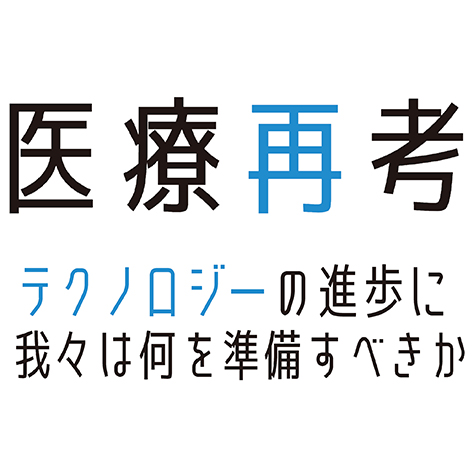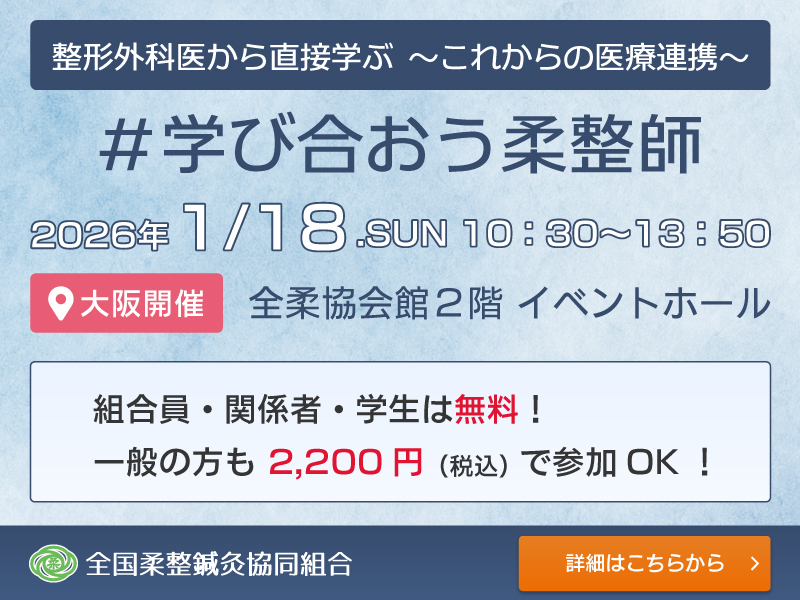連載『医療再考』7 カルテは誰のために書くのか?
2019.09.10
これからは情報社会です。医療の世界も例外ではなく、情報コミュニティーが患者の中心になると考えられます。そして、情報コミュニティーに加わるには、「コミュニティーにどのような情報を提供するのか」または「どのような情報を基にコミュニティーの中で活用されるのか」という視点が必要だと話してきました。特に前者は情報を提供する役割となることから、どこから情報を収集し、どんな情報を提供するのかが重要です。そこで、これからの情報収集の中心となるものが電子カルテでしょう。
カルテはそもそも、治療した内容を記録しておくためのツールです。自分が行った診察や治療の流れが分かるようにまとめるとともに、その内容は医療事故などの裁判の証拠にもなることから、自分の身を守るという意味でも大切なものです。ただ、自分のためというレベルであれば、自分自身が理解できれば良いので、用語や記載方法などの統一化は必要なく、紙媒体のカルテでもそれほど問題ではありません。他方、医療連携の流れの中で、患者の情報を他の鍼灸師や他職種と共有したりする役目もあります。情報共有が目的であれば、用語や記載方法の統一は必要不可欠であり、必要とする情報もそれぞれ異なることから、診察・治療に対する考え方も統一する必要があります。
また、近年では、カルテの役割として、情報を収集・集積することが注目されています。カルテに記載された情報が数値化されていれば、その情報をまとめることが可能です。そして、同じカテゴリーで情報をたくさん集めることができれば、同一疾患や同一分類の患者の傾向や治療効果などを解析できるため、ビッグデータとして注目されているのです。ビッグデータがRCTなどの従来の臨床研究と異なる点として、同じカテゴリーの症例をリアルタイムに何万例も集められることから、常に最新の治療効果や予後予測を可能とします。そのため新たなエビデンスとして注目されており、医師は既に、カルテの中にある膨大な医療情報から同じ傾向の患者データを集約し、解析する取り組みを始めています。情報の集約には同じ種類のデータを集めないと意味がありませんから、診察ガイドラインを設けることで、どこでも同じデータを集約できるようにしているのです。こうした仕組みを形にしたものが、まさに電子カルテです。電子カルテは今後の医療を大きく変える救世主となり得ます。情報コミュニティーに鍼灸師が加わるためには、まず鍼灸師が持つ情報を電子化し、他の情報と連携させることが大切でしょう。
ただ、残念ながら現時点の鍼灸師のカルテには、情報を記録しておくだけの価値しかないと言えます。我々しか持っていない身体の情報を電子化し、そのデータを基に社会問題を解決することができれば、鍼灸は情報コミュニティーの主役に躍り出ることができるでしょう。そう考えると、鍼灸の電子カルテ化には、未来の鍼灸、さらには医療を変える力があるかもしれないのです。
【連載執筆者】
伊藤和憲(いとう・かずのり)
明治国際医療大学鍼灸学部長
鍼灸師
2002年に明治鍼灸大学大学院博士課程を修了後、同大学鍼灸学部で准教授などのほか、大阪大学医学部生体機能補完医学講座特任助手、University of Toronto,Research Fellowを経て現職。専門領域は筋骨格系の痛みに対する鍼灸治療で、「痛みの専門家」として知られ、多くの論文を発表する一方、近年は予防中心の新たな医療体系の構築を目指し活動を続けている。