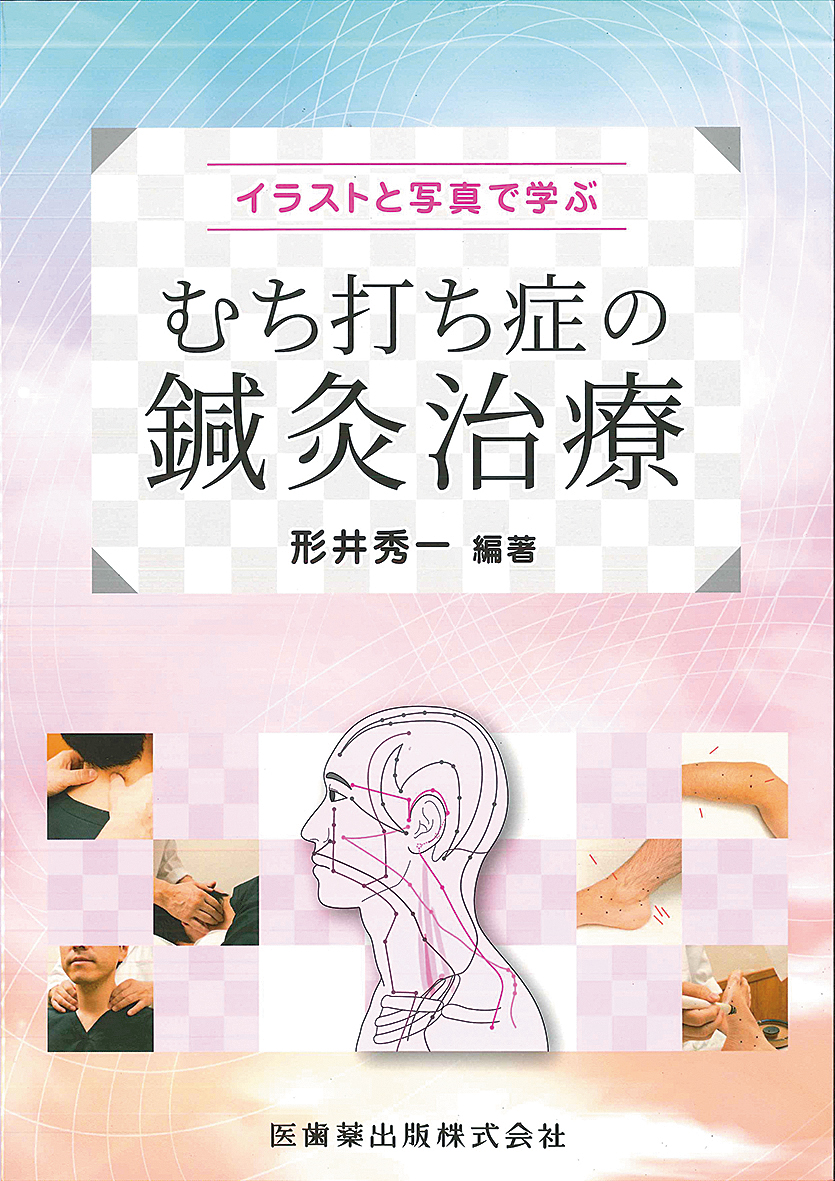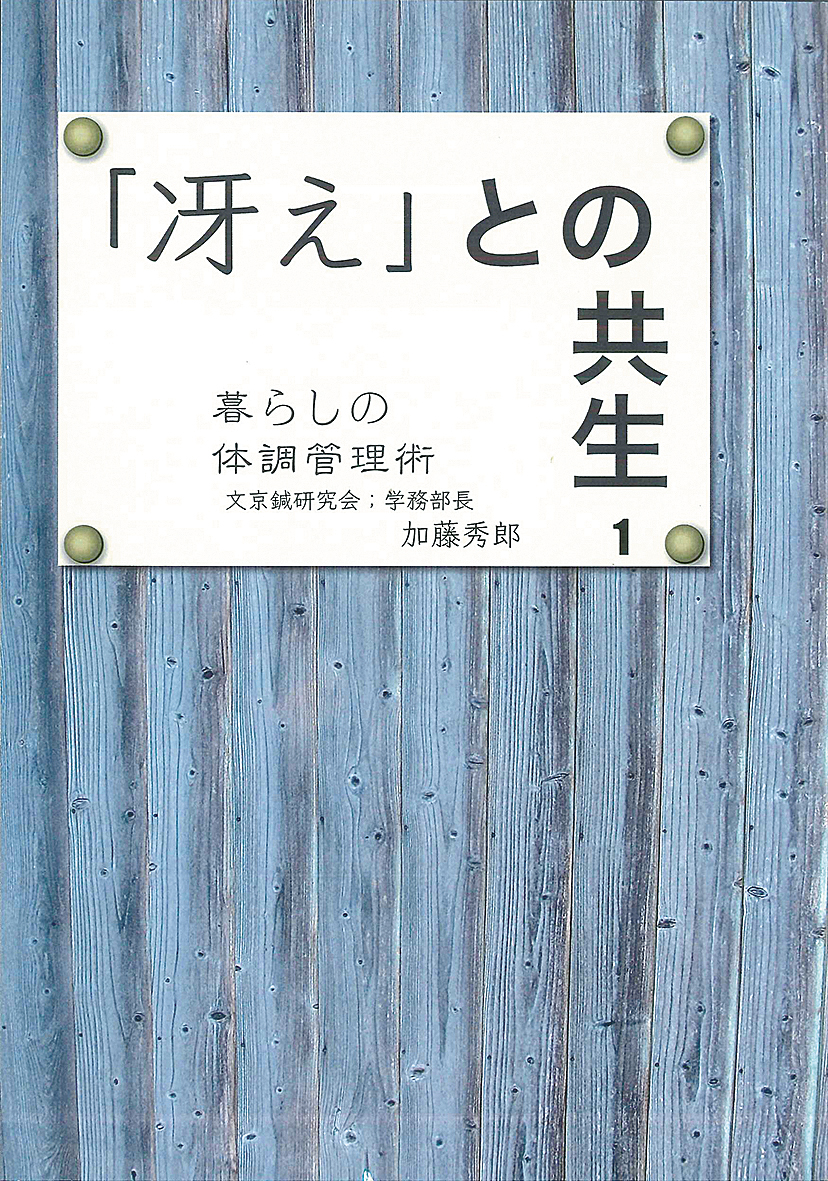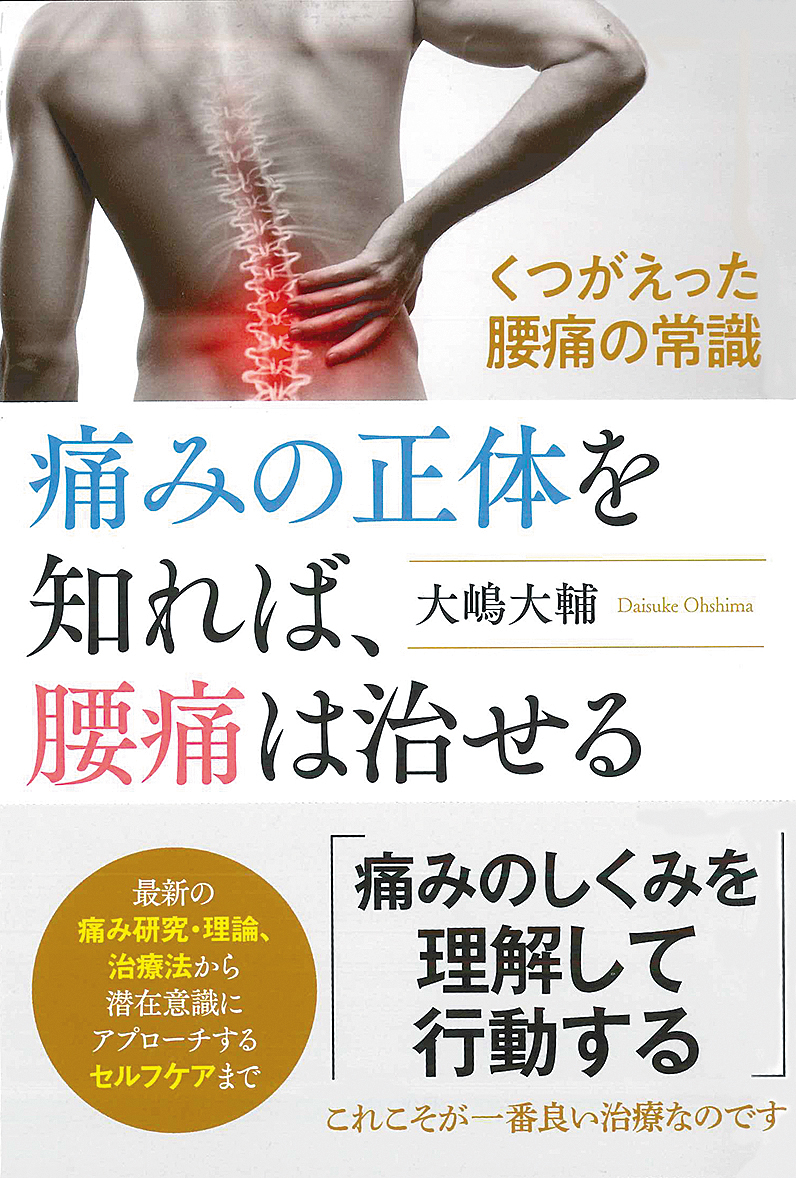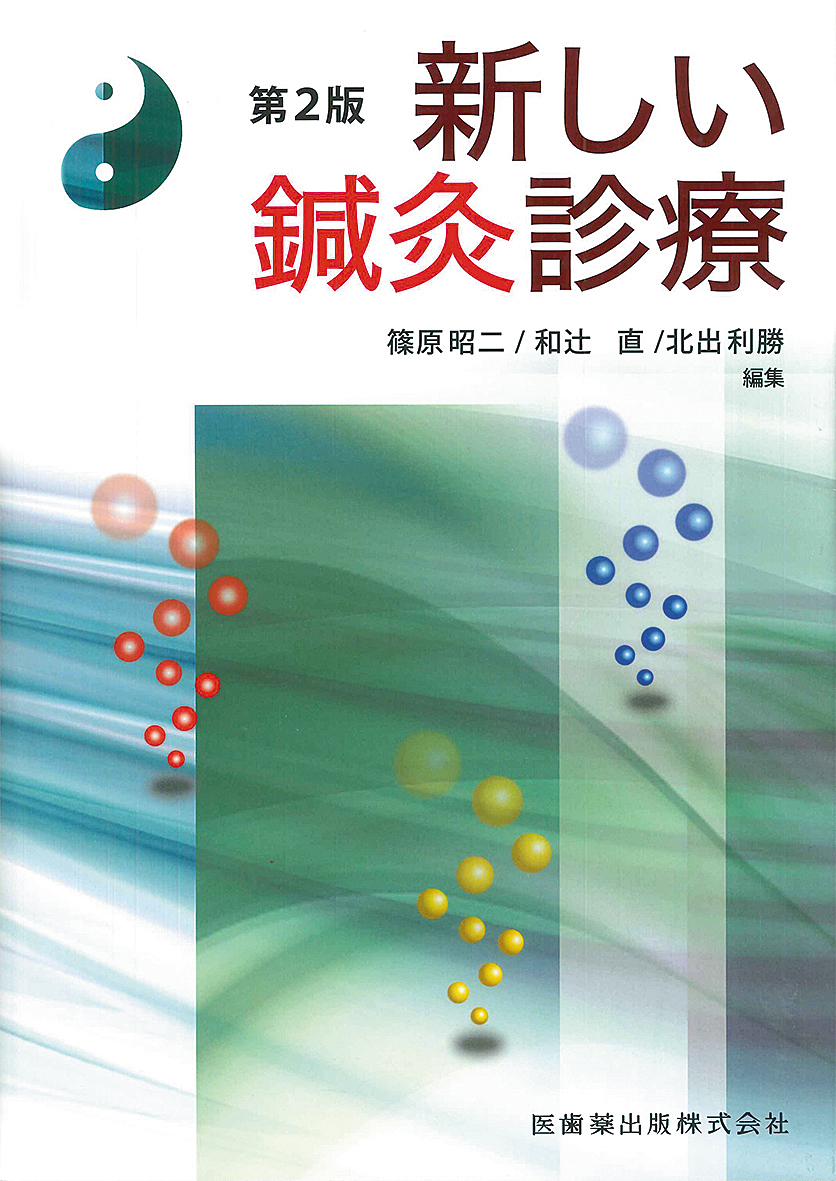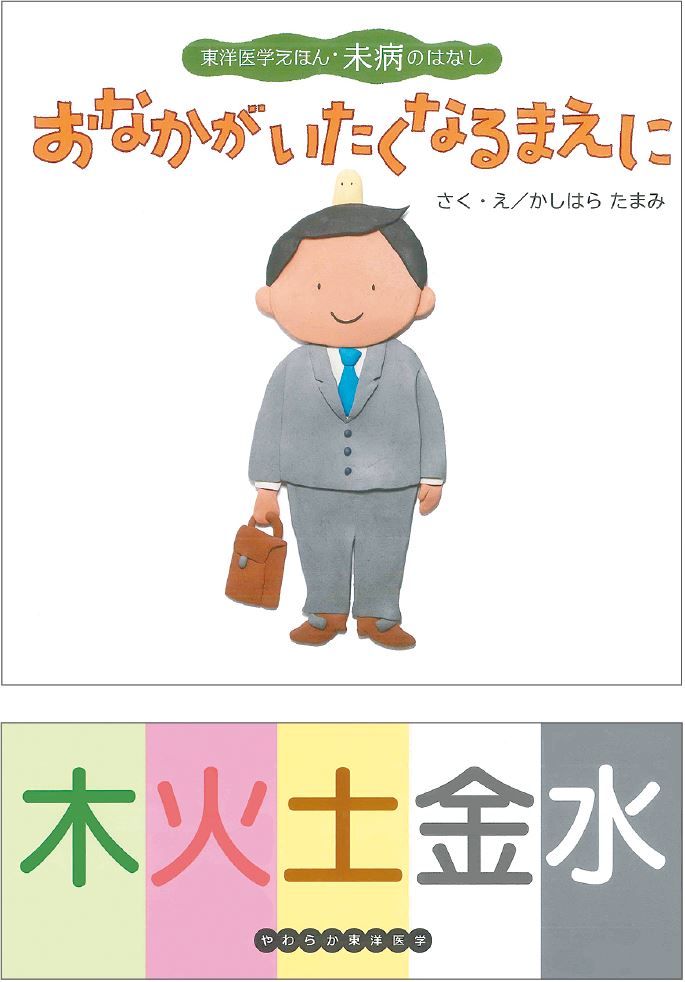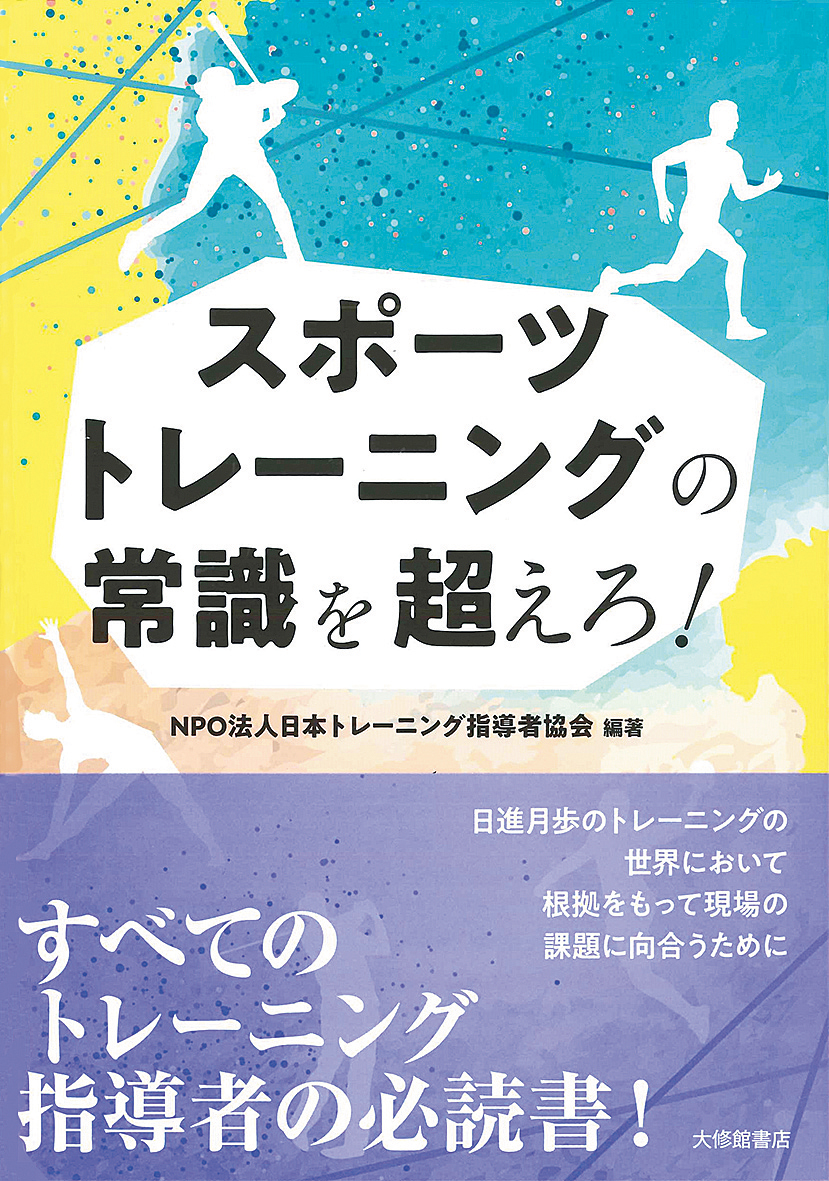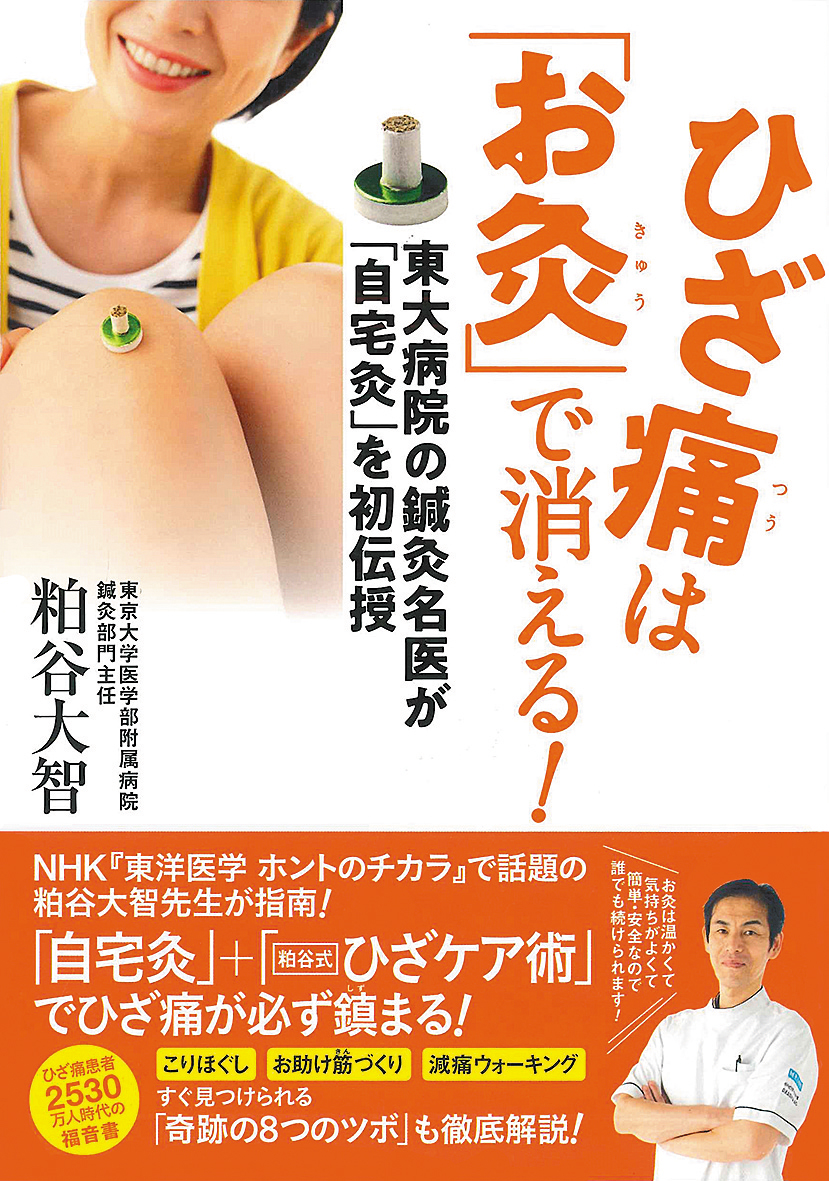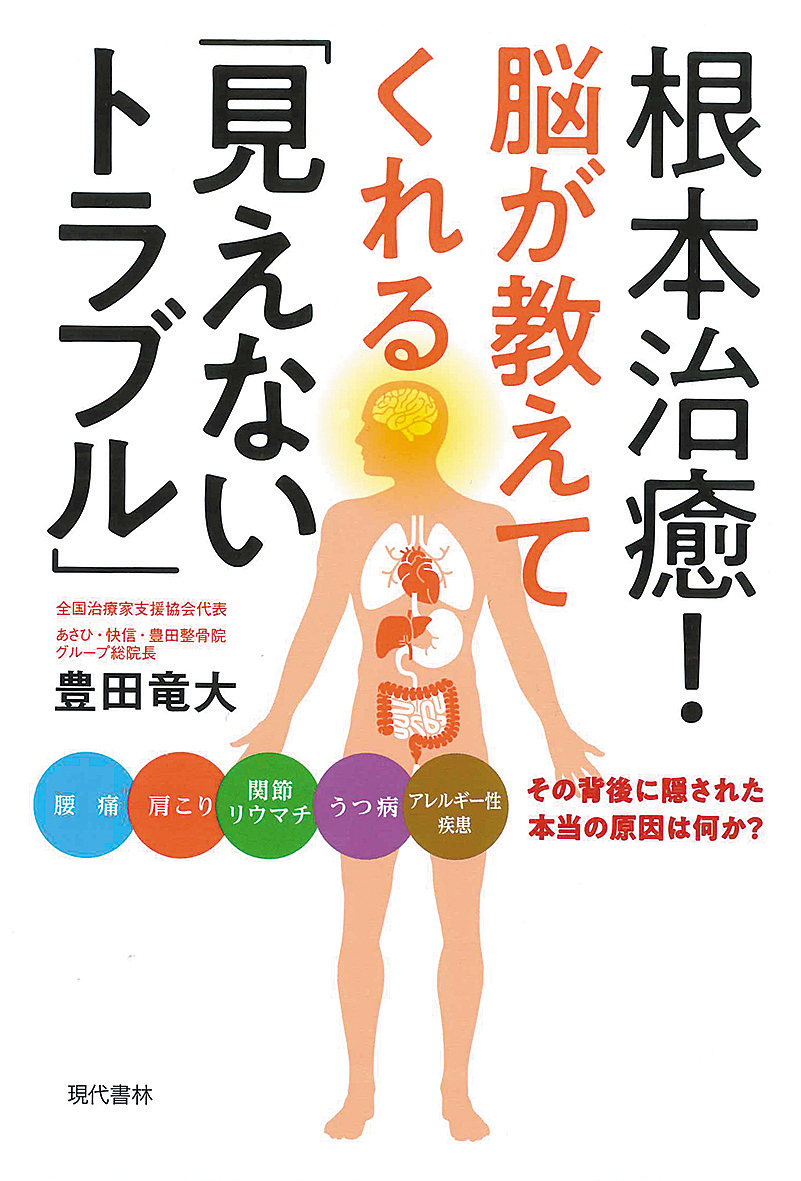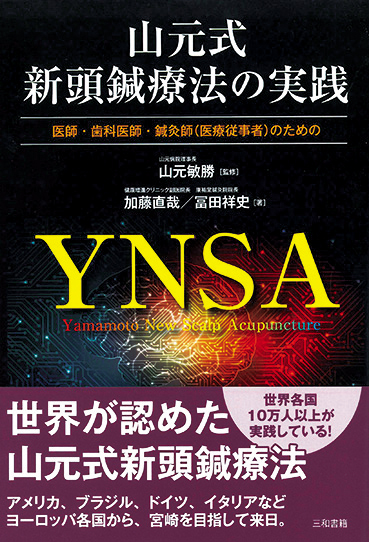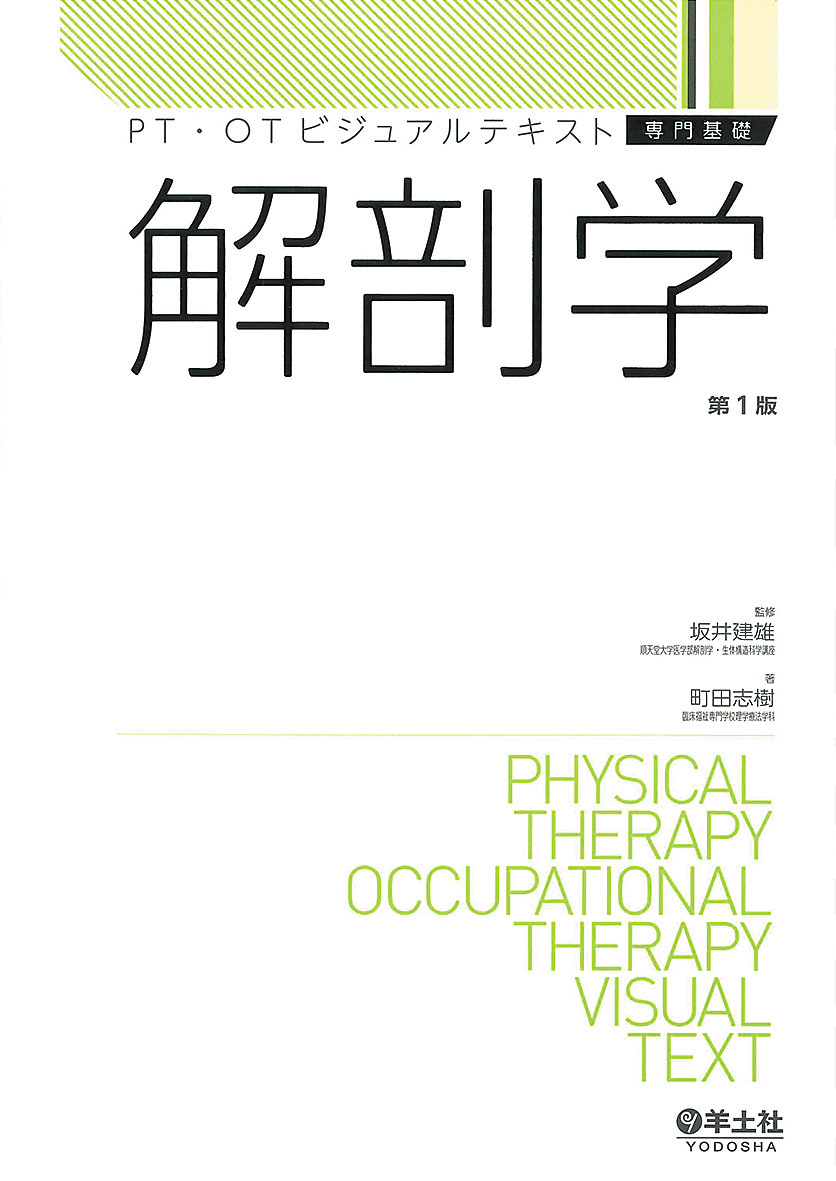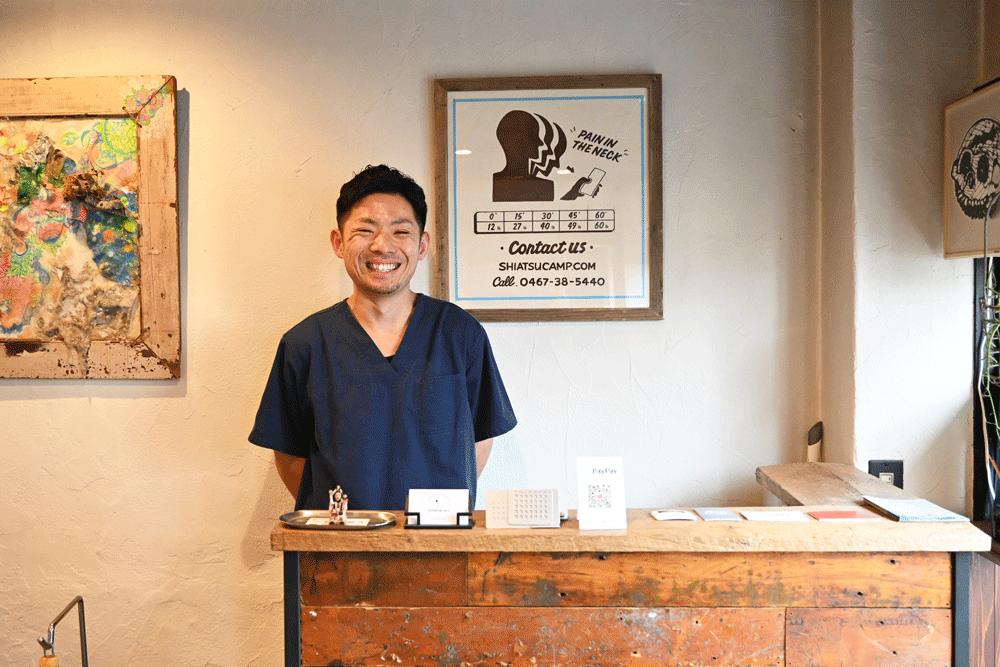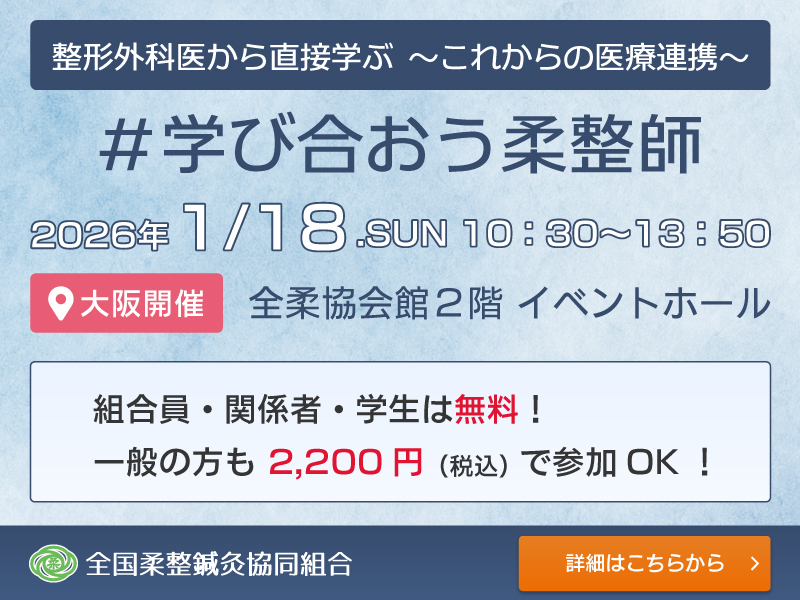Good Products――注目商品紹介コーナー
2019.05.25
1096-1097号(2019年5月10-25日合併号)、紙面記事、
1096-1097号(2019年5月10-25日合併号) ほか
※画像をクリックで拡大します
場所を選ばず施術できる
セイリン『セラミック電気温灸器』
セイリン株式会社(静岡市清水区)の家庭用熱療法療器、『セラミック電気温灸器』。
火を使わず煙も出ないため、施術場所を選ばない。重さ140gと軽量で、サイズもコンパクト。温度は43℃から3℃刻みで5段階に設定できる。先端部の素材はアレルギーフリーのセラミックを採用、消毒用エタノールで全面の拭き取りができるため清潔に保てる。見やすい液晶画面で温度を表示し、通知音も分かりやすい。消し忘れ防止機能付き。ホワイトとブラックの2色。
販売に関する問合せはセラピ株式会社(0120-89-8128)へ。
「痛くない! スムーズな刺入を実現!!」
セラピ『ishin CURE』
セラピ株式会社(大阪市北区)のオリジナルディスポ鍼、醫鍼シリーズの『ishin CURE(イシン キュア)』。
鍼尖を丸く加工したことで従来品よりも刺入時の痛みを抑え、皮膚組織の損傷や内出血のリスクを軽減。従来品より鍼体に柔軟性・弾力性を持たせ、「極力痛みを軽減することに成功した」と同社。また特許技術(特許番号第3828064号)によって鍼柄の先を丸く密閉することで、施術者の指への負担も併せて軽減したという。入り数は1箱240本入。
販売に関する問い合わせは同社(0120-89-8128)へ。
オームパルサーの「最上位モデル」
全医療器『Ohm Pulser LFP-2000e』
株式会社全医療器(福岡市南区)の『Ohm Pulser LFP-2000e』。
低周波・鍼通電低周波治療器「オームパルサー」の「最上位モデル」。治療前後の変化が数値で分かる計測機能や微弱電流に調整できるマイクロカレント、人間が心地良いと感じるリズムの「1/fゆらぎ」モードなどの新機能を搭載。オプションで皮下から筋層にかけて通電刺激ができる新アイテム「電気ていしん」もある。各種数値を分かりやすくし細かく設定できるデジタル表示を採用。
販売に関する問合せはセラピ株式会社(0120-89-8128)へ。
小型・軽量タイプの光線治療器
東京医研『SUPER LIZER mini PRO』
東京医研株式会社(東京都稲城市)が『SUPER LIZER(スーパーライザー)mini PRO』を新発売。
生体深達性の高い波長帯(0.6μm~1.6μm)の近赤外線を、最大出力2,500mWでスポット状に照射する。HA-2200シリーズの機能と操作性を継承しつつ、ハンドイン治療に特化した小型・軽量タイプ。3種類の先端ユニットにより様々な部位への照射ができる。「スーパーライザーの治療効果は、ペインクリニックをはじめ多岐にわたる医療の現場で高く評価されている」と同社。
販売に関する問合せはセラピ株式会社(0120-89-8128)へ。
灸を「科学」する艾燃焼解析システム
チュウオー『MOXATH MX-5』
チュウオー(兵庫県宝塚市)の、灸を「科学」する艾燃焼解析システム『MOXATH(モクサス) MX-5』。
灸の温度や人体が得る熱量、艾の捻り方によって変わる温度の立ち上がり時間、最高温度をグラフで可視化する。測定部は人体表面を再現するため30~40℃に設定可能。パソコンに接続して使用、データの保存もできる。対応するOSはWindows。「教育・研究機関や灸の研究家に活用してもらい、灸の科学的アプローチやエビデンスの充実に」と同社。
製品に関する問合せは同社(0797-88-2121)へ。
疼痛の除去・緩和などの治療に
豊和ES『定電流治療器AAP』
疼痛の除去・緩和に豊和ES株式会社(兵庫県尼崎市)の『定電流治療器AAP』。
微弱電流で血流・神経・筋肉を活性化させて自己回復力を助け、損傷部位や筋肉を調整・回復・改善する。関節痛や腰痛、筋肉痛、野球肘やテニス肘などに効果的で、プロのアスリートの治療実績も。治療器が発する音で患部を捉えられ、音の変化で回復・改善の程度も分かる。持ち運びできるトランク収納型で往療にも便利。
販売に関する問合せはセラピ株式会社(0120-89-8128)へ。
頚・腋窩・鼠径部にフィットする冷却剤
三重化学工業『くるっとクール』
三重化学工業(三重県松阪市)の冷却剤『くるっとクール』。
三日月形で頚・腋窩・鼠径部にフィット、動脈を冷やし体温を急冷させるので熱中症対策に好適。藤田保健衛生大学病院との共同開発で、看護師の「首や脇を効果的に冷やせるものを」との声を反映した。ジェル素材は経口毒性の無い安全なものを使用、冷凍庫で凍らせても「カチカチにならない」。専用カバー付き。「病院や学校、事業所などで常備しては」と同社。
販売に関する問合せはセラピ株式会社(0120-89-8128)へ。
「お顔への施術など美容にも」
山正『NEOディスポ鍼SPタイプ5分』
株式会社山正(滋賀県長浜市)の『NEOディスポ鍼SPタイプ』に、鍼体長15mmの短い鍼で細めの番手(0.10mmと0.12mm)が新たに登場した。「お顔への施術やデリケートな施術にご使用いただけます」と同社。
カラー鍼柄で容易に鍼の番手(太さ)を確認できる。鍼柄の先が丸く、「治療家の手にもやさしい設計」。鍼体には滑らかな刺入感のためにシリコーンコーティング加工を施している。
製品に関する問い合わせは同社(0749-74-0330)へ。
5種の精油と天然メントール配合
吉田養真堂『MEGUREFRE―めぐリフレ―』
株式会社吉田養真堂(奈良県橿原市)の足リフレッシュシート『MEGUREFRE―めぐリフレ―』。
足の裏や足首、ふくらはぎなどに貼ってリフレッシュ。ラベンダー・グレープフルーツ・ベルガモット・マジョラム・ローズマリーの5種類の精油と天然メントールを配合した。シートの素材は水分を含まないため気化熱で体温を奪うことがなく、菌が繁殖しにくいので防腐剤不使用、パラベンフリーでかぶれにくい。1箱20枚入り、参考上代980円(税抜)。
製品に関する問合せは同社(0744-22-2374)へ。
貼るだけで指圧効果、肩こり、腰痛をはじめ運動前後のケアにも
和光電研『プチバン』
和光電研株式会社(大阪府八尾市)の、貼るだけで指圧効果が期待できる『プチバン』。
40年来のロングセラー『ロイヤルトップ』をベースにした、患者のセルフケアにも使える家庭用貼付型接触粒(一般医療機器)。同社では、運動前後に貼ることで疲労を軽減する、上肢の可動域を広げる、といった用途も提案、マラソン大会に『プチバン』ブースを出展するなど普及にも努めている。180粒入(写真)6,000円・60粒入2,160円(税込)など。
販売に関する問合せは和光電研商事株式会社(0120-765-890)へ。