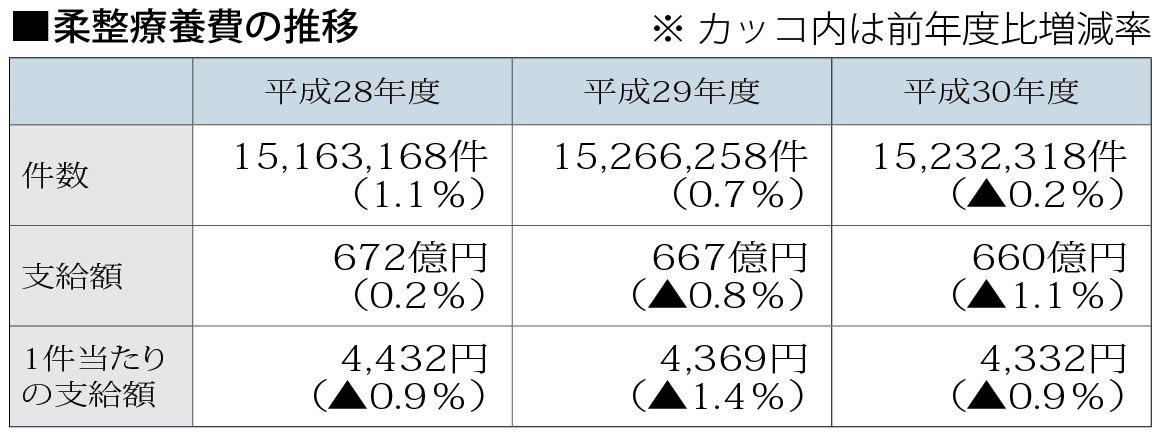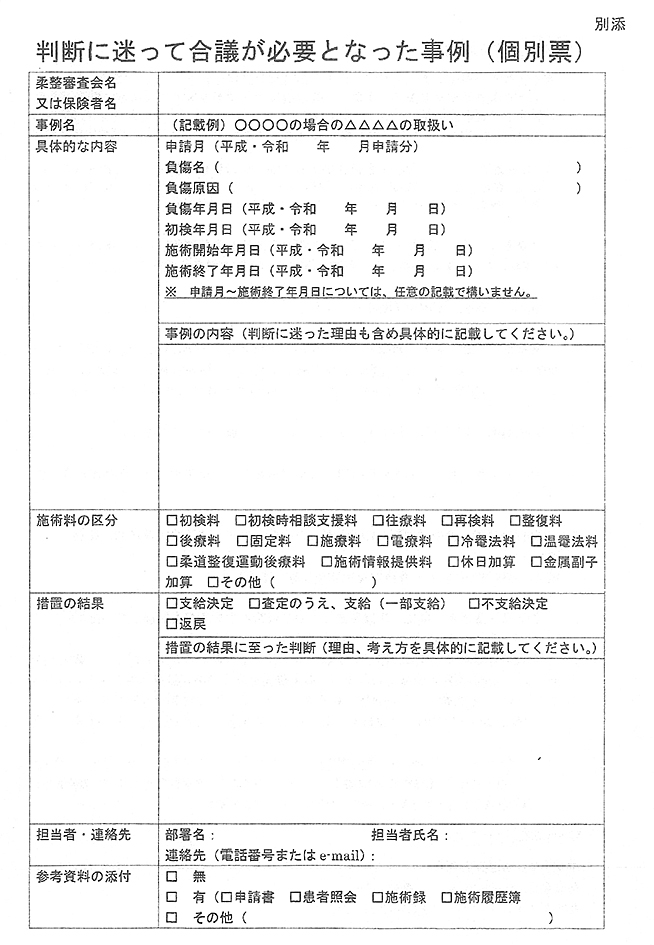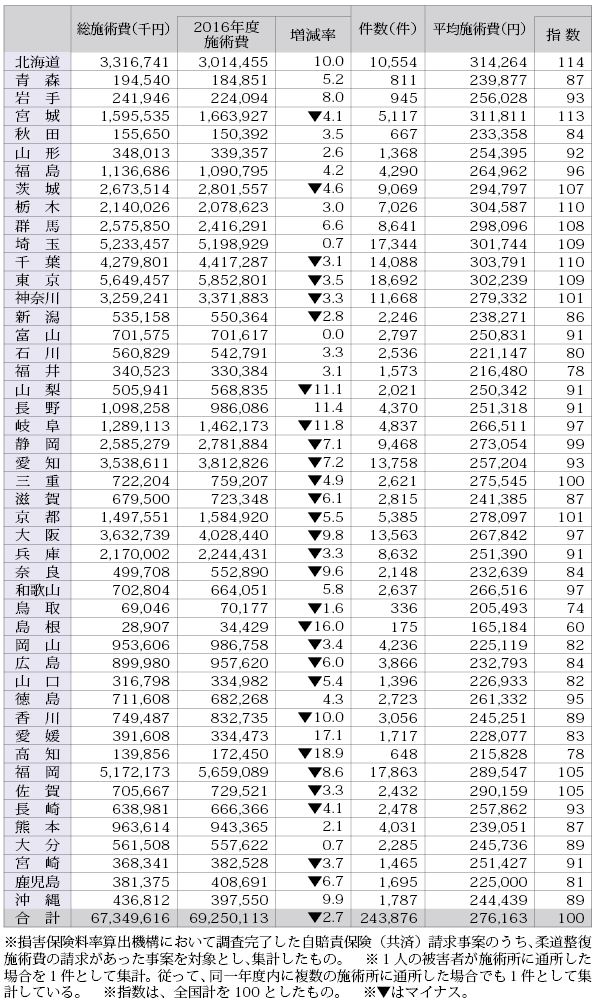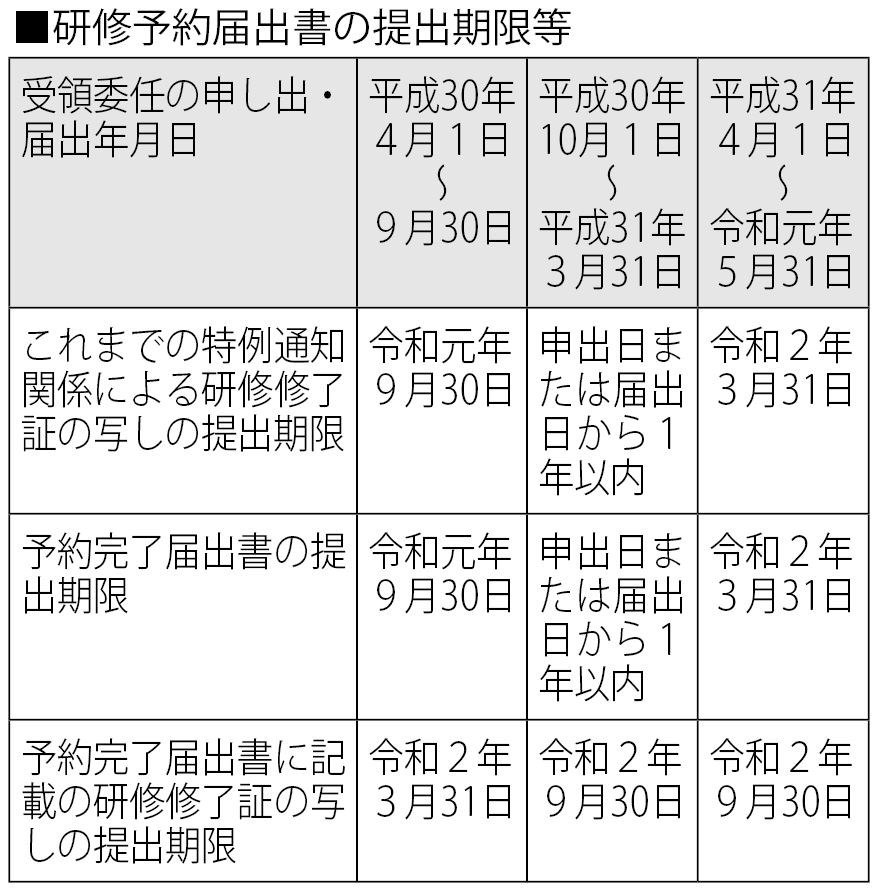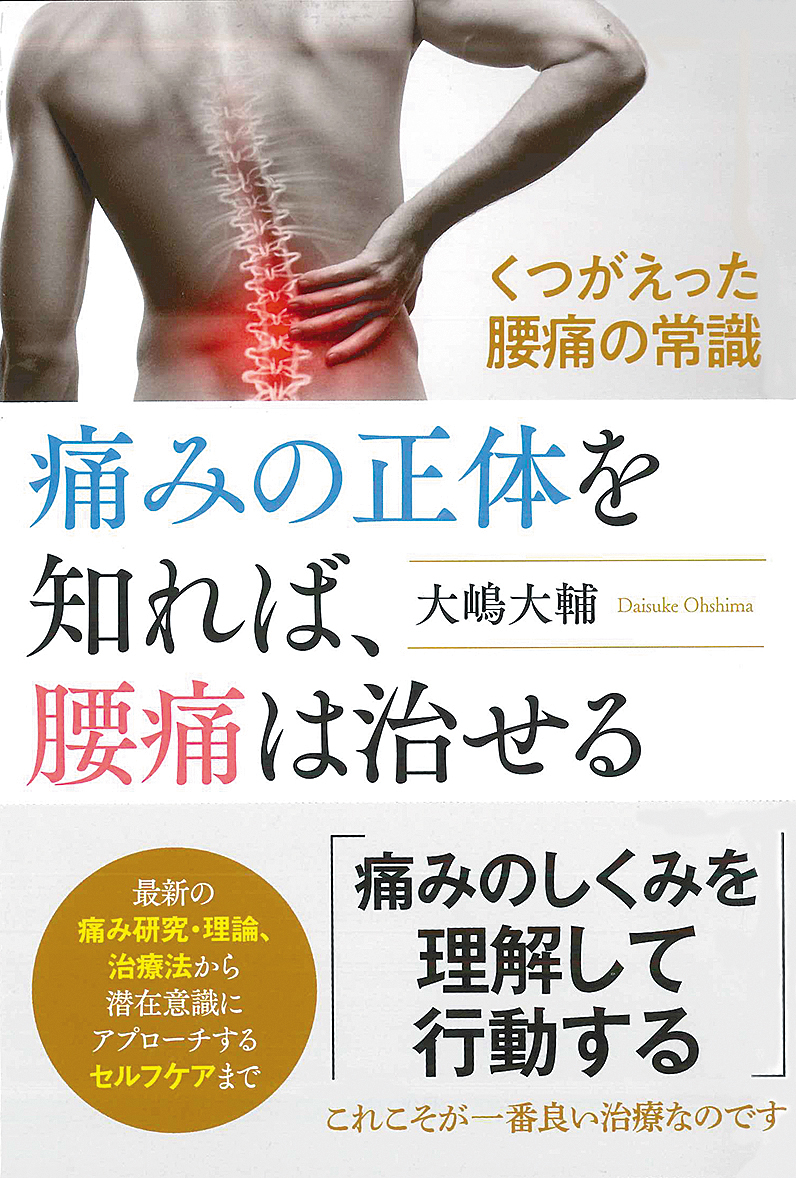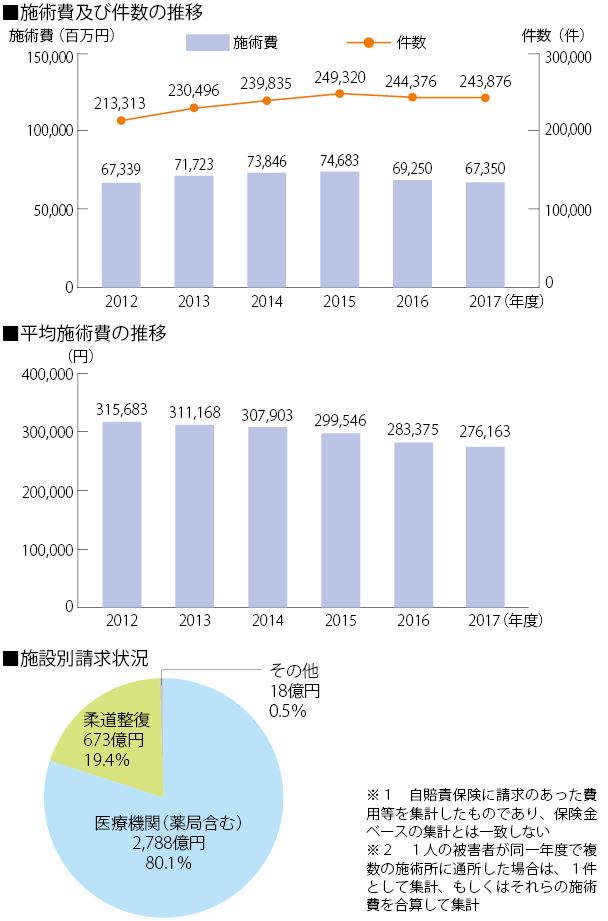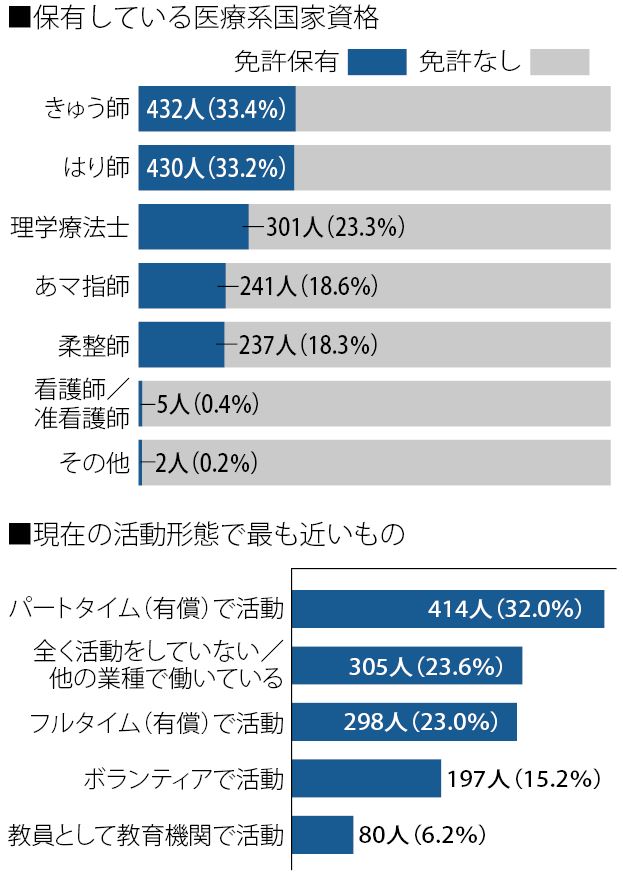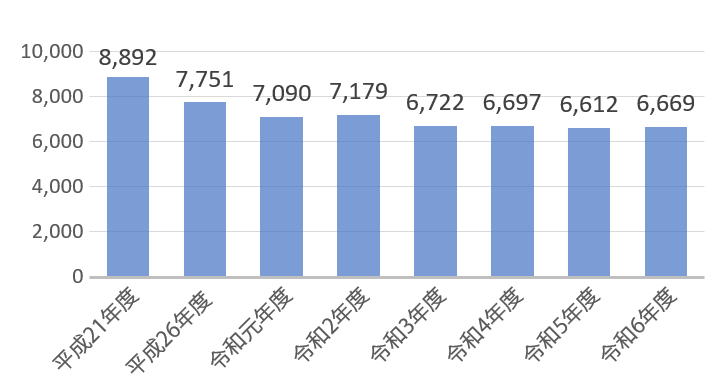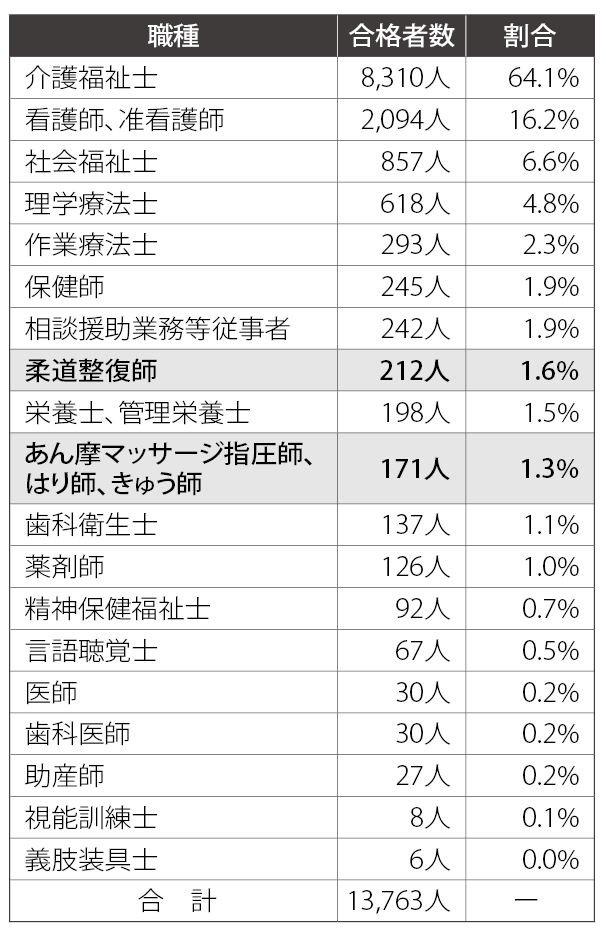平成医療学園グループ 世界最高峰のサッカーチームと提携
2019.09.10
スペイン強豪・エスパニョールに学生トレーナーを現地派遣など
柔整・鍼灸養成校で全国初
全国に柔整・鍼灸の養成校を複数持つ平成医療学園が、サッカーの世界最高峰・スペイン1部リーグ所属の『RCDエスパニョール』とトレーナー研修に関するパートナーシップ契約を締結した。柔整科・鍼灸科を設置する学校法人では全国初。
8月21日には大阪市内の同専門学校で調印式を行い、岸野雅方理事長は「日本のみならず、世界のサッカーの発展に貢献できるトレーナーを育成していきたい」と述べた。エスパニョールでメディカル部門の責任者を務めるマノロ・ゴンザーレス氏(理学療法士)も同席し、トップチームから育成年代まで全カテゴリーの選手を抱える同チームの医療体制を説明し、「医療への投資が今、積極的に行われ、世界的に広がっている」とスポーツ医療の現状を語った。
今後、両者間ではトレーナー養成の交換研修制度(2日~2週間の滞在)を実施するほか、同学園の学生を最長1年間のインターン生として現地スペインに派遣していく予定という。調印式後は、ゴンザーレス氏により、同チームで実践しているトレーニング・リハビリのプランの立て方や故障者の競技復帰までの対応などの講演が行われた。