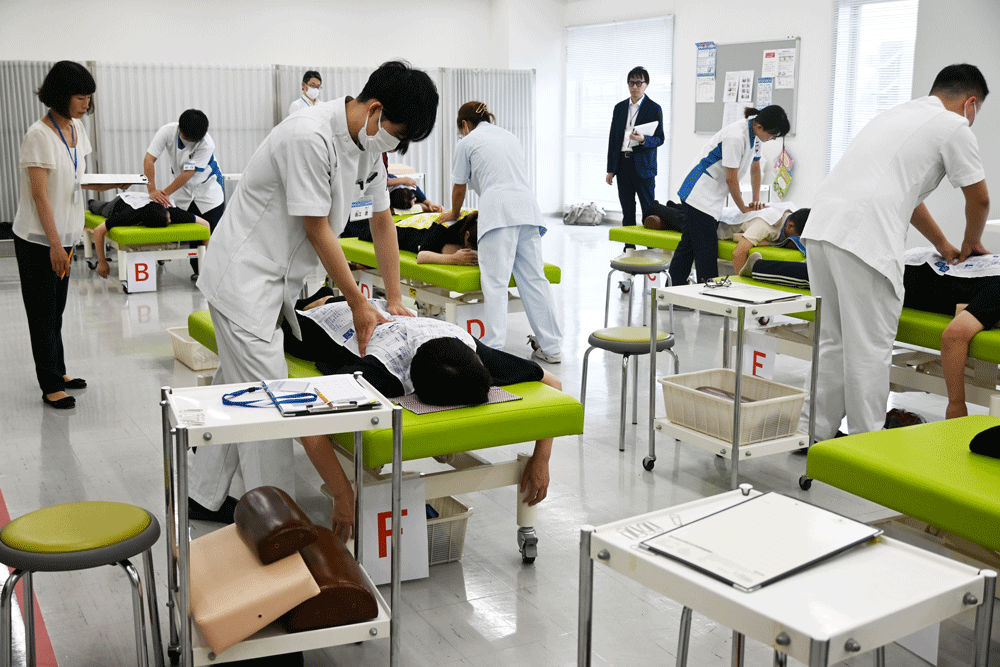連載『先人に学ぶ柔道整復』十八 アンブロアズ・パレ(中編)
2019.11.25
―戦場で経験と実証を重ねた外科医―
パレの生きた16世紀のヨーロッパは、麻酔も消毒もなかったため、外科処置の際、患者を縛り付けたり、時には額に一撃見舞わせて失神させたりして手術するような時代でした。戦場では血や膿にまみれながら傷の手当てをし、銃弾を摘出し、脱臼・骨折を治し、手足を切断するなども外科医には重要な仕事でした。このような時代に、優れた外科治療と書を残し、外科学の地位向上に貢献したパレのエピソードを『大外科全集』の「弁明と旅行記」から見てみたいと思います。
1510年に生まれたといわれているパレは、少年時代をフランス北西部のラヴァルで過ごしました。兄や親戚が床屋外科医で、パレも幼い頃からこの道を目指したと思われます。20歳になる頃、パリに出て本格的な訓練を行い、パリ唯一の公立病院「オテル・デュー」でのポストを得ました。その後の1537年、床屋外科医として、フランス軍のトリノ遠征に随行することとなりました。パレはモンテジャン侯ルネの隊に専属。ルネ一行がパリからトリノまでの最大の難所であるアルプスを越え、イタリア国境近くのスーサの峠に差し掛かったところで、敵軍と初めて衝突します。ルネの分遣隊長であったル・ラ大尉が脚に被弾し、この治療をパレは命じられました。これまで都会であるパリの病院で外科訓練は受けていましたが、銃創の処置は経験の少ない分野でした。ベテラン外科医から「銃弾には毒があるから熱油で焼灼すべし」と習ったことなどを思い出し、パレはできるだけ熱くした油に麻布を浸して大尉の傷を慎重に焼灼しました。大尉は激痛に耐え、治療は成功。後年、パレはこの経験を「私が処置をし、神がこれを癒し給うた」という言葉で残しています。
ある時、治療中に油が足りなくなったことがありました。助手を調達に走らせましたが、他の床屋外科医も同様に不足していました。「毒という点を除けば、銃創も矢の傷も大差ない……」とパレは考え、助手に卵黄とテレピン油で軟膏を作らせ、これを塗っておいた包帯を傷口に巻いてみました。兵士たちはあの熱油の激痛を免れたと大喜びしましたが、パレは「明日、毒が全身に回って死んでしまうのではないか」と気が気でありませんでした。その夜、パレは一睡もできず、夜も明けないうちにそっと患者小屋をのぞきました。軟膏治療した兵士たちは傷の痛みも腫れもなく、静かに休んでいたのです。一方、従来の熱油治療を受けた兵士たちは熱を出し、患部は腫れて痛み、眠れずにうなっていました。パレはこれまでの療法がいかに間違っていたかを認識し、以後、熱油による治療は用いまいと心に誓い、同時に経験に基づく実証を重視した本を書こうと思い立ちました。
パレは初めてとなる著書『火縄銃その他の創傷の治療法』を1545年に出版します。床屋外科医たちが戦地でも役立てられるよう64ページの小型サイズで、パレの軍医経験を含めた本文と23の木版画で構成。硬めの装丁で安く印刷されていました。同書は教養の必要なラテン語ではなく、平易なフランス語で書かれた科学書として最も古い書の一つにランクされています。
参考文献:
森岡恭彦編著『近代外科の父・パレ』(1990年)日本放送出版協会
【連載執筆者】
湯浅有希子(ゆあさ・ゆきこ)
帝京平成大学ヒューマンケア学部柔道整復学科助教
柔整師
帝京医学技術専門学校(現帝京短期大学)を卒業し、大同病院で勤務。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科博士後期課程を修了(博士、スポーツ科学)。柔道整復史や武道論などを研究対象としている。