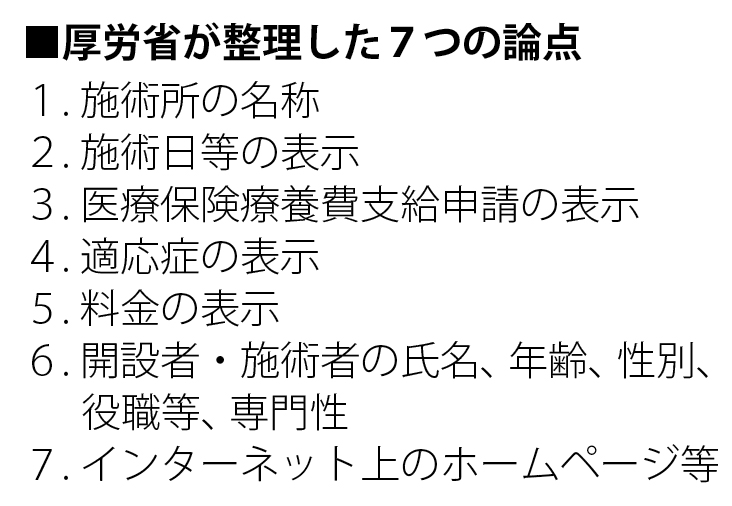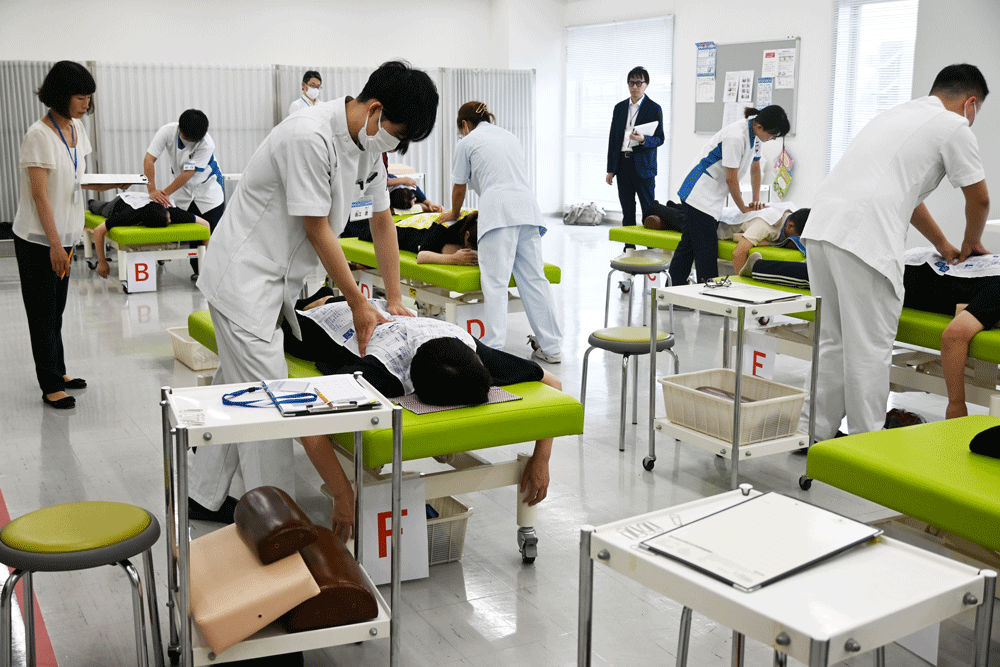接骨医学会の第27回学術大会 『佛手仏心』テーマに
2018.12.25
―医師で柔整校学長の米田氏講演―
一般社団法人日本柔道整復接骨医学会(櫻井康司会長)の第27回学術大会が11月17日、18日、ウインクあいち(名古屋市中村区)で開催された。大会テーマは、『佛手仏心―柔道整復師が患者様のためにできること』。
特別講演は、米田病院院長・米田柔整専門学校学長の米田實氏が、『「仏の心」と「柔(道)の心」に共通するもの―柔道はなぜ柔道整復師に欠かせないのか』をテーマに登壇した。「仏手仏心」という父・一平が唱えた標語に言及し、「外科医の理想」と言われる仏典からの言葉である「鬼手仏心」が語源で、「鬼」を「仏」に言い換え、手術も薬も使わない徒手の保存療法を慈悲深い「仏の心」で行う大切さを説いていると説明した。また、柔道の「受身」は「良い学習ツール」だと強調し、「自分を守り、相手をかばう」といった柔道の創始者・嘉納治五郎の教えに立ち返り、実践しなければ危険を招いてしまうと述べた。この嘉納の「柔(道)の心」は、「仏手仏心」とともに、聖徳太子の「和の心」やWHOの「ケアの概念」とも共通性を見いだすことができ、東洋的かつ普遍的な思想が根底にあると語った。祖父・松三、父・一平と続く同病院の保存療法重視の診療体制にも触れ、米田氏自身が診た新患のうち、約40%が接骨院からの紹介であるなど医接連携の現状を報告した上で、腰椎分離症の早期発見・治療の重要性やアキレス腱断裂に対する早期加速リハによる治療法についても解説した。
「外傷に対する技術の伝承」をテーマとしたシンポジウムでは、整骨院勤務の立場から深澤晃盛氏(野島整骨院)と佐藤隆史氏(さとう接骨院)、整形外科勤務の立場から堀口忠弘氏(堺整形外科医院)と早川雅成氏(宏友会接骨院)の計4名が登壇。それぞれ修行時代には数多くの新鮮外傷に遭遇し、整復・固定技術を研鑚したという。深澤氏は、小児上腕骨顆上骨折等の症例を紹介しつつ、指導する側・される側の「整復師としての思い」を同調させることが不可欠で、技術伝承には精神面も大きな要因となると強調。佐藤氏は、足関節の包帯固定を行う際のアーチパッド作製等の経験を例に、工夫や失敗を重ねて技術のアップデートを繰り返すべきであるとし、すぐそばで熟練の柔整師が助言をくれる接骨院という場の重要性も説いた。堀口氏は、整形外科内では医師との意思疎通が必須なことから勉強会も多く、しかも内容は医師国家試験レベルだと説明。ベテラン柔整師が新人を育成する仕組みも整ってはいるが、治療技術が特殊になればなるほど、一緒に患者を診るなど同じ時間を共有しないと伝承は困難だと話した。早川氏は、「メスを使わない保存療法は究極の未来の治療であり普及すべき技術」との師である整形外科医の言葉が印象に残っていると紹介。自身が考案・制作した、骨折のタイプ別でどの徒手整復手技が適しているか選択するといった「分類表」にも言及し、治療後の検証と技術の体系化は重要で、結果として医師の理解も促すと話した。
このほか、実践スポーツ医科学セミナー『カーリングにおける競技力向上の取り組み』(柳等氏・北見工業大学)や40歳以下の若手柔整師によるディスカッション、各分科会フォーラム、会員・学生による発表などが行われた。