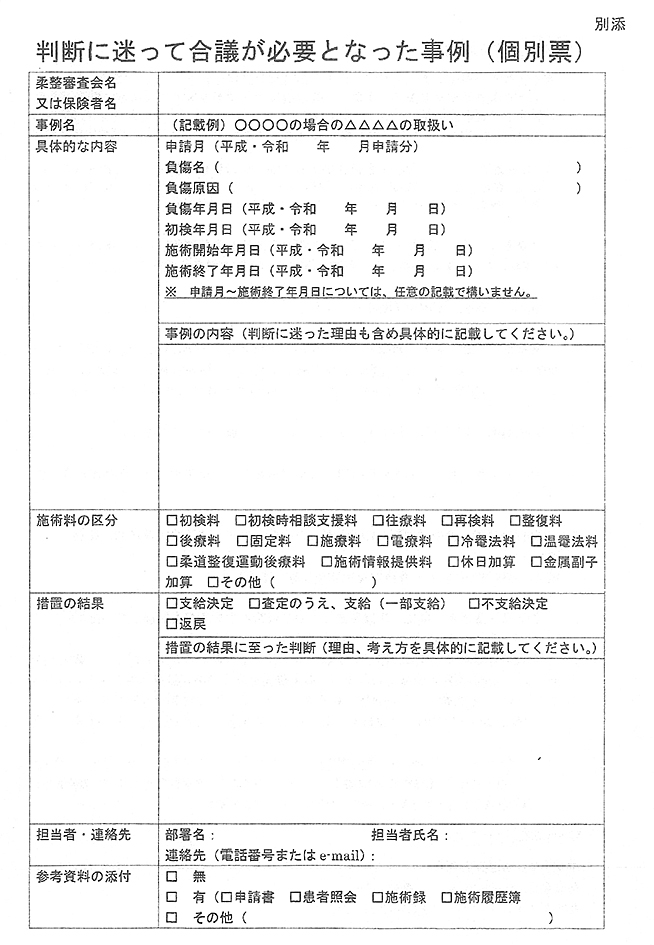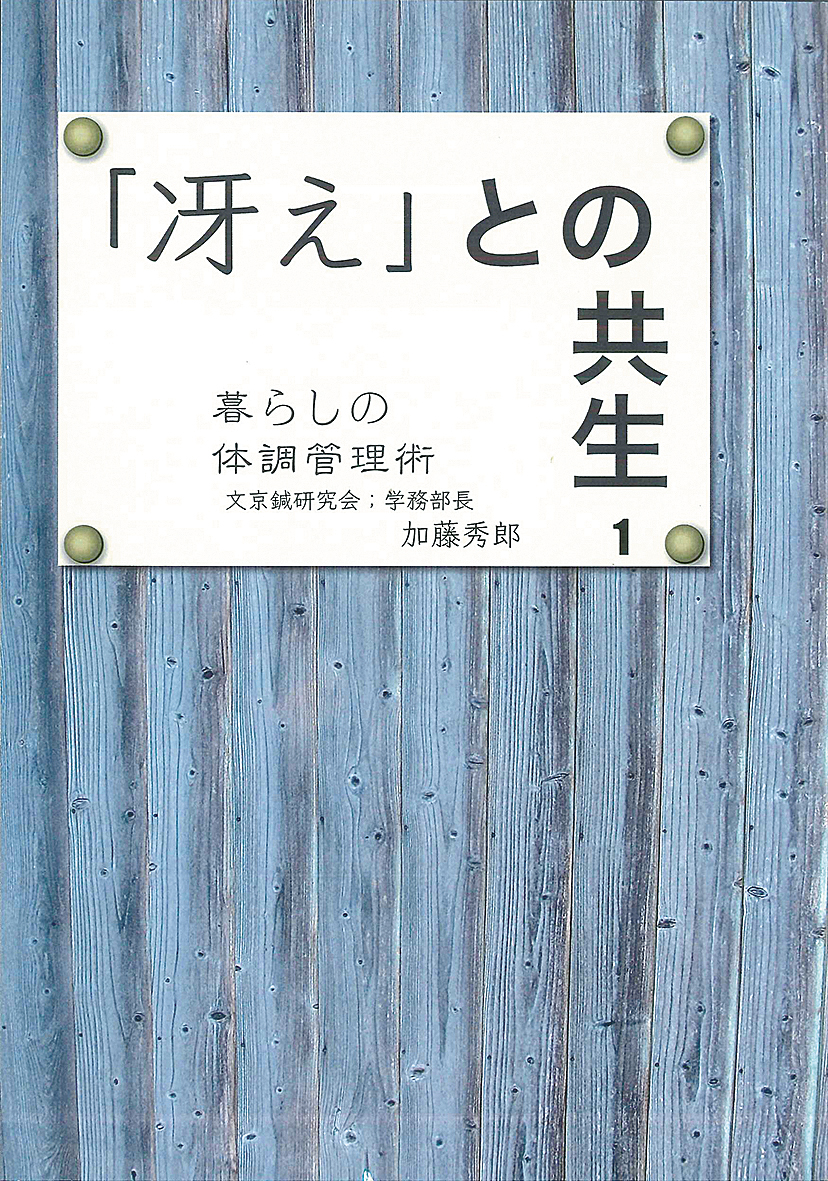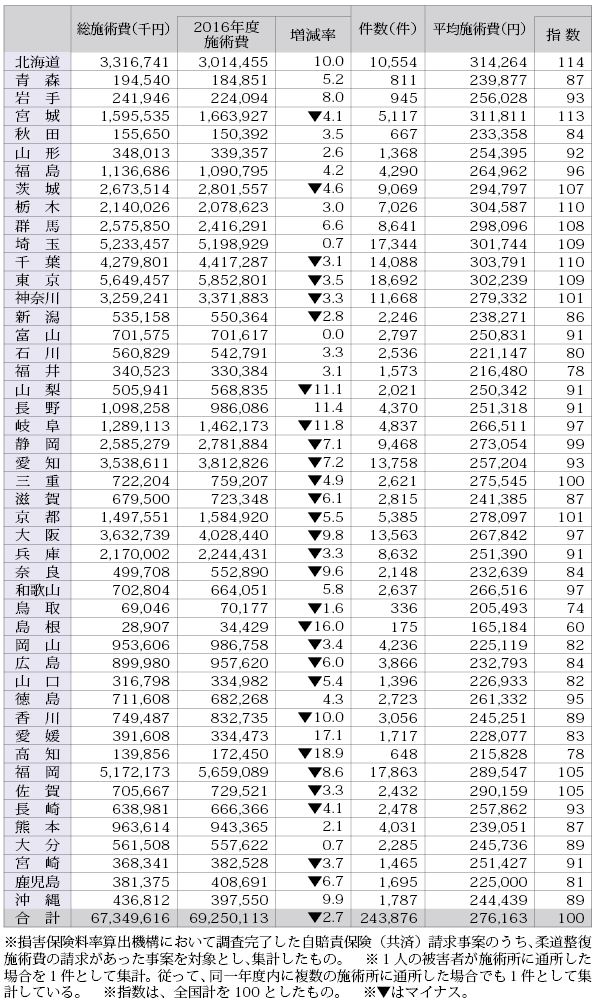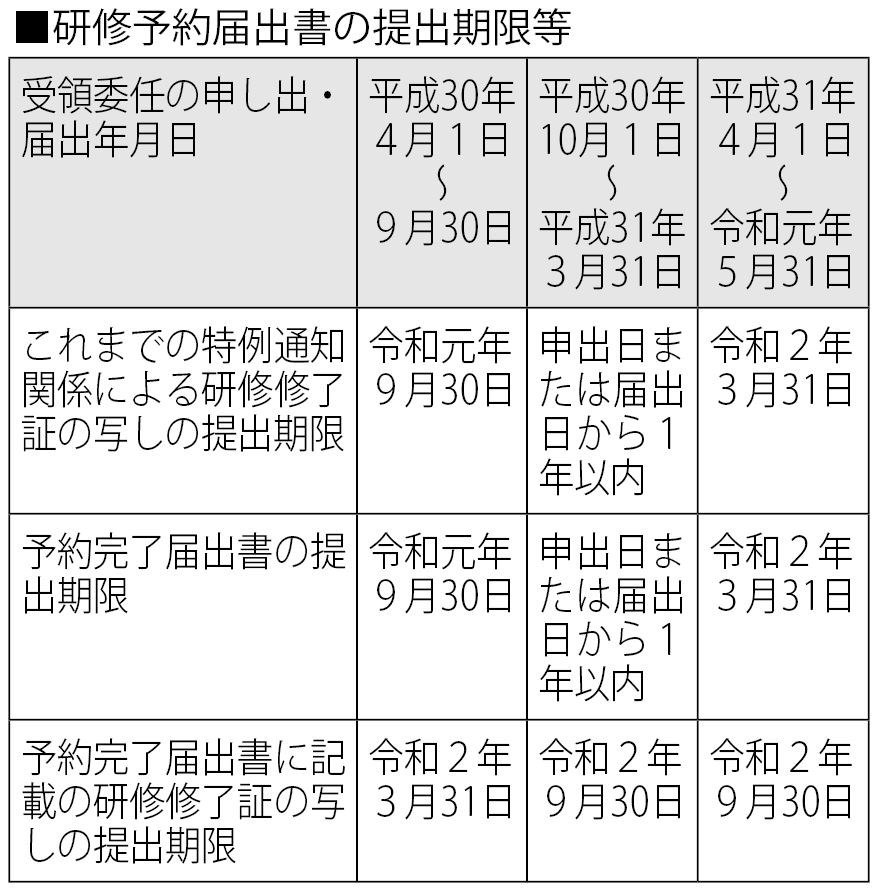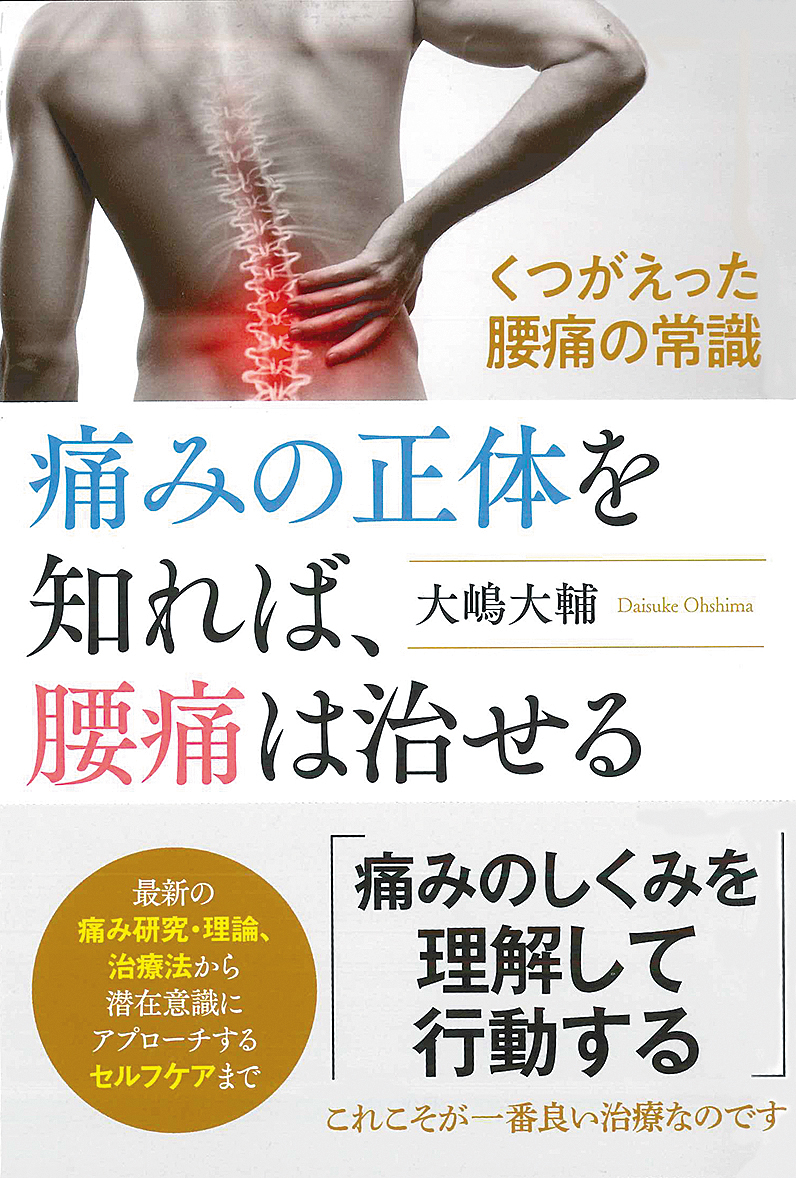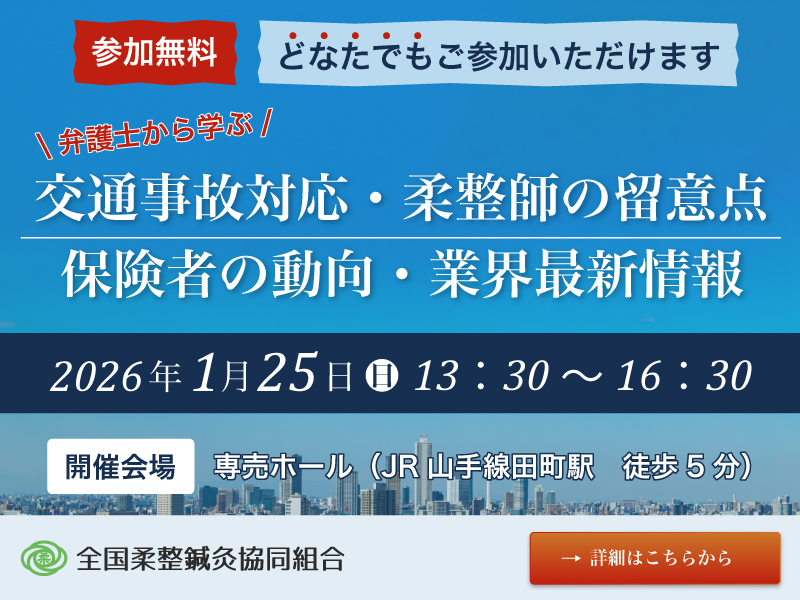桜雲会、医歯薬出版から新刊 『「冴え」との共生 1 暮らしの体調管理術』など
2019.08.25
桜雲会から新刊
「冴え」との共生 1 暮らしの体調管理術
社会福祉法人桜雲会から新刊『「冴え」との共生1―暮らしの体調管理術』が発行された。著者は文京鍼研究会学務部長の加藤秀郎氏。A5判387頁。本体価格2,400円。
鍼灸師の著者が新時代に遺す、古典医学の健康理論。シリーズ1では、人体がどのようにして生理活動をしているか、生理活動の理由は何なのかを、人類の発祥や文明、大自然、食べ物などから考える。著者は冒頭で、「冴え」とは頭の回転の速さでも勘の鋭さでもなく、学習を経由したことで発揮される、人間のみにある新たな本能かもしれないと指摘。この危機察知能力を自分自身の健康管理に使ってみようというのが、本書で言う「冴えとの共生」であると述べている。
医歯薬出版から新刊
実践 鍼灸美容学 第2版
医歯薬出版株式会社から新刊『実践 鍼灸美容学 第2版』が発行された。著者は『わかりやすい臨床中医実践弁証トレーニング』などの著書で知られる王財源氏(関西医療大学教授)。A4判168頁。本体価格4,200円。
前半では、鍼灸美容学の基礎から美容を乱す外部環境などの原因に対する考え方や、「からだ全体で診る」中医美容学を紹介。後半は刺鍼(灸)操作法として、シワに対する具体的な鍼の施術法や皮膚に瘢痕や火傷を残さないヨモギ蒸し、あぶり灸法を用いた「湧泉燻蒸法」「大椎燻蒸法」などの新しい術式を図説。進化系接触鍼、現代科学からみた「審美六鍼」の効果なども解説した、「鍼灸・美容関係者の必携書」と同社。
※読者プレゼントの応募期間は終了しました