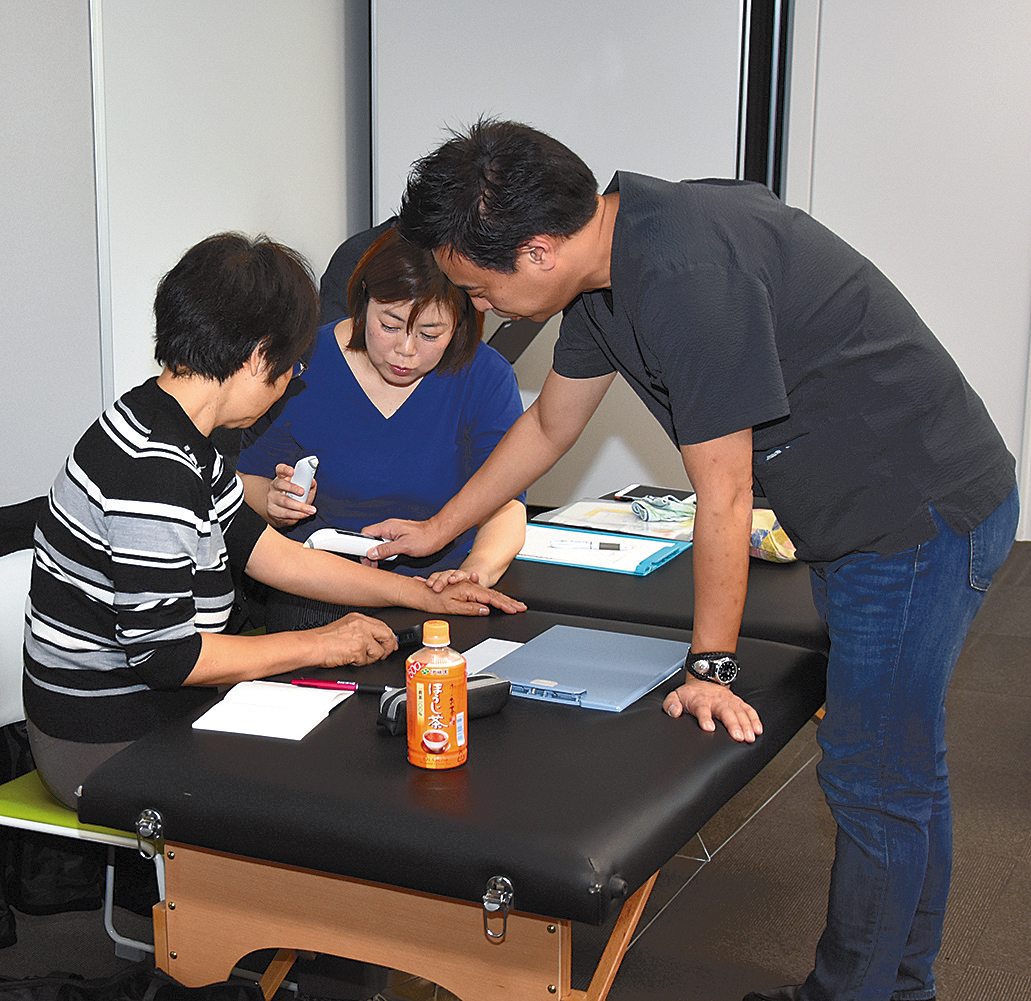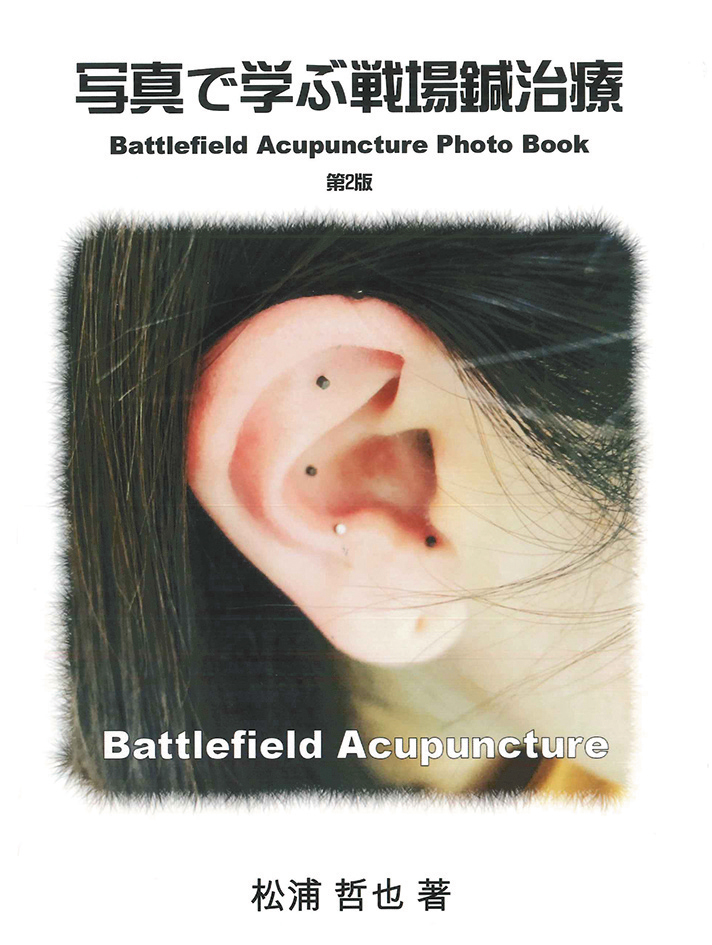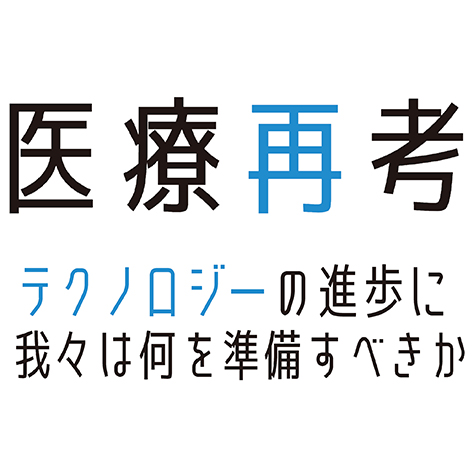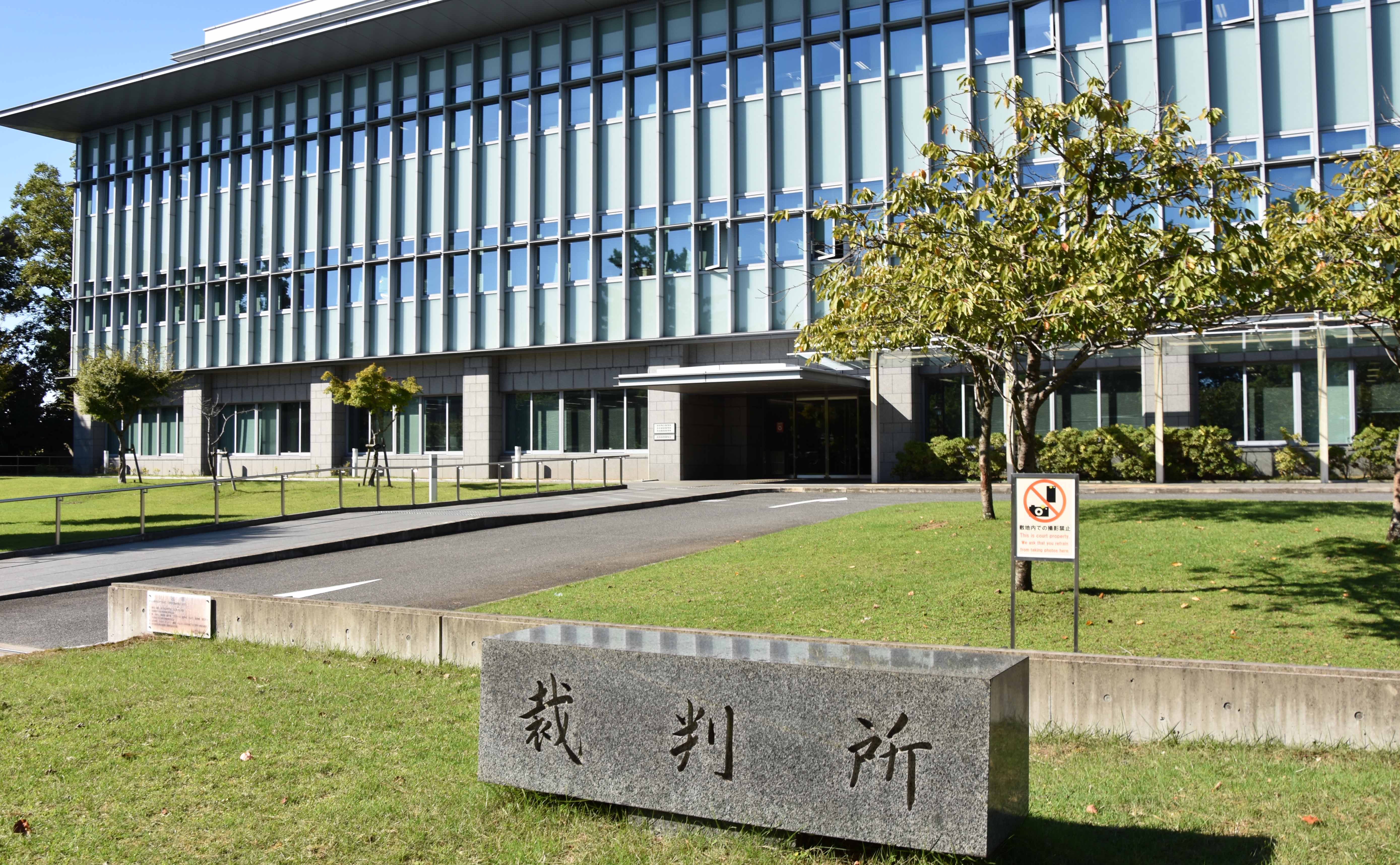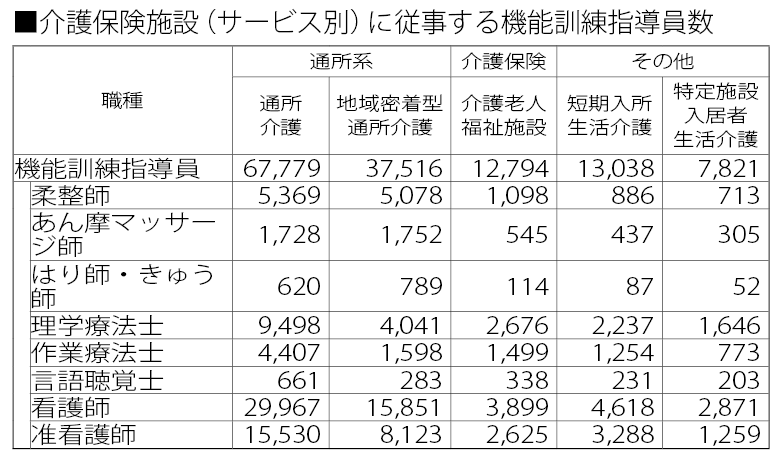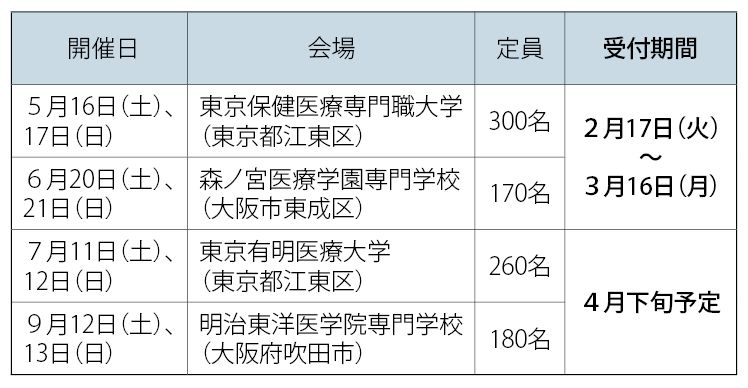晴眼者のあマ指師課程新設をめぐる裁判の東京地裁判決〈要旨〉
2019.12.25
1111号(2019年12月25日号)、あマ指師課程新設をめぐる裁判、紙面記事、
主 文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事案の概要
本件は、原告・平成医療学園が、運営する横浜医療専門学校について、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下、あはき師法)に基づき、視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師養成施設の認定の申請をしたところ、厚生労働大臣が、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があるとして、同法19条1項に基づき、認定をしない旨の処分をしたため、原告において、19条が憲法22条1項(職業選択の自由)等に違反して無効であるなどとして、処分の取り消しを求める事案である。
あはき師法19条1項制定(昭和39年)後の状況等
【視覚障害者の数、就労状況等】
●視覚障害者数の状況
①昭和30年から平成18年までの視覚障害者の総数(18歳以上の推計値)は、昭和35年が20万2,000人、昭和40年が23万4,000人、昭和62年が30万7,000人、平成18年が31万人である。
②昭和34年から平成26年までの身体障害者手帳交付台帳登載数における「視覚障害」の登載数(18歳未満を含む)は、昭和35年が18万3,530人、昭和39年が24万820人、平成18年が38万9,603人、平成26年が34万9,328人である。平成27年の同登載者数は、18歳以上が33万8,994人、18歳未満が5,044人である。
●視覚障害の就労状況の推移
①昭和30年から平成18年までの視覚障害者の有職者数及び就業率は、昭和35年が7万2,114人(35.7%)、昭和40年が7万5,000人(32.0%)、昭和62年が6万8,154人(22.2%)、平成18年が6万6,340人(21.4%)である。
②昭和40年から平成18年までの視覚障害者の不就業者数及び不就業率は、昭和40年が15万9,000人(68.0%)、昭和62年が23万7,925人(77.5%)、平成18年が22万7,540人(73.4%)である。
●あん摩・マッサージ・はり・きゅう関係の業務の割合
①昭和30年から平成18年までのあん摩・マッサージ・はり・きゅう関係業務に就いている視覚障害者の数及び有職者に占める割合は、昭和35年が2万7,548人(38.2%)、昭和40年が1万8,825人(25・1%)、昭和62年が2万6,989人(39・6%)、平成18年が1万9,637人(29.6%)である。
②平成18年度から平成26年度までのハローワークにおける重度の視覚障害者に対する職業紹介の全体件数の中であん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許を基礎とした職業が占める割合は、70.8%から75.0%の間で推移している。
③平成15年の実態調査によると、視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けているあん摩マッサージ・はり・きゅう業者の83.8%が、障害等級1級と2級を合わせた重度の視覚障害者である。
●あん摩・マッサージ・はり・きゅう以外の就業状況
①視覚障害者の有職者の就いている職種のうち、農業・林業・漁業の割合は、昭和40年が36.5%、平成18年が8.6%、あん摩・マッサージ・はり・きゅうを除く専門的技術的職業の割合は、昭和40年が2.6%、平成18年が11.1%、事務の割合は、昭和40年が1.7%、平成18年が7.4%である。
②平成27年度のハローワークにおける視覚障害者の就職内訳は、運搬・清掃等の職業が16.5%、事務的職業が13.4%、サービスの職業が8.3%である。
●あん摩マッサージ指圧師の収入状況
①平成25年のあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の年間収入(税込ベース)の平均値は、全体が571万2,000円、視覚障害者以外の者が636万2,000円、視覚障害者が290万円である。このうち、視覚障害者の年間収入の最大値は1,000万円、中央値は180万円、最頻値は200万円であり、年間収入300万円以下の割合は76.3%である。
②平成14年分のあん摩マッサージ・はり・きゅう業者の施術料収入(税込ベース)においては、年間施術料収入300万円未満の業者の割合は、全体で46.7%、視覚障害者で58.0%である。同じ年に、視覚障害者であるあん摩マッサージ・はり・きゅう業者の63.4%が施術料以外の収入を得ており、そのうち84.5%が公的年金による収入である。
●視覚特別支援学校の生徒数及び卒業者の就職状況等
①昭和38年から平成29年までの視覚特別支援学校の在籍生徒数、学校数、高等部学科別生徒数、高等部本科卒業者の進路・就職先等は、高等部本科の保健理療科並びに高等部専攻科の理療科、保健理療科及び理学療法科の生徒数の割合が減少している。
②視覚障害のある新卒者のあん摩マッサージ指圧師国家試験の受験状況は、平成18年が受験者数615名、合格者数521名(合格率84.7%)、平成28年が受験者数355名、合格者数288名(同81.1%)である。同じ年の視覚障害者以外の新卒者の合格率は、平成18年が98.6%、平成28年が97.0%である。
【あん摩マッサージ指圧師の総数及び視覚障害者以外の者が占める割合】
昭和37年におけるあん摩師の総数は5万1,477人であり、このうち視覚障害者以外の者が占める割合は40.1%(2万619人)である。これに対し、平成26年におけるあん摩マッサージ指圧師の総数は11万3,215人であり、このうち視覚障害者以外の者が占める割合は77.0%(8万7,216人)である。
【あん摩マッサージ指圧師の養成施設等の定員及び視覚障害者以外の者が占める割合】
平成9年度から平成27年度までのあん摩マッサージ指圧師の養成施設等の数及び定員の推移は、平成10年度が1学年の定員3,003人、平成27年度が1学年の定員2,706人である。このうち視覚障害者以外の者の定員が占める割合は、平成10年度が40.3%、平成27年度が45.8%である。昭和39年度のあん摩師の養成施設等の定員における同割合は36・8%である。
【視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等の設置状況】
平成27年度において、視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等は、10都府県(宮城県・埼玉県・東京都・神奈川県・静岡県・愛知県・京都府・大阪府・香川県・鹿児島県)に合計21施設あり、その1学年の定員は合計1,239人である。
【あん摩マッサージ指圧師の養成施設等の視覚障害者以外の者の受験者数】
平成27年度の厚生労働省所管の視覚障害者以外の者を対象とする養成施設の定員数に対する受験者数の割合は、あん摩師の昼間養成施設が149・2%、同夜間養成施設が118・6%、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の昼間養成施設が202.3%、同夜間養成施設が296.6%である。
障害者福祉等に関する法令の整備状況
【障害者福祉に関する法律】
昭和24年、最初の障害者福祉の法律として、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)が成立した。同法の目的は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)と相まって、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ること」(1条)とされている。
【障害者雇用に関する法律】
昭和35年、障害者雇用対策について、身体障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)が成立し(昭和62年に「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改名)、昭和51年には、民間企業の努力義務であった法定雇用率制度を義務化するとともに、法定雇用率を満たしていない事業主から納付金を徴収し、障害者を多く雇用している事業主に対して調整金等を支給する制度が導入された。同法48条1項及び政令の規定により、あん摩マッサージ指圧師は、労働能力はあるが、障害の程度が重いため通常の職業に就くことが特に困難である身体障害者の能力にも適合すると認められる職種である特定職種に、特定身体障害者の範囲を視覚障害者として唯一指定され、国及び地方公共団体は、一定の視覚障害のあるあん摩マッサージ指圧師の職員の採用に関する計画を作成することを義務付けられている。
【障害者施策に関する基本的な法律】
昭和45年、各省庁が所管する障害者関連の個別法律を指導する障害者施策に関する基本的な法律として、心身障害者対策基本法(昭和45年法律第84号)が成立し(平成5年に「障害者基本法」に改名)、政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者基本計画を策定しなければならないとされている。
【障害福祉計画に関する基本指針】
平成17年、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)が成立し(平成24年に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改名)、他の障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とし、自立訓練(リハビリ等)、就労移行支援等に関する訓練等給付費の給付や市町村又は都道府県が行う障害者等の地域生活支援事業に関することのほか、国が障害福祉計画に関する基本指針を定めることなどが定められている。
【障害者差別の解消に関する法律】
平成25年、障害を理由とする差別の解消を推進し、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく共生する社会の実現に資することを目的として、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が成立した。同法では、国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならないとされ、国民においても、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならないとされている。
【障害年金制度】
国民年金法は、障害等級を障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、その状態のある者に障害基礎年金を支給する旨を定め、その年金額は、2級が年額78万900円に改定率を乗じて得た額、1級がその100分の125に相当する額とされている(同法33条)。
また、昭和61年度以前は、20歳未満の時に初診日がある傷病による障害者には障害福祉年金が支給されていたが、同年度以後は、障害基礎年金に裁定替えされ、このような無拠出型の基礎年金についても、拠出型の基礎年金とほぼ同様の取扱いとなった。
裁判所の判断(争点・職業選択の自由の適合性について)
■立法の目的
原告は、あはき師法19条1項の制定から50年が経過し、その立法の目的は、正当性を失っている旨主張するので、以下、検討する。
①原告は、19条1項は、昭和22年の同法制定の際に所定の届出をした医業類似行為業者に限っては、期限を定めて医業類似行為の禁止が猶予されていたものが、昭和39年改正において、この期限が外され、猶予が事実上一代限り継続することになったため、これに異議を唱えていた視覚障害者に対する融和策として設けられた規定であり、19条1項の「当分の間」とは、上記の届出医業類似行為業者の高齢、死去等により業が行われなくなるまでと解すべきであるから、19条1項の制定から50年を経過した以上、既に同期間は経過している旨主張する。
しかしながら、19条1項の制定経緯をみると、従前より、国会等において視覚障害者であるあん摩師等の職域の保護を求める意見がみられ、昭和34年頃には、中央審議会の要望を受けて、視覚障害者以外のあん摩師の養成学校等の新設及び生徒の定員増加を抑制する行政措置がとられ、昭和36年のあはき師法改正時において、視覚障害者であるあん摩師の職域優先確保のための法的措置を速やかに検討・実施することが附帯決議されていたこと、その後、中央審議会において、あん摩師を保健あん摩師と医療マッサージ師とに分けた上、保健あん摩師について視覚障害者の職域を優先的に確保するという意見が採択されたが、この意見については一部の関係団体から強い反対があったことから法案提出には至らず、議員提出法案の形で、上記意見に代わる視覚障害者の職域優先措置として、19条1項が制定されたことが認められる。
これらの制定経緯からすれば、19条1項は、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の職域を優先することを専らの目的として制定されたものというべきであり、19条1項の「当分の間」も、視覚障害者に関し、あん摩マッサージ指圧師以外の適職が見出されるか、又は視覚障害者に対する所得保障等の福祉対策が十分に行われることにより、視覚障害者がその生計の維持をあん摩関係業務に依存する必要がなくなるまでの間を意味するものと解するのが相当である。
19条1項の規定に「当分の間」との文言を挿入することが、届出医業類似行為業者に係る禁止猶予期限を撤廃することと関連づけて議論されていた形跡はうかがわれず、原告の主張は採用できない。
②原告は、視覚障害者をめぐる福祉・補償の法制度が整備され、社会のバリアフリー化により職業の選択の幅も広がり、視覚特別支援学校においても生徒数が減少し、あん摩マッサージ指圧を履修する生徒も激減するなど、視覚障害者のあん摩マッサージ指圧師業への依存度は減ってきており、障害年金制度の拡充等により視覚障害者の生計が改善し、国の法律や政策における障害者像も変化した現在では、19条1項の目的は正当性を失っている旨主張する。
確かに、19条1項が制定された昭和39年当時と現在とを比較すると、障害者に対する年金制度(障害年金)が拡充されるなど障害者の福祉等に関する法制度が更に整備され、パソコン等のICT技術の普及により、視覚障害者には、事務的職業等の職業選択の道が開かれるようになるなど、視覚障害者をめぐる社会事情は変化してきていることが認められる。
しかしながら、一方で、視覚障害者の総数は減少しておらず、視覚障害者の就業率は現在も低水準となっており(平成18年で21.4%)、就業者の中ではあん摩・マッサージ・はり・きゅう関係業務に就いている者の割合がなお高い状況にあり(平成18年で29.6%)、重度の視覚障害のある有職者に至っては、7割を超える者があん摩・マッサージ・はり・きゅう関係業務に就いていることが認められる。
また、視覚特別支援学校における生徒数やあん摩マッサージ指圧関係の科目を履修する生徒が減少しているとしても、平成28年において、視覚障害のある新卒者のうちの相当数(355名)があん摩マッサージ指圧師国家試験の受験をしていることが認められる。そうすると、視覚障害者におけるあん摩マッサージ指圧師業の重要度が特別な保護を必要としない程度にまで低下したとみることは相当ではない。
さらに、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の収入をみても、平成25年時点で年収300万円以下の者が約76%を占めており、また、障害年金は必ずしも視覚障害者全員が受給できるものではなく、実際、平成14年時点では視覚障害者であるあん摩マッサージ・はり・きゅう業者のうち約半数が公的年金を受給していなかったことからすれば、障害年金制度の拡充等によっても、視覚障害者の生計が更に特別な保護を必要としない程度にまで改善されたとみることは相当ではない。
これらのことからすれば、19条1項の目的の正当性が、現在において失われたと認めることはできない。
■規制の必要性及び合理性
①規制の内容・程度
19条1項は、視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等の設置等について一種の許可制を採用するものであり、養成施設等を設置しようとする者の職業選択の自由を制約する程度の強いものである。一方、養成施設等の設置等を全面的に規制しているわけではなく、諸般の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認められる場面に限っての規制であるから、規制の必要性に係る厚生労働大臣等の判断が適正に行われている限り、その制限は限定的であるといえる。
また、19条1項は、養成施設等の設置等がされないことにより、あん摩マッサージ指圧師の資格を取得するために必要な知識・技能を修得する機会が制限されるという意味において、その資格を取得しようとする視覚障害者以外の者の職業選択の自由を制約しているものである。もっとも、資格を取得しようとする視覚障害者以外の者は、現に設置されている養成施設等に通うことによりその取得が可能となることからすれば、その職業選択の自由に対する制約は限定的である。
②規制の必要性
(ア)視覚障害者は、その障害のため、事実上及び法律上、従事できる職種が限られ、転業することも容易ではないところ、就業率も現在も低水準となっており、重度の視覚障害のある有職者のうち7割を超える者があん摩・マッサージ・はり・きゅう関係業務に就いており、現在においても、あん摩マッサージ指圧師業に依存している状況にある。
他方で、視覚障害者以外のあん摩マッサージ指圧師は、昭和39年頃より増加し、その収入も、平成25年時点であん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の年間収入が平均636万2,000円と、視覚障害者の290万円を大幅に上回っており、視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設の受験者数も平成27年度において定員を大幅に上回っている状況にある。また、19条1項に相当する規定のない隣接業種(はり師、きゅう師及び柔道整復師)においては、柔道整復師養成施設の指定をしない処分を違法として取り消す旨の判決(福岡地裁平成10年8月27日判決)があった平成10年度以降、大幅に養成施設等の施設数及び定員が増加している状況が認められる。
これらのことからすれば、19条1項による制限がなくなれば、視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等の数及び定員が急激に増加し、視覚障害者以外のあん摩マッサージ指圧師の数も急激に増加することが想定され、このような急激な増加は、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の業務を圧迫することになる。
以上によれば、現在においても、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の職域を優先し、その生計の維持が著しく困難とならないようにするという目的を達成するため、視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等の設置及び定員の増加を抑制する必要性の存在を認めることができる。
(イ)これに対し、原告は、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が困難であるとすれば、その原因は、19条1項の存在により、需要に対応できるだけの有資格者が養成できないことによる無資格のあん摩師の急増・跋扈にあるから、必要なことは、有資格者の数を抑制することではなく、無資格者を根絶することにある旨主張する。
しかしながら、19条1項の存在と無資格者の増加との関連性の有無及び程度が実証されているわけではなく、また、視覚障害者が置かれている状況は、医業類似行為業者を含む無資格者の取締りが従前より継続的に行われている中での状況であるから、これらの無資格者の取締りと併せて、19条1項のような養成施設等の規制を行うことが、今なお必要であると認められる。したがって、原告の主張は採用できない。
③規制手段の合理性
(ア)上記のとおりの目的を達成するために必要な規制の手段として、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認められる場合に限り、視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等の設置の認定及び定員増加の承認をしないことができるという手段を採用することは、それ自体合理的なものということができる。
そして、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため規制が必要か否かの判断において勘案すべき事情として、あん摩マッサージ指圧師の総数及びあん摩マッサージ指圧師の養成施設等の生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合を挙げることには合理的な関連性が認められるし、その判断は、その時々における割合のほか、視覚障害者の総数、雇用状況及び医療の状況、社会におけるあん摩マッサージ指圧師に対する需要等の様々な事情に左右されるものであり、その要件や勘案すべき事情を立法者においてあらかじめ詳細に規定することが困難な性質のものであるから、その判断を右記割合のほか諸般の事情に基づく厚生労働大臣等の専門的・技術的な裁量に委ねることとすることも不合理とはいえない。
さらに、あはき師法19条2項は、厚生労働大臣等は、19条1項の規定により認定又は承認をしない処分をしようとするときは、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならないとしている。これは、学識経験等を有する委員により構成される医道審議会の意見を処分に反映させることを意図したものと解され、その委員の構成や議事の運営が適正なものである限り、処分の適正さを担保するための方策として合理的であるといえる。
以上によれば、19条1項による規制には、手段としての合理性が認められる。
(イ)これに対し、原告は、目的を達成するためには、他の妥当な手段として、台湾での成功事例のように障害者が職業的に自立するような政策・立法を行うことや、昭和39年改正当時の中央審議会において検討されていたように一定の地域ごとに施術所の開設を規制することなども考えられるから、19条1項による規制は不合理である旨主張する。
しかしながら、原告の主張するような各種手段が、19条1項による規制よりも明らかに合理性の点で優れており、その反面として19条1項による規制の合理性に疑いがもたれるというまでの事情は認められず、これらの手段の中からどれを選択するかは、正に立法府の政策的・技術的な判断によるものというべきであるから、原告の主張を採用することはできない。
(ウ)また、原告は、19条1項は、①視覚障害者と他の障害者との間、②既に養成施設等を設置していた者とこれから設置しようとする者との間に差別を生じさせるものであるから、手段として合理性がない旨主張する。
しかしながら、①の点は、視覚障害者の生計維持の困難性に着目してその保護を図ること自体がいかなる意味において他の障害者を差別することになるというのか明らかでなく、②の点は、特定の分野への新規参入を規制する立法が一般にもたらす結果であり、規制自体に合理性が認められる限り、そのような結果が不合理な差別に当たるということはできないから、原告の主張を採用することはできない。
■まとめ
以上を総合的に考慮すると、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の職域を優先し、その生計の維持が著しく困難とならないようにすることを重要な公益と認め、その目的のために必要かつ合理的な措置として19条1項を定め、これを今なお維持している立法府の判断が、その政策的・技術的な裁量の範囲を逸脱するもので著しく不合理であるとはいえない。したがって、19条1項は、視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等を設置しようとする者及びあん摩マッサージ指圧師の資格を取得しようとする視覚障害者以外の者の職業選択の自由を制約するものとして憲法22条1項に違反するということはできない。