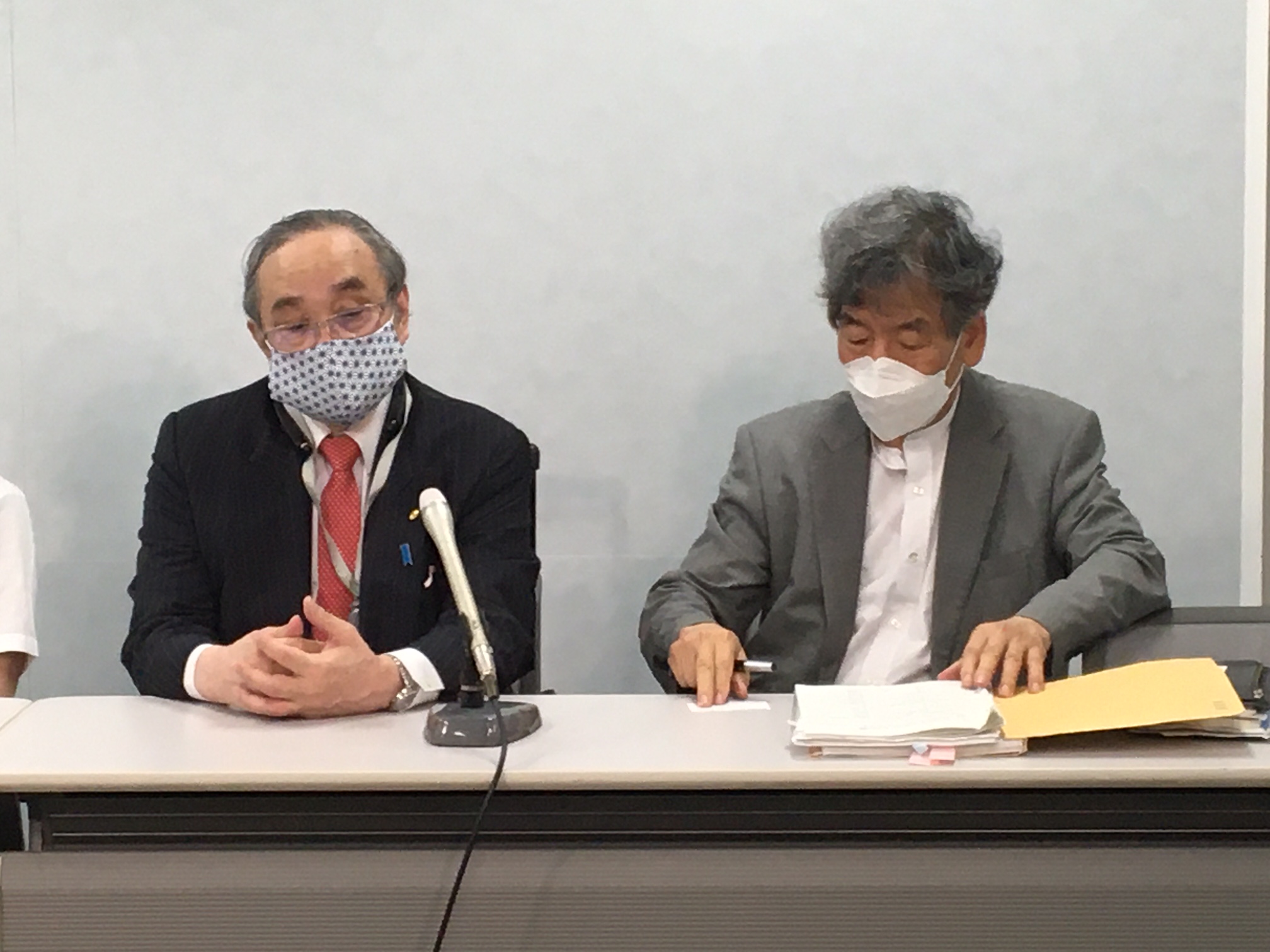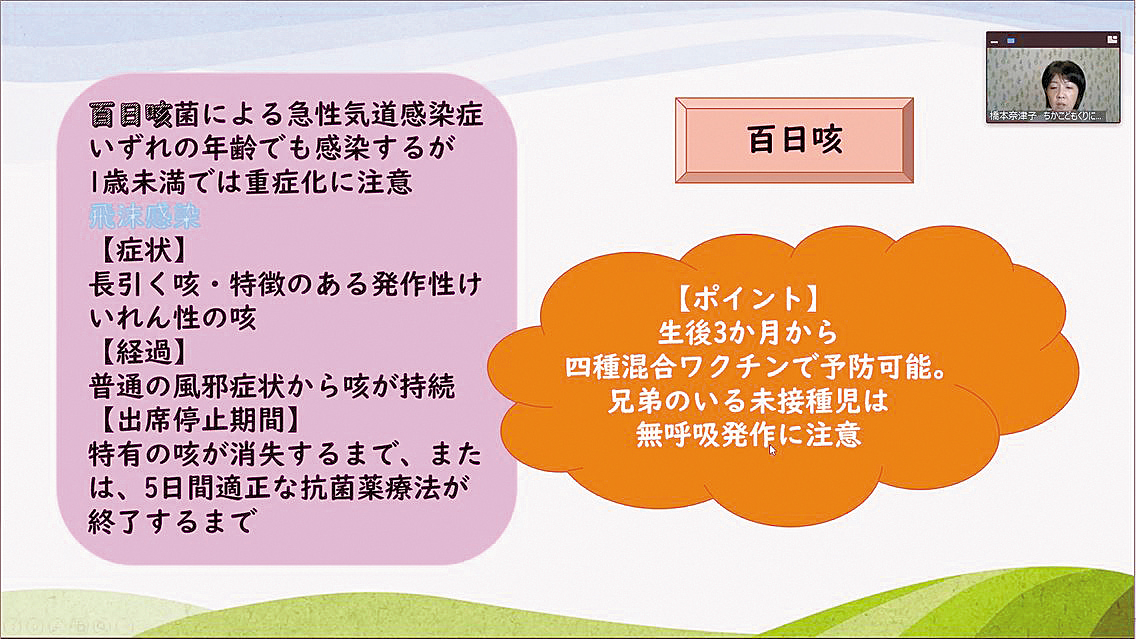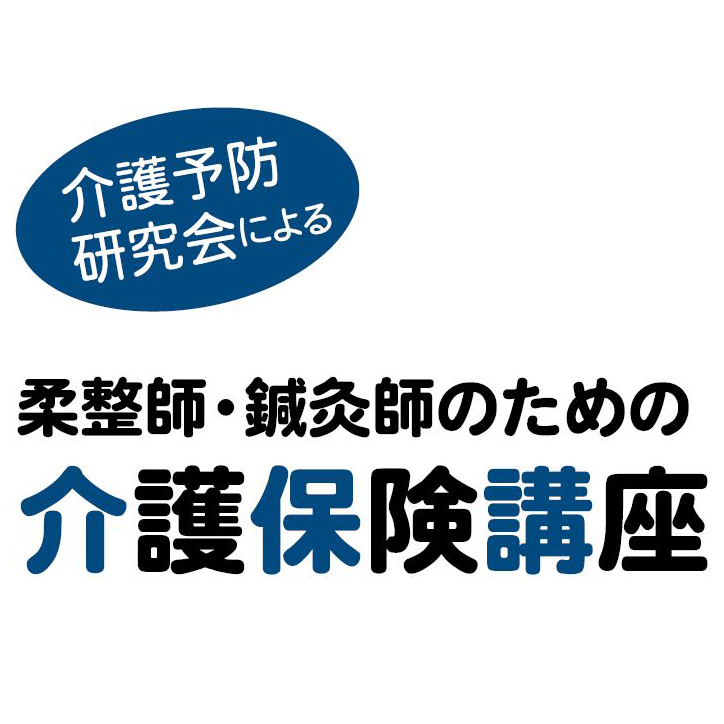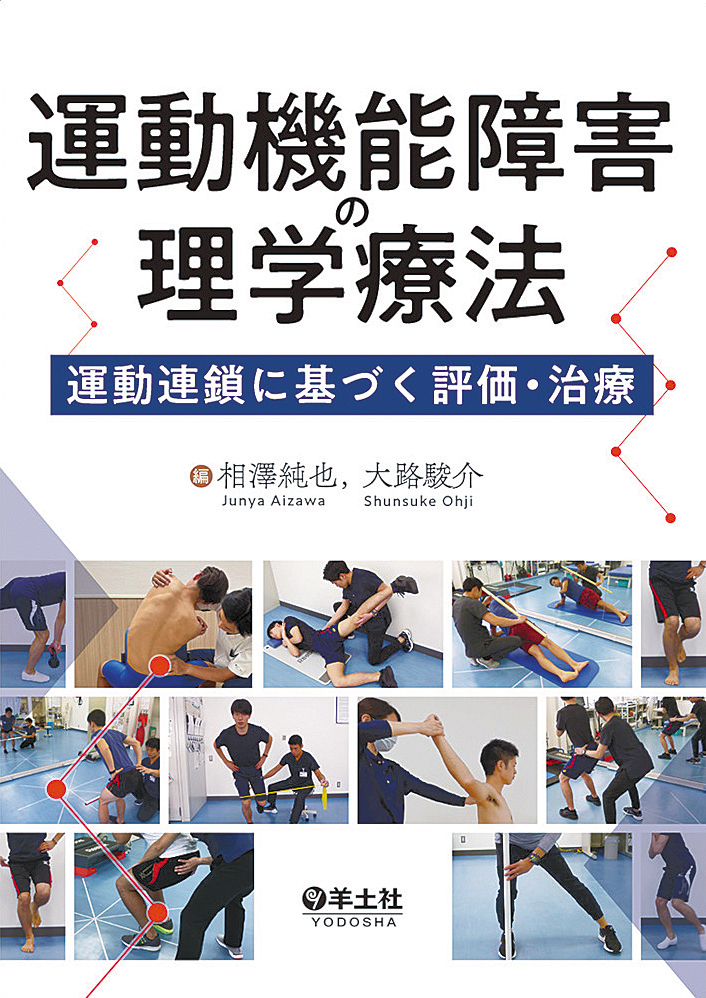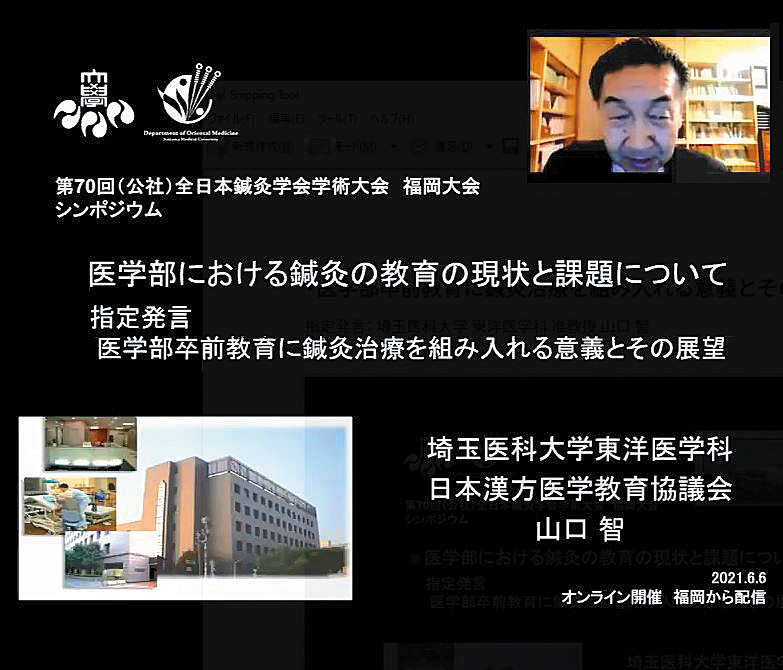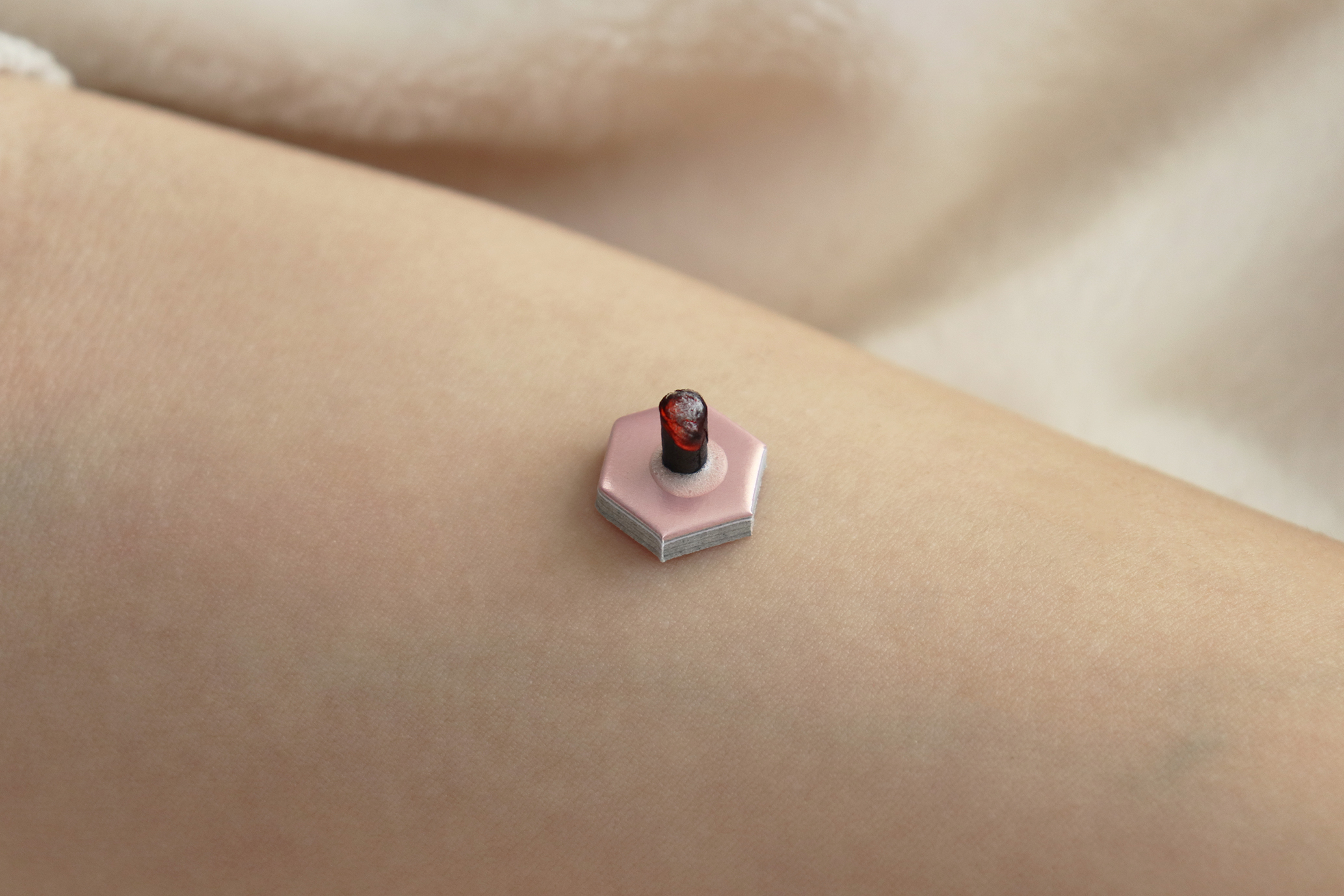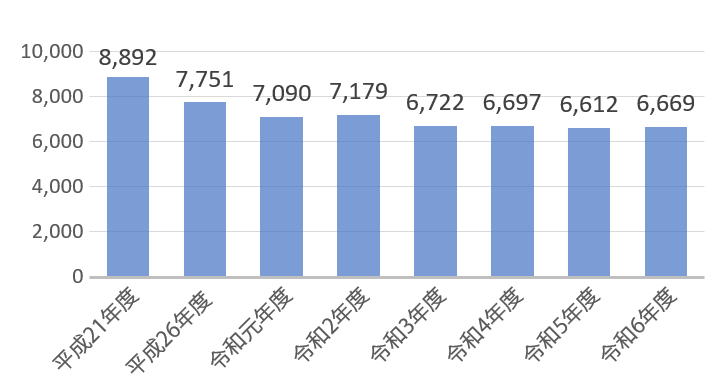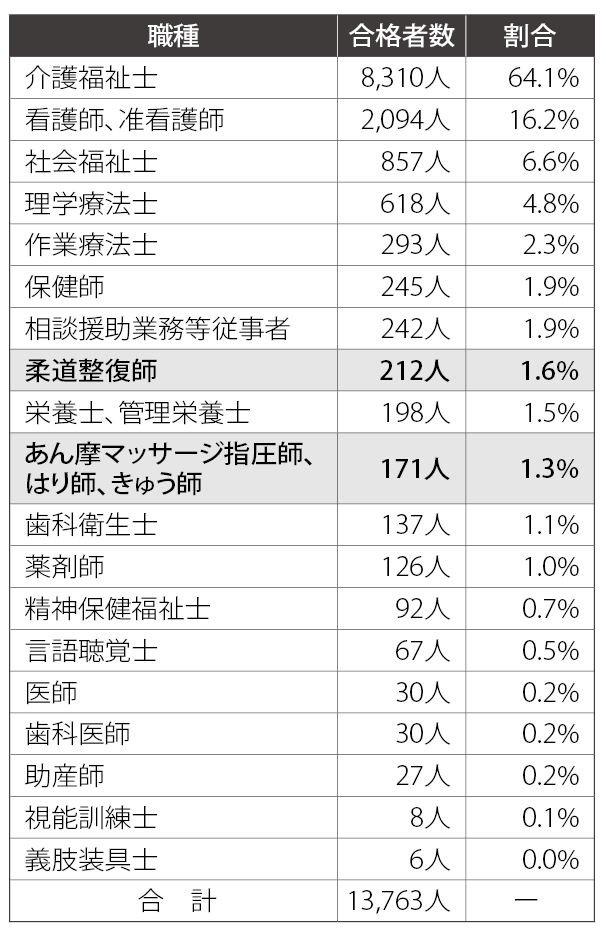編集後記
2021.08.10
▽先日、ある大手ホビー雑誌の編集者が、個人のTwitterアカウントで「転売業者」を擁護して大炎上しました。限定品を買い占めて高額で転売し利鞘を稼ぐ、読者はもちろん業界内の企業にも問題視され続けている脱法的行為……つまるところ弊紙でいえば無資格整体を擁護したようなもの。なんと数日後には本人は退職、編集長と副編集長、常務取締役の上司3名が降格という惨事に……。現代の企業にとっての、SNSの炎上事案の重大さがよく分かります。ちょうど同時期に鍼灸柔整新聞の公式Twitterアカウント(@ShinkyuJusei_np)を開設、「中の人」を担当している身としては思わず背中に嫌な汗が。炎上に気を付けつつ、無料の速報ニュースなども発信していますので、どうぞ一度ご確認下さい。(平)