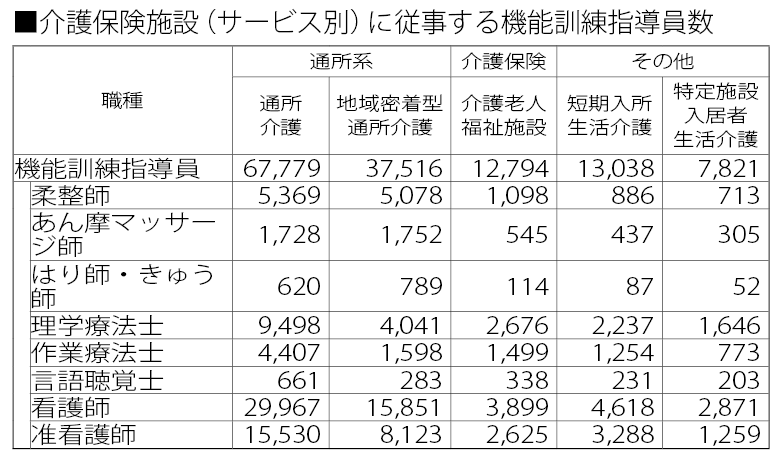新連載『鍼灸師・柔整師のための痛み学―UPDATE』1 痛みの原因を探る―4つの問診とは
2025.03.12
痛みの治療は総合診療科です。患者さんは「〇〇が痛い」と痛みの部位は教えてくれますが、その原因は教えてくれません。痛みの診察では、痛みの原因はどこかを明確にすることから始める必要があります。
痛みの原因は末梢・脊髄・脳の3つに分類されます。
末梢とは皮膚や筋肉、関節、骨、神経といった組織のことで、末梢組織に原因がある場合、それらの侵害受容器が興奮して痛みが生じているため、その組織や周辺に治療を行います。
脊髄に原因がある場合、複数の神経で支配されている内臓に障害があったり、脊髄そのものに直接的な障害、もしくは痛みの記憶があるものを指します。ただし、障害への直接的な治療はできないので、関係のある障害高位の分節に治療を行います。
脳の痛みは、痛みをコントロールしている脳の実質的、または機能的な障害(記憶を含む)で、こちらも脳へ直接的な治療ができないことから、脳に影響の強い部位である四肢や顔面部・頭部などに治療を行います。注意点として、脊髄や脳の痛みでも、その痛みは特別に感じるわけではなく、脊髄分節や脳の関連領域に存在する末梢組織の痛みとして感じるということです。
問診では手始めにどこの組織が痛いのかを割り出し、その痛みが予想した組織の痛みで正しいのか、またそのレベルは末梢なのか、それとも脊髄や脳なのかを探ることで原因を特定します。今回は診察の第1段階である、どの組織の痛みかを判断する4つの問診を紹介します。
初めの問診項目は時間的な要因。時間は急性期(3カ月以内)か慢性期(3カ月以上)を判断します。特に慢性期の場合は脊髄や脳に痛みが記憶されている可能性があります。
2番目は痛みの質。痛みの質は鋭いか鈍いかで、鋭い場合は皮膚や神経の、鈍い場合は筋肉や骨、関節などの深部組織の痛みが考えられます。なお、深部組織でも炎症がある場合は、鋭く感じるので注意が必要です。
3番目は痛みの部位(エリア・範囲)。範囲が明確な場合(点で示せる、色で塗りつぶせる)は皮膚や神経、明確でない場合は深部組織の可能性が考えられます。なお、炎症がある場合には、2番目と同様に深部組織でも範囲が明確になります。
4番目は痛みの軽減悪化因子。動きに伴い変化する場合は、筋肉・関節・骨などから来る痛み、常に痛い場合は神経の炎症から来る痛み、食事や生理などで症状が変化する場合は内臓から来る痛み、と考えられます。
最後に4つの問診を総合的に組み合わせることで、どこの組織に痛みがあるのかを予測し、その上でその予測が正しいのか、さらなる問診や検査を行います。まずは、4つの問診を行い、痛みの原因として疑わしい組織を絞り込みましょう。
POINT!
痛みの原因は3分類
①末梢 ②脊髄 ③脳
痛みの原因を特定するための4つの問診
①経過時間を探る ②痛みの質を探る ③痛みの部位を探る ④軽減悪化因子を探る
【連載執筆者】
伊藤和憲(いとう・かずのり)
明治国際医療大学鍼灸学部長、鍼灸師
2002年に明治鍼灸大学大学院博士課程を修了後、同大学鍼灸学部で准教授などのほか、大阪大学医学部生体機能補完医学講座特任助手、University of Toronto,Research Fellowを経て現職。
専門領域は筋骨格系の痛みに対する鍼灸治療で、「痛みの専門家」として知られ、多くの論文を発表する一方、近年は予防中心の新たな医療体系の構築を目指し活動を続けている。