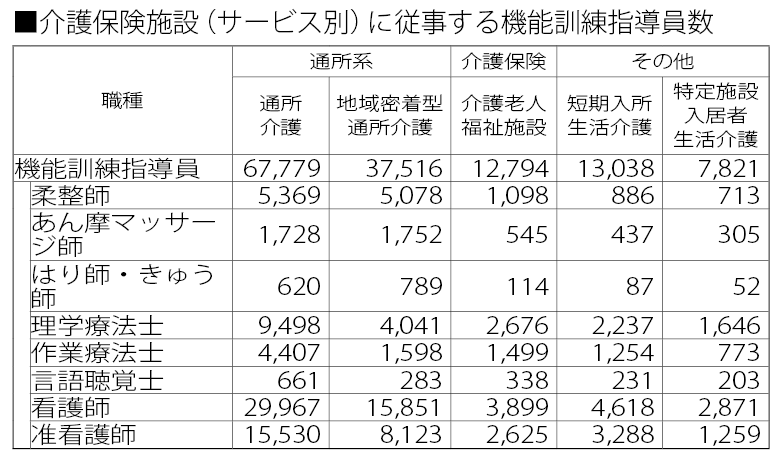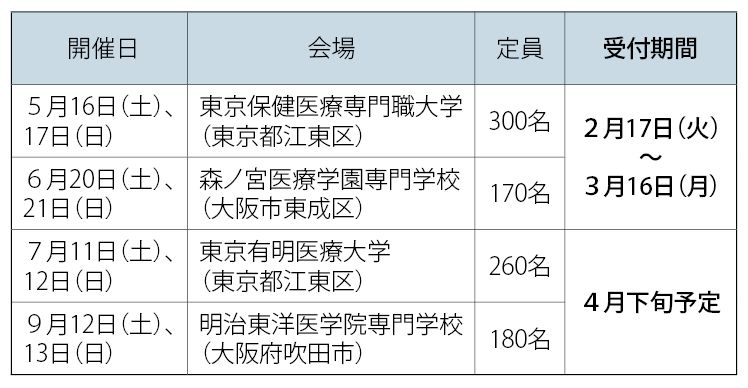連載『柔道整復と超音波画像観察装置』191 腹直筋肉ばなれの経過観察
2021.02.25
肉ばなれは、筋肉の収縮時に急激な伸張ストレスが加わることにより筋線維の損傷を起こす障害で、スポ-ツの種目、活動内容によって好発部位がある。陸上のトラック競技などではハムストリングや腓腹筋に多く、サッカ-では大腿四頭筋にも発生する。私はバドミントン選手に携わることが多いが、バドミントンの場合、練習や試合の中で腹直筋の損傷が起きることが少なくない。今回は、腹直筋損傷の超音波画像観察装置(エコー)を使っての経過観察を報告する。 (さらに…)