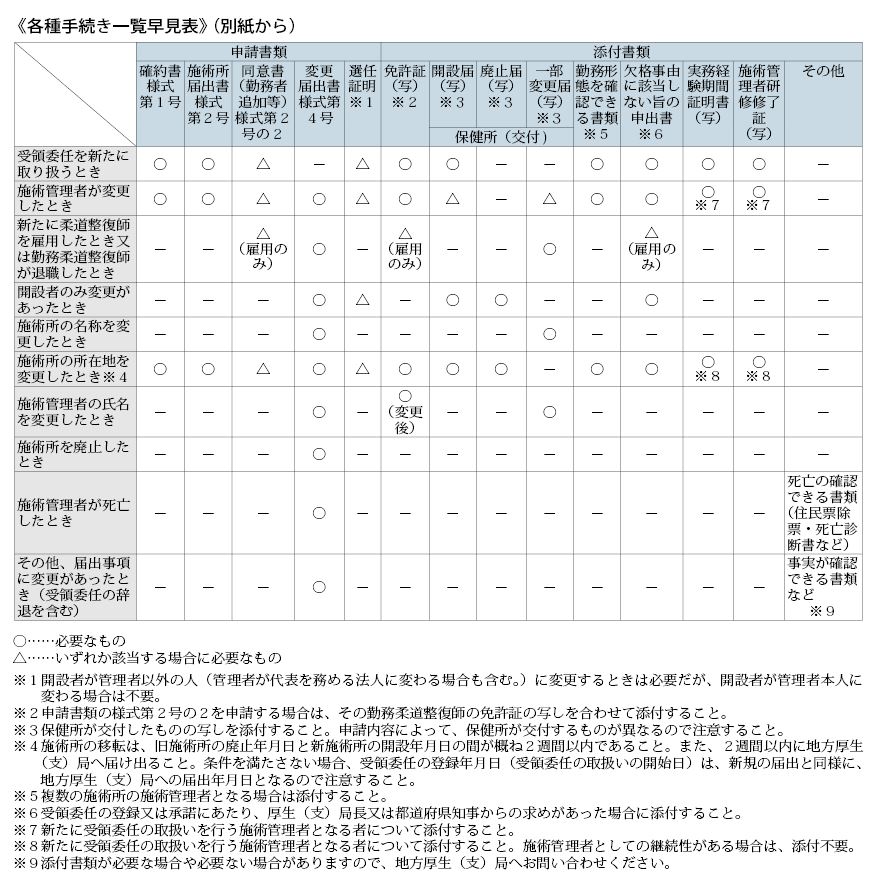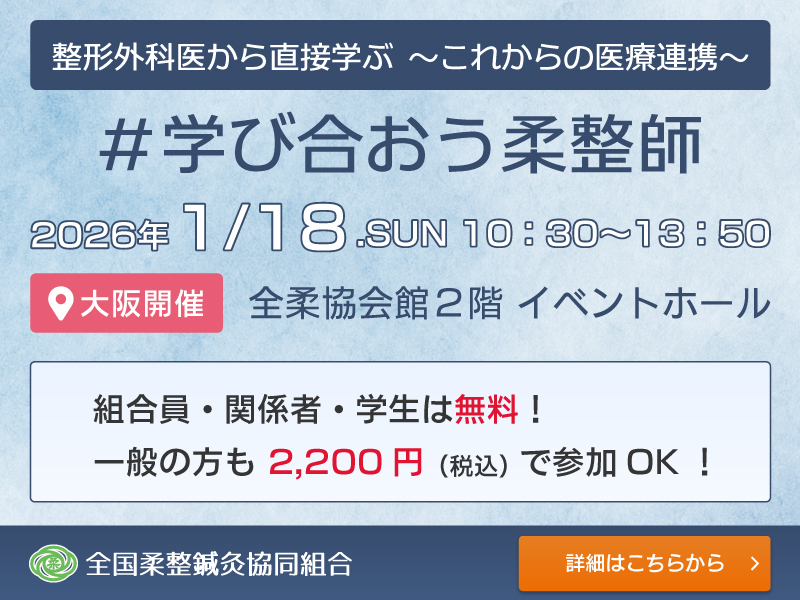今日の一冊 高機能アルコール依存症を理解する お酒で人生を棒に振る有能な人たち
2018.07.10
高機能アルコール依存症を理解する お酒で人生を棒に振る有能な人たち
星和書店 3,024円
セイラ・A・ベントン 著
コミュニケーション能力に長けている。エネルギッシュで身体的にタフ。専門的なスキルや学業をこなす能力が高い――。これらは「高機能アルコール依存症者」に特有の人格的特徴である。「飲み過ぎかもしれないが、仕事はきちんとやっているから問題無い」。高い社会的地位や有能さから見過ごされがちな高機能アルコール依存症。米国の元大統領ジョージ・ブッシュや世界的ミュージシャンのエリック・クラプトンといった著名人も高機能アルコール依存症だったという。同じ病を経験した著者が、回復までの道程を綴る。