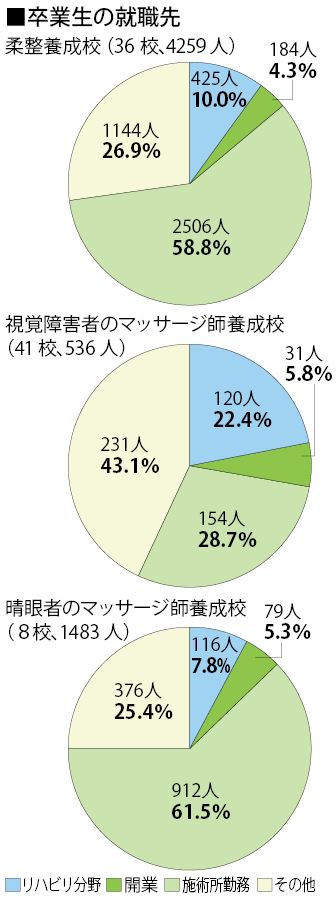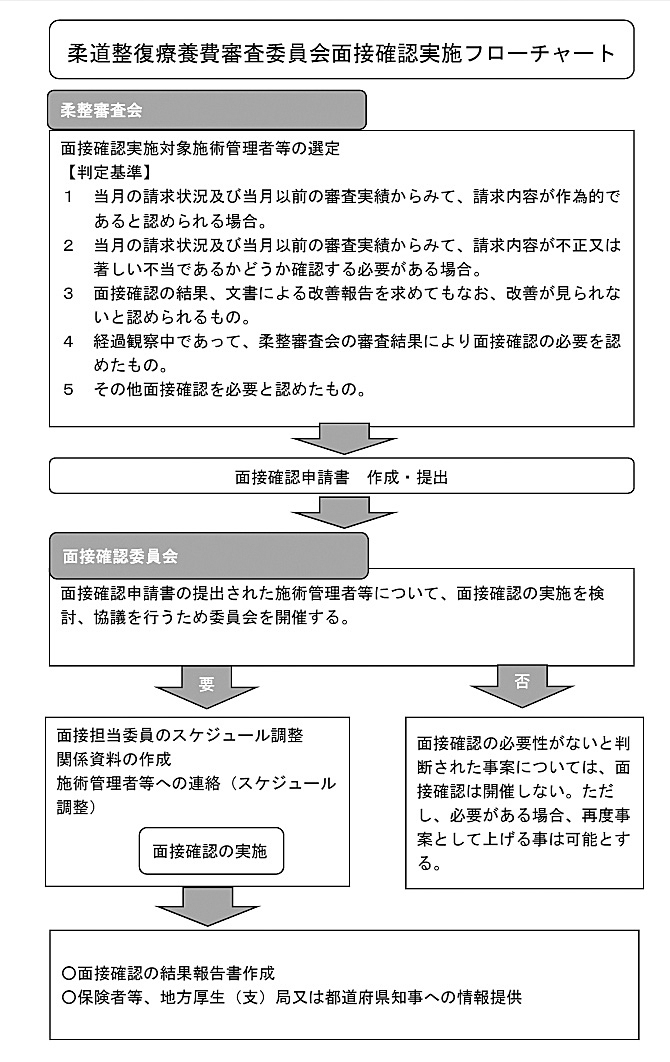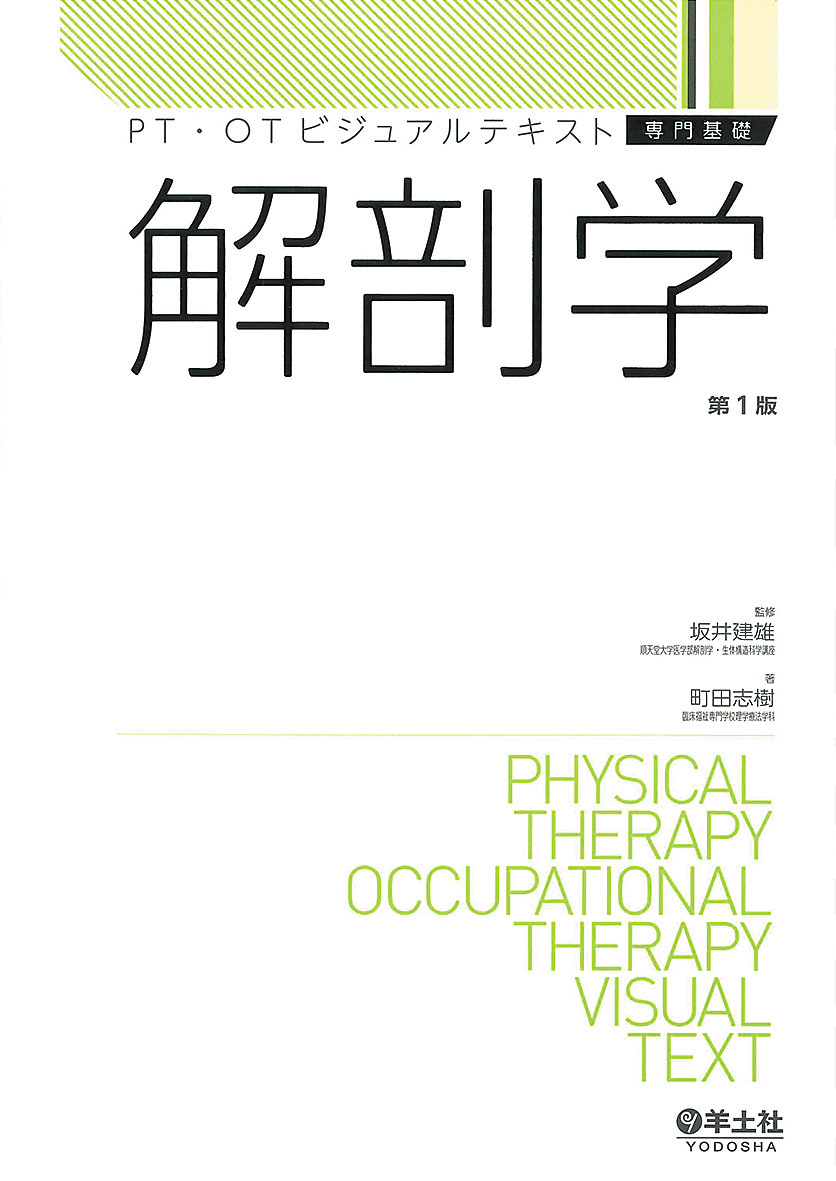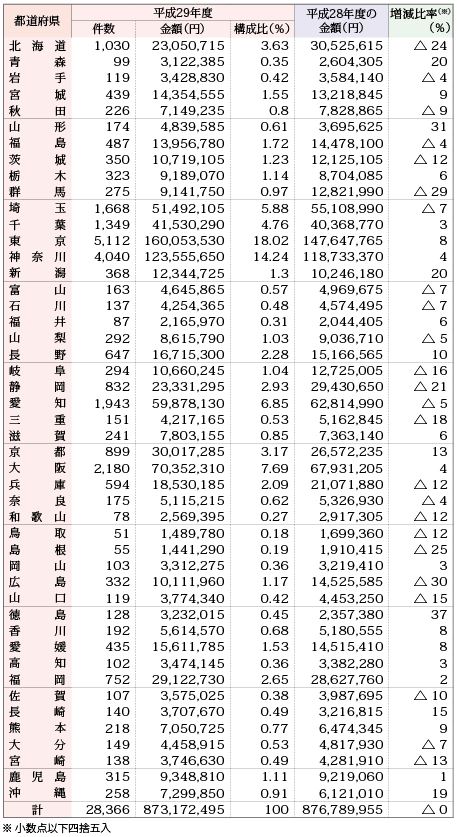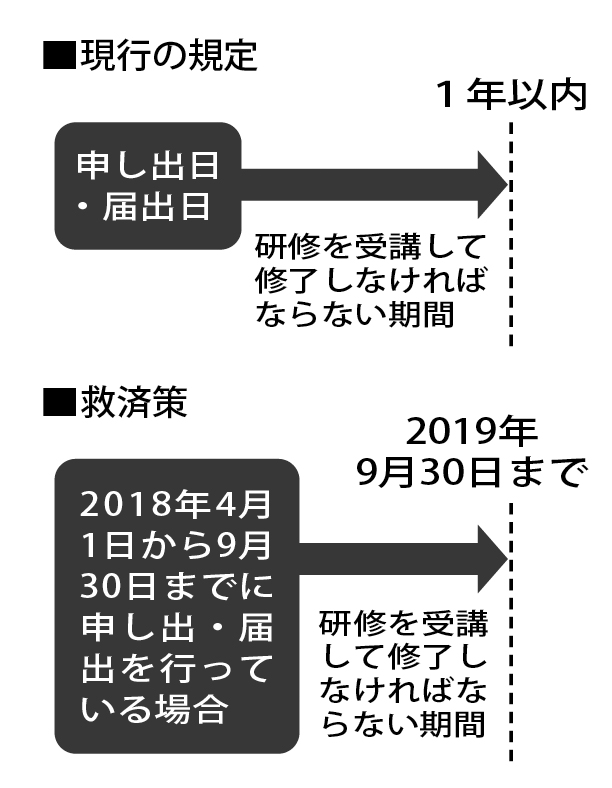『ちょっと、おじゃまします』 ~女性のために女性とともに~ アクア鍼灸治療院<大阪市天王寺区>
2019.01.25
「優秀なパートナーがいたからこそ、ここまでやってこられた」と話す、アクア鍼灸治療院院長の松本茂文先生。専門学校時代の同級生で女性治療家の鈴木千草先生と同院を立ち上げておよそ10年。松本先生は治療にも携わりつつ経営に取り組み、鈴木先生は治療に専念してきたといいます。松本先生にとって鈴木先生は「自分が見てきた中で、一番腕の確かな鍼灸師」だとか。
大手総合小売業でスポーツ用品の仕入れを担当していた松本先生。消費者のニーズをくみ取ったり、提案の仕方を考えたりするのは治療院経営にも通じるものがあるといいます。開院してしばらくは整骨院然とした内外装でしたが、女性の患者さんをメインに想定して、温かみのある和モダンなものに改修。お香も焚くなどして「女性がリラックスできる空間」を演出しています。柱となる治療やメニューもスポーツや美容などと変遷してきましたが、昨年から不妊鍼灸に特化するように。「同じ商品分野、例えばシューズの品ぞろえの幅と奥行きを充実させるのは良いことですが、そこにテニスラケットやゴルフクラブまで並べるとお客さんの混乱を招くでしょう。ターゲットを明確にするというのも、小売業に通じているかもしれません」とのことです。現在、鈴木先生のほかにもう一人、女性の治療家が勤務していて、「2人の、女性ならではのきめ細やかな対応にはいつも感心します」と松本先生。例えば、身体を冷やすような服装で来院してきた患者さんにファッションにからめてさり気なくアドバイスするのは、「男性にはなかなかできないこと」だとか。治療もさることながら、そういった面でも全幅の信頼を寄せています。
実は、国家資格取得を目指すのに決定的な契機は無かったという松本先生ですが、今の仕事には大きなやりがいと喜びを感じているといいます。「身体が動く限り、ずっと続けていきたいですね」とのことでした。
松本茂文先生
平成17年平成医療学園専門学校柔道整復師科卒、同年柔整師免許取得。平成20年同鍼灸師科卒、同年はり師・きゅう師免許取得。53歳