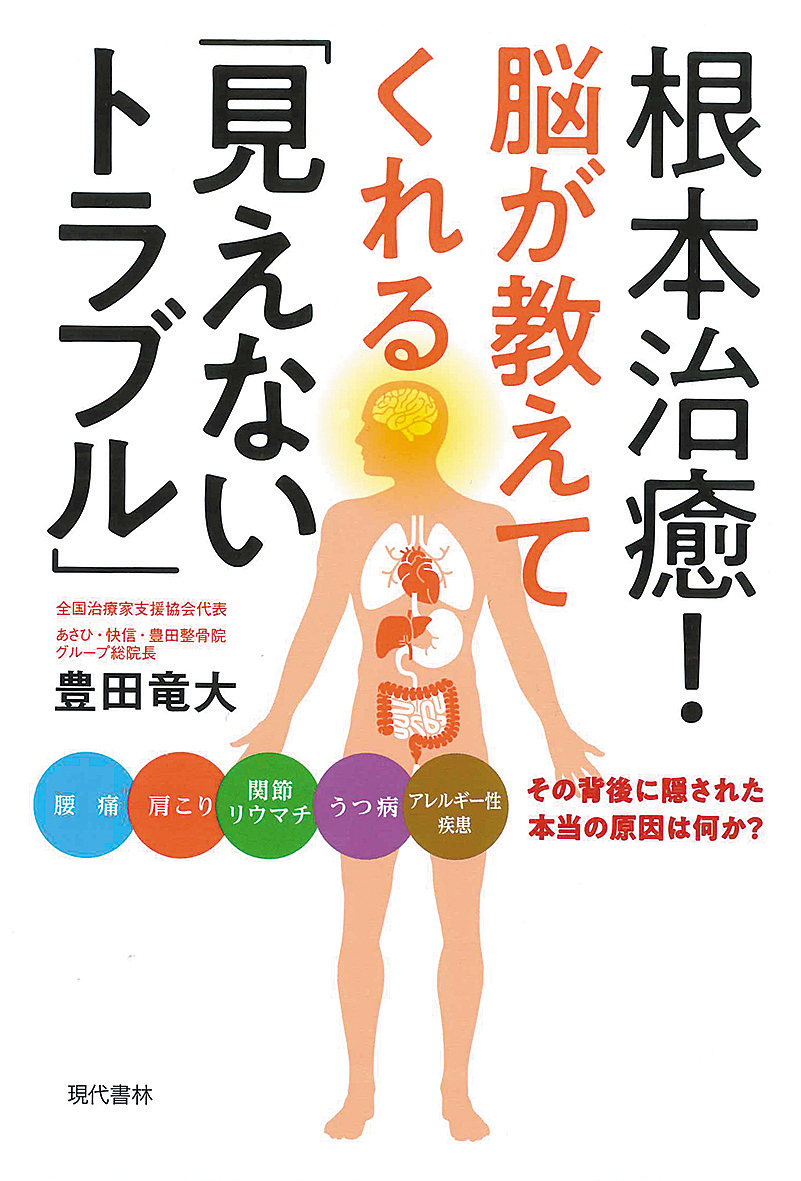「全日本鍼灸Summarize」発足 鍼灸情報 ネットで集約・共有
2019.02.25
無料チャットアプリでコミュニティ
2月13日、完全実名制の鍼灸業界関係者向けオンラインコミュニティ「全日本鍼灸Summarize(サマライズ)」が発足した。運営者は鍼灸師の平松燿氏。
平松氏は、近年のインターネットの発達に伴って、これまで学会・勉強会・書籍などでしか得られなかった知識や情報が各団体や個人から発信されるようになる一方で、有益な情報がウェブ上に分散していると指摘。オンラインコミュニティ上に、鍼灸に関する知見、歴史や文化、多種多様な治療法、各団体や施術者の社会活動等の情報を集約することを目的に、同コミュニティを発足したという。
参加資格は「身分を明らかにした鍼灸業界関係者」で、鍼灸学生やメーカーの社員などを含む。参加に当たって鍼灸免許証や学生証、社員証などを提示する必要があり、運営側が身分照会を行うという。参加料金などは不要。
運営には、無料チャットアプリ「Discord」を使用する。Discordは、グループチャットやビデオ通話といった機能を備えたフリーソフト。パソコンのほか、スマートフォンなどでも利用可能。導入が手軽で多機能なことからシェアを拡大し、昨年5月時点でユーザー数は約1億3千万人。話題ごとに別のチャンネル(チャットルーム)を作ることができ、全日本鍼灸Summarizeでも、学術、経営、雑談など、混同することなくそれぞれの話題別に議論を深めることができるとしている。
【問合せ先】全日本鍼灸Summarize
メール acusummarize@gmail.com
Facebook https://ja-jp.facebook.com/pg/acusummarize/posts/