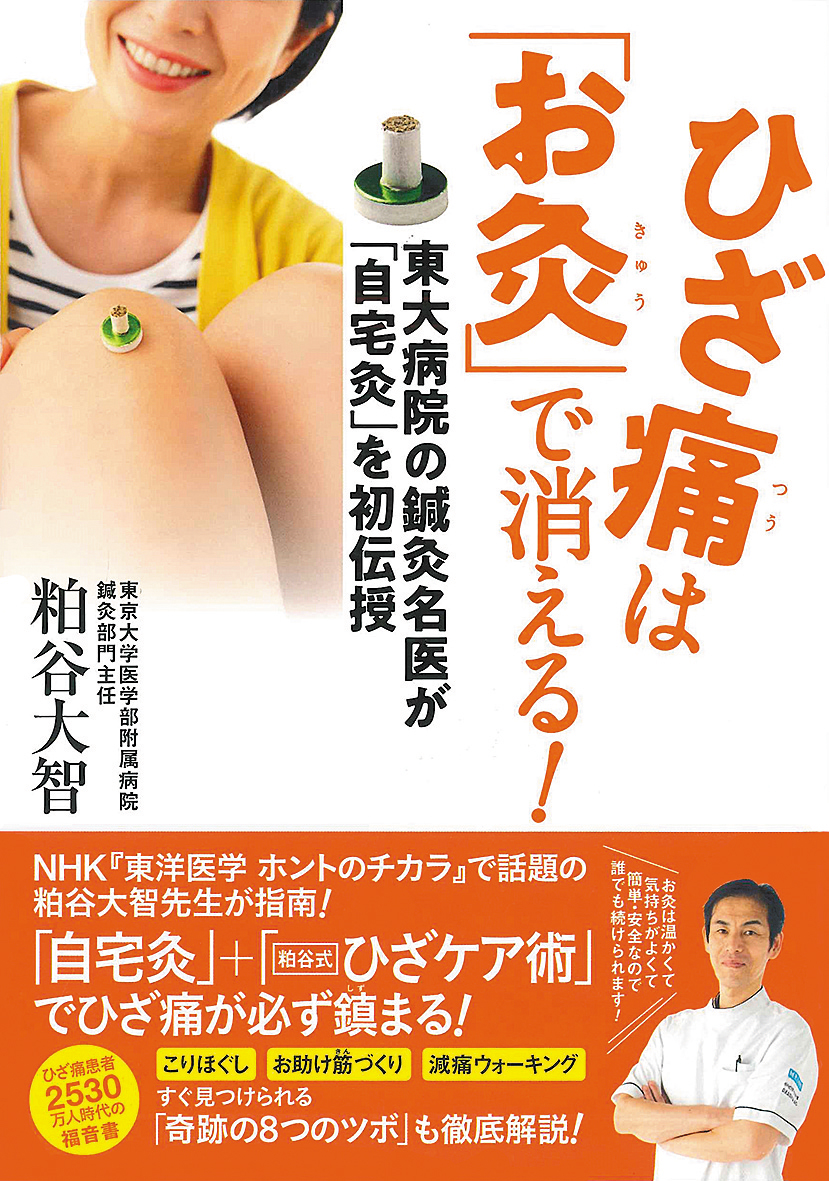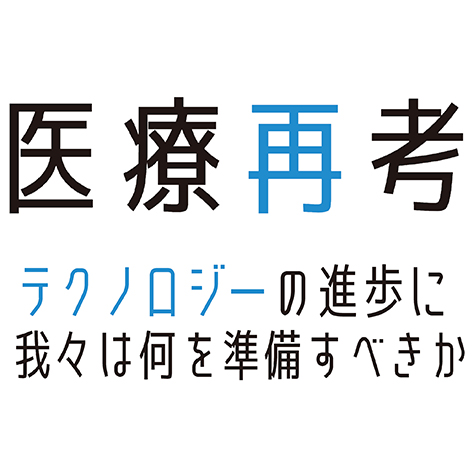連載『不妊鍼灸は一日にして成らず』11 公開講座の意義
2019.03.10
今回は、私たちの活動を紹介させていただきます。私たちは2012年、「不妊鍼灸ネットワーク」として活動を開始しました。年3回の研修のうち1回を公開しており、2014年度の第1回公開講座には全国から百人を超える鍼灸師が集まりました。その後も毎年開催し、2017年度、「一般社団法人JISRAM(日本生殖鍼灸標準化機関)」に組織変更してからの新たな第1回公開講座(通算第5回)は、初の高度生殖医療施設での開催となりました。
第2回となる今年のテーマは「男性不妊のA to Z」。近年問題となっている男性不妊について、基礎、臨床、最先端の知見まで俯瞰的に網羅する内容となっています。夫婦間の性交渉の頻度が低下している上に、NHKで『精子力クライシス』などという特番が組まれるほど、日本人の精子は危機的な状況を迎えています。精子の状態を良くするためには、6時間以上のきちんとした睡眠、肉より魚、長時間の座位を避ける、ブリーフよりトランクス、熱い長湯を避ける、などが根拠のある生活指導として推奨されています。私たちのライフスタイルの変化の多くが、悪化の手助けをしているのは一目瞭然ですね。精子の状態を良くするのに生活指導が大切なのは、精子が「常に作り続けられている」からです。おおよそ74日間かけて完全な精子になるのですが、そうすると治療の効果判定には、またもや長い加療観察期間が必要となります。更に精子の状態は日々刻々と変化しているので、2、3回の検査で正しい判断はできません。そこで私は、産婦人科で使われているものと同等の位相差倒立顕微鏡一式を導入し、挙児を希望される男性の精子を観察しています。このレベルの設備は鍼灸院では例が無いと思います。精子の成績はランダムに変動しますが、繰り返し細かく観察を続ければ、改善の傾向がしっかりと把握できます。
また、男性の精子力を確認せずに女性不妊を扱うことはできません。「タイミング(性交渉)を取ってくださいね」と言っても、ご主人の精子が不良な場合もしばしばあります。以前、来院された男性不妊の方の場合、当院に来られる前に1年以上通院しておられた鍼灸院では精子の成績には一切言及されず、体調を整えていただけとのことでした。この方の精巣容積は実は7㏄ほどで、造精能力下限でした。器質的に改善不可能なのに1年以上も治療を継続されていたことに驚きました。例えば肩が痛くて腕が上がらないとして、日々の改善の程度を、普通の鍼灸師なら必ず診ると思います。精子の数や運動率などから治療の効果を確認せずに、どうして漫然と治療が行われるのでしょうか。知識も無く検査を推奨もせず、自分でも調べられないなら、そういった患者を安易に引き受けるべきではありません。その間に配偶者の加齢は進み、妊娠しにくくなっていくのです。その重大さを全く理解していません。観察スパンが非常に長い生殖領域ではその精査がとても困難、しかし極めて重要なのです。巷の不妊鍼灸の実技公開は、その効果まで検証しているものはほとんど無いそうです。今回の公開講座で発表する本会の精子研究グループは、何と全員が自分の精子(女性の場合はご主人の精子)で効果を検証しています。まずはそういった姿勢が重要です。
公開講座では、私たちの研究や観察のエッセンスをお届けします。また最先端の研究を行う講師を招聘します。その意義を理解している方々は、毎年受講されています。公開講座は3月24日(日)京都にて。詳細はJISRAMのサイト(http://jisram.com/contents/activities/learning/)で。
【連載執筆者】
中村一徳(なかむら・かずのり)
京都なかむら第二針療所、滋賀栗東鍼灸整骨院・鍼灸部門総院長
一般社団法人JISRAM(日本生殖鍼灸標準化機関)代表理事
鍼灸師
法学部と鍼灸科の同時在籍で鍼灸師に。生殖鍼灸の臨床研究で有意差を証明。香川厚仁病院生殖医療部門鍼灸ルーム長。鍼灸SL研究会所属。