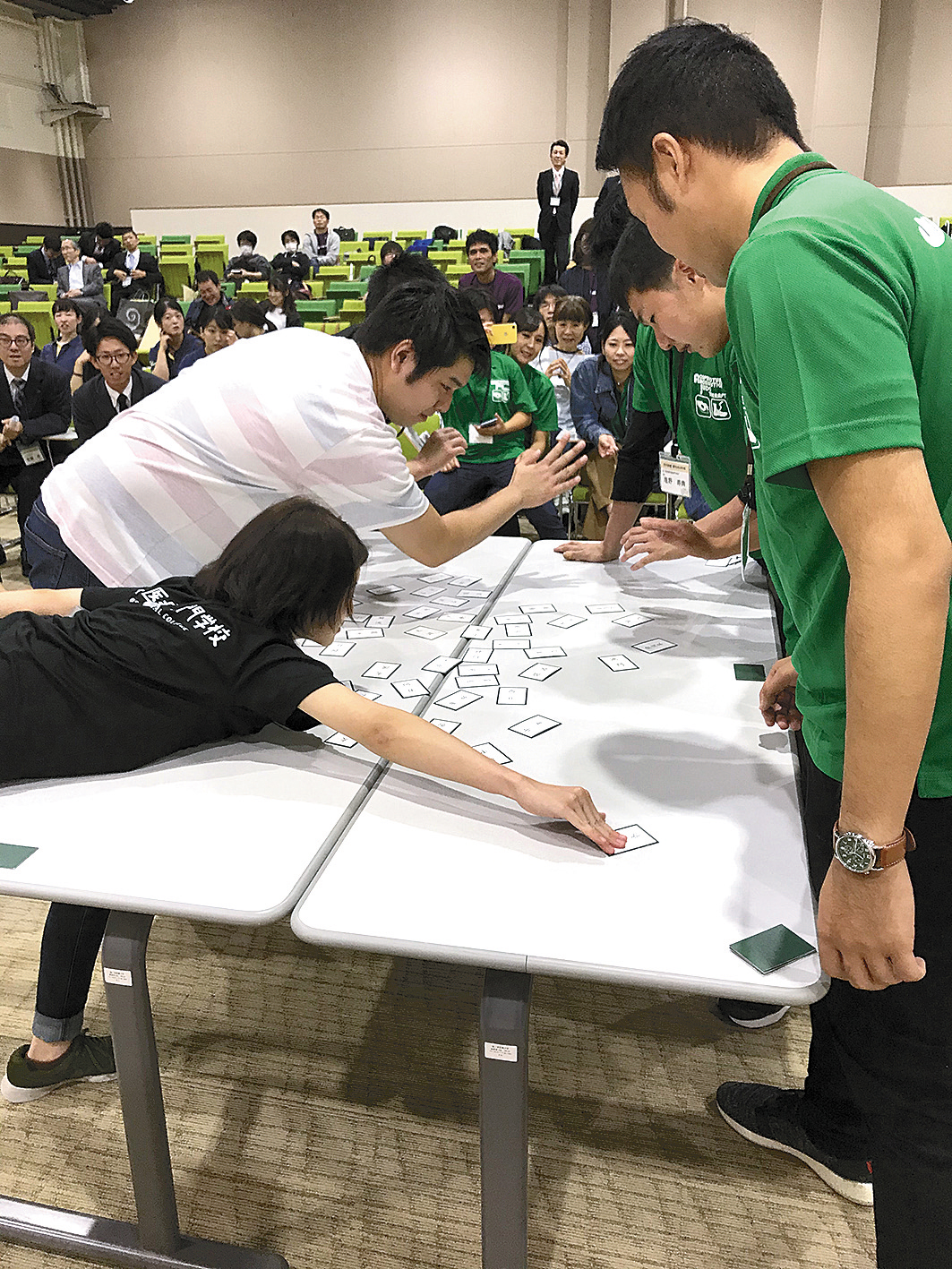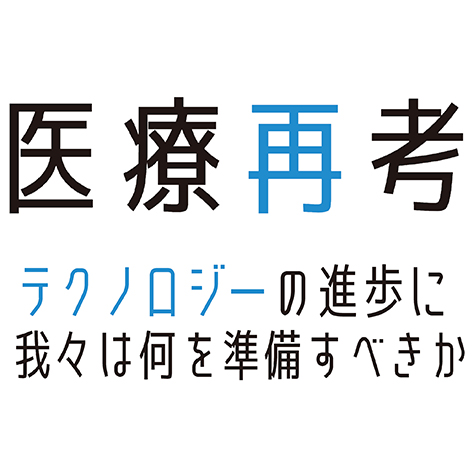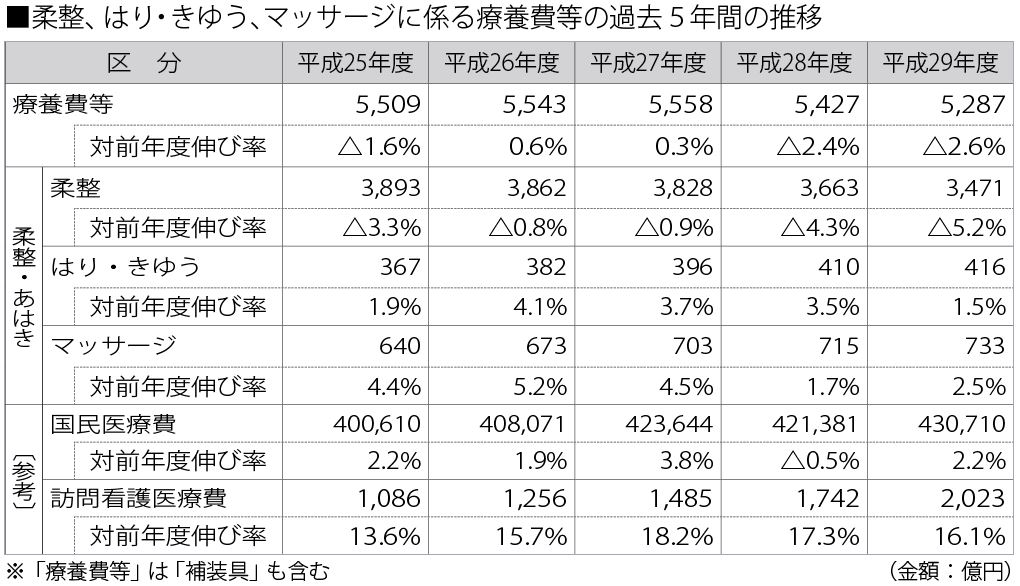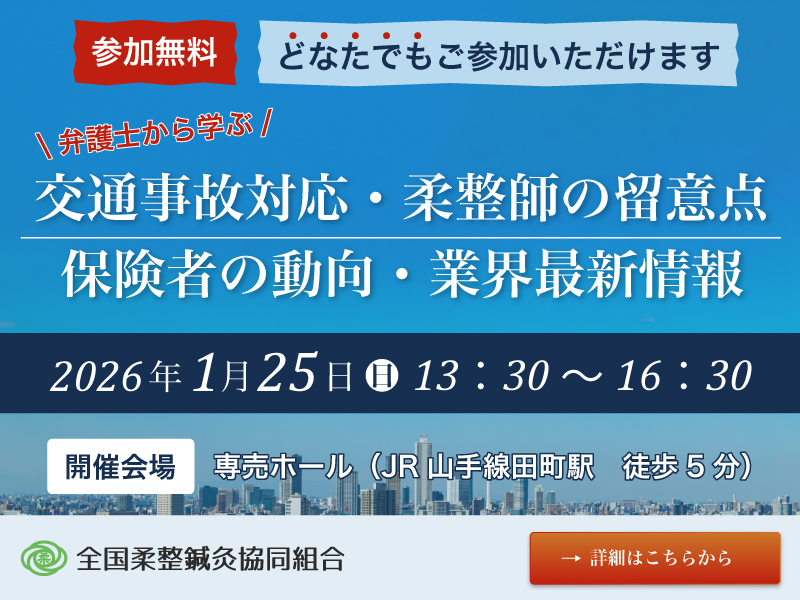連載『不妊鍼灸は一日にして成らず』19 The Fertility Diet
2019.11.10
この記事が出る頃には、「第64回日本生殖医学会」が終わっています。そこでシンポジウムの座長を私が務めることは、以前お話ししましたね。この学会は生殖領域を扱う日本最大級の学会で、演題数も500を軽く超えます。そこで鍼灸師が座長を務めるというのは、史上初かもしれません。さて座長をお引き受けしたものの、その後から、ハーバード大学のジョージ・E・チャヴァロ博士がシンポジストに加わったからさあ大変! 共同座長のドクターと話し合って「総合討論をAll English にする」などの案も出ましたが、通訳を付けてもらうことで一件落着。ほっとしました。さて、チャヴァロ博士は、全米の妊活中の2万人近い看護師さんへの食事調査を長期にわたって細かく分析され、疫学から導かれた妊娠に向けた食事療法を本にされた方です。似たような本は数々あれど、これほど大規模なデータから理論的根拠を備えたものは他に類を見ないでしょう。私はシンポジストの本は読んでおくべきだと、久方ぶりに英語の原著に挑戦しました。治療の合間に本文230ページを精読するのに3カ月弱を要しました。書名は『The Fertility Diet』。ダイエットというと痩身を思い浮かべますが、「Diet」の第一義的な意味は「食品」です。この本を読んで自分でもその食事療法を実践してみました。原則がいくつかあります。①炭水化物は精製されたものより全粒粉や玄米といった形で摂る②清涼飲料水は飲まない③油は不飽和脂肪酸を多く摂って飽和脂肪酸は控え、トランス脂肪酸は摂らない④タンパク質は植物由来に重点を置き、次に魚、肉は少なく、という比率にする、などです。そこで私は朝食の食パンを全粒粉に、マーガリンをオリーブオイルに変えました。私は昼食を取らないのですが、チョコレートやクッキーをつまむ代わりにミックスナッツ(油、塩なし)にしました。すると、かなりの運動をしても73kg以下に落ちなかった体重がたった2カ月で67kgを切ったのです。これには驚きました。食事の内容を変えただけなのに。
その仕組みはこうです。精製された炭水化物は血糖値を一気に上げてインスリンの大量分泌を促します。そして血糖を脂肪に変換し蓄積するも、結果として血糖値は一気に下降して空腹感が早く来る。しかし精製されていない炭水化物の摂取では、血糖値は緩やかに上下するのでインスリンの大量分泌も脂肪への変換もなく、空腹を感じるまでに時間もかかるというわけです。実際に、白い食パン6枚切りを全粒粉の食パン8枚切りに変えてから、空腹感が来るのが以前より1、2時間遅いのです。そして昼食代わりのミックスナッツは良質の脂肪とタンパク質、糖分を含み、非常にバランスが取れています。考えたらナッツは種ですから、植物が一定の成長をするまでに必要な養分です。ならばと先日、かぼちゃとひまわりの種を買ってミックスナッツと一緒に食べることにしました。それを見た従業員が「先生、もはやリスですね」と……。
さて、ある生殖専門医から「生殖医学会のシンポジウムの座長になられたとは、それはそれは大変名誉なことだと思います。おめでとうございます。昔からお付き合いのある先生がその様な立派なお役目を務められることは、私どもにとってもうれしい限りです。どうか頑張ってください」とのメールが。やはりかなり格の高い学会のようです。実は、シンポジストに我がJISRAMの徐大兼先生も選出されています。大きな肩書を持たない市井の鍼灸師2人が座長とシンポジストに指名され、こんなにうれしいことがあるでしょうか。鍼灸の真骨頂を存分に披露して来るとしましょう。
【連載執筆者】
中村一徳(なかむら・かずのり)
京都なかむら第二針療所、滋賀栗東鍼灸整骨院・鍼灸部門総院長
一般社団法人JISRAM(日本生殖鍼灸標準化機関)代表理事
鍼灸師
法学部と鍼灸科の同時在籍で鍼灸師に。生殖鍼灸の臨床研究で有意差を証明。香川厚仁病院生殖医療部門鍼灸ルーム長。鍼灸SL研究会所属。