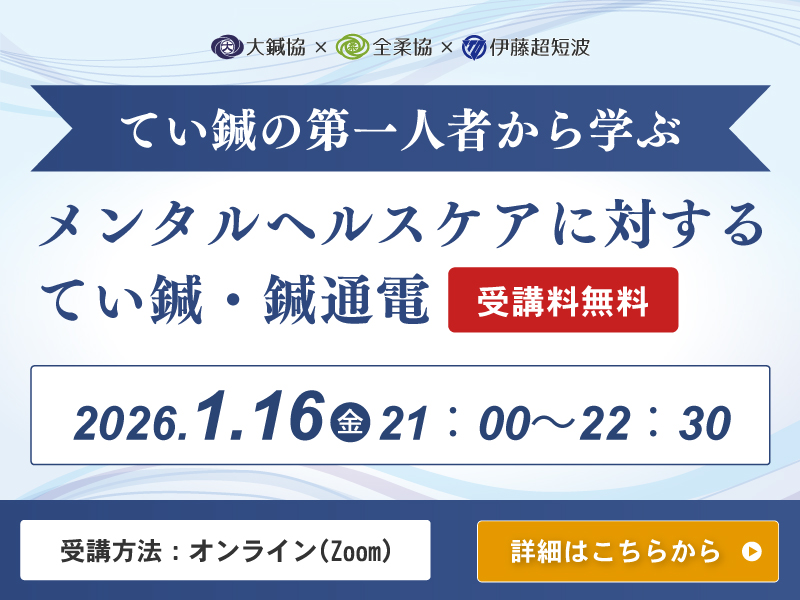『医療は国民のために』283 近年、厚労省が作成する文書に違和感を覚える
2019.11.25
10月中旬に東日本を襲った台風19号では、多くの施術所も被害を受けた。今回の台風接近に伴って厚労省保険局医療課は10月12日、被災者が保険証を提示しなくても保険診療を受けられるように手立てを講じた事務連絡「令和元年台風19号に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」を事前に発出した。この事務連絡は医科・歯科・調剤薬局に係る文書なので、柔整・あはき療養費には関係ないものと思いながらも、念のため、当方から保険局医療課に確認を入れたところ、「療養費も同じ取扱いになる」という、まさかの回答を得て、驚いた。理由を尋ねると、事務連絡の本文中にある「保険医療機関等」の〝等”に「柔整・あはきの施術所も含まれる」というのだ。従来、私が厚労省に在籍していた頃も含め、柔整・あはきの施術所を保険医療機関と厚労省は見なしていなかったし、保険医療機関等の“等”とは「保険薬局」を指すものだと明確にされていた。
今回のケースもそうだが、最近、厚労省が従来と異なる用語の使用を認めるようになってきたと感じる。果たして、行政が何らかの方向転換をしたのか、それとも単に担当者が過去の経緯や取り扱いを知らないだけなのかは分からない。ほかに例を挙げれば、「受領委任の取扱い」を「受領委任制度」と言い始めた。柔整・あはき療養費は法制化されておらず、単に「事務処理の取り扱い」という位置付けなのだが、〝制度”となってしまっている。また、柔整療養費に係る平成30年5月24日付の事務連絡では、〝診”の文字が堂々と使用されている。療養費に係る文書に関しては〝診”の文字を使わないのが鉄則ではなかったのか。重箱の隅をつついていても、情けなくなってくるばかりなのでもう止めよう。
話を台風19号関連の事務連絡に戻そう。これは地方厚生局医療課や都道府県の国保主管課・後期高齢者医療主管課宛てに出された文書であるから、受け手側が柔整・あはきにも適用されるとの理解があれば、事務処理上何の問題もないが、果たしてトラブルは生じないだろうか。10月30日付であはき療養費が適用される旨は事務連絡で発出されたが、柔整療養費に関しては何ら示されておらず、「支給は認めない」と言い出す保険者が現れてもおかしくない。無用なトラブルに巻き込まれるのだけは御免だ。
思えば、柔整師とあはき師が「医業を行う者」とみなされない現行の解釈となった原因の一端に、昭和30~40年代に通知された厚生省(当時)の文書の誤りが挙げられる。最近の行政からの発出文書の誤りも、これら同様に単に厚労省担当部局の認識不足に過ぎないと推察している。繰り返すが、保険医療機関等の〝等”に施術所が含まれるというのはやはり行政担当者の判断の誤りだろう。
【連載執筆者】
上田孝之(うえだ・たかゆき)
全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長
柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。