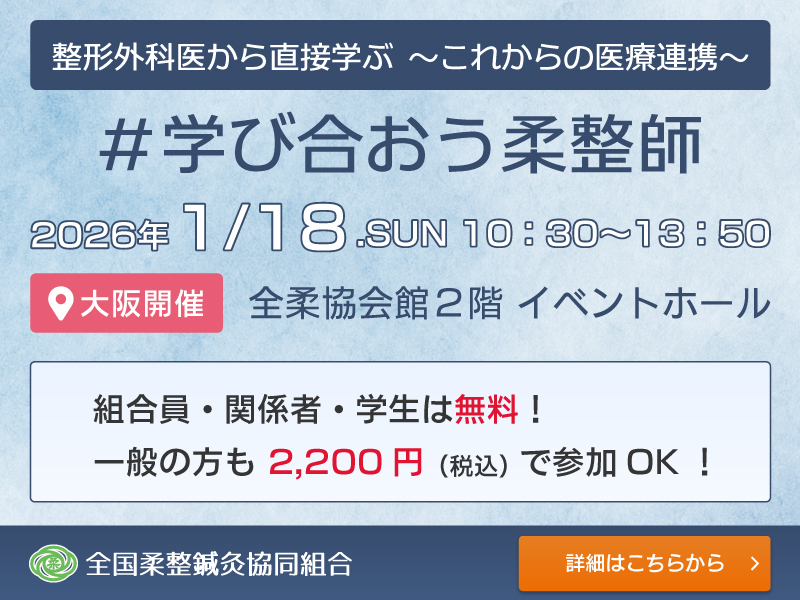連載『中国医学情報』170 谷田伸治
2019.05.25
☆早発卵巣不全(POF)の不妊症には鍼併用治療
河南省鶴壁市の侯紹亮らは、早発卵巣不全(POF)による不妊症患者で西洋薬単独治療と鍼併用治療の効果を比較した(上海鍼灸雑誌、19年1期)。
対象=早発卵巣不全(POF)による不妊症患者96例、平均年齢約33歳(27~39歳)。これをランダムに西洋薬単独群・鍼併用群各48例に分けた。
治療法=両群とも常軌の西洋薬治療(女性ホルモン剤)。治療期間6週間(2クール)。
<鍼治療>①取穴―腎兪・百会・神庭・本神・関元・子宮(奇穴。中極穴の左右三寸)・足三里・三陰交・太渓・太衝。
②使用鍼―腎兪・関元・子宮・足三里・三陰交が0.25×40mm、百会・神庭・本神・太渓・太衝が0.25×25mm。
③操作―腎兪:脊柱に向け45°の斜刺35mm。百会・神庭・本神:後方に15°の斜刺20mm、得気後に平補平瀉法。関元・子宮・足三里:直刺35mm、得気後に重挿軽提補法。三陰交:上方に45°の斜刺、得気だけ。太渓:直刺15mm、得気後に重挿軽提補法。太衝:直刺10mm、得気後に軽挿重提補法。以上は、毎回置鍼25分(行鍼1回)。各穴を交替使用。毎週3回、1クール36回で2クール治療。
観察指標=①卵巣機能(卵巣体積・胞状卵胞数・卵巣拍動指数)、②血清ホルモンレベル(E2・FSH・LH)、③妊娠率と不良反応発生率。
結果=妊娠率は、単独群12.5%(6例)併用群31.3%(15例)。①と②では、いずれも併用群の数値が単独群より有意に良い状態。不良反応発生率は、単独群8.3%(悪心・腰痛各2例)併用群10.4%(悪心1例・暈鍼2例・腰痛2例)で有意差なし。
<付記>早発卵巣不全(POF)に対する鍼灸治療は、本年4月10日号の本欄でも紹介。
☆寒湿型の腰痛患者には通電+灸頭鍼治療
広州中医薬大学・頼鵬輝らは、明らかな神経障害のない寒湿型(冷えて痛み四肢が冷たいタイプ)の腰痛患者126例で、鍼通電・灸頭鍼・通電+灸頭鍼の3種類の治療法の効果を比較した(鍼灸臨床雑誌、19年1期)。
対象=126例(男66例・女60例)、平均年齢約51歳(30~85歳)、平均罹患期間約30日。これをランダムに3群各42例に分けた。
治療法=<取穴>腎兪・大腸兪・腰陽関・命門・阿是穴。
<操作>0.30×40~75mmの鍼で、腰部の筋肉の肥厚状況に合わせて直刺25~50mm、提挿捻転し得気後、通電または灸頭鍼治療。
<通電>電極は3組:左右の腎兪・大腸兪と阿是穴1組。断続波・2Hzで30分。
<灸頭鍼>通電と同じ穴位の鍼柄上に約2cmの長さのモグサを挿入して点火、穴位のところに火傷予防の紙片を置く。毎回30分。
<併用>通電後に灸頭鍼。
以上の治療を毎日1回、1クール6回、1週間休止後に更に12クール、計12回治療。
観察指標=JOAスコア(日本整形外科学会腰痛疾患治療成績判定基準)、VAS(視覚的アナログスケール)、FFD(指床間距離)。
結果=通電群:全快2例・著効8例・好転21例・無効11例・総有効率73.8%。灸頭鍼群:全快6例・著効14例・好転16例・無効6例・総有効率85.7%。併用群:全快12例・著効19例・好転10例・無効1例・総有効率97.6%。
☆ドライアイに対する選穴データ
甘粛中医薬大学・馬雪嬌らは、データベースを利用し中国でのドライアイに対する鍼灸治療文献の選穴状況を報告した(中国鍼灸、19年1期)。
対象=国内の3つのデータベースで検索した、2007~2017年に報告された文献145篇から、総述・動物実験などを除外した52篇。
検索結果=穴位数は経外奇穴を含め60穴。
<選穴>(カッコ内篇数)①睛明(47)、②攅竹(44)、③太陽(40)、④三陰交(32)、⑤合谷(29)、⑥風池(28)、⑦糸竹空(27)、⑧四白(26)、⑨太衝(24)、⑩太渓(21)、⑪足三里(21)、⑫承泣(17)、⑬百会(16)、⑭肝兪/腎兪(各14)、以下略。
<選経>陽経が選穴総数の62.7%で、その頻度は、①足太陽膀胱経(11穴、25.1%)、②足陽明胃経(6穴、14.0%)、③足少陽胆経(6穴、9.3%)、④足太陰脾経(5穴、9.4%)、⑤経外奇穴(5穴、9.1%)、以下略。
【連載執筆者】
谷田伸治(たにた・のぶはる)
医療ジャーナリスト、中医学ウォッチャー
鍼灸師
早稲田鍼灸専門学校(現人間総合科学大学鍼灸医療専門学校)を卒業後、株式会社緑書房に入社し、『東洋医学』編集部で勤務。その後、フリージャーナリストとなり、『マニピュレーション』(手技療法国際情報誌、エンタプライズ社)や『JAMA(米国医師会雑誌)日本版』(毎日新聞社)などの編集に関わる。