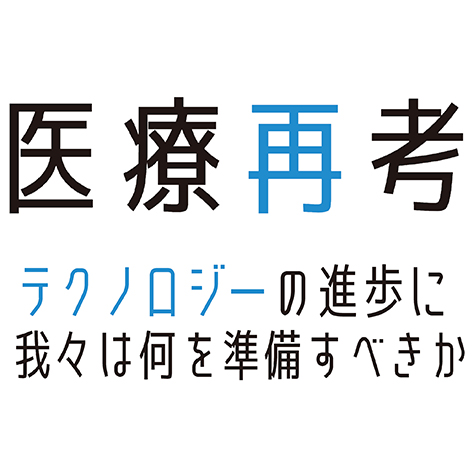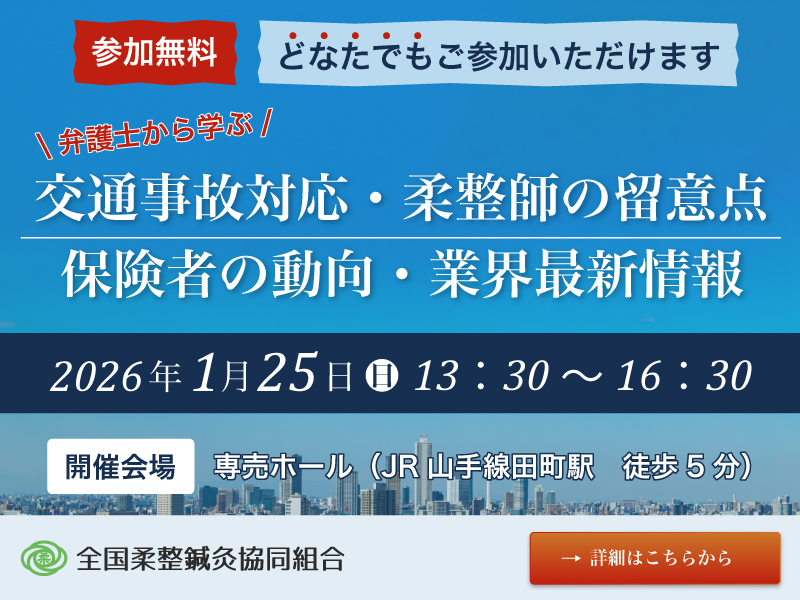『医療は国民のために』290 広告規制の行方について、「皆さん、本当にこれでいいんですか?」
2020.03.10
1116号(2020年3月10日号)、医療は国民のために、紙面記事、
平成30年春から始まった『あはき師及び柔整師等の広告に関する検討会』も既に8回もの会議を重ね、そろそろガイドライン(指針)が決定されようとしている。この機に再度、念押ししたい。業界関係者の皆さん、本当にこれでいいんですか? 中でも、あらゆる場面で「治療」という言葉が使用禁止にされ、施術所名に「整骨院」の名称が使用できなくなるといった理不尽な内容が最近示されたガイドライン案に盛り込まれているという点を、どのように受け止めているのだろうか。
柔整・あはき業界では、このように何かが「決まる、決まった」という際、自らの無能さをごまかすため、「悪いのは厚労省だ」と国のせいにすることがよくある。が、今回の医政局医事課の対応は、そうとばかりはいえない。できれば業界側からの要望を一つでも通そうとの配慮もうかがえる。例えば、あはきの施術所名に「業態名+治療院」を認めるとした原案を厚労省は提示した。ただ、医師会、保険者、自治体、そして患者団体からなる構成員の合意を得なければ、この配慮も意味をなさないのはいうまでもない。
厳しい現状において、残すところは「座長との高度な政治的判断」によるペンディングの箇所であり、この点をいかに業界寄りに仕切れるかどうかだ。「業態名+治療院」はここまでの議論で完全否定されているが、それでも「マッサージ治療院」、「はり治療院」といった名称は、政治的判断によるものであるから今後どうなるか分からない。国はあくまで公平・公正な見地から議論をテーブルに乗せており、敵ではないのは明らかで、決まるのは検討会の席上で顔を合わせている構成員の議論次第だ。
とはいえ、ガイドライン案では単に「治療院」とした施術所名などは認められないとし、「整骨院」もダメというのが基本路線となってしまっている。加えて「鍼灸整骨院」も広告不可。ガイドライン適用後の保健所による指導業務の煩雑さなどの実効性を鑑みて、「遡及適用しない」とは言うが、果たしてこの内容を本当に許していいのか? そもそも「治療」の文言を認めたくないとする理由も、医科・医師との混同により「医業」と紛らわしく、誤解を生じるからだという。残念ながら、本来あはき・柔整は医業の一部にもかかわらず、「医業類似行為」におとしめられているのが現状だ。また、「整骨」という表現も、これだけ認知されているのだから大臣告示に加えるだけで事足りるはずなのに……。不毛ともいえる議論を8回も続けてきた上で、なぜ結局認めないとの結論になるのか、疑問でならない。
それでも、今後ガイドラインは医政局長通知で示され、それ以降は広告に関する指導マニュアルとして浸透していくこととなろう。しつこいと嫌われるのを覚悟でもう一度言おう。「皆さん、治療院・整骨院・鍼灸整骨院が使えなくなっても、本当にいいんですか」。
【連載執筆者】
上田孝之(うえだ・たかゆき)
全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長
柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。