連載『汗とウンコとオシッコと…』189 垣根無し
2020.05.10
藤の花が4月末に咲いた。日差しは夏だというのに、風は涼風だ。初夏が到来した割に空気が冷たく、太陽光線の紫外線で焼かれている割には発汗がうまくいかない。そのために、3月から4月にかけてよく現れる少陽胆経の病が多く見られる。片頭痛、めまい、寝違い様の頸部痛、仙腸関節痛、膝内側痛だ。 (さらに…)
連載『汗とウンコとオシッコと…』189 垣根無し

連載『汗とウンコとオシッコと…』189 垣根無し
2020.05.10
藤の花が4月末に咲いた。日差しは夏だというのに、風は涼風だ。初夏が到来した割に空気が冷たく、太陽光線の紫外線で焼かれている割には発汗がうまくいかない。そのために、3月から4月にかけてよく現れる少陽胆経の病が多く見られる。片頭痛、めまい、寝違い様の頸部痛、仙腸関節痛、膝内側痛だ。 (さらに…)
連載『医療再考』15 何のためにエビデンスを構築するのか―鍼灸の信頼価値とは
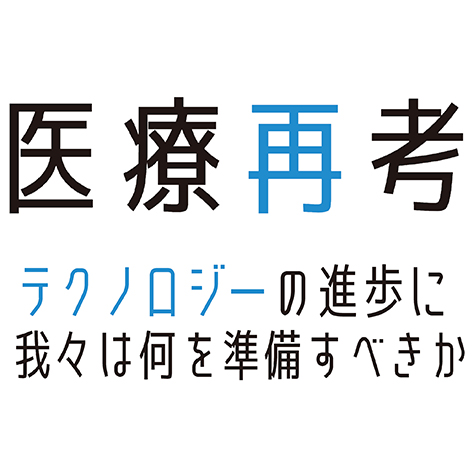
連載『医療再考』15 何のためにエビデンスを構築するのか―鍼灸の信頼価値とは
2020.05.10
現代の医療はエビデンスを求め、重視する傾向にあります。ある疾患に対してどのような選択肢が存在し、その中でどの選択肢が最も効果的かという情報は、最善の医療を提供するためにはとても重要です。重篤な疾患では予後にも影響するために尚更です。そして、このエビデンスが立体的に構築されていくと、「Aの場合はB」「Cの場合はD」というようにアルゴリズムを形成し、ガイドライン化を進めることができます。だからこそ、医療においてエビデンスは信用であり、鍼灸の世界でもエビデンスの構築が進められているのです。 (さらに…)
今日の一冊 からだとこころの健康学

今日の一冊 からだとこころの健康学
2020.05.10
からだとこころの健康学
稲葉俊郎 著
NHK出版 737円
「私たちが思い描く『健康』は、間違っている?」。西洋医学だけではなく伝統医療、補完代替医療、民間医療も広く修めた医師である著者が、西洋医学の心身を科学の力を借りて他力で管理していく考えと、東洋医学の身体感覚を整えて自力を活かして健康になっていく二つの視点から考察。「あたま」「からだ」「こころ」の三つのつながりから、健康に生きる心構えを伝授する。普段は意識しない「自分の仕組み」を改めて知れば、健康の概念が一変する。医学知識ゼロで読める、目からウロコのレッスン。
『医療は国民のために』293 新型コロナウイルスへの対応で思うこと

『医療は国民のために』293 新型コロナウイルスへの対応で思うこと
2020.04.24
新型コロナウイルスの感染拡大が続いている。各施術者団体には、所属している会員の施術者から「院を開けるか、休業すべきか」との問い合わせが殺到していることだろう。仮に「院を開けるべきだ」と言えば、ウイルス罹患による損害補填の問題が持ち上がり、また「休業すべき」と言えば、その間の休業補償の問題が生じるなど、いずれも「金銭的補填」が浮上し、よって各団体とも明言が難しい。つまるところ、開設している施術者自身の判断ということになる。
そもそも今回の緊急事態宣言において、「医療」はその対象となっていない。 (さらに…)
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』137 「備え」つつ、「感染・発症防止」を

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』137 「備え」つつ、「感染・発症防止」を
2020.04.24
こんなにも大変な世の中になってくるとは、誰も想像していなかったのではないでしょうか。ただ、日本は幸運なことに、欧米ほどの感染拡大や医療崩壊には至っていません。世の中は自粛ムード一色ですが、これがこのまま景気低迷のムードにのしかかり、非常事態宣言解除後の経済回復の足を引っ張るのではないかと心配しています。日本人らしいとは思いますが、このままではまずい。
治療院経営者は自粛閉院し、資金繰りに奔走されているケースもあるかと思いますが、比較的、今は時間があります。私のクリニックでも、患者さんが通院を不安がって電話再診になったり、予約変更が増えたりしています。発熱者の対応もしていますので最前線には違いありませんが、普段と比べると少し時間的余裕ができました。そのような「空いた時間」を、家で子供と過ごしたり、新しい趣味を始めたりして費やしていませんか。家族と過ごすことも大切ですが、外出自粛で命を守りつつ、これからの経済的混乱を生き残らなければなりません。この時間の使い方で、後々の差が出てくると私は思います。自粛解除になった時に何をすれば生き残れるのか、どのような世の中になるのか先を読んで、今から準備を進めなければなりません。明けてから準備するのでは遅いです。未確定要素が多すぎる未来を、あらゆる想定でシミュレーションしまくって、何が必要かを考えて考えまくる必要があります。そして、シミュレーションするには情報を収集してそれを吟味することが必要です。一辺倒な情報収集では不十分で、他人とは違う視点や視野が求められます。前提をも疑うような大局的な思考回路が生き抜く力につながると思います。
一方で、自分が感染しているようでは元も子もありません。誰もが高い確率で誰もがウイルスに「汚染」される前提で動くべきです。汚染されたからといって、必ず「感染」するわけではありません。体外への「汚染」→体内へ入ることによる 「感染」→ウイルスが増幅して「発症」という流れがあります。「感染」→「発症」しないためには、ウイルスを体内に入れないこと、増殖させないこと。そのためには手指消毒とうがいが重要です。ウイルスが付着して感染の原因となる上気道粘膜は、天然のマスクでもあります。頻回にうがいをしてマスクを洗浄しましょう。また、感染成立には「宿主(健康状態)」「感染経路(接触感染・飛沫感染)」「感染源(感染者の咳痰等の飛沫、便等の排泄物)」の3要素があります。感染経路や感染源ばかりが注目されがちですが、宿主が強ければ発症しないし、発症したとしても重症化しません。暴飲暴食や湯冷め、夜ふかしなど、風邪のきっかけになるような行動を控えることが何より大事です。
【連載執筆者】
織田 聡(おだ・さとし)
日本統合医療支援センター代表理事、一般社団法人健康情報連携機構代表理事
医師・薬剤師・医学博士
富山医科薬科大学医学部・薬学部を卒業後、富山県立中央病院などで研修。アメリカ・アリゾナ大学統合医療フェローシッププログラムの修了者であり、中和鍼灸専門学校にも在籍(中退)していた。「日本型統合医療」を提唱し、西洋医学と種々の補完医療との連携構築を目指して活動中。
連載『柔道整復と超音波画像観察装置』181 第5中足骨基底部骨折(下駄骨折)①

連載『柔道整復と超音波画像観察装置』181 第5中足骨基底部骨折(下駄骨折)①
2020.04.24
竹本 晋史(筋・骨格画像研究会)
第5中足骨基底部骨折、いわゆる「下駄骨折」について、超音波画像観察装置(以下、US)を用いて患部を観察し、整復、固定後に経過観察を行った症例を2回に分けて報告する。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 ウェブサイト上の表現の野放し状態について

Q&A『上田がお答えいたします』 ウェブサイト上の表現の野放し状態について
2020.04.24
Q.
広告において「治す」「治療」「診断」などの表記(表現)は医科以外に認められていませんが、現在、ウェブサイト上では放置されています。これらの表現は柔整師法・医師法・景品表示法の観点から見てどうなのでしょうか。また、MJGの「やせプログラム」やウェブサイト上の「全国1位」という表記について消費者庁の行政指導がありましたが、接骨院がウェブサイトで同様の表記を行った場合、指導が入るのでしょうか? (さらに…)
連載『食養生の物語』83 食術継承のチャンス

連載『食養生の物語』83 食術継承のチャンス
2020.04.24
新型コロナウイルスの感染拡大からの外出自粛要請、そして緊急事態宣言。不安で何もできなくなってしまう人と、できることを探してやろうとする人との差が出てきています。
当院の患者さんには、どうせ家に居てもすることがないならと、断食(ファスティング)を実践してみている方が複数名いらっしゃいます。断食の効果には、胃腸の負担をなくすことで自然治癒力を向上させる効果があるといわれるほか、心も体も澄んできて落ち着きを得られます。何より、数日間食べずにいても平気でいられるという実体験は大きいでしょう。
何をしたらいいか分からないという患者さんには、親子で料理をする時間を持つように伝えました。普段であれば学校に行き、部活動や塾、習い事などで忙しい子どもたちにとって、なかなか時間を割けないことです。とはいえ、地震や台風などの災害時とは違ってガス・水道・電気といったライフラインは保たれていて普段と変わらず、普段と違うのは家族が家にいることだけです。だからこそ、家事手伝いに参加させ、「おふくろの味」を伝えていく絶好の機会ではないでしょうか。20年前に著された『伝統食の復権』(島田彰夫著・東洋経済新報社)という書籍では、「葉の付いたダイコンが一本あったとします。そこから何種類の料理がつくれるでしょうか」と、生きていく知恵を『食術』として親から子に継承していく必要性が説かれていました。大根があれば、煮物はもちろん生で食べることもでき、漬けて漬物に、干して切干大根にすれば保存食にもなる。葉っぱも炒めたりして利用できますよね。バリエーション豊かに、飽きずに美味しく食べ続けることは生きる術なのです。食養生では「一物全体」といって、自然にあるがままの状態、丸ごと全体でバランスが取れていて、そのままいただくことが体内のバランスを取るのにも望ましいという考えがあります。穀物は精白せず、野菜は皮ごと・葉ごと、できるだけ丸ごと食べるのが健康に良いとされています。現代栄養学の観点からも、植物の皮や葉には栄養が豊富であることが分かっています。普段なら半分・部分にカットされたものを買うようなものでも、今だからこそ丸ごと一つで買ってきて、様々な調理法で使い切ってみることをすすめます。買い物に外出する機会を減らし、ゴミを減らすこともできます。「食術」を見直し、継承できるチャンスとして前向きに取り組んでみてはいかがでしょうか。
外出自粛要請の頃から、スーパーマーケットではインスタント麺やレトルト食品、缶詰などが売り切れていったところが多かったようです。繰り返しになりますが、ライフラインが保たれていて外出自粛が長期化している現状、備蓄は必ずしもこうした非常食である必要はなかったはずです。メディアの情報に振り回されて過度に不安にならず、「情報断食」も心掛けたいところですね。
【連載執筆者】
西下圭一(にしした・けいいち)
圭鍼灸院(兵庫県明石市)院長
鍼灸師
半世紀以上マクロビオティックの普及を続ける正食協会で自然医術講座の講師を務める。
連載『あはき師・絵本作家 かしはらたまみ やわらか東洋医学』18 「それでも春はやってきた」

連載『あはき師・絵本作家 かしはらたまみ やわらか東洋医学』18 「それでも春はやってきた」
2020.04.24
黄帝内経素問には、春には人の心にやりたいことが自然と湧くと書かれています。 (さらに…)
今日の一冊 感染症 増補版

今日の一冊 感染症 増補版
2020.04.24
感染症 増補版
井上 栄 著
中公新書 902円
平成15年、香港で起きたSARSの流行。日本人観光客は多く存在したにもかかわらず、日本人の患者が出なかったのはなぜか――そんな問いかけから始まる、感染症への探究。伝染病との闘いの歴史、病原体の種類や性質、伝播の基礎知識と遮断法、そしてこれから気を付けるべき感染症……コレラから新型インフルエンザまで、感染症研究の第一人者として知られる著者が、平易な文体で分かりやすく解説する。平成18年に発行されたロングセラーに、新型コロナウイルスの特徴や予防法に関する考察を加えた増補版。
東京都の休業要請、あはき・柔整の施術所は対象外

東京都の休業要請、あはき・柔整の施術所は対象外
2020.04.14
新型コロナウイルスの緊急事態宣言を受け、東京都が要請している休業施設について、「鍼灸、マッサージ、柔道整復の施術所」が対象外であることが分かった。都が4月13日夕、休業を要請する対象施設などの詳細を公表した。
発表では、あはきと柔整の施術所は、病院、診療所、歯科、薬局とともに、「医療施設」に含まれ、「社会生活を維持するうえで必要な施設」として休業の対象外となった。備考欄には「適切な感染防止対策の協力を要請 ※有資格者が治療を行うもの」との記載があった中、「整体院」も含まれていたのは疑問というほかない。
『医療は国民のために』292 療養費改定率で実施される「医科の半分」に思う

『医療は国民のために』292 療養費改定率で実施される「医科の半分」に思う
2020.04.10
あはき・柔整療養費の次期料金改定が迫っている。2年前の前回(平成30年度)改定では、プラス改定となった。療養費の改定率については、20年も前から続いている「医科の2分の1(半分)」というルールが存在していることは、周知の通りだろう。ちなみに、大昔にはなぜか「歯科の半分」ということもあったと記憶しているが、それはともかく、現在、この「2分の1ルール」(実際はルールというほどのものではなく、単なる申し送りに過ぎないが……)に対し、支払い側の保険者はもちろん、施術者側である業界も否定的な見解を示している。 (さらに…)
連載『不妊鍼灸は一日にして成らず』24 パンデミックとは

連載『不妊鍼灸は一日にして成らず』24 パンデミックとは
2020.04.10
新型コロナウイルスのパンデミック真最中です。当院の従業員達に「パンデミックはどうして起こるのか」と問うと、返答があいまい。流行の大きさは、ウイルスと免疫のどういった攻防で変わるのでしょう。感染防御については薄くしか勉強してこなかったので、復習も兼ねて振り返ります。例外的な場合もありますが、まずは三つの言葉を示します。「①抗原原罪による免疫の抑制」「②突然変異による抗原ドリフト」「③遺伝子組み換えによる抗原シフト」です。 (さらに…)
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』136 新型コロナに「抗体検査」を

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』136 新型コロナに「抗体検査」を
2020.04.10
こんなにも、新型コロナウイルスの話を続けることになるとは思いませんでした。この原稿を書いているのは4月6日。明日には、ついに緊急事態宣言が出されていることでしょう。多くの施術者が治療院を閉めたり、半ば休業状態になったりしているのではないかと想像します。色々な噂が飛び交う中、正確に情報をつかむように努力しましょう。コロナに関しては一日ごとに新しい情報が入ってきて、検証され、廃れていく――。そんな目まぐるしい情報の更新があります。足元の情報に飛びつきたくなりますが、大局的に判断して、少し先を見通すようにすると、冷静に落ち着くこともできます。
さて現在、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)の診断に「抗体検査」を行うべきだという言論が飛び交っています。 (さらに…)
連載『中国医学情報』181 谷田伸治

連載『中国医学情報』181 谷田伸治
2020.04.10
☆全身性無汗症の鍼治療例
成都中医薬大学・趙映らは、難病の無汗症の鍼治療例を報告(中国鍼灸、19年9期)。
患者=男、51歳。
主訴=全身無汗で6カ月あまり。時々身体の倦怠疲労感あり。
現病歴=半年前、特に誘因なしに全身無汗となり、暑い日や運動後も無汗。病状が次第に重くなり、日常活動に影響するが、他に異常なし。皮膚科の検査では異常なしで、自律神経失調と診断されるが服薬せず。後に自ら益気補脾方剤(内容不明)を服用するが無効。
現症=顔色悪く、肥満体でBMI27.3、睡眠中よだれ出る、酒やタバコの嗜好なし、運動後に息切れを自覚、外食多く、脂肪分の多い甘い物を好む、小便黄色、大便正常、睡眠可、舌胖苔白膩、唇舌乾燥状態、脈象濡軟無力。
診断=無汗症。証は湿遏営衛、肺脾気虚。
治法= (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 今後は長期施術継続理由を「SOAP形式」の記載で求められる?

Q&A『上田がお答えいたします』 今後は長期施術継続理由を「SOAP形式」の記載で求められる?
2020.04.10
Q.
協会けんぽからの柔整療養費の返戻理由に「長期施術の継続の必要性の理由につきましては、患者さんの自覚症状だけではなく、施術者の方の患部ごとの所見など客観的情報も含めたSOAP形式での記載をお願いします」とありました。よく分かりません?
A.
確かに最近、一部の協会けんぽから、ご質問にあるような理由で返戻がありますね。「SOAP(ソープ)」とは、医療や看護の分野における、患者さんの経過をカルテに記載する際の形式の一つで、 (さらに…)
連載『汗とウンコとオシッコと…』188 臨機応変

連載『汗とウンコとオシッコと…』188 臨機応変
2020.04.10
春が早く過ぎ、夏の脉の弛緩する姿が現れている。血圧に関係なく脉が弛緩するのだ。それにより血圧が高めの人は、腫脹するまではいかないものの組織の深部が痛むことが多く、血圧が低い人には弛緩性の関節痛やめまいなどが多くみられる。季節の移り変わりの早さは、小中学校の卒業式や幼稚園や保育園の卒園式に桜が咲くほどだ。しかも薄桃色のソメイヨシノに加えて濃い桃色の山ツツジが咲いたなんて、筆者も初めて見た。また、新型コロナの蔓延も早い。事前の想定は難しく、その時々で対策を立て臨機応変に対応しないと難しいところである。人は未知なるものを恐れる傾向が強く感情論に走りがちだから、冷静な対応が望まれる。ただ、ウイルスと菌の違いが分からず、若い人が「コロナ菌」と称した姿を見て、かつての教育改革の弊害を垣間見たことは残念でならない……。
白川女史が40代半ばの上杉某という女性を治療していた。結婚しているものの子宝に恵まれず、悠々自適な生活を送っている女性だ。元々貧血で低体温、低血圧で更年期に差し掛かる不定愁訴を白川女史が調整していた。スイーツを控えさせ、いわゆるGIの値が高い食事を改善してもらい、適度な運動を勧めてきた結果、全体的には改善してきたものの、性周期の乱れがまだまだ残る状態だ。
「先生、先日から頭が重かったり、急にふらついたりして……なんだか右の肩が凝ってるのかしらね、首の動きも悪いんです……」
と、症状を訴えていた。
脉を確認した白川は、
「これは高温期が終わりかけて月経前の状態に近づいているのと、気温差、暖かいといえまだ寒いですからね……冷え逆のぼせみたいなのが重なって出てるだけですよ。あと、尿が減っているのもそれを助長させますね」
と、説明しながら治療を終えた。
だが、上杉某さんが会計をしている時、鷹の目の横転先生は彼女が、左手でこめかみを押さえて撫でながら、ややうつむき加減で、白川と世間話をしている姿を見逃さない。白川は何も気付いていないようだ……。 彼女が帰った後、横転先生はたしなめる。
「白川、緩めすぎたな……。川端ならいざ知らず、鍼後、マッサージしているとき女同士の会話に気を取られて緩めすぎたの分からんかったやろ。鍼後はシャキッとしとったのに……」
「えっ、どういうことなんでしょう? 分かりません」
表情を引き締める白川。
「会計の時、こんな感じでこめかみを手の平で押さえとったやろ。楽になりましたなんて言いながらでも……。あれ、後でくるぞ。あれは患者が無意識に胆経を押さえて外頚動脈を按圧して調整してるんや、緩めすぎた圧を上げるためにな……患者の何気ない動作を意識下に置かんとあかん。最後まで気を抜くな。そうすれば、失敗の対策がすぐ打てる」
「あ~、あの時の……」
と、思い出した様子の白川が驚いている。この話には後日談があり、やっぱり、何時間か後にふらつきがひどくなったとのことだった……。
【連載執筆者】
割石務文(わりいし・つとむ)
有限会社ビーウェル
鍼灸師
近畿大学商経学部経営学科卒。現在世界初、鍼灸治療と酵素風呂をマッチングさせた治療法を実践中。そのほか勉強会主宰、臨床指導。著書に『ハイブリッド難経』(六然社)。
連載『医療再考』14 得られた情報でどこに導くのか?―鍼灸の立ち位置を考えた新しい情報の形
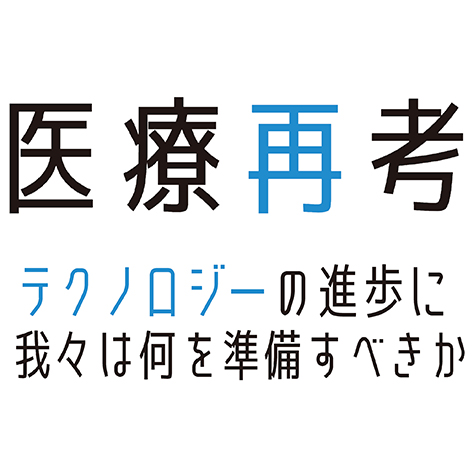
連載『医療再考』14 得られた情報でどこに導くのか?―鍼灸の立ち位置を考えた新しい情報の形
2020.04.10
これからの診断・治療には、治療院から得られる一次元的なデータだけでなく、ウエアラブルデバイスから得られる生活情報(生活ログ)が積極的に用いられることになるでしょう。生活ログと治療院で取得した東洋医学的な診察情報を掛け合わせた結果から、新しいアルゴリズムを導ければ、新たな治療パターンを提唱していけます。
そこで、我々は新たに医療関係者向けのアプリとして、患者の生活ログとしての「YOMOGI」のデータと東洋医学的な診察結果を合わせて新しいタイプ(証)を分類するアルゴリズム「YOMOGI Pro」を作成し、治療に応用する検証実験を始めています(7月一般公開予定)。 (さらに…)
『ちょっと、おじゃまします』 ~今後のために良い状態を~ 大阪府堺市<あおい整骨院>

『ちょっと、おじゃまします』 ~今後のために良い状態を~ 大阪府堺市<あおい整骨院>
2020.04.10
「目の前の治療だけではなく、今後のために身体の良い状態を作っていくことが大切です」。そう語るのは、柔道整復師の西村光紘先生です。進路を決めたのは高校3年生の頃。もともと、スポーツトレーナーの道を考えていたそうですが、サッカー部の練習中に内側側副靭帯を痛め、治療後のリハビリで整骨院のお世話になった経験から、ケガを含めた幅広い状況に対応できる柔整師の道を志しました。 (さらに…)
今日の一冊 ウォーキングの科学 10歳若返る、本当に効果的な歩き方

今日の一冊 ウォーキングの科学 10歳若返る、本当に効果的な歩き方
2020.04.10
ウォーキングの科学 10歳若返る、本当に効果的な歩き方
能勢 博 著
ブルーバックス 990円
「『一日に1万歩』は間違いだった?」。医師で研究者の著者は個人的に「きつい」と感じる速歩を1日15分以上・週4日以上実施すれば持久力、筋力の向上を図れると指摘する。また血圧や血糖値、コレステロールなどの生活習慣病指数を下げ、さらには癌や認知症など様々な病気に影響を与える炎症反応を抑制したり、関節痛や不眠の改善、骨年齢の若返りも確認されているという。7,000人ものデータから導き出された、「運動嫌いでも、膝や腰が痛くてもできて、リハビリにも応用できる」最適な歩き方を徹底解説。