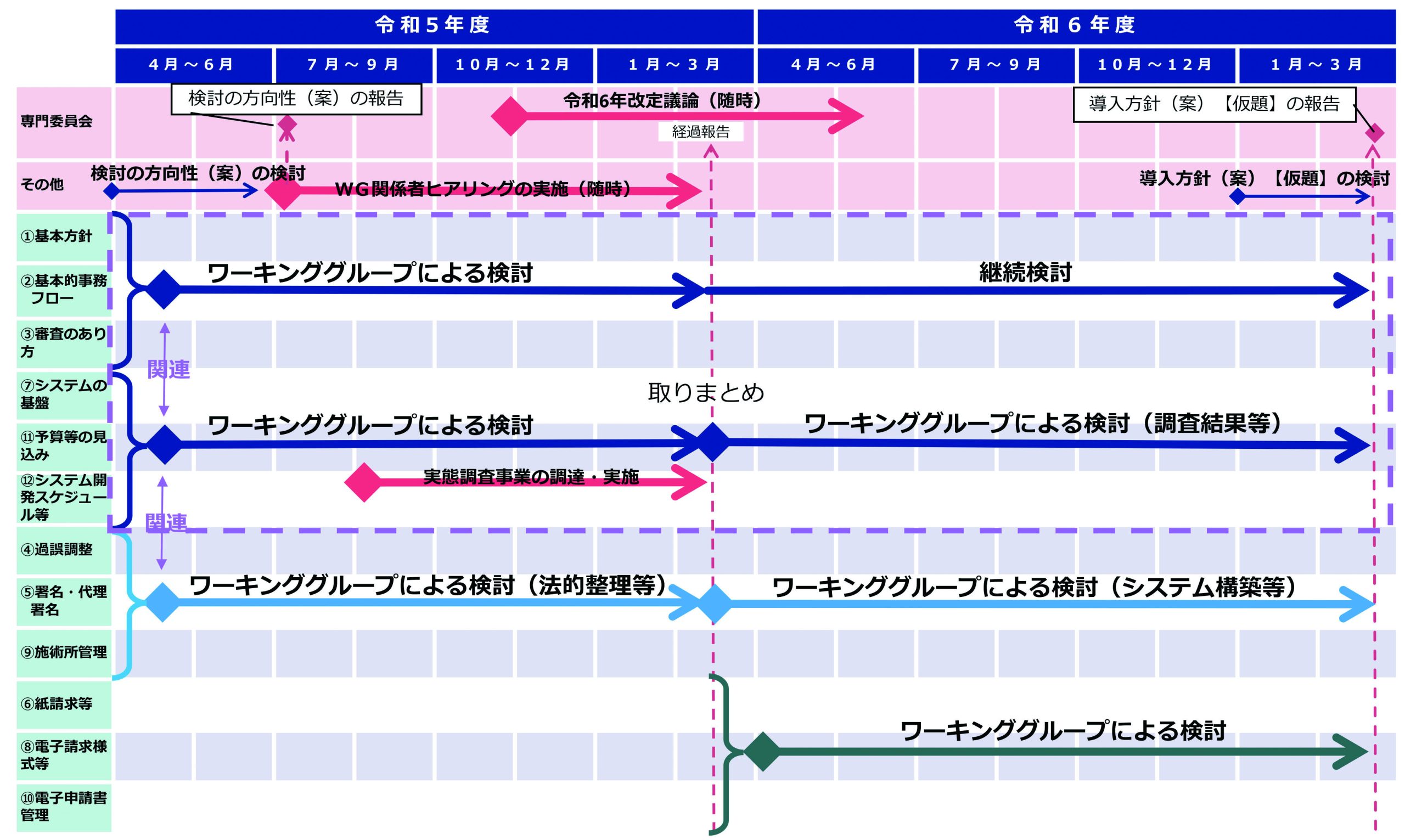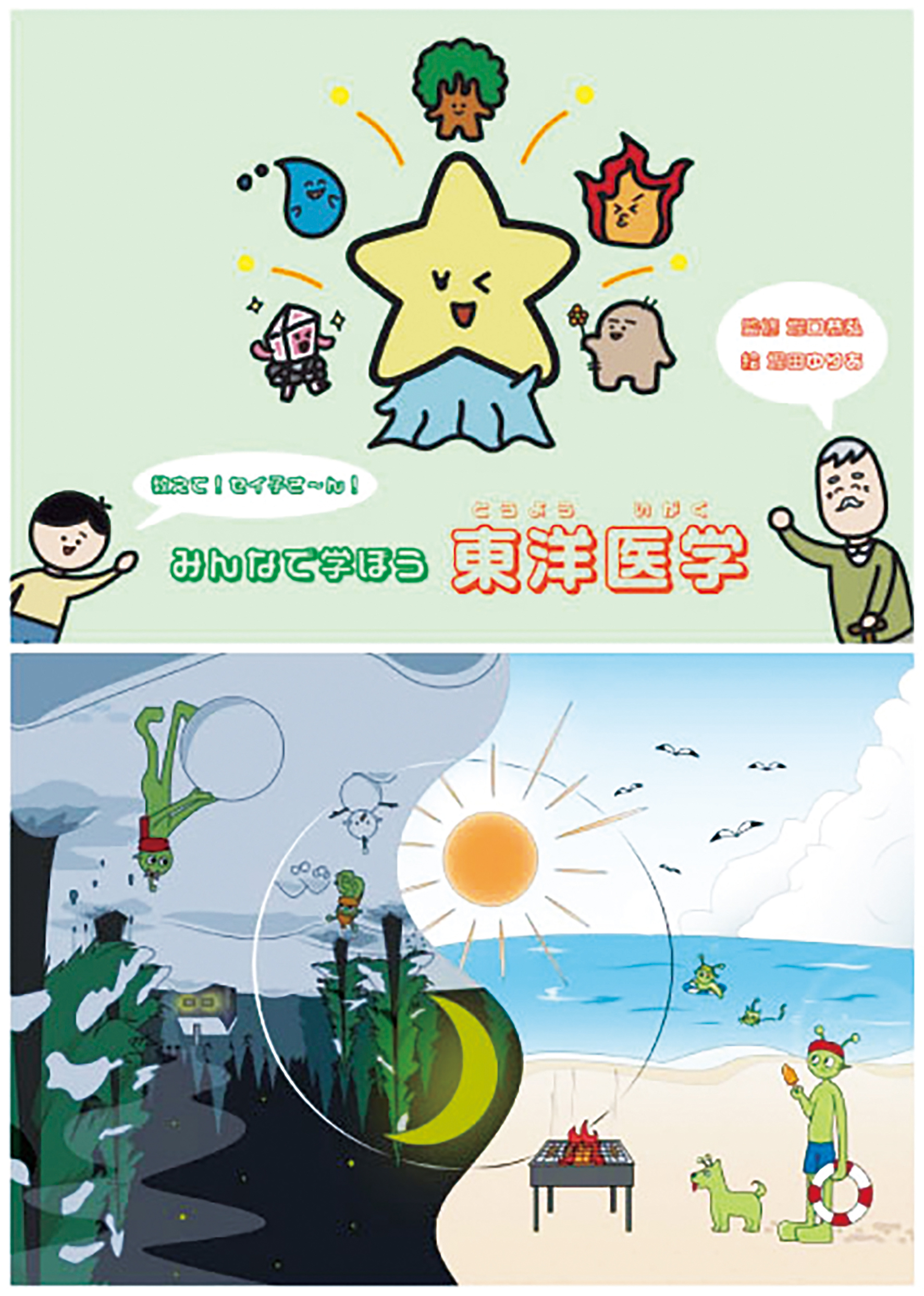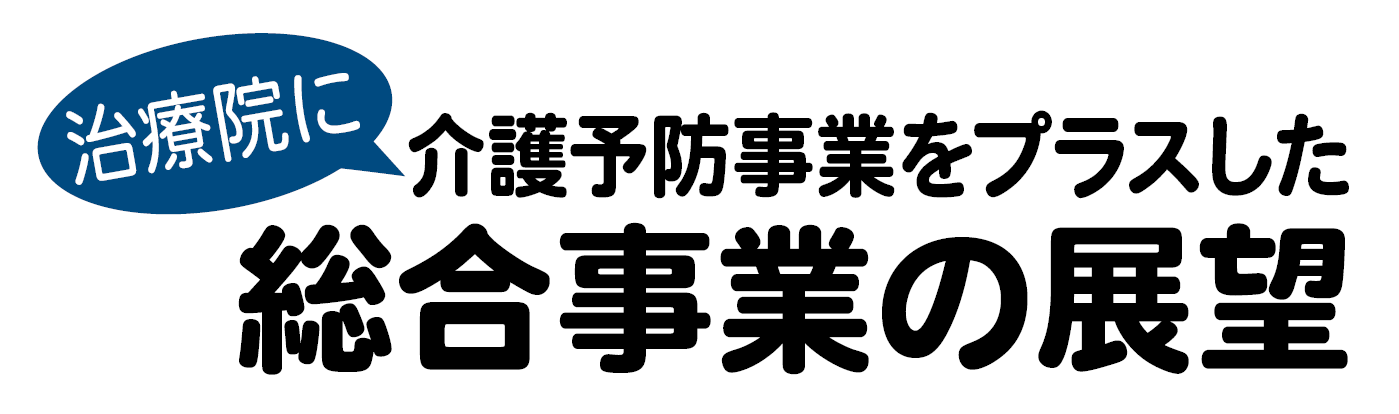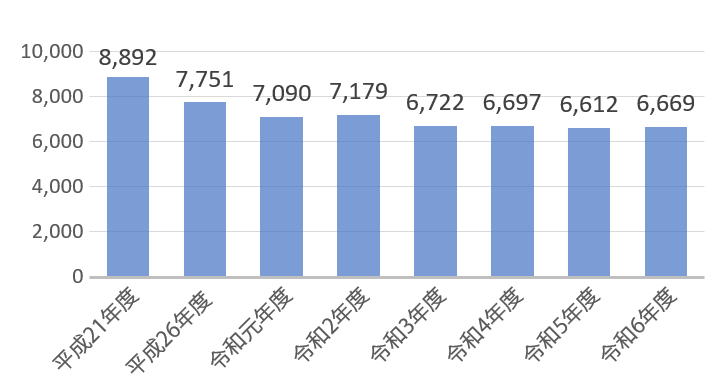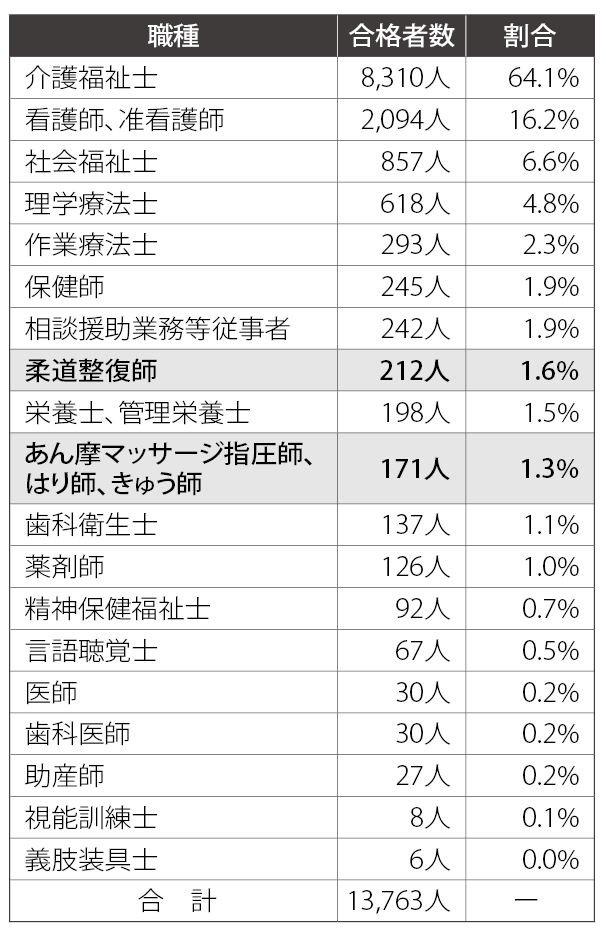東京都、施術所向け物価対策支援の申請を10月より
2023.07.27
物価高騰に直面する施術所の負担軽減のため、全国的に支援策が実施されるなか、東京都がこのほど、緊急対策支援金を創設して10月上旬より申請の受付を始めると公表した。
支給額は1施術所当たり5000円で、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所、または償還払による保険診療を行っている施術所に限るとしている。
なお、ほかの都道府県の手続き状況としては、愛知県が7月10日から、長崎県が7月18日から、福岡県が7月25日から、それぞれ申請の受付を開始している。
■東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/iryo-bukka.html
■愛知県医療機関等物価高騰対策支援金
https://jimukyoku.site/aichi/iryokikanbukkakoutoushien/sejutsujo/
■長崎県医療機関等物価高騰緊急支援事業支援金
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/iryo/hojokin/iryo_bukka/
■福岡県医療機関等物価高騰対策支援金
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/iryo-bukkakoutou-shien.html