コロナ禍の受療控えにより 柔整・あはきとも後期高齢が大幅減 厚労省・令和2年度の保険者別療養費
2023.03.24
厚労省保険局調査課が1月に公表した『医療保険に関する基礎資料』において、令和2年度の保険者別療養費の状況が示された。 (さらに…)
コロナ禍の受療控えにより 柔整・あはきとも後期高齢が大幅減 厚労省・令和2年度の保険者別療養費

コロナ禍の受療控えにより 柔整・あはきとも後期高齢が大幅減 厚労省・令和2年度の保険者別療養費
2023.03.24
厚労省保険局調査課が1月に公表した『医療保険に関する基礎資料』において、令和2年度の保険者別療養費の状況が示された。 (さらに…)
『医療は国民のために』361 時代の流れとともに 施術者団体も変貌を遂げる必要がある

『医療は国民のために』361 時代の流れとともに 施術者団体も変貌を遂げる必要がある
2023.02.24
住宅融資やグリーンピアを手掛けていた「年金福祉事業団」と、健康保険・年金事業を国として担当していた「社会保険庁」は、ともに巨大組織であった。かつて私も職員として勤務していたのだが、今はもう存在しない。組織の廃止やその体制を変更せざるを得なかったのも時流だったといえるだろう。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 オンライン請求は柔整師にとってメリットだらけ!?

Q&A『上田がお答えいたします』 オンライン請求は柔整師にとってメリットだらけ!?
2023.02.24
Q.
柔整療養費のオンライン請求議論が本格化しているようですが、私たち柔整師個人にとってはメリットだらけですよね。そうであれば、早期の導入を求めたいです。 (さらに…)
『医療は国民のために』360 患者のニーズは骨折や脱臼ではなく、 疼痛を伴う慢性的な運動器疾患への手技だ

『医療は国民のために』360 患者のニーズは骨折や脱臼ではなく、 疼痛を伴う慢性的な運動器疾患への手技だ
2023.02.10
最近の柔整療養費における返戻・不支給処分で、私が脅威に思っている事例を紹介したい。新規外傷の請求にもかかわらず、保険者が同部位を過去に遡って調査し、同部位の治療実績を見つければ、「×年前から継続した慢性的な疼痛のための処置であって、これは慢性の筋肉疲労にあたりますから、療養費の対象とはなりません」と返してくるのだ。当然、医科であれば新規の再発(一度治癒して再発)と捉えるものを、柔整では異なる判断をされ、冒頭に述べた暴挙に出る保険者がいる。しかも、既に複数の事例が発生している。 (さらに…)
施術業界展示会「からだケアEXPO’23」
の様子.jpg)
施術業界展示会「からだケアEXPO’23」
2023.02.10
3月に東京で、初の土日開催
施術業界が対象の総合展示会『からだケアEXPO東京'23 第4回健康施術産業展』が3月18日(土)、19日(日)、東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催される。主催はブティックス株式会社(東京都港区)。
土日開催は今回が初めて。治療機器や患者管理システム、自費メソッド、健康関連用品など、施術所向け商品・サービスが一堂に会し、出展企業数は120を超える。来場事前登録をすることで5千円の入場料が無料に。
会期中は、「開業支援」と「物販推進」がテーマの2つの特別専門展を新設し、併せて業界有識者によるセミナーも開かれる。業界動向セッションとして、『激減する療養費に対する具体的な対策と適正化に対する当会の見解』(上田孝之氏・全国柔整鍼灸協同組合専務理事)、『鍼灸・マッサージの未来予想図』(粕谷大智氏・新潟医療福祉大学リハビリテーション学部鍼灸健康学科学科長)などが行われる。
Q&A『上田がお答えいたします』そもそも医療情報をもらえる仕組みづくりなど 当初から無かったのだ!

Q&A『上田がお答えいたします』そもそも医療情報をもらえる仕組みづくりなど 当初から無かったのだ!
2023.02.10
Q.
令和6年の秋からマイナンバーカードが保険証となり、実質的な保険証の廃止にあたり、鍼灸整骨院でも患者さんの診療歴情報を確認できると期待していたところ、単に資格の得喪記録情報のみになってしまうとお聞きしました。 (さらに…)
柔整療養費のオンライン請求WG 第1回会議の議事要旨公開

柔整療養費のオンライン請求WG 第1回会議の議事要旨公開
2023.02.10
昨年12月28日に開かれた『第1回柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループ』の議事要旨が、厚労省ホームページで1月26日に公開された。会議で厚労省が提示した検討課題等について、業界代表らを含む構成員が意見交換を行ったようで、以下、議事要旨で記された「主な意見等」だ。
※太字は柔整業界の代表が発言したと思われる意見 (さらに…)
連載『鍼灸師・柔整師のためのIT活用講座』24(最終回) オンラインもオフラインもない時代を どのように生き抜くのか?
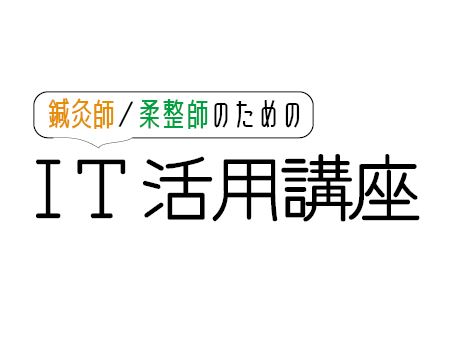
連載『鍼灸師・柔整師のためのIT活用講座』24(最終回) オンラインもオフラインもない時代を どのように生き抜くのか?
2023.02.10
医療・健康の未来はIT化が進み、データドリブンな情報社会になるであろう……。本連載を通して、鍼灸師や柔道整復師の先生方にもIT技術を役立ててもらおうと記事を書き進めて参りました。
昨今、デジタル庁が発足し、様々なデータをデジタル化、DX(デジタルトランスフォーメーション)化することで業務の効率化を図り、ビッグデータ化することで様々な社会問題の解決に取り組んでいます。特に医療・健康分野では、厚生労働省がマイナンバーカードと保険証のデータを紐づけることで医療情報の一元化を目指しています(鍼灸・柔整師の療養費請求情報を含むかは検討中)。また、健康に関してはウェアラブルデバイスやアプリによる健康管理が一般化し、デジタルヘルスの占める割合が次第に増えています。 (さらに…)
柔整療養費 オンライン請求に向けWGを開催

柔整療養費 オンライン請求に向けWGを開催
2023.01.25
柔整療養費のオンライン請求導入に向け、多岐にわたる課題を検討するワーキンググループ(WG)が、厚労省保険局長の主導で設置されたことが分かった。
昨年12月28日に第1回会議がオンラインで開催され、参加者の自由な意見交換を確保するため、原則、会議は非公開とされている。
WGは、今後オンライン請求を実施するに当たり、審査・支払等の事務フローや法令(制度)といったソフト面の課題と、システム等の開発における技術的・実務的なハード面での課題など、整理・解決をしなければならない事項が多数で広範囲にわたっていることから設置された。
今後、会議を重ねて意見や提言などをとりまとめ、社会保障審議会部会の柔整療養費検討専門委員会に適宜報告を行っていくようだ。
本紙の取材によれば、 (さらに…)
『医療は国民のために』359 柔整での電子カルテの検討は始まるのか?

『医療は国民のために』359 柔整での電子カルテの検討は始まるのか?
2023.01.25
医科では、患者がより質の高い医療サービスを受けられるよう、厚労省が電子カルテについてのガイドラインを発出し、様々な必要様式を策定している。
一方、柔整師の施術に係る電子施術録(電子カルテ)の検討は全く進んでいないように感じる。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 支給基準の記載は要件を確認するだけでなく、 文中の「接続詞」にも十分に注意を払うこと

Q&A『上田がお答えいたします』 支給基準の記載は要件を確認するだけでなく、 文中の「接続詞」にも十分に注意を払うこと
2023.01.25
Q.
あはき療養費の施術報告書交付料は、同意有効期間の最終月に交付した場合において前5カ月の期間に係る療養費の支給で施術報告書交付料が支給されていない場合に支給するものということでいいのですか。 (さらに…)
厚労省、「柔整レセコン導入」調査 明細書加算や次期改定の議論のため

厚労省、「柔整レセコン導入」調査 明細書加算や次期改定の議論のため
2023.01.10
厚労省がこのほど、全国の接骨院・整骨院を対象に、レセプトコンピューターシステム(レセコン)の導入状況などの実態調査を進めていることが分かった。柔整療養費の令和4年度料金改定で新設された「明細書発行体制加算」に関連する調査で、調査結果を次期改定に向けた議論の場で用いる予定だ。厚労省は柔整団体にも広く周知するよう求めているという。 (さらに…)
柔整の令和5年度施術管理者研修

柔整の令和5年度施術管理者研修
2023.01.10
2月頃に申込開始
柔整療養費の受領委任を取り扱う上で義務化されている「施術管理者研修」の令和5年度上半期の開催日程が発表された。
5月から9月まで毎月1回開催され、計5回(下表参照)。いずれもオンライン研修で実施され、一部で会場視聴も可能。
費用は2万円。受講申込みは、公益財団法人柔道整復研修試験財団のホームページ(https://www.zaijusei.com/)から。
Q&A『上田がお答えいたします』オンライン請求導入までの「過渡期問題」を 柔整団体はどう考える?

Q&A『上田がお答えいたします』オンライン請求導入までの「過渡期問題」を 柔整団体はどう考える?
2023.01.10
Q.
柔整療養費のオンライン請求導入の議論に絡めて、「復委任」の問題も検討されているようですが、施術者団体はどのように対応すればよいのでしょうか。 (さらに…)
連載『鍼灸師・柔整師のためのIT活用講座』23 鍼灸・柔道整復の プラットフォームを再構築する
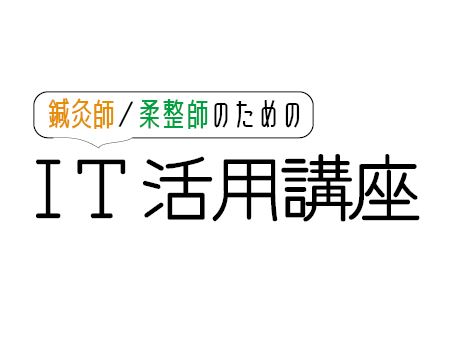
連載『鍼灸師・柔整師のためのIT活用講座』23 鍼灸・柔道整復の プラットフォームを再構築する
2023.01.10
本連載では、あらゆる分野の中心的な仕組みとなってきたIT技術の考え方を学ぶことで、鍼灸・柔整師に今後必要な新しいテクノロジーとは何かについて考えてきました。
医療や健康分野は、近年、人工知能(AI)やIoT、ウェアラブルデバイス、ビッグデータ解析、仮想現実(VR)など最新のデジタル技術を活用するデジタルヘルスが急速に発展しています。生体情報を記録するセンシング技術が発展したおかげで、自宅に居ながら様々な情報を記録することができるようになりました。 (さらに…)
あはきの令和5年度施術管理者研修

あはきの令和5年度施術管理者研修
2022.12.23
申込み、来年1月から
あはき療養費の受領委任を取り扱う上で義務化されている「施術管理者研修」の令和5年度の開催日程が、公益財団法人東洋療法研修試験財団より公表された。
令和5年4月22日を皮切りに、年度末まで計12回開催される(下表参照)。いずれも会場とオンラインでの同時開催(ハイブリッド式)。費用は2万3000円。2日間(16時間)にわたり、適切な支給申請などを学ぶ。
『医療は国民のために』357 もはやこれまでか?療養費のマイナス傾向が止まらない

『医療は国民のために』357 もはやこれまでか?療養費のマイナス傾向が止まらない
2022.12.23
厚労省が11月末に公表した令和2年度の療養費の支給額を見て、愕然とした。柔整療養費は2863億円で、前年度比10%以上の減少だった。あん摩・マッサージ療養費も636億円で同16%もの減少、同じくはり・きゅう療養費も419億円で同5%下がっているではないか。推計値であるとはいえ、おおよそ実態に近い数値と考えることができるだろう。 (さらに…)
全国柔道整復師統合協議会が日整に宛てた公開質問状〈全文〉

全国柔道整復師統合協議会が日整に宛てた公開質問状〈全文〉
2022.12.23
私たち「全国柔道整復師統合協議会」は、個人契約柔道整復師及び個人契約請求団体の統合団体です。すべての柔道整復師の社会的地位向上と現場の先生方が目の前の患者の施術に専念できる環境作り、そして未来の柔道整復師の育成等に全力を尽くすため活動しており、会員数は、令和4年3月31日現在で柔道整復施術所15251ヶ所であります。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 療養費支給申請書転帰欄の「中止」は どういったタイミングで使う?

Q&A『上田がお答えいたします』 療養費支給申請書転帰欄の「中止」は どういったタイミングで使う?
2022.12.23
Q.
療養費支給申請書の転帰欄には、治癒、中止、転医の別を記載することとなっていますが、「中止」とは具体的にはどのような場合なのでしょうか。 (さらに…)
令和2年度の柔整療養費、3,000億円下回る あはきもコロナ禍で減少に転じ

令和2年度の柔整療養費、3,000億円下回る あはきもコロナ禍で減少に転じ
2022.12.09
令和2(2020)年度に外傷による治療で全国の接骨院・整骨院に支払われた柔整療養費が2863億円だった。厚労省が11月30日に発表した「国民医療費の概況」で示した。15年近く3000億円以上で推移してきたが、今回これを下回り、減少に歯止めがかからない状況となっている。 (さらに…)