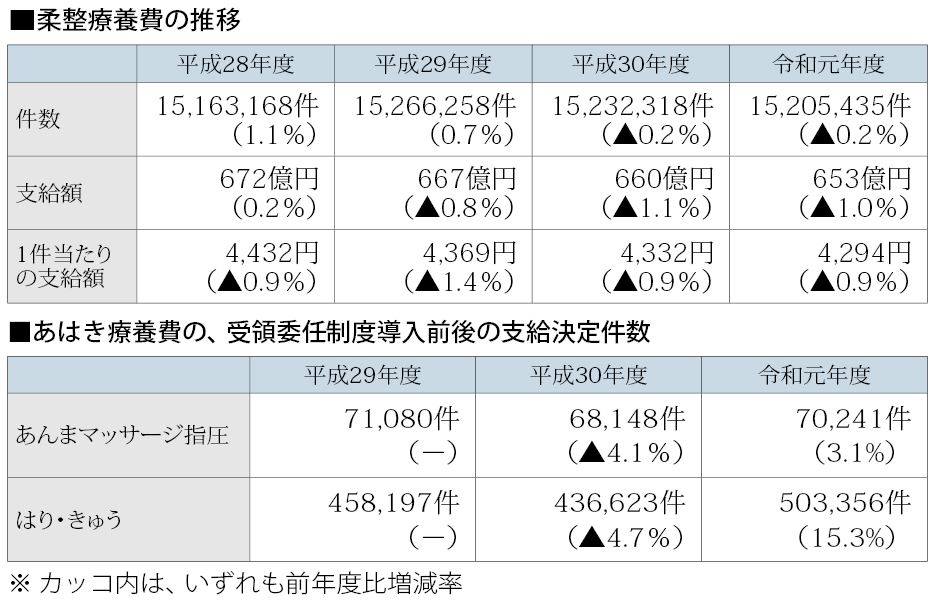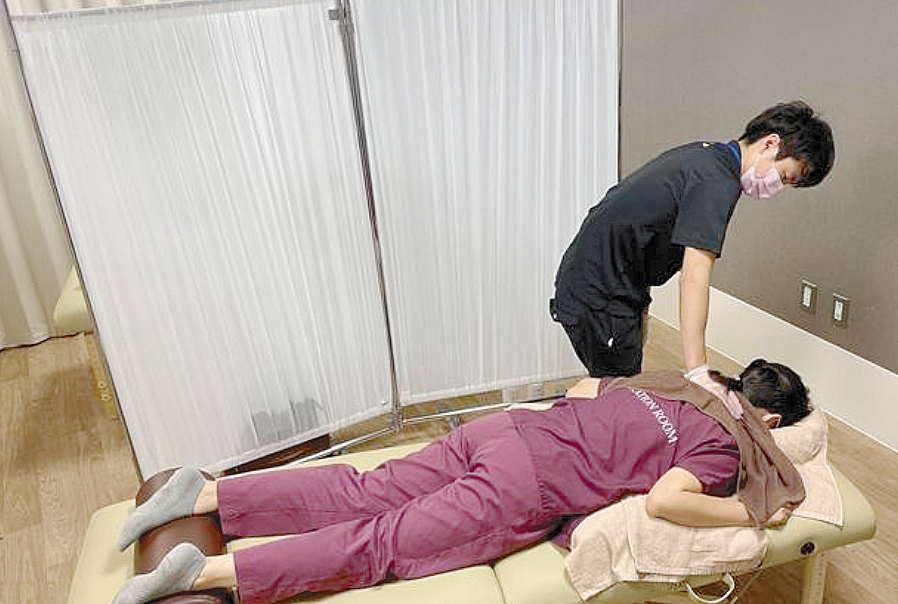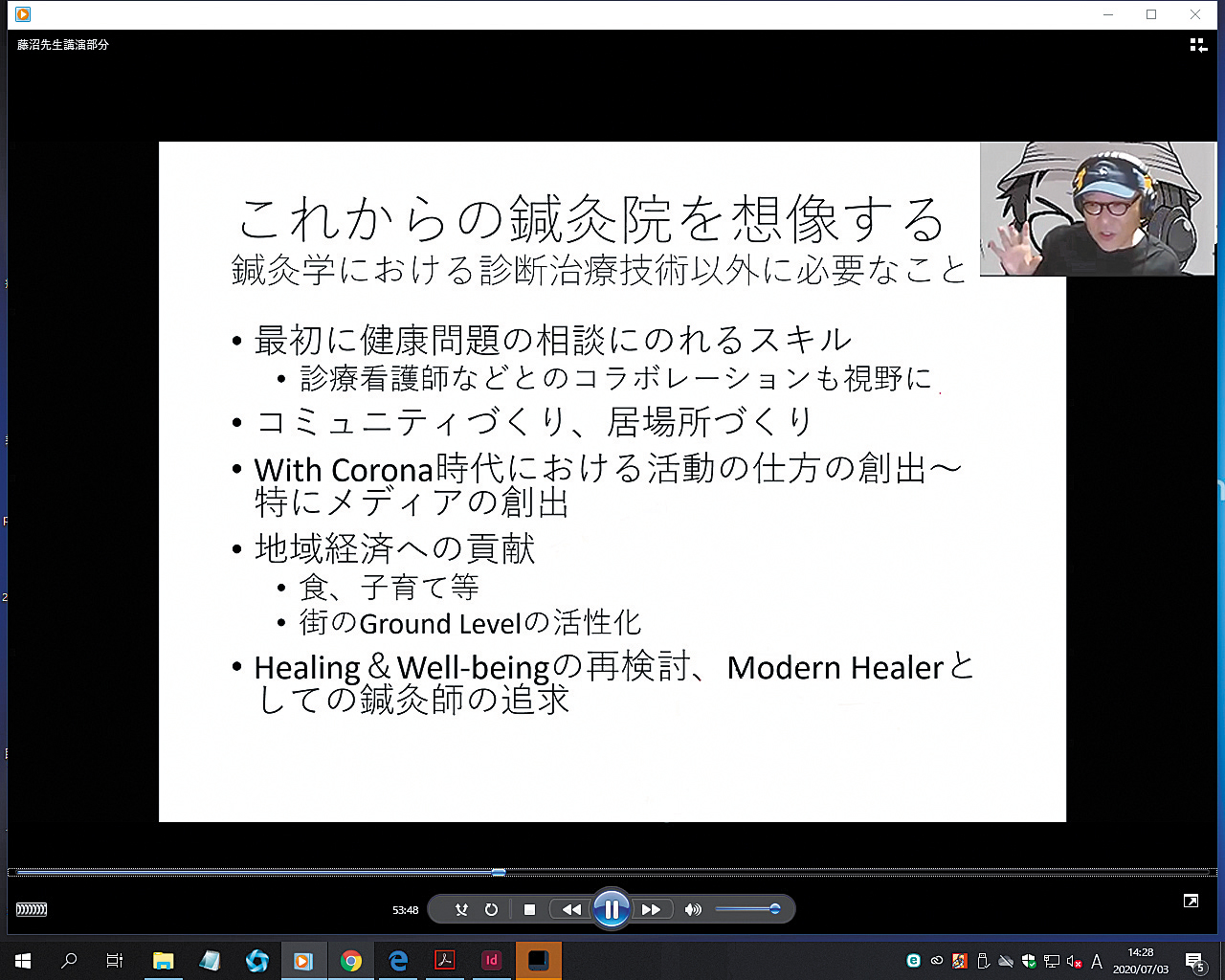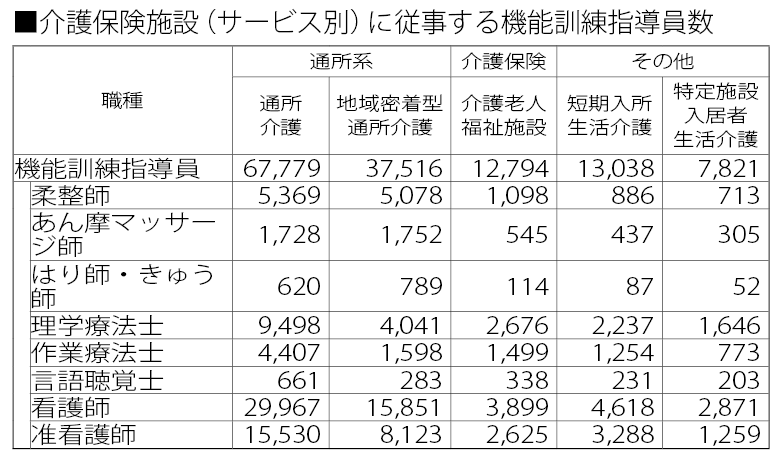【寄稿】コロナ禍に「灸」で免疫力アップを
2020.08.25
直接灸によって白血球が増加する、つまり免疫能が向上することは知られているが、熱い、臭い、艾炷を作るのが面倒といった理由で「直接灸離れ」が進んでいる。宝塚医療大学教授・中村辰三氏は直接灸と同等の温熱と温熱時間を実現した電子灸をメーカーと共同開発。その電子灸による施灸によって直接灸と同様に白血球が増加したとの研究結果を報告した。コロナ禍で「免疫力向上」などが叫ばれる今、注目の論文――。
N灸(電子灸)による白血球増強効果について
宝塚医療大学教授 中村辰三
【研究の背景】
直接灸(透熱灸)は日本で古くから鍼灸治療で用いられ、多くの研究がなされてきた。その効果の特徴は間接灸と異なり白血球の遊走速度、貪食能などの増加、特に白血球数が増加することである。 (さらに…)