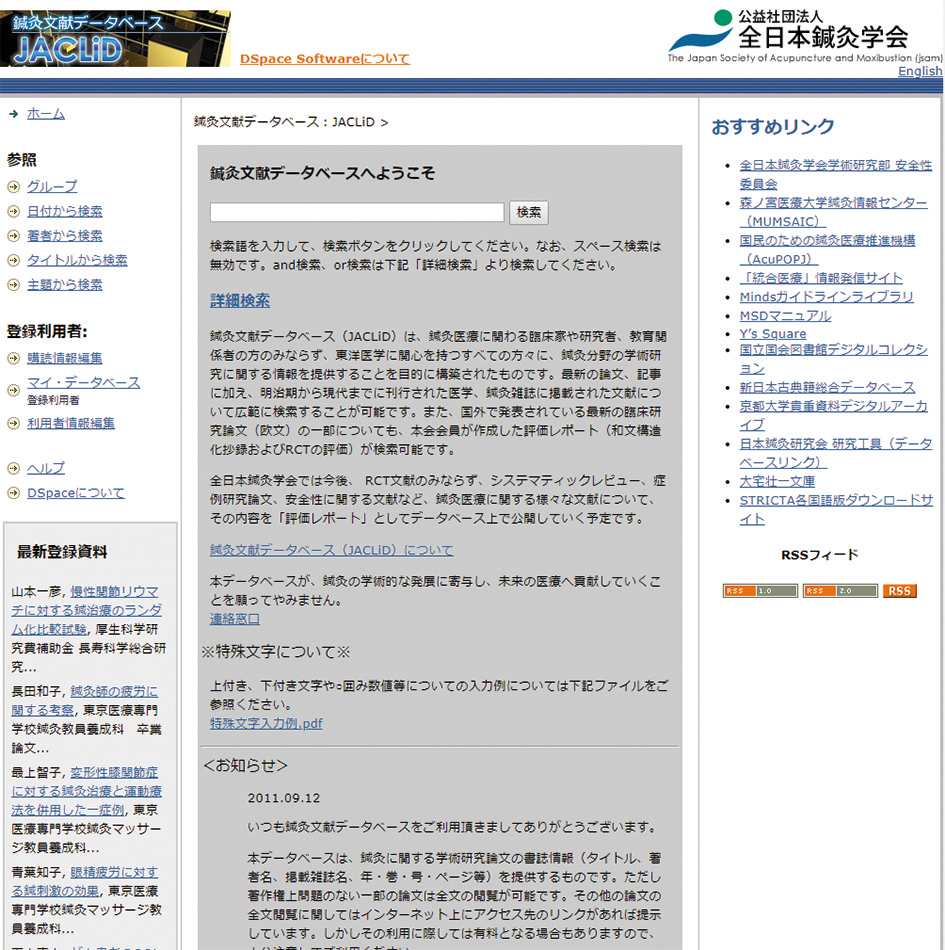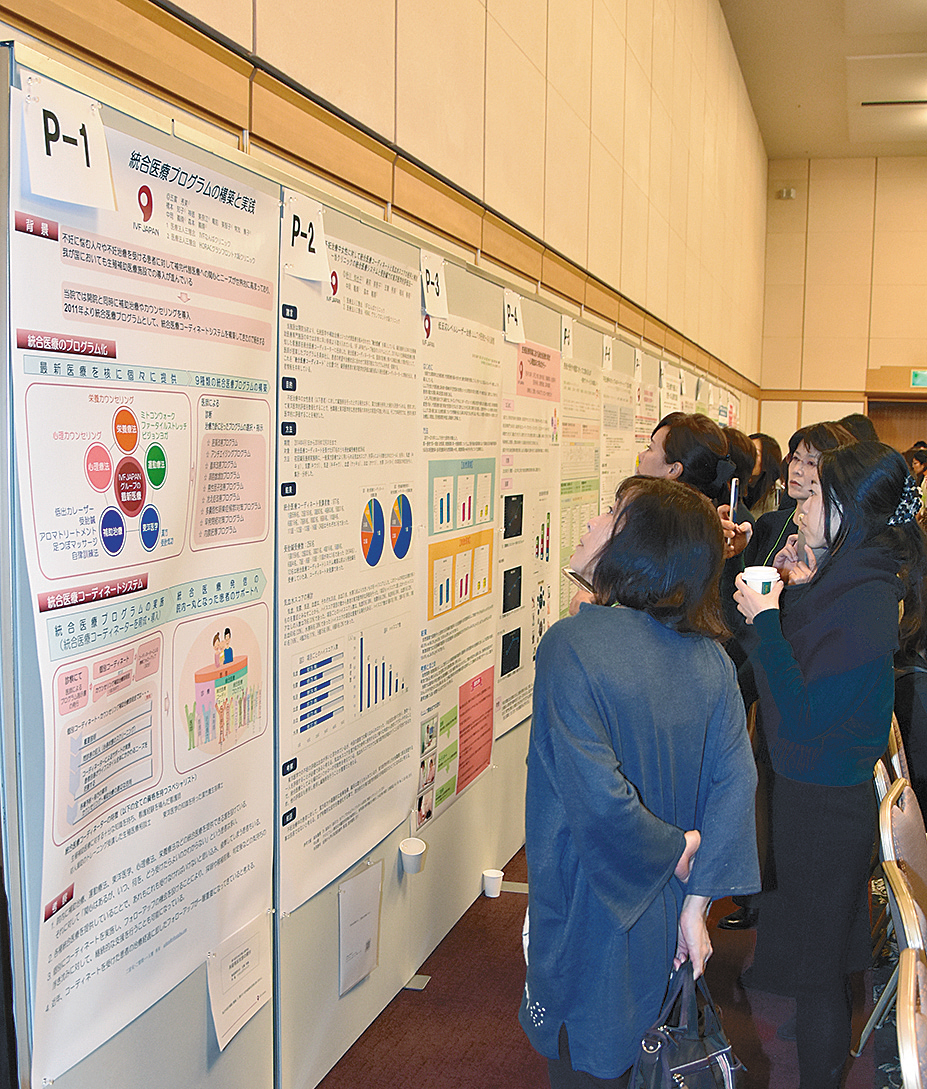新元号記念号インタビュー 第2弾 斉藤宗則氏(JLOM鍼灸代表者会議事務局長) 日本鍼灸守る、鍼灸国際標準化の最前線
2019.05.25
1096-1097号(2019年5月10-25日合併号)、紙面記事、
1096-1097号(2019年5月10-25日合併号) ほか
WHOのICD(国際疾病分類)に、鍼灸の経絡病証を含む「伝統医学」の項目が、1年間の試用期間を経て正式に採択される見通しだ。主に工業製品の国際標準を策定するISO(国際標準化機構)においても、鍼や灸に関する機器についての標準策定が進んでいる。こうした国際会議で、日本の代表として参加しているのがJLOM(日本東洋医学サミット会議)。昨年7月に新たに発足したJLOM鍼灸代表者会議の事務局長を務める斉藤宗則氏に現状を聞いた。
JLOM鍼灸代表者会議事務局長 斉藤宗則氏
さいとう・むねのり:明治国際医療大学鍼灸学部はり・きゅう学講座、同大学院鍼灸学研究科特任准教授。JSAM/JLOM部長、JLOM鍼灸代表者会議事務局長。
WHO、ICD大改訂は「保健衛生の変化」見据え
――JLOM鍼灸代表者会議発足の経緯は?
同会議は、JLOMにおける鍼灸業界の意見集約を図るために発足しました。それまではJLOMから鍼灸業界への照会窓口が決まっておらず、ISOやWHO会議出席者に多大な負担が生じていました。全日本鍼灸学会JLOM部長で、ISOの会議にも参加経験のある私自身、意見集約の必要性を痛感していたことから、会議の発足を提案しました。幸いなことに各団体から賛同を得られ、JLOM加盟団体に加え、全日本鍼灸マッサージ師会、鍼灸学系大学協議会が参加する形で発足し、私が事務局長に推挙されることになりました。
――WHOのICDに「伝統医学」が正式に収載されます
5月下旬にジュネーブで開催されるWHOの総会で正式に採択される見込みです。WHOはICDのほか、ICF(国際生活機能分類)、策定中のICHI(医療行為分類)を駆使して、今後の社会構造の変化に伴う保健衛生の変化に対応しようとしています。今回のICD―11への採択は、鍼灸が現代医療の中に入っていくチャンスです。日常臨床の病態把握、治療目標、治療、効果などをコーディングし、鍼灸のデータとして蓄積することで、鍼灸臨床の実態を把握・公表していこうと考えています。
後日、鍼灸代表者会議を通じて、業界の皆さんへデータ入力の依頼をする予定です。その際は、ぜひご協力をお願いしたいと思います。
――ISOでの国際標準作成の進捗はいかがですか
TC249(中国伝統医学)とTC215(医療情報)という二つの専門委員会で、鍼灸を含む伝統医学の標準が検討されています。TC249では現在、教育や臨床も標準化したいと画策する中国を中心に、スコープ(所掌範囲)の拡大が大きな焦点です。昨年の会議後にスコープの拡大について投票が行われましたが、日本などの反対で僅差で否決することができました。ISOルールに則り、投票結果の正式な文書化を要求しているのですが、引き伸ばされており、まだ実現していません。次回、6月上旬に行われるバンコク会議で文書化を実現し、同じ内容の投票を3年以内には実施できないなどのルールを決められるかが重要になります。
――その他の動きは?
WFAS(世界鍼灸学会連合会)で、一昨年より標準化委員会が再度立ち上がり、新たな学会標準を策定し、将来的にISOの場で提案しようとする流れがあります。WFASの運営は現在、中国が中心ですから、これはISO/TC249と同様に、単に中国の標準を学会標準にスライドさせる動きで、注視が必要です。今年のWFAS学術大会は11月、トルコで開催予定です。ぜひご参加ください。
また、先ほども触れましたが、現在WHO国際分類ファミリーの中心分類の一つとしてICHIが策定中です。10月にファイナルベータ版が公表の見込みですが、この中にも鍼灸が入っており、介入の部位として361経穴を入れるべく活動しています。
道具や技術が突然使えなくなることも?
――国内の施術者に求めたいことはありますか
まずは国際標準に関する情報に関心を持ち、目を通していただきたいです。例えば、皆さんが施術に使っている鍼灸鍼が、既に策定済みのISOの標準に合わせて作られていることをご存知でしょうか。様々な標準が策定されていき、使っていた道具が知らぬ間に使えなくなる、技術が応用できなくなるといった事態が起きないよう、会議参加者は常に国内のメーカーや施術者を守り、そしてそれを通じて世界の鍼灸に貢献することを目指し、活動を続けています。業界全体で注視していただければと思います。
また、ISOやWHOなどの国際会議に出席されている先生は、日々多くの時間を割いて問題に対応しています。活動へのご理解、応援をいただくと共に、会議参加者より問い合わせがありました際はぜひご協力をお願いします。