伝統鍼灸学会 石原克己新会長が承認、来年4月から
2020.11.19
日本伝統鍼灸学会(形井秀一会長)の総会が11月15日に行われ、次期会長として石原克己氏(東明堂石原鍼灸院院長)が選出・承認された。
任期は2021年4月からの3年間。
伝統鍼灸学会 石原克己新会長が承認、来年4月から

伝統鍼灸学会 石原克己新会長が承認、来年4月から
2020.11.19
日本伝統鍼灸学会(形井秀一会長)の総会が11月15日に行われ、次期会長として石原克己氏(東明堂石原鍼灸院院長)が選出・承認された。
任期は2021年4月からの3年間。
第3回国際美容鍼灸学会 ウェブ開催 「インフォデミック」テーマにシンポ

第3回国際美容鍼灸学会 ウェブ開催 「インフォデミック」テーマにシンポ
2020.11.10
治療家は無根拠な情報の拡散にも注意を
第3回国際美容鍼灸学会が10月11日、Zoomを使用してウェブ開催された。 (さらに…)
全日本鍼灸学会の新会長に若山氏就任

全日本鍼灸学会の新会長に若山氏就任
2020.10.22
公益社団法人全日本鍼灸学会の新会長に国際部長の若山育郎氏(関西医療大学教授)が就任した。10月20日、同学会のホームページで若山氏のあいさつとともに公表された。
若山氏はあいさつの中で、「臨床情報部」と「辞書用語部」の新設に言及。臨床情報部は臨床試験を中心とした最新の情報をウェブを通じて提供し、辞書用語部は日本鍼灸に必要な用語を整理して同学会会員が参照・利用できるデータを提供する準備を進めていくという。
全日 特別講演会を対面・リモート併用で 鍼灸の国際情勢を概説

全日 特別講演会を対面・リモート併用で 鍼灸の国際情勢を概説
2020.09.25
ICHIへの361経穴収載、承認へ
コロナ禍で多くの学術大会が中止あるいはリモート開催となっている中、全日本鍼灸学会(全日、久光正会長)の特別講演会が9月12日、リモートを併用して東京都内で開催された。 (さらに…)
接骨医学会、対面開催中止の大会を来年オンラインで

接骨医学会、対面開催中止の大会を来年オンラインで
2020.09.14
一般社団法人日本柔道整復接骨医学会(安田秀喜会長)が、新型コロナウイルス流行のため、対面開催を中止し、オンラインのみでの実施と発表していた第29回学術大会の日程が改めて決まった。
9月9日付で同学会ホームページ上に公表され、開催期間は令和3年1月12日(火)から31(日)までとした。実施方法等の詳細は、後日公表するという。
全日、新型コロナに関する鍼灸論文を紹介

全日、新型コロナに関する鍼灸論文を紹介
2020.08.31
全日本鍼灸学会が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の鍼灸による治療や予防に関する論文を収集し、ホームページで紹介している。
同学会によると、PubMedやCENTRALなどのデータベースで「COVID-19」「acupuncture」「moxibustion」のキーワードで検索したところ35の論文が抽出されたとのこと。筆頭著者所属の国別では中国が30編で、ドイツ2編、米国1編、日本1編、ベルギー1編だったという。
会津医療センターが鍼灸研修生を募集、給与も

会津医療センターが鍼灸研修生を募集、給与も
2020.08.21
福島県立医科大学会津医療センターは鍼灸師の卒後教育として、様々な現代医学が学べて給与も支給される鍼灸研修生を8月中旬から募集している。
前期研修初年度は各診療科を回って医学的知識を習得し、2年目は漢方外科と鍼灸部で鍼灸の臨床と研究について研修。全体を通じてチーム医療の知識も習得できる。後期研修(最長3年)で臨床へ参加、研修生への教育にも携わり、研究活動も行う。応募条件は「研修終了後、福島県内の医療に携れる者」等。
給与(日給)は前期研修では専門学校卒7,200円、鍼灸師養成大学卒8,200円、大学院卒(医科学、鍼灸学)10,000円。後期は準職員として10,000円。
募集は10月23日まで(必要書類必着)。
福島県立医科大学会津医療センターにおける鍼灸研修生の募集について
接骨医学会、新会長に安田氏

接骨医学会、新会長に安田氏
2020.07.29
一般社団法人日本柔道整復接骨医学会(会員数4,732名)の新会長に、安田秀喜氏(帝京平成大学健康医療スポーツ学部長)が就任した。7月の同会理事会で選出され、前会長・櫻井康司氏(学校法人花田学園理事長)の後任。
副会長について、坂本歩氏、紙谷武氏がそれぞれ新たに選ばれた。
オンライン勉強会・イベント続々 病鍼連携連絡協議会、セイリンなど
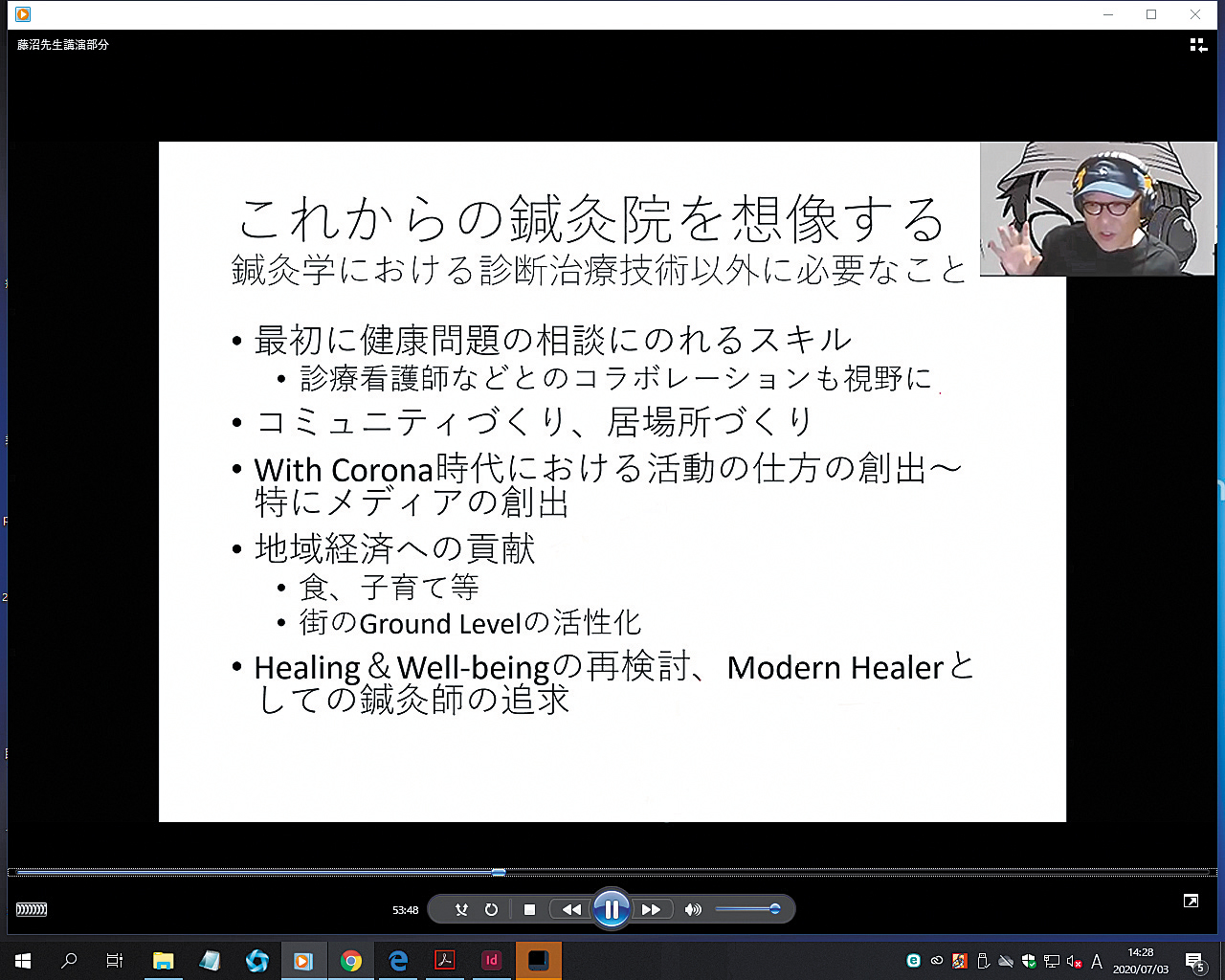
オンライン勉強会・イベント続々 病鍼連携連絡協議会、セイリンなど
2020.07.10
コロナ禍で自宅から/子育て中・遠方でも参加
新型コロナウイルスの流行で各種イベントの中止・延期が相次ぐ中、「3密」を回避できるオンラインの活用が急速に進み、あはき・柔整業界でもオンラインによる勉強会やイベントの動きが広がっている。参加人数は? 雰囲気は? 従来の対面式との違いは? 主催者に素朴な疑問を聞いた。
(さらに…)
業界代表する2学会 対面開催中止

業界代表する2学会 対面開催中止
2020.07.10
接骨医学会、全日本鍼灸学会
コロナ禍でやむなく
新型コロナウイルスの新規感染の収束が見通せない中、業界内では大規模な学会の対面開催中止が相次いで発表された。
一般社団法人日本柔道整復接骨医学会(櫻井康司会長)は6月15日、11月に東京都内で開催予定だった第29回学術大会の対面開催中止をホームページで発表。 (さらに…)
東方医学会、コロナの医療従事者に無料の鍼灸施術を提供

東方医学会、コロナの医療従事者に無料の鍼灸施術を提供
2020.07.03
日本東方医学会が「ありがとう! スマイルケア」と銘打ち、新型コロナウイルス感染症に携わる医療従事者に無料の出張鍼灸施術を行っている。
首都圏の病院に鍼灸師を派遣し、医師や看護師、薬剤師、理学療法士など施術を行う。派遣するのは、同学会で医療連携に関する認定制度をクリアした鍼灸師。マスクや手袋、フェイスシールドなどの感染予防具は鍼灸師が持参するという。
日本東方医学会「ありがとう!スマイルケア」プロジェクト
「部活動再開後は0.8~1.3倍の負荷から」JSAT指標

「部活動再開後は0.8~1.3倍の負荷から」JSAT指標
2020.06.01
6月以降、学校再開の本格化に伴い、部活動も順次活動が解除され、施術者によるトレーナー業務も再び動き出す。一般社団法人日本アスレティックトレーニング学会(JSAT)が5月中旬、中高生の部活動再開後の練習でケガをしないためのガイドラインを作成し、公表している。
休み明けの練習はケガが起こりやすいため、自粛中のトレーニングの「0.8~1.3倍の負荷」で始めるよう勧めている。指標となる負荷を割り出す計算式も紹介しており、まず1週間程度は「計算した負荷」で練習に取り組み、徐々に増やしていくことが望ましいとしている。急がば回れだ。
JSAT『中学校・高校の部活動自粛解除後の練習でケガをしないために』
全日、新型コロナ感染予防に指針

全日、新型コロナ感染予防に指針
2020.04.27
全日本鍼灸学会がホームページ上に『鍼灸施術における新型コロナウイルス感染の拡大防止のための注意点』を公表。施術者は毎日施術前に体温を測定する、予約などで患者を分散させる、患者が発熱している場合や感冒症状がみられる場合は施術を行わない、といった10の項目を施術の指針として挙げている。
一般的な感染予防法については同学会がまとめた『鍼灸安全対策ガイドライン2020年度版』を参考にしてほしいと呼び掛けている。
新型コロナ、鍼灸関連学会など大会延期

新型コロナ、鍼灸関連学会など大会延期
2020.04.10
全日は9月に、東洋医学会は来年夏に
5月下旬に京都で開催予定だった全日本鍼灸学会の第69回学術大会(北小路博司会頭)が、新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、開催の延期を決めた。日程を3カ月以上延ばし、9月11日から13日の間で開催される。会場(国立京都国際会館・京都市左京区)の変更はないが、大会内容に変更が生じた場合は随時通知するとしている。
同様の事情から、6月中旬に開催予定の日本東洋医学会の第71回学術総会(三潴忠道会頭)も来年8月に延期すると発表。会場の仙台国際センター(仙台市青葉区)に変更はないとしている。11月に名古屋で開催予定だった第35回経絡治療学会学術大会も開催の中止が決定された。
JLOM ICD-11収載で会見 医療現場での伝統医学活用を

JLOM ICD-11収載で会見 医療現場での伝統医学活用を
2020.03.25
電子システム化を学会で検討
日本東洋医学サミット会議(JLOM)はICD-11への伝統医学分類(漢方・鍼灸)収載を受けた記者会見・記念講演会を2月20日、東京都内で開催。現在の状況や今後の展望について報告した。
【ICD-11(国際疾病分類第11版)】
国際疾病分類(ICD)は、WHOが作成する国際的に統一した基準で定められた死因及び疾病の分類。日本では公的統計や診療報酬明細書などの死因・疾病分類に、ICD準拠の統計基準を利用している。昨年6月に約30年ぶりの改訂が行われ、「伝統医学の病態」などの章が追加された。
会見に臨んだのは、JLOM議長の伊藤隆氏(一般社団法人日本東洋医学会会長)、同副議長の若山育郎氏(公益社団法人全日本鍼灸学会副会長)。 (さらに…)
第37回日本東方医学会 『大腸が寿命を決める』テーマに

第37回日本東方医学会 『大腸が寿命を決める』テーマに
2020.03.25
便秘への鍼灸や近年の知見など
第37回日本東方医学会が2月9日、『万病撃退! 大腸が寿命を決める』をテーマに都内で開催された。
マリーゴールドクリニック院長の山口トキコ氏が『大腸肛門病専門医の視点で健康を再考する』をテーマに会頭講演を行った。 (さらに…)
第1回健康施術産業展 施術所向け商品・サービス出展

第1回健康施術産業展 施術所向け商品・サービス出展
2020.03.25
70社がブース構え、15,818人来場
『第1回健康施術産業展』が2月12日~14日、東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催された。ブティックス株式会社(東京都港区)主催。 (さらに…)
新型コロナ あはき・柔整業界も自粛ムード

新型コロナ あはき・柔整業界も自粛ムード
2020.03.10
催しやイベント中止・延期、相次ぐ
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、あはき・柔整業界に「自粛ムード」が広がっている。政府が「今後2週間の大規模イベントの中止や延期」を要請した先月26日頃を境に、業界内の学会やセミナー、講習会や研修などの中止・延期が相次いでいる。併せて、治療の現場でも影響が出ている。
あはき関連では (さらに…)
催し物案内 鍼灸師・歯科医師が講演と実技、函館で

催し物案内 鍼灸師・歯科医師が講演と実技、函館で
2020.02.10
―『実践!! 臨床歯科東洋医学』テーマに―
3月14日(土)16時半から、サン・リフレ函館(北海道函館市)で開催される。函館鍼灸マッサージ師連絡協議会(函鍼連)主催、函館歯科医師会後援。
鍼灸師・歯科医師で、日本スポーツ歯科医学会認定医や美容鍼灸の会「美真会」顧問、アスレティックトレーナーなど、様々な肩書を持つ関根陽平氏が登壇。歯科医師の立場から、また東洋医学的な視点からも、顎関節症・不正咬合・オーラルフレイル・口腔機能低下症などについて解説し、歯科領域と東洋医学の「相性の良さ」にも触れる。「明日から使える鍼灸実技」も披露する。
参加対象は医療系国家資格所持者で参加費5,000円。申込みは函鍼連事務局(TEL/FAX 0138-41-8901)もしくは函館歯科医師会(TEL 0138-23-3650/FAX 0138-23-4765)へ。申込締切りは3月9日(月)。
日本伝統医療看護連携学会 第1回設立記念総会・学術大会 「伝統医療」「看護」の連携へ向け発足

日本伝統医療看護連携学会 第1回設立記念総会・学術大会 「伝統医療」「看護」の連携へ向け発足
2020.01.24
昨年末、あはき・柔整などの伝統医療と看護の連携を模索し、学術の発展や社会貢献を目指して、『日本伝統医療看護連携学会』(佐竹正延会長)が発足。昨年12月18日には、第1回の総会・学術大会が仙台市青葉区の仙台赤門短期大学で開催された。講演やシンポジウムでは、伝統医療と看護はともに全人的であり親和性が高いということが、異口同音に言及されていた。
―ともに『全人的』で高い親和性―
佐竹会長(仙台赤門短期大学学長)は開会のあいさつで、看護学も医学にならい、実証科学を踏襲しているが、それは方法論としての側面であると指摘。看護することの本来的意義から見れば、看護学では人間を全体的・全人的に把握する傾向があるのは歴然としており、一方、伝統医療もまた「パーツではなく全体」として人間を捉えていると述べ、二つの分野が連携することで相互に利益を与えて学際的な発展を遂げ、ひいては社会福祉にも貢献できるよう願うと語った。
鍼灸師と看護師が担う「在宅」
シンポジウム『医療連携の未来を拓く―融和』は村上理恵氏(なの花訪問看護ステーション仙台訪問看護師/鍼灸りえる院長)、柴田克実氏(晩翠通り治療院院長)、亀井啓氏(亀井接骨鍼灸治療院院長)、佐藤喜根子氏(仙台赤門短期大学教授)が登壇した。村上氏は、在宅療養中の末期癌患者や要介護状態の利用者の便秘や浮腫、痛みなどの症状緩和に対して鍼灸治療を行っていると説明。その際、患者宅にある各事業所の記録などから他職種のケア内容や患者の状況を把握し、自分の施術記録も残すことで情報を共有していると述べた。看護師や利用者の家族に温灸の指導をしたり、指圧のツボの位置をマーキングしたりするなどのアドバイスを行い、看護師とともに症状緩和に取り組むケースもあると解説。治療院では、地域包括支援センターを通じて患者に介護予防教室を紹介するなど、個々に適した社会資源につなげるようにしていると話した。柴田氏は十数年携わってきたリンパ浮腫治療について、治療が受けられる医療機関の情報が入って来ない、施設を見つけても予約が一杯ですぐに治療が受けられない、といった患者の現状を紹介。医療リンパドレナージを行えるのは医師や看護師のほか理学療法士や作業療法士、あマ指師なども含まれるとして、それぞれの立場からリンパ浮腫治療に関わっていくことが望ましいと語った。亀井氏は『疼痛の本質を探る―治療のピットホール』、佐藤氏は『東洋医学と看護の「融和」』をテーマに講演を行った。
ほかに、佐竹会長の学術大会長講演『医学にあるもの、医学にないもの』、矢野忠氏(明治国際医療大学学長)の『東洋医学の再発見―医療連携の可能性』と谷口初美氏(九州大学大学院教授)の『補完代替医療(CAM)と看護ケア』の特別講演2題、『看護・介護の場での小さいゴムボールを使ったリハビリテーションの一考察』(藤井裕文氏・ふじい接骨院院長)など一般口演10題、ポスター発表3題が行われた。