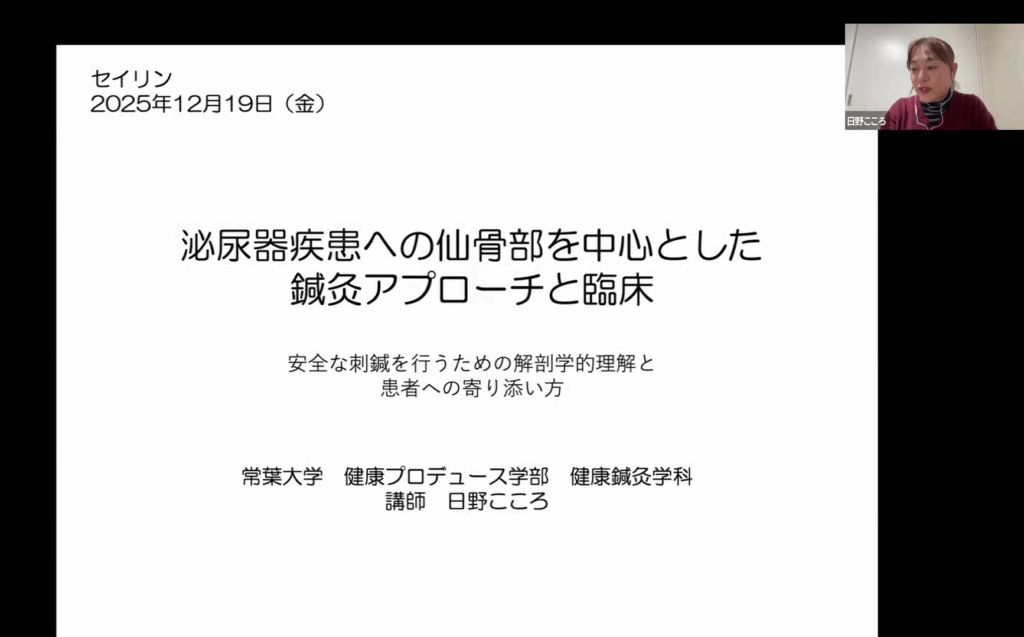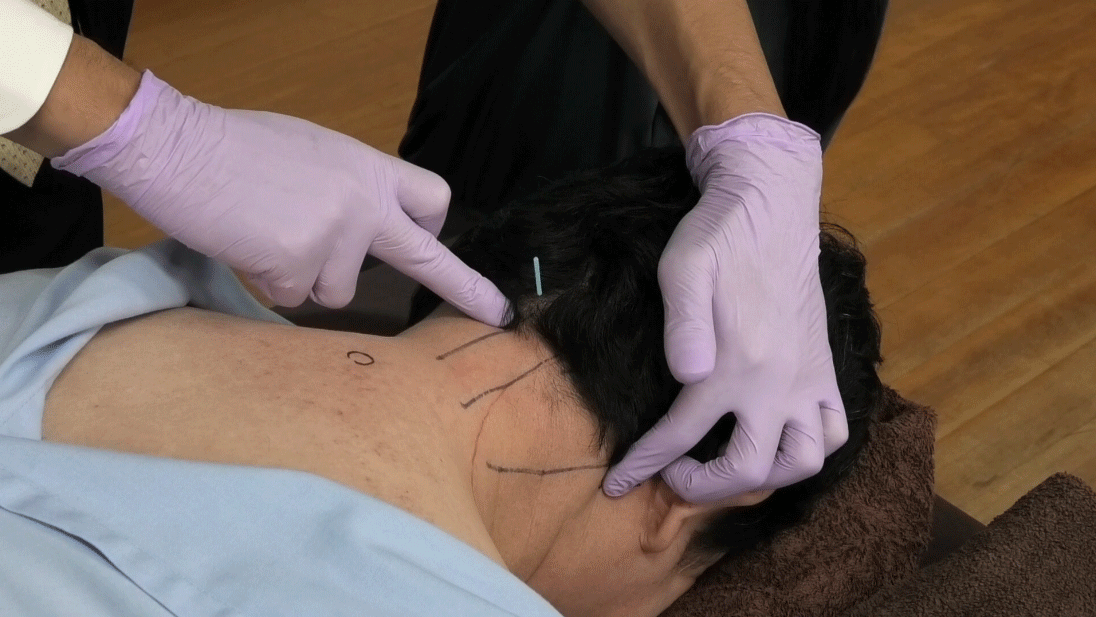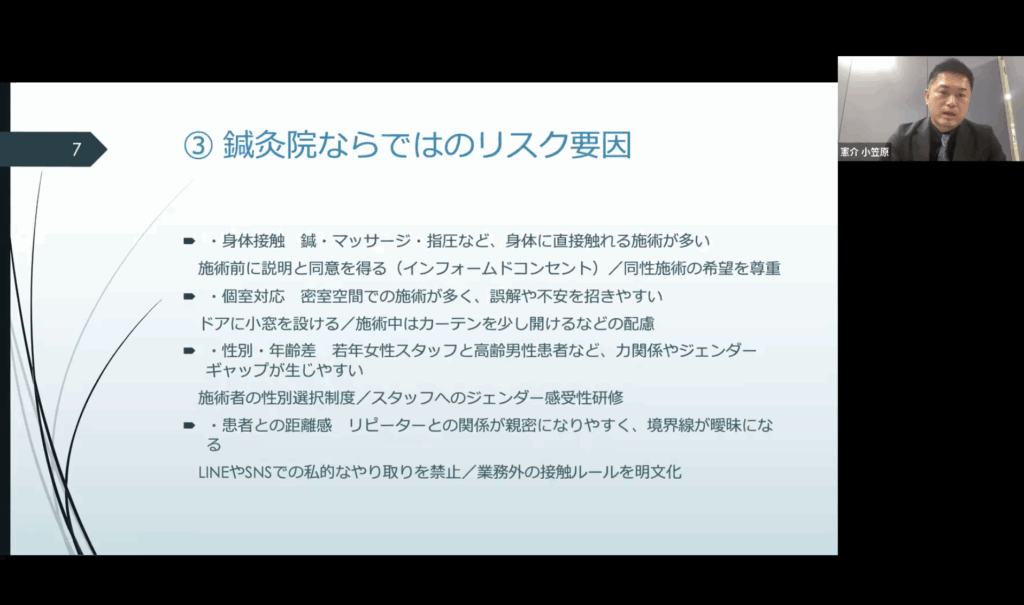五行説に基づく古代中国星座をプラネタリウムで鑑賞、『古代中国星座の世界へようこそ!(東洋医学も少々…)』
2026.02.03
2月25日の13時10分より、多摩六都科学館(東京都西東京市)にて、古代中国星座を紹介する大人向けプラネタリウム『古代中国星座の世界へようこそ!(東洋医学も少々…)』が投影される。当日の星空と照らし合わせながら、現在の西洋星座とはまったく違う古代中国星座の世界を、陰陽説・五行説などの当時の思想とともに旅する45分間の番組になっている。
「中国古代星座と東洋医学はどちらも2000年以上前の古代中国で成立し、ともに当時の思想の影響を反映しているという点では同じ流れをくむと考えた」と説明するのは、同番組を企画した平野都子氏。実は平野氏は鍼灸あん摩マッサージ指圧師でもある。かつて市職員として別の科学館で偶然プラネタリウムの解説に携わっていたそう。
その際に、「中国星座は五行説に基づく」という概念と、四方・四季・四神……といった四にまつわる言葉ばかりが解説に登場する矛盾・「四と五問題」に、腑に落ちないもやもやを抱きながらも、惹かれていったと話す。その後異動により職を離れた際に、手に職をつけたいこと、「四と五問題」の謎を追求したいことがあり、養成校に入学した平野氏。鍼灸師となり訪問鍼灸で経験を積んでいたころ、多摩六都科学館から話があったそうで、「プラネタリウムの仕事が好きだったけど一生縁がないだろうと諦めていた」と当時の思いを口にした。
今回の番組では、ちょっと変わった星座の紹介や、平野氏の解釈をふまえた「四と五問題」の話に耳をかたむけながら、今晩の空に古代中国の空を重ね、星空を楽しむことができる。東洋医学に関するミニ知識解説もあり。
多摩六都科学館はこれまでも古代中国星座の番組を制作・投影している。また、同科学館は文化庁、奈良文化財研究所、国立天文台からなる「キトラ天文図研究会」に参加しており、キトラ古墳に残された中国式の円形星図をはじめ、壁画の超高精細な写真を大きなプラネタリウムドームに映写する番組の制作など、キトラ古墳の壁画の魅力を伝える企画にも尽力してきた。
「五行説をきっかけに、『ちょっと空を見上げてみようか』と思ってもらえると嬉しい」と平野氏。興味のある方は足を運んでみてはいかが?
多摩六都科学館
大人向けプラネタリウム
『古代中国星座の世界へようこそ!(東洋医学も少々…)』
2月25日(水)13時10分~
対象:中学生~大人 ※小学生以下は入場不可
料金:大人1,040円、中学生・高校生420円(観覧付入館券)
※当日開館時よりインフォメーションにて先着順で観覧券を販売