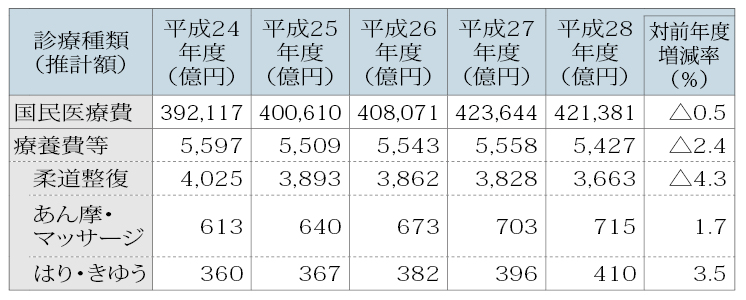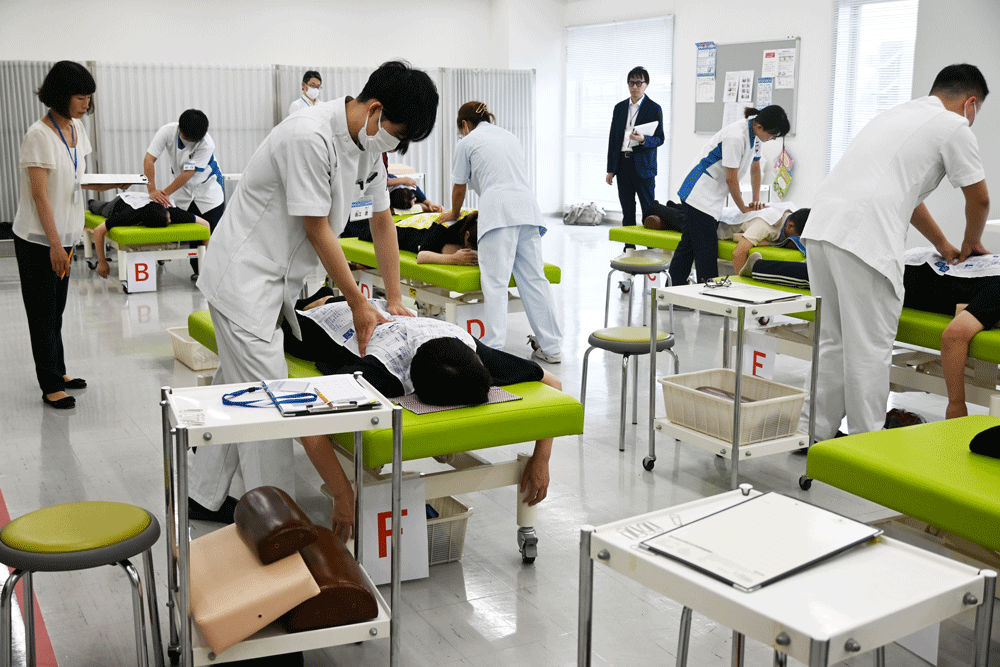今日の一冊 永善堂病院 もの忘れ外来
2018.10.25
永善堂病院 もの忘れ外来
佐野香織 作
ポプラ社 1,620円
ある事情で仕事を続けられなくなり、都会を離れた主人公・佐倉奈美は、田舎町の永善堂病院で看護助手として働き始める。風変わりな三兄弟の医師など個性的なスタッフに囲まれ、慣れない医療の仕事に戸惑いながらも真っ向から取り組んでいく奈美。もの忘れ外来には、家族に認知症を疑われる老婆、「僕はもうすぐ死ぬんだから」と諦観する脳血管性認知症の男性、ベテラン医師とその妻など「自分が自分でなくなる恐怖」と戦う様々な患者が訪れて――。第五回ポプラ社小説新人賞・奨励賞受賞の作者が描くデビュー作。