IMJの新理事長に伊藤壽記氏
2018.12.10
一般社団法人日本統合医療学会(IMJ)の新理事長に伊藤壽記氏(大阪がん循環器予防センター所長)が就任した。11月の理事会等で決定し、前理事長の仁田新一氏(東北大学名誉教授)は名誉理事長に就いた。
IMJの新理事長に伊藤壽記氏

IMJの新理事長に伊藤壽記氏
2018.12.10
一般社団法人日本統合医療学会(IMJ)の新理事長に伊藤壽記氏(大阪がん循環器予防センター所長)が就任した。11月の理事会等で決定し、前理事長の仁田新一氏(東北大学名誉教授)は名誉理事長に就いた。
商品紹介 和光電研『プチバン』

商品紹介 和光電研『プチバン』
2018.12.10
―貼るだけで指圧効果、肩こり、腰痛をはじめ運動前後のケアにも―
和光電研株式会社(大阪府八尾市)の、貼るだけで指圧効果が期待できる『プチバン』。
40年来のロングセラー『ロイヤルトップ』をベースにした、患者のセルフケアにも使える家庭用貼付型接触粒(一般医療機器)。同社では、運動前後に貼ることで疲労を軽減する、上肢の可動域を広げる、といった用途も提案、マラソン大会に『プチバン』ブースを出展するなど普及にも努めている。180粒入(写真)6,000円・60粒入2,160円(税込)など。
販売に関する問合せは和光電研商事株式会社(0120-765-890)へ。
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』105 「リテールクリニック」という市場

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』105 「リテールクリニック」という市場
2018.12.10
年の瀬です。今年も気候が異常で、急に寒くなったり、暖かくなったりして体調を崩される方も少なくないですね。私が今年、仲間と設立したMedQuery(メドクエリ)株式会社は、こういった、ちょっと体調不良になった方々を診られる「リテールクリニック」を開発しています。柔整師の適用は本来急性軽症の疾患であるはずで、鍼灸は慢性疾患も適用するかもしれませんが、実際には「筋骨格系の慢性的な症状」が、顧客のイメージする治療院像ではないかと感じます。例えば、風邪を引いた時に鍼灸院に行きますか? 私の周りは鍼灸に親和性の高い友人が多いので、感冒初期でも鍼灸を選択する人もいますが、一般的には風邪で鍼灸院に行くということが頭に浮かぶ人は少ないと思います。
実は、風邪の初期に医療機関を受診する患者さんは13.3%しかいません。それ以外の人はどうしているかというと、12%が薬局に行き、50%が手持ちの薬で何とかする人、そして、何もしないという人が23.7%です。風邪薬の売上は年間1,300億円で、薬局に行く人が12%、風邪症状で医療機関を受診する人が毎日1万人当たり28人いることを考えると、風邪の症状がある人は210人/1万人/日ということになり、1兆円/年ほどの市場になります。 そのうち、病院にも薬局にも行かない人の市場は7,000億円/年ほどにもなり、この市場は誰も手付かずなのです。
風邪に限らず、その他の咽頭痛や腹痛、下痢などの急性軽症で病院に行くまでもない市場に、自費で「やすくて、はやくて、あんしん」を提供する「場所」を作ろうという計画ですが、そうなるといったい誰が実際のオペレーションをするかが問題になります。
一方、アメリカではリテールクリニック市場が成長しています。最近10年で1,500億円程度の市場となり、クリニック数も2500を超えています。私は以前から、治療院がそういう「場所」になりうると言い続けてきましたが、なかなかそのような方向に向かっていないようです。アメリカのリテールクリニックでは医師が診察するわけではなく、「ナースプラクティショナー」という一部の医療行為を自らの判断で行える看護師が対応します。ターゲットも急性軽症疾患で、高い医療機関へ行くまでもない患者さんです。日本では皆保険制度のために、なかなかリテールクリニックが育ちませんでしたが、コンビニ受診が非難される時代とあってそろそろ登場しても良いはずです。
日本においてもそのオペレーターは、看護師や薬剤師が想定されます。また、同じ国家資格者のあはき師や柔整師も活躍できるかもしれません。そこで皆さん、急性軽症疾患を診ることはできますか? 国民医療費の高騰を抑えるために、この活動に私は今後も注力していく予定です。
【連載執筆者】
織田 聡(おだ・さとし)
日本統合医療支援センター代表理事、一般社団法人健康情報連携機構代表理事
医師・薬剤師・医学博士
富山医科薬科大学医学部・薬学部を卒業後、富山県立中央病院などで研修。アメリカ・アリゾナ大学統合医療フェローシッププログラムの修了者であり、中和鍼灸専門学校にも在籍(中退)していた。「日本型統合医療」を提唱し、西洋医学と種々の補完医療との連携構築を目指して活動中。
連載『中国医学情報』165 谷田伸治

連載『中国医学情報』165 谷田伸治
2018.12.10
☆高脂血症を合併した重度肥満症に対する鍼灸治療の効果と性別
南京中医薬大学・黄迪迪らは、脂質異常症(高脂血症)を合併した重度肥満症の鍼灸治療を報告(中国鍼灸、18年07期)。
対象=同大国医堂ダイエット科の264例(男106例・女158例)、平均年齢(41±6)歳。肥満症罹患期間は、男が平均(18.0±14.3)年、女が平均(16.4±13.6)年。
中医分型基準=6型に分類し治療。
①胃腸腑熱型―食欲比較的良好・燥熱嫌う・冷飲料好む・汗かき・大便乾燥など。
②脾虚湿阻型―食欲不良・体が重だるい・尿少ない・下痢便・舌辺に歯痕など。
③痰湿内阻型―咳痰多い・食欲減少・吐き気・頭が重い・体が重だるいなど。
④肝鬱脾虚型―いつも胸苦しく息切れ・憂鬱や煩躁を伴うなど。
⑤脾腎陽虚型―いつも四肢無力で冷えを感じる・腰がだるく冷える・大便少・頻尿など。
⑥陰虚夾瘀型―毎日決まった時間に発熱・寝汗・胸中や掌や足底が火照る・頬が赤い・口乾・尿少なく黄色・大便乾燥など。
治療法=鍼灸治療のみを2日1回、計3カ月。この間、他の治療法(薬物・手術・運動・食事療法)はしない。
<取穴>①―内庭・曲池・小海・二間・上巨虚・前谷・大腸兪・中脘・支溝。②―天枢・陰陵泉・足三里・豊隆・三陰交・太白・中脘・気海。③―合谷・太淵・中脘・天枢・豊隆・足三里・太白・太渓・脾兪。④―膈兪・期門・章門・曲池・足三里・豊隆・三陰交・太衝・太白。⑤―膈兪・腎兪・足三里・陰陵泉・豊隆・飛揚・太白・太渓・中脘・中極・気海・関元。⑥―曲池・合谷・太淵・神門・血海・陰陵泉・豊隆・足三里・三陰交。以上は常軌刺鍼。さらに、②には太白・陰陵泉、③には豊隆、⑤には気海・足三里に、灸頭鍼追加。
<操作>0.30×40/50/60mmの毫鍼で刺鍼、得気後に置鍼30分(10分ごとに刺激1回)。灸頭鍼は、直径2cm・長さ3cmの艾で2壮。
結果=<治療前→後の平均値>肥満度―体重(kg):男107.00±15.26→96.72±17.30/女87.95±11.65→81.04±13.04。血清脂質値(mg/dLに換算)―LDL-C:男220.20±27.86→153.25±33.67/女210.14±30.19→150.16±33.28、HDL-C:男27.09±6.58→44.12±8.13/女28.64±12.77→44.89±12.00、TG:男170.67±20.90→99.46±28.25/女167.96±19.35→106.04±30.96。
<総合評価>男:著効68例・有効29例・無効9例・総有効率91.5%/女:著効83例・有効52例・無効23例・総有効率85.4%。
☆顔面麻痺後の流涙症に大小骨空穴への灸
山東中医薬大学・郭婷らは、顔面神経麻痺後の流涙症患者への灸治療例を報告(中国鍼灸、18年07期)。
女性・67歳。
主訴=顔面麻痺後の流涙が3カ月余り、重症化し5日。
現病歴=3カ月前に風で冷えた後に、左眼が閉じ涙嚢炎で風を受けると涙があふれ、左側の額のしわ・鼻唇溝が浅くなり、口角が右にゆがむと共に耳の後ろが痛む。同大付属病院で末梢性顔面神経麻痺と診断され、現代医薬などの治療で改善したが、流涙症が残ったため鍼灸科を受診。
現症=額のしわと鼻唇溝は基本的に左右対称、微笑時に口角がやや右寄り、左眼部の筋肉に異常感、流涙は冷たい風で悪化、息切れし気力がない、膝腰がだるく力がない、睡眠不足で夢多い、眼瞼と内眼角に発赤、左右眼球結膜に軽度充血など。
診断=西医:流涙症、中医:顔面麻痺後遺流涙症(肝腎両虚型)。
治療法=①選穴―古医書(『鍼灸集成』など)で本症に有効とする奇穴の大骨空穴(拇指背側IP関節横紋中点)・小骨空穴(小指背側PIP関節横紋中点)。②操作―両手を机の上に置き、ショウガ汁をツボに塗り、麦粒大の艾を置き線香で点火、2/3燃えるか患者が灼熱感や耐えられなく感じたら艾を取る。毎日1回、毎穴各9壮、治療時間約25分間、連続3日後は2日1回治療。
治療経過=治療期間中は他の治療なし。第1回治療後、患者は肘まで熱感あり。第3回後、肩まで熱感。第5回後、頭頂部少し発汗。第8回後、眼部筋肉が前より緩むのを自覚、その日の午後症状好転。続けて治療すると、毎回少しの発汗を自覚。第13回後、流涙症状や眼部筋肉の緊張感がなくなったと言う。効果を強化するためその後2回治療し終了。3カ月後も再発なし。
【連載執筆者】
谷田伸治(たにた・のぶはる)
医療ジャーナリスト、中医学ウォッチャー
鍼灸師
早稲田鍼灸専門学校(現人間総合科学大学鍼灸医療専門学校)を卒業後、株式会社緑書房に入社し、『東洋医学』編集部で勤務。その後、フリージャーナリストとなり、『マニピュレーション』(手技療法国際情報誌、エンタプライズ社)や『JAMA(米国医師会雑誌)日本版』(毎日新聞社)などの編集に関わる。
Q&A『上田がお答えいたします』 受領委任は「制度」か「事務取扱い」か

Q&A『上田がお答えいたします』 受領委任は「制度」か「事務取扱い」か
2018.12.10
Q.
最近の厚労省の発出文書には「受領委任制度」と書かれることがほとんどですが、以前は「制度」などと書かれていませんでしたよね。あともう一つ、「復委任」について保険者はこれを承認しているのでしょうか。
A.
私が厚生省に勤務していた時、柔整の国会想定問答を作成し、参議院での「受領委任を廃止できないか?」との問いに対して「受領委任払いは『制度』として広まっているので今さら廃止するわけにはいかない」と、保険局長に答弁させたことがあります。後で上司に「受領委任は通知一本で廃止できる単なる『事務取扱い』で、『制度』ではない」と叱られたのですが、「法によって定められ明文化されたものが制度である」という観点から、法律に基づかず、単に保険局長の通知で運用される受領委任は「事務取扱い」であると今は理解しています。しかし、ご指摘の通り、柔整療養費の適正化関連の資料や、来年1月のあはき療養費への受領委任導入に向けて厚労省が発出している周知パンフレットや事務連絡、ホームページ上の案内などには、保険局長通知を除く全てにおいて「受領委任制度」と書かれています。
さて、受領委任の取り扱いにおいて受任者(施術管理者であるあはき師・柔整師)が自ら受けた仕事(療養費の受領)を、さらに他者(団体もしくは団体の長)に委託することを「復委任」といいます。厚労省は施術管理者と被保険者の関係しか定めていないため、療養費支給申請書の参考様式には団体の長の情報欄はありません。しかし、復委任によって、保険者は施術管理者ではなく団体もしくは団体の長の口座に療養費を振り込むことになります。大半のケースで復委任に対する支給事務が滞ることなく完了しているのは、保険者が復委任を認めているからこそです。また厚労省はこのことを知っていますが、「保険者が判断してそうしている」と考えています。これはあはきの受領委任にも全く同様のことが言えます。「あはきの受領委任払いだけ復委任を認めない」とはならないでしょう。
ただ、ここにきて国は「受領委任を制度として導入したのだから、今まで保険者判断で行われてきたあはき療養費の代理受領を今後は一切認めない」と主張していますが、それは誤りではないでしょうか。少なくとも、代理受領を黙認し放置してきた行政が、今頃になって認めないなどと保険者宛てに連絡する法的論拠は見いだせません。
【連載執筆者】
上田孝之(うえだ・たかゆき)
全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長
柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。
日鍼会の第14回全国大会in沖縄 「統合ヘルスケアチーム」を紹介

日鍼会の第14回全国大会in沖縄 「統合ヘルスケアチーム」を紹介
2018.12.10
―モクサアフリカの最近の動向も―
公益社団法人日本鍼灸師会(日鍼会)の第14回全国大会が10月27日、28日、那覇市内で開催された。テーマは『時代を支える鍼灸―病に体にそして心に』。
日鍼会で国際委員会委員長などを務める児山俊浩氏が、名古屋大学医学部付属病院総合診療科で統合医療を実践している「統合ヘルスケアチーム」について講演を行った。チームは児山氏も含めた鍼灸師7名、医師5名のほか、芳香療法士や保健師、管理栄養士、臨床心理士、僧侶などのおよそ20名で構成。単に西洋医学と各種療法を組み合わせるのではなく、患者とチームとで一致した目標に向け、様々な療法の中から患者の状態に合ったものを選択していると述べた。会議は円卓式で、メンバーが対等に話し合える場であると説明し、顔の見える関係を築くことができるといった特長を挙げた。また、チームで取り組むことで医師の診察の負担が軽減し、患者にとっては、医師による投薬や検査が無くても「医療から見放されていない」という安心感が与えられ、当初は混乱していた情報を整理して伝えられるようになって、正確な診断につながることがあると話した。
『お灸フェスin沖縄』では「モクサアフリカジャパン」の栢之間理沙代表が、アフリカを中心とした途上国の結核患者への施灸活動を紹介。今年6月にはその集大成として、アフリカ・ウガンダの大学との共同研究『結核に対する補助的な灸療法―無作為化臨床試験による潜在的有効性と安全性の比較の調査』を『European Journal of Integrative Medicine』に発表したと話した。
近年では北朝鮮でも活動しており、足三里への施灸に加え、現地の韓医の協力を得てアフリカではできなかった腰部八点穴への施灸が可能になったと説明。6カ月に及ぶ薬剤耐性結核患者の治療では、灸を併用しなかった患者のうち症状の改善を見せたのは64%にとどまったのに対し、灸併用群では90%が改善したと報告。体重の増減についても、灸併用群が平均2.7kg増だった一方で対照群は同1.2kg減と顕著な差があったと述べた。
経営シンポジウムは中村聡氏(日鍼会業務執行理事・療養費担当)、得本誠氏(大阪府鍼灸師会会長)、斎藤晴香氏(晴香堂針灸院院長)、猪狩賢二氏(IT&鍼灸「クレバースキッド」代表)が登壇した。中村氏は介護事業運営の経験から、鍼灸師が地域包括ケアシステムに参画する際の、ケアマネジャーをはじめとする他職種との連携の重要性を強調。得本氏は、元料理人の腕を生かした料理教室の開催や麻雀などの多彩な趣味を通じて、他業種の人々と親交を深めていると話した。斎藤氏は青年会議所での活動で人脈を広げるとともに、鍼灸の認知度向上にも努めてきたと説明。AcuPOPJ(国民のための鍼灸医療推進機構)のウェブ管理者を務める猪狩氏は、ホームページやSNSで鍼灸や健康にまつわる情報を絶えず発信し続けることで新規の鍼灸ファンや固定ファンを獲得してきたと述べた。座長の小川卓良氏(日鍼会業務執行理事・学術・研修担当)は「四者四様に何らかの形で人とのつながりを大切にしてきたことが、成功の基盤となっている」としてシンポジウムを締めくくった。
ほかに、沖縄県鍼灸師会会長の久場良男氏による鍼灸公開実技『挫刺鍼による久場式跳鍼法』や、三瓶真一氏(福島県鍼灸師会会長、JISRAM副代表)らが登壇した婦人科シンポジウム、日鍼会危機管理委員会委員長の堀口正剛氏が座長を務めた委員会講座『求められる災害時の鍼灸とは』などが行われた。
連載『汗とウンコとオシッコと…』172 リミット限界

連載『汗とウンコとオシッコと…』172 リミット限界
2018.12.10
既に年の瀬だが、「今年は秋があったのか?」と感じてしまう。暖冬で12月初頭は20度……昭和ではあり得なかった気候だ。今までなら早ければ北風が吹いて小雪がちらついてもおかしくないのに、妙に暖かい。もう「今までなら~」のような表現は通用しないのかもしれない。振り返れば、一兆円を超える災害続きでまれに見る変化の激しい年だった……。
これで身体はどうなるのかというと、秋と夏の混在した病が増える。例年ならば仙腸関節痛がトレンドだが、暖かさで緩みを伴い深部が収縮する肩関節痛、股関節痛がやたらと多い。暖かさによって上焦部の血管が弛緩すれば、眩暈や動悸を伴い、女性ならば疑似月経前症候群が現れたりすることが多いようだ。
「先生、またお願いします。今日は娘なんです」
そう話す母親が連れてきたのは、西山楓香ちゃんという10歳の女子だった。なんでも、バドミントンで今年の夏に全国上位ランクの好成績を残したという。家族を挙げての応援で年末の大会に出場するのに、右肩が痛いということだ。整形外科の受診では問題なく、一週間物療を行ってはみたが変化がないということで来院した。肩のどの辺りが痛むのかと聞くと、右魄戸を指で押さえていた。
「なんや、その年で目の下にクマなんか作って……楓香ちゃんは今、何キロなんや?」
「今、29キロ」
横転先生の問いに、可愛らしい声で答える楓香ちゃん。
「春から何センチくらい伸びたんや?」
「う~ん。分からへん……」
「春からは5センチくらい伸びました」
代わりに答えたのは母親だ。
「まあ、平均より小柄なんやな……」
珍しく時計を見て確認をしながら脉を診つつ、母親に質問を続ける横転先生。
「バドミントンの練習は毎日あるんか?帰宅時間は?」
「週に4回です。大会が近いと毎日かな……帰宅時間は夜9時を少し回ります」
「練習時間は?」
「そうですね……大体4時間で、実質は3時間くらいかしら」
「寝るのは何時?」
「宿題があるから、11時くらい……」
と、これは本人が申告した。
「胸が重く感じたり、右の下腹が痛くなるやろ?」
「よくなる……」
うなずく少女。
「これな……睡眠不足で出てくる神経反射的な痛みや。筋肉性の疲労じゃないし、バドのやり過ぎでもない。30代女性のOLさんや看護師さんが、眼精疲労や寝不足で自律神経が乱れた時に出てくるようなところに反応がある。胸の重たさは疲労で心臓の拍出圧力にバラつきが出てるせいやな……。お母さん、10歳の時は何時に寝てた?」
「……9時には……」
「そうやろ、頑張り過ぎで寝不足なんだわ。それが目の下のクマ。限界ギリギリや。これ以上やると、喘息系になるか心臓が苦しくなるぞ」
「本当ですか」
「時間配分を考えんと本末転倒になるぞ。……ええか、楓香ちゃん。適当に手を抜かんと大人につぶされるぞ。大人の都合にな……」
諭すように話す横転先生だった。
【連載執筆者】
割石務文(わりいし・つとむ)
有限会社ビーウェル
鍼灸師
近畿大学商経学部経営学科卒。現在世界初、鍼灸治療と酵素風呂をマッチングさせた治療法を実践中。そのほか勉強会主宰、臨床指導。著書に『ハイブリッド難経』(六然社)。
連載『未来の鍼灸師のために今やるべきこと』23 鍼灸・柔整が社会システムを変える~養生を用いた新しいシステム~

連載『未来の鍼灸師のために今やるべきこと』23 鍼灸・柔整が社会システムを変える~養生を用いた新しいシステム~
2018.12.10
これまで、社会情勢の変化を踏まえながら色々な角度から鍼灸治療の形を考えてきました。日本の医療は、超高齢化などに伴う医療費の高騰、AIなどのテクノロジーの進歩、人口減少による人材不足など、かつてないほどの転機に直面しています。これは何も医療に限ったことではなく、サービス業や農業など様々な分野でも同様です。特に工業では、ドイツの産官共同プロジェクトをきっかけに「第4次産業革命」という言葉が定着しつつあるほど、産業構造や働き方そのものが変化の時を迎えています。
医療は、今まさに「治療」から「予防」、そして「予防」から「健康(養生)」へのシフトが進んでいます。そのため、我々も患者へのセルフケア指導や災害後のケアという「治療」をきっかけに、小中学生への教育、企業との健康事業としての「予防」、そして過疎地を活用した養生場構想などの「養生」へと取り組みをシフトしてきました。これらは、形は違ったとしても、どこかで誰かが行ってきた取り組みでもあります。しかし、今後必要なのは、それぞれ単独で取り組むのではなく、各取り組みを一つのシステムとしてつなげること。そしてそのシステムに社会的価値を付加し、誰にでも分かるように「見える化」することだと考えています。
「治療」は何か症状がある時に行う受動的なものですが、「予防」や「健康(養生)」は症状がない段階から行わなければいけない能動的なものです。そのため、予防や養生を行うためのきっかけ作り(健康の物差し)と、それを継続していくための仕組みが何よりも重要であり、それがなければ、よほど健康への意識が高い人でない限り継続できません。予防や養生に興味を持つきっかけはそれぞれ異なることから、興味を持ってもらうためのきっかけを沢山作るとともに、きっかけを次への取り組みにつなげるための仕掛け(システム)を構築することが必要なのです。
我々は病気や災害をきっかけに養生の大切さを知ってもらい(患者教室・患者会)、日常でも養生を学んで体験できる場(養生場や企業との健康教室)を提供するとともに、市町村や行政にも働きかけ、地域(学校教育・広報誌・市民公開講座など)で身近に養生を感じてもらえるよう活動を続けています。このように、異なる立場や状況から、何度も同じ養生の考え方を学び、習慣化させていくことで、それぞれの取り組みに橋渡ししていくシステムは、養生を浸透させていくには必要不可欠なものです。しかし、こうした「養生を浸透させるためのアプローチ」だけでは、養生を長期間継続してもらうには不十分です。養生を持続可能な健康システムとするためには、「何のために健康になるのか?」という目的が必要なのです。
次回は、持続可能な養生システムをテーマとします。
【連載執筆者】
伊藤和憲(いとう・かずのり)
明治国際医療大学鍼灸学部長
鍼灸師
2002年に明治鍼灸大学大学院博士課程を修了後、同大学鍼灸学部で准教授などのほか、大阪大学医学部生体機能補完医学講座特任助手、University of Toronto,Research Fellowを経て現職。専門領域は筋骨格系の痛みに対する鍼灸治療で、「痛みの専門家」として知られ、多くの論文を発表する一方、近年は予防中心の新たな医療体系の構築を目指し活動を続けている。
『ちょっと、おじゃまします』 ~継承しつつ新しいことも~ 大阪府吹田市<五月が丘鍼灸治療院>

『ちょっと、おじゃまします』 ~継承しつつ新しいことも~ 大阪府吹田市<五月が丘鍼灸治療院>
2018.12.10
明治鍼灸大学(現明治国際医療大学)を平成19年に卒業して以来、父親の治療院で治療に携わってきた内名先生。一昨年、名実ともに院長を引き継ぎました。その治療法は先代譲りで、まず背骨の歪みを手技で正して全身を調整し、症状に応じて鍼をするというもの。運動器だけでなく内科領域も扱っており、内名先生の代からは不妊治療にも力を入れています。
不妊治療に本格的に取り組むきっかけになったのは、数年前、患者さんが自然妊娠した時の喜び。改めて不妊や妊娠に関する書籍を紐解くことから始め、勉強会などにも足を運ぶようになりました。そんな中、縁あってJISRAM(日本生殖鍼灸標準化機関)の前身・不妊鍼灸ネットワークと出会い、現在ではJISRAMの正会員に。また、主に看護師や医師が所属する日本不妊カウンセリング学会認定の不妊カウンセラーの資格も取得。その役割は妊娠・出産や不妊に関する適切な情報提供を行って最適な治療を選択できるようにすることですが、患者さんの声に耳を傾けるのも大切な仕事です。「取ったら終わり」の資格ではなく、定期的な講座の受講などが求められています。今後は男性不妊にも注力していくとのこと。男性不妊に関する情報発信など、男性が来院しやすい環境づくりを模索中です。
「今日の治療の手応えはイマイチやな……と感じたら、父が『あれはやってみたか? あそこは?』とアドバイスしてくれたものです。それが的確で」と、思い出を語る内名先生。いつも「父が後ろから見てくれていた」そうです。先代の頃、発育の状態が思わしくないと、2歳半の男の子が母親に連れて来られたことがありました。治療の甲斐あって身長や体重は正常な範囲内になったといい、その男の子ももう中学2年生。今では母親が通って来ているそうです。「まだまだ父には及びません」としながらも、院長として着実に歩み始めた内名先生でした。
内名博志先生
平成19年、明治鍼灸大学(現明治国際医療大学)鍼灸学部鍼灸学科卒。JISRAM正会員、不妊カウンセラー 33歳
今日の一冊 死を生きた人びと

今日の一冊 死を生きた人びと
2018.12.10
死を生きた人びと―訪問診療医と355人の患者―
小堀鷗一郎 著
みすず書房 2,592円
「死は敗北」とばかりにひたすら延命する医者。目前に迫る死期を認識しない家族や患者自身。病院以外での死を例外と見なし、老いを予防しようとする社会や行政――。様々な要因が複雑に絡み合い、現代日本では患者の望む最期を実現することが非常に難しくなっており、その背景には病院死の一般化によって人々が「死を忘れた」ことがあるという。日本の終末医療が「在宅」中心へと大きく舵を切りつつある今、355人の看取りにかかわった訪問診療医である著者が在宅診療・在宅看取りの実際とその意義を伝える。
編集後記

編集後記
2018.12.10
▽あはき師で絵本作家の、かしはらたまみ先生の連載が始まりました。毎月1枚、「東洋医学絵本」の絵が掲載されますのでお楽しみに! ところで、かしはら先生のご自宅に伺った際に、珍しい絵本を見せていただきました。本紙でも取り上げた『針聞書』に描かれている虫たちが登場する、『はらのなかのはらっぱで』という作品。『針聞書』の復刻にも尽力された鍼灸師の長野仁先生の監修で、アーサー・ビナードという、米国出身の詩人・翻訳家が本文を書いています。「この人の本、持ってます!」。奇遇にも、ビナード作の『さがしています』という絵本を買ったばかり。東洋医学とは関係ありませんが、大人も読ませる内容です。あ、かしはら先生の連載は毎月25日号ですので、お間違えなく!(前)
あマ指師課程新設非認定処分取消裁判・大阪地裁 「藤井調査」、統計学的に全面否定

あマ指師課程新設非認定処分取消裁判・大阪地裁 「藤井調査」、統計学的に全面否定
2018.11.25
―「科学的信頼性が無い」と原告―
晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設申請を認めなかったとして、学校法人平成医療学園らが国を相手取って処分取消を求めている裁判で、11月9日、大阪地裁で口頭弁論があった。今回は、原告側から反論文書が出され、国が「あはき法19条は現在も正当性を有する」との主張の根拠に用いた、筑波技術大学教授・藤井亮輔氏らによる「あん摩業に関する実態調査」(以下、藤井調査)に対し、「科学的信頼性が無い」と否定するなど主張を展開した。
藤井調査は、平成28年秋に実施されたアンケート調査(回答数4,605人)。国は主張の中で、視覚障害者の「1カ月の患者数」や「平成27年分の年収」が、晴眼者と比べ低い水準にある(本紙1080号参照)といった調査結果から、あマ指師養成課程の自由化(新設・増設)をする合理的な理由が見いだせないとしていた。
今回提出された原告の文書は、これに対し、鑑定を依頼した統計学の専門家の意見を交えながら反論。主な指摘として、▽調査に利益相反のバイアスがかかっている、▽調査対象者の属性に偏りがある、等を挙げた。バイアスに関しては、研究代表者である藤井氏が基本的に「新設反対、19条支持」とのスタンスを取っており、その旨を表明している出版物も存在する上、調査自体が国の補助金による研究事業で、被告からの資金提供で実施されたものだと懸念を示した。調査の内容では、調査対象者のうち、あマ指師免許保有者以外が4割にも上回り、国勢調査(総務省が5年ごとに実施)の職業分類「あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師柔道整復師」と比較すると、男女比や年齢分布に大きな隔たりがあり、現状を反映していないと指摘した。また「患者数・年収」についても、藤井調査は「施術者」ではなく、「事業所」を対象に数値を調査しており、回答者の事業所規模も不明で、視覚障害者・晴眼者1人当たりの収入等の実態を正確に比較するのは不可能と強調。「調査の方法論並びに統計学について十分な訓練を受けていないと推測され、不十分な調査項目に関する標本比率の比較に終始しており、推論に無理があるため、納得的な結論が導出できていない」といった専門家の評価にも触れ、藤井調査を全面的に否定した。
台湾の例を19条廃止後の代替案に
また原告は、視覚障害者の職域の保護という目的を達成する手段として、「台湾」の事例に言及。2008年、あん摩業を視覚障害者の専業と規定する心身障害者保護法が違憲であると判断されたが、その後の各種行われた施策の結果、以前よりも視覚障害者のあん摩業が盛況になっていると説明した。その施策の中には、政府による営業費用の補助のほか、病院、駅、空港、公園、政府機関等の場所は視覚障害者しかあん摩業を行えないという規制なども設けられているとし、たとえ19条を廃止したとしても、この台湾の例が代替政策として具体的な案を提示していると主張した。
当日の口頭弁論では、原告から、視覚障害者の中にも19条に対する多様な意見があることから、証言に立ってもらうことを予定していると述べられた一方、被告は「必要があれば反論する」と話した。次回は、来年2月1日を予定。
『医療は国民のために』260 柔整師の生き残り戦術は、自費メニューの取り組みだ!

『医療は国民のために』260 柔整師の生き残り戦術は、自費メニューの取り組みだ!
2018.11.25
私はこれまで療養費をテーマとした著書を5冊書き上げ、療養費に関するプロとしての自任により、柔整師の療養費取扱いを推進してきた。しかし近年、私の願いと取り組みをあざ笑うかのように、療養費支給申請は厳しくなり、大量の返戻もしくは不支給処分が行われている。また、柔整師数も施術所数も依然増えているにもかかわらず、療養費の取扱高は増加せず、減少し続けている。「療養費を申請すれば何でも通る」などというのは昔の話で、今後そんなことは絶対にないだろう。一部の保険者からは柔整師は「終った資格」などと揶揄され、療養費に関わってきた者として残念であり遺憾に思うばかりだ。
このような状況にあって今のトレンドとなっているのは、自費メニューの開発・取り扱いを手掛ける施術者が集まり、団体を設立するといった事業展開だ。ここには金も集まり、人も集まるようだ。療養費のみに終始する施術者団体は、その取り扱いに係る手数料が次第に減少していく中で自滅し、淘汰されていく。これからの施術者団体は、患者保護の見地も含めて療養費も当然取り扱うが、それが全てではないという組織が生き残っていくであろう。「療養費+自費」の収入で活動する柔整師像が成功への第一歩となってきているのは明らかだ。
ただ、一口に自費と言ってもそのメニューは様々で、
①整体・カイロプラクティックなどの法令上では「指圧に含まれるもの」
②タイ古式マッサージ・ヘッドマッサージなどの「マッサージもの」
③骨盤矯正・小顔矯正・産後骨盤矯正・猫背矯正・全身矯正などの「矯正もの」
④不眠症・自律神経失調症・慢性疲労・冷え性・頭痛などの「自覚症状の悩み」
⑤リフレクソロジー・アロマテラピー・まき爪・デトックス・育毛・ダイエットなどの「外見的及び美容的要素」
など、主だったものだけでも20以上はある。これらを用いた自費メニューの取り扱いは既に始まっているのだ。
さて、私は本紙で、過去に何度も「療養費には混合診療の禁止は適用されない」と鍼灸療養費を例に挙げて解説してきた。もちろん、柔整療養費でも問題ない。もし、混合診療の禁止の概念により「自費メニューは認められない」と躊躇しているのであれば、それは間違いである。問題は、保険ではなくて「医事の問題」だ。広告規制と同様、保健所の管轄である「専用の施術室」が問題で、柔道整復師法施行規則第18条に抵触するか否かだ。すなわち、専用の施術室の構造設備上で柔整施術以外を行うことについての説明ができなければならない。今後、私も積極的に自費メニューの取り扱いについて調査研究して参りたい。
第20回JSSPOT大会 柔整師の古今から考える未来への展望

第20回JSSPOT大会 柔整師の古今から考える未来への展望
2018.11.25
―外国語が柔整師の必須スキルに?―
日本スポーツ整復療法学会(JSSPOT)の第20回大会が10月20日、21日、東京都内で開催された。
シンポジウムでは、幡中幹生氏(株式会社タシマ創健)、伊澤政男氏(伊澤接骨院)、内藤晴義氏(内藤接骨院)が登壇。第20回大会の節目と、2020年の東京オリンピックを見据え、「柔道整復師の古今から考える未来への展望」をテーマに報告と意見交換を行った。
江戸時代、1820年に創業した田島接骨院の九代目当主である幡中氏は、一子相伝・門外不出だった治療技術が今の時代に必要なものだと考え、広く門戸を開いて継承する決断をし、スタッフは総勢40名を数えるほどとなったと説明。また、平成19年にデイサービス、同23年には「運動器の障害に運動療法は必須」との八代目の理念の下で会員制フィットネスの経営を始めたことで、毎日来院していた患者が安心して生涯にわたってサービスを受けられるようになるなど、より広く国民の健康に寄与するための取り組みを模索し続けているとした。
伊澤氏は、東京都柔道整復師会やNPO法人ジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会(JATAC)の活動を振り返り、柔整師・ATが果たしてきた役割の大きさを強調。超高齢化社会への対処や、東京オリンピック・パラリンピック、またその後のスポーツボランティアへの参画へ向けて、生計の成り立つ専門職として活躍できる環境作りが必要だとした。内藤氏は、開業施術者は地域特性を考慮する必要があると指摘。在留外国人が多いことで知られる神奈川県大和市で開業する同氏の院では、患者の多国籍化が進んでおり、その多くが英語を話せないと説明。外国人労働者の受け入れ拡大などの議論が進む中、将来的に柔整師に外国語の習得が求められる可能性を示唆した。
特別企画『東京オリンピックに向けて―4度の五輪と怪我、そのケア』では、アテネ、北京、ロンドン、リオデジャネイロオリンピックで4大会連続金メダルを獲得した伊調馨氏(ALSOK)が講演。そのほか、特別講演『2020年を健康で迎えるための貯筋運動』(福永哲夫氏・東京大学名誉教授)、実技ワークショップ『2020年を健康で迎えるためにできること』、一般研究発表12題、学生発表コンペ5題などが行われた。
イベント『お灸×デザイン』 デザインは問題解決の手段

イベント『お灸×デザイン』 デザインは問題解決の手段
2018.11.25
―「医療職 ≒ デザイナー」―
10月8日に京都市内でセミナー『お灸×デザイン』が開かれた。講師を務めたのは、新町お灸堂(京都市下京区)院長の鋤柄誉啓先生。お灸の普及啓もうのため、お灸にまつわる言葉やイラストをあしらったTシャツなどのグッズを開発したり、お灸の漫画を監修するなど多角的に活動、最近では治療院のブランディングも手掛ける。
「デザインとは、ただ単におしゃれにしたりカッコよくしたりするということではありません」と言う鋤柄先生。課題や問題を解決したり、調整したりする手段だと説明する。デザイン業界には「デザイナーとは医者のようなものである」という言葉があるという。クライアントの課題や問題を発見して共感するのは「診察」。デザインのコンセプトの決定は「治療方針の決定」。そして、実際の作業は「治療」。アフターケアは治療後の生活指導など。これらはみな、鍼灸師にも当てはまる。「デザイナー≒鍼灸師」と表現した。
数年前、あるイベントに出店した際の好評とはうらはらに当時の来院患者数は非常に少なかった。「鍼灸は世の中に必要とされているのに……」。需要と供給との間の溝を埋めるため、鋤柄先生は自身の治療院をデザインし直すことにした。まずはターゲットを明確にしようと、「今の日本の社会で一番悩んでいるのはどんな人なのか」を探った。浮かび上がって来た人物像が、「35歳前後の女性」だ。年齢による体調の変化や子育ての負担、仕事における責任の増大、さらには親の大病や介護などが重なることもあり、ストレスからさまざまな不定愁訴を抱えている。この層を想定して、メニューをお灸のみとシンプルにして来院のハードルを下げる、来院してもらいやすい身近な雰囲気の空間をつくる、定期的な来院が難しい人へのセルフ灸と養生の指導を行う、などに取り組んだ結果、新町お灸堂は軌道に乗ることになったという。
セミナーでは問診票や問診そのもののデザインを試みるなどのグループワークも行われ、「IT技術を活用した問診」といったアイデアが飛び出した。
レポート 美容メディカルエステ コスメトロジー講座
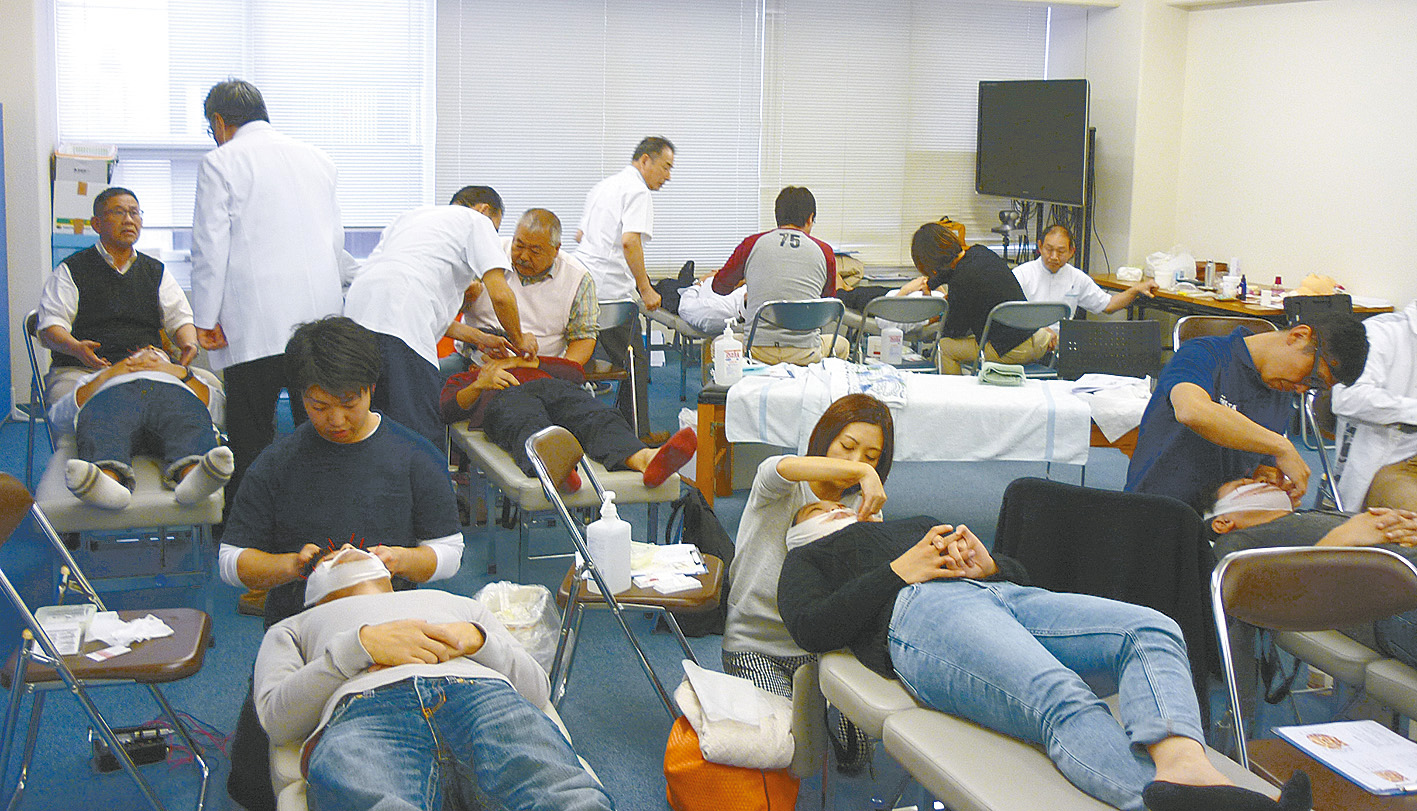
レポート 美容メディカルエステ コスメトロジー講座
2018.11.25
11月11日、全国柔整鍼灸協会より講師依頼をいただき、表題で鍼灸師対象の講座を都内で行った。当日は満席で、熱気で溢れ返るほどの大盛況だった。
講座では、施術のスキームや概論を画像を用いて、美容鍼灸の初心者や現在業務されている方も興味が持てるようフローチャートで説明した。その後、顔のSMASへの刺鍼やリガメントの形成外科での切開術法、牽引箇所の応用でリフトアップ施術、当協会オリジナルの「包帯美容鍼」などは非常に参加者の関心が強かった。特に包帯使用の美容術は、鍼灸柔整師の特長を生かせられる。さらにニキビや丘疹などへの応用について、DDS(ドラッグデリバリーシステム)のビタミンC誘導体経皮吸収などのデモストレーションを行った。実技は参加者各自が交替で行ない、講座終了後は万雷の拍手をもらい気恥ずかしかった。
受講後アンケートでは、「顔の引き上げ効果がとてもあった」「想像していたよりも専門的な美容の話が聞けた」「女性への細かい対応の仕方が勉強になった」など、好評だった。新たな患者層発掘の一助としてほしい。12月9日には第2部となる柔整師も対象とした講座もあり、表情筋のフェイシャルリンパ、静脈マッサージなどでのリフトアップを講義する予定。(一般社団法人日本美容医療協会 理事長 吉田洪先)
あはき療養費の受領委任 スタート時、1249の保険者参加

あはき療養費の受領委任 スタート時、1249の保険者参加
2018.11.25
―協会けんぽは全て、健保組合は25のみ―
各保険者に参加の自由を認める「あはき療養費の受領委任」の来年1月スタートを前に、参加することを決めた保険者が発表された。厚労省保険局医療課が11月8日付で発出した事務連絡と、同省ホームページで計1249の全ての保険者名を公表した。
保険者別でみると、全国健康保険協会(協会けんぽ)が48、健保組合が25、市町村(特別区を含む)が1083、国民健康保険組合が76、後期高齢者医療広域連合が17となった。いずれも来年1月1日の受領委任取扱い開始時より参加する。
あはき療養費検討専門委員会で受領委任導入に強く反対をしていた協会けんぽは47都道府県支部に船員保険部を加えた全てが参加を決めた一方、同じく反対していた健保組合(平成30年4月時点で1389組合)は25のみだった。後期高齢者医療広域連合も参加率は低く、市町村については大阪府、京都府、兵庫県などの近畿を中心に9府県が不参加となった。ただ、来年4月からは参加の追加も始まり、既に受領委任への参加を表明している保険者もいるほか、準備が整い次第、参加に踏み切る保険者も出てくることが見込まれる。厚労省も適宜「参加保険者」情報を更新していく予定としている。
連載『先人に学ぶ柔道整復』十二 名倉直賢(後編)

連載『先人に学ぶ柔道整復』十二 名倉直賢(後編)
2018.11.25
―直賢の精神、子孫通じて今の柔整師へ―
今回は直賢の子孫で、明治期に活躍した陸軍医監である名倉知文と大正期の柔整師の関係について触れてみます。
知文は、幕末に江戸医学所で松本良順(初代陸軍軍医総監)から医学を学び、1874(明治7)年3月に『整骨説略』を出版しています。同書は、知文がまだ軍籍に入る前にドイツのケルストの軍陣外科書の骨傷編を訳したもので、同僚の石黒忠悳や三浦煥らがこの翻訳を強く勧めたといいます。内容は、「諸骨交節毀傷及移位論」「脱臼総論」「下牙床骨脱」「脊柱骨脱」「脋骨脱」「尻盤骨脱」「鎖子骨脱」「上臂骨脱」「轉肘骨脱」「手腕骨脱」「前後掌骨及指骨脱」「大腿骨脱」「膝蓋脱」「膝膕脱」「輔腿骨脱」「足跗骨脱」「足拗骨脱」について書かれています。それぞれ、脱臼の発生機序、症状、転位方向のパターン、整復法、固定法、合併症が記載されていて、現代の柔整師による脱臼の整復法に通じるものがあります。例えば、「上臂骨脱」(肩関節脱臼)では、肩関節の特徴として「上臂骨ハ運用最モ多ク窩臼狭隘ニシテ浅ク且ツ其臼ニ比スレハ骨體長大ナリ是ヲ以テ脱離ノ多キ餘處ニ過ク」とあり、「肩関節は運動が多く、関節窩が上腕骨頭に対して浅く狭いため、脱臼をしやすい」ことを既にこの時代で説明しています。また、全体の整復法にはドイツの医師による方法が紹介されていて、中でもストロメール(G. F. Stromeyer、1804~1876)の整復法が多くみられます。
同書が口火となり、知文の同門である足立寛(7代陸軍軍医総監)がドイツのホエリッヒの外傷による骨折と脱臼の成書を翻訳した『整骨図説』を1900(明治33)年に出版します。ドイツから輸入したエックス線像及び原色付図を初めて日本で紹介しました。また、『整骨図説』の肩関節脱臼の整復法はコッヘル(Emil Theodor Kocher、1841~1917)による方法が紹介されています。
知文による『整骨説略』は、『整骨図説』、『臨床小外科』(松本喜代美著、1915年)、『新撰外科総論』(茂木蔵之介著、1920年)とともに、1921(大正10)年に柔道整復師試験対策のために出版された『柔道整復術』(安井寅吉著)に大きな影響を与えました。直賢の接骨に対する勉学の精神は、子孫である知文に受け継がれ、さらには今日の柔整師の教科書の礎となっています。
参考文献:名倉弓雄『江戸の骨つぎ』(1974年、毎日新聞社)他
【連載執筆者】
湯浅有希子(ゆあさ・ゆきこ)
帝京平成大学ヒューマンケア学部柔道整復学科助教
柔整師
帝京医学技術専門学校(現帝京短期大学)を卒業し、大同病院で勤務。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科博士後期課程を修了(博士、スポーツ科学)。柔道整復史や武道論などを研究対象としている。
商品紹介 チュウオー『MOXATH MX-5』

商品紹介 チュウオー『MOXATH MX-5』
2018.11.25
―灸を「科学」する艾燃焼解析システムー
チュウオー(兵庫県宝塚市)の、灸を「科学」する艾燃焼解析システム『MOXATH(モクサス) MX-5』。
灸の温度や人体が得る熱量、艾の捻り方によって変わる温度の立ち上がり時間、最高温度をグラフで可視化する。測定部は人体表面を再現するため30~40℃に設定可能。パソコンに接続して使用、データの保存もできる。対応するOSはWindows。「教育・研究機関や灸の研究家に活用してもらい、灸の科学的アプローチやエビデンスの充実に」と同社。
製品に関する問合せは同社(0797-88-2121)へ。
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』104 医療の破壊的イノベーション再び

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』104 医療の破壊的イノベーション再び
2018.11.25
中国・深センのホテルでこの原稿を書いています。先日、中国で「1分間診療所」という無人クリニックが発表されました。『平安健康医療科技』による発表で、人工知能が、患者の声や画像を通じて初期診断し、実在の医師が確認して正式な診断を下すという仕組みで、診断から処方までを数分で完了するというものです。しかも、併設する自動販売機で、薬をすぐに入手することもできます。私たち「MedQuery(メドクエリ)株式会社」が、先日発表した事業計画の一部に非常に似ているモデルです。
日本では「このような無人クリニックで質の高い診療ができるのか」、「皆保険制度の日本は中国とは違い、すぐには不可能だろう」といった声も聞こえますが、破壊的イノベーションとはこんなものです。最初はおもちゃみたいだったものが、既存の市場を凌駕する。医療にもそういう流れが来そうです。MedQueryでは日本の医療は次の診療報酬改定で行き詰まるのではないかという仮定の下に事業開発を進めています。医療は5年後にはずいぶん変わっているのではないでしょうか。鍼灸マッサージ・柔整業界の変化はもっと早いかもしれません。
さて、近い将来、ウェルネスやセルフケアと言われる領域と急性軽症の疾患の診療との境界がなくなると見ています。私自身、鍼灸治療院と医療機関をつなげることで、それを引き起こそうとしてきました。そして同時に、ライセンスによる業界の〝くくり〟が消失すると思います。つまり、多職種連携です。宮崎大学の吉村学教授の言う「ごちゃまぜ師」というような新たなくくりでサービスは提供され、ライセンスが必要ない代替サービスが生まれてきます。一例として、肩こりという愁訴に対し、国家資格が必要のないリラクゼーション業が生まれました。さらに、医師が行っていたことを医師以外がやれるようになる。場合によっては機械が代替するかもしれません。このような世界が本当に来るのかと思うかもしれませんが、こういった流れは医療以外では既に先行して起きています。今まで守られていた業界は縮小し、新しい業界が生まれるということです。
これはもう必然で、鍼灸マッサージ師や柔整師も同様でしょう。「AIによって無くなる仕事」とあおる記事も見られますが、その前に職域の壁の崩壊が起きて「資格制度の事実上の崩壊」が生じると思います。医療は公益性が高く保守的で、こういった流れが起きにくい業界でしたが、逼迫した財政などの環境により変わらざるを得ないところにきています。それは多分、2020年の東京オリンピックまでに起きるでしょう。
【連載執筆者】
織田 聡(おだ・さとし)
日本統合医療支援センター代表理事、一般社団法人健康情報連携機構代表理事
医師・薬剤師・医学博士
富山医科薬科大学医学部・薬学部を卒業後、富山県立中央病院などで研修。アメリカ・アリゾナ大学統合医療フェローシッププログラムの修了者であり、中和鍼灸専門学校にも在籍(中退)していた。「日本型統合医療」を提唱し、西洋医学と種々の補完医療との連携構築を目指して活動中。