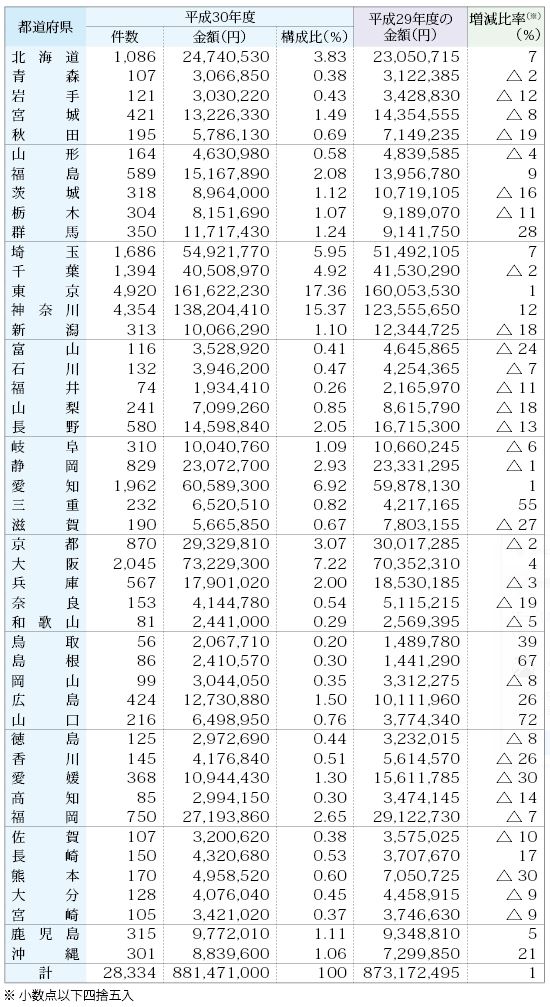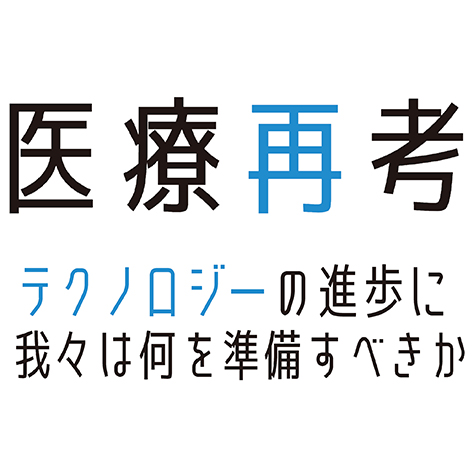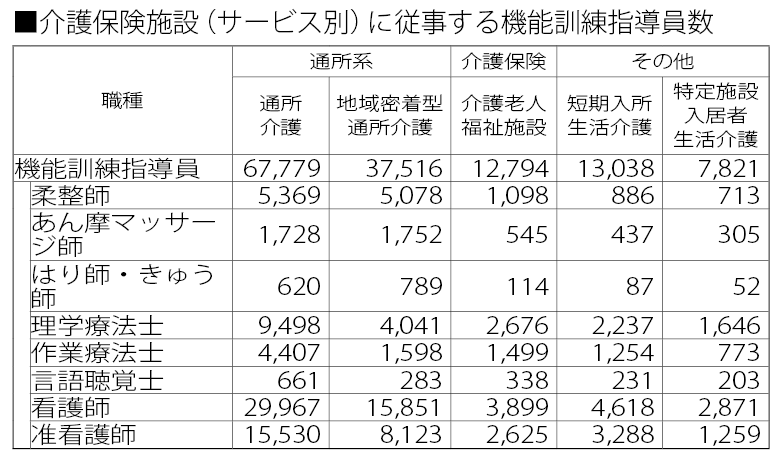JATAC関東ブロック研修会 厚底シューズの構造など解説
2020.02.10
安全性の研究不足も示唆
ジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会(JATAC)の関東ブロック研修会が1月26日、埼玉県内で開催された。
講演では、JATAC専務理事の蛭間栄介氏(帝京大学医療技術学部教授)が、足部アライメントに着目して長距離走におけるスポーツ障害の機序を概説したほか、スポーツシューズ開発の歴史を紹介した。
この3、4年ほどの厚底シューズブームの発端となった『Hoka One One』のシューズの場合、厚底である意義は、クッション性向上のほか、踵に丸みをつけた「ゆりかご」状の形状により、後足部接地からスムーズに前方へ体重移動できる作りを実現できる点にあったと説明。一方で、最近話題となっているナイキの厚底シューズはカーボンプレートを内蔵し、爪先が曲がらないほど固く、前足部接地を前提とした構造であり、使用時はこうした差異を理解しておく必要があるとした。また、平成30年に同シューズを使用した設楽悠太選手が日本新記録を更新した際の走りを「膝が内転し、踵が外に出ている」と指摘。結果を出しているとはいえ、膝を痛める危険のある走り方を誘発している可能性を示唆した。また、カーボンファイバーシューズの最新報告として、▽は下腿部の関節への負荷を分散するとした研究、▽酸素摂取量やストライド、重心の上下動などを改善するとした研究、▽ミッドソールにカーボンファイバーを挿入する場合と比べ、靴内部に挿入すると床反力が減少し、ショパール関節背屈と足関節底屈が優位に増加するとした研究を紹介。「足下のアーチにわずかな角度の変化があれば、姿勢全体には大きな影響が生じる」として、安全性に関する研究を増やしていくよう呼びかけた。
このほか、3月1日開催の東京マラソンへの提言を掲げたシンポジウムでは、JATACの小池龍太郎副理事長、今井裕之理事が登壇。ボランティアの参加呼びかけなども行われた。