連載『織田聡の日本型統合医療“考”』212 「健康ガイドライン」策定へ、エビデンス構築にテコ入れを
2023.06.09
あっという間に5月の爽やかな季節が終わりを告げ、西日本では早々に梅雨入り宣言がなされました。今年はエルニーニョ現象の影響があるらしく、冷夏になるかと思いきや、ラニーニャ現象の影響で、猛暑になるかもしれないのだそうです。極端なのはやめて欲しいですね。 (さらに…)
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』212 「健康ガイドライン」策定へ、エビデンス構築にテコ入れを

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』212 「健康ガイドライン」策定へ、エビデンス構築にテコ入れを
2023.06.09
あっという間に5月の爽やかな季節が終わりを告げ、西日本では早々に梅雨入り宣言がなされました。今年はエルニーニョ現象の影響があるらしく、冷夏になるかと思いきや、ラニーニャ現象の影響で、猛暑になるかもしれないのだそうです。極端なのはやめて欲しいですね。 (さらに…)
羊土社から新刊 軟部組織の障害と理学療法 解剖と病態の理解に基づく評価と治療
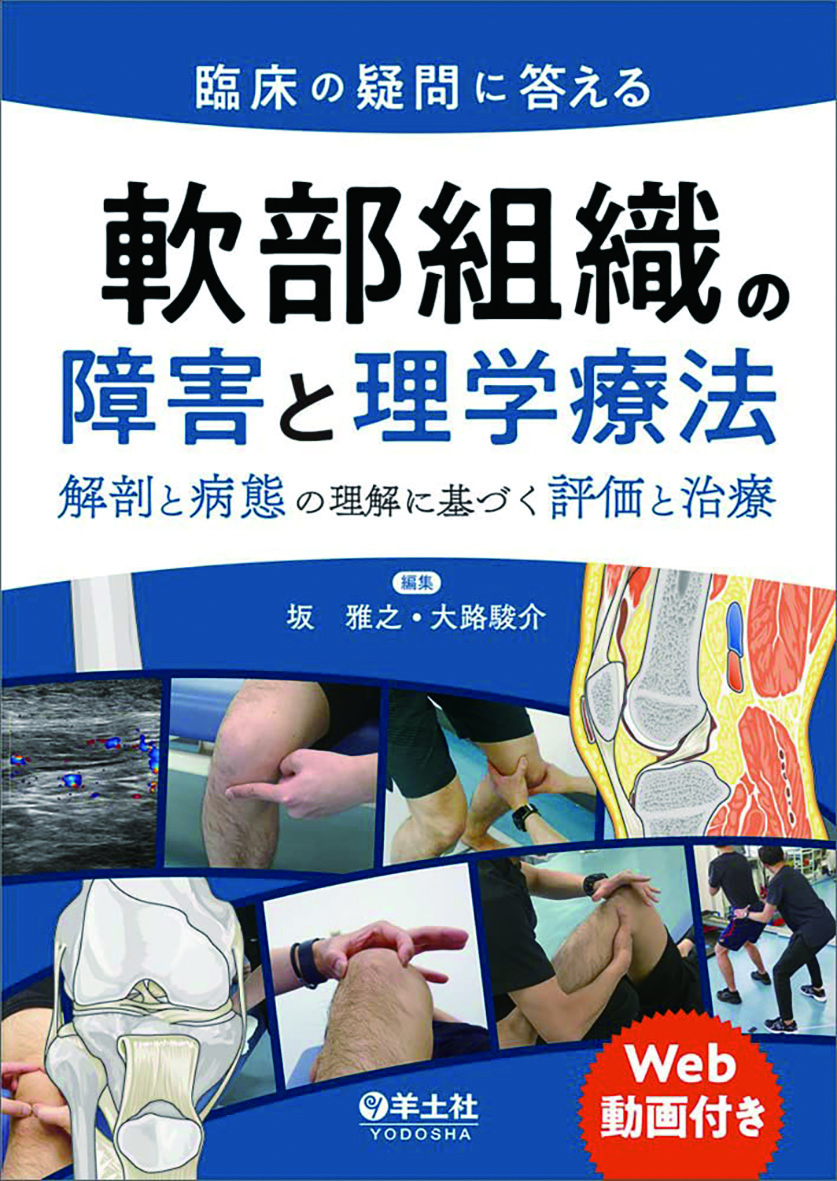
羊土社から新刊 軟部組織の障害と理学療法 解剖と病態の理解に基づく評価と治療
2023.06.09
株式会社羊土社から新刊『臨床の疑問に答える軟部組織の障害と理学療法―解剖と病態の理解に基づく評価と治療』が発刊。編集はともに理学療法士の坂雅之氏と大路駿介氏。B5判、277項、6820円(税込)。
臨床で遭遇する「困った」を解決! 軟部組織に焦点を当て、カラー画像やイラストとともに解剖や病態を解説する。本書は総論、頸胸部、肩、肘、手、腰殿部、股関節前方、膝、大腿下腿部、足と10章で構成され、章の内容は①解剖、②病態、③評価、④治療の流れで展開する。例えば腰殿部では「腰殿部軟部組織障害と機能解剖」、「軟部機能障害部位の特定と機能評価」、「組織特性を考慮した理学療法プログラムの要点」、「徒手療法・物理療法・運動療法の選択」の4項目、項目内はQ&A形式で知識を整理できるように工夫している。
誌面とリンクする動画もあり。目の前の悩む患者さんを救うヒント盛りだくさんの一冊。
(さらに…)
連載『中国医学情報』219 ニキビの耳穴刺絡・貼圧治療―治療頻度をランダム化比較 ほか

連載『中国医学情報』219 ニキビの耳穴刺絡・貼圧治療―治療頻度をランダム化比較 ほか
2023.06.09
☆ニキビの耳穴刺絡・貼圧治療―治療頻度をランダム化比較
河北中医学院鍼灸推拿学院・高亜玉らは、ニキビ(尋常性痤瘡)患者90例で耳穴への刺絡・貼圧治療の治療頻度別効果を比較(中国鍼灸、2022年6期)。
対象=患者90例、平均21(18~35)歳。これをランダムに3群(週1・週2・週3回)各30例に分けたが、脱落11例。週1群:28例(男4例・女24例)、罹患期間平均62.3カ月、BMI平均20.7。週2群:26例(男10例・女16例)、罹患期間平均66.0カ月、BMI平均21.2。週3群:25例(男7例・女18例)、罹患期間平均60.9カ月、BMI平均21.4。いずれも治療30日以内の服薬と、7日以内の外用薬塗布なし。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』時間外加算・休日加算にかかる「応需」の要件とは?

Q&A『上田がお答えいたします』時間外加算・休日加算にかかる「応需」の要件とは?
2023.06.09
Q.
柔整療養費の時間外加算(540円)や休日加算(1,560円)の要件について、通知で示された「応需」の意味がよく分かりません。これらの加算は実際に行わなければならない環境にあれば当然認められると思いますが、だからといってなんでも加算が認められるというものでもないでしょう。 (さらに…)
2021年度自賠責・都道府県別の柔整施術費 45都道府県で施術費減少

2021年度自賠責・都道府県別の柔整施術費 45都道府県で施術費減少
2023.06.09
全国的に下落幅縮小も減少傾向止まらず
損害保険料率算出機構が毎年春に発行する『自動車保険の概況』から、2021年度の自賠責保険における柔整の都道府県別施術費を前年度比較と併せて掲載する。 (さらに…)
連載『汗とウンコとオシッコと…』226 過ぎる

連載『汗とウンコとオシッコと…』226 過ぎる
2023.06.09
例年、近畿地方の梅雨入りは6月半ばであるが、今年の梅雨入りはやや早かった。だが、運気論的に火運不及の年周りであるがゆえに地熱が上がらず空気が冷たい。逆に海水の温度が高いために南方で雲が発生しやすく、それゆえの気圧の上昇が雲を北上させて日照量の減少と温度の低下を引き起こしているようだ。 (さらに…)
連載『未来の鍼灸・柔整を考える』第4回 社会に必要なプラットフォームとは?

連載『未来の鍼灸・柔整を考える』第4回 社会に必要なプラットフォームとは?
2023.06.09
世の中はデータに基づいて判断・アクションする「データドリブン」な社会になりつつあります。データドリブンが注目される理由は、消費者の価値観や行動の多様化により、経験や勘に頼った判断が通用しにくくなってきたからです。 (さらに…)
今日の一冊 スローフード宣言 食べることは生きること

今日の一冊 スローフード宣言 食べることは生きること
2023.06.09
スローフード宣言 食べることは生きること
アリス・ウォータース 著
海士の風 1,980円
ファストフードは「早い・安い・多い・便利」を掲げ人々の欲を満たしてきた。そうした食事やサービスを享受し続けるうち、それらは人々の価値観に影響し、「文化」となった。ファストフード文化が浸透した結果、無個性で、サプライヤーのさじ加減が多大な影響を与える社会になった。
本書はそうした即物的な文化や社会に疑問を投げかけ、「地域や季節に合わせた、多様で顔の見える」スローフード文化を紹介する。高速で止まらない毎日に、「それだけじゃないよ」と気づかせてくれる、そんな一冊。
編集後記

編集後記
2023.06.09
▽副委員長に就任しました。何のか、といえば、子どもが通う小学校のPTAの「ベルマーク委員会」の。
「とうとうお鉢が回ってきた」と妻と話し、しかも「ベルマーク」と聞き、驚き2倍。と思っていたら、近々平日の昼に顔合わせをするというので、都合が付かない妻に変わって出席しました。
勝手な思い込みで「今さらベルマークなんて集まるの?」と思っていたら、前任者が100個近いプラスチックコップを出し、手作業でこれにベルマークを入れて集計するのだとか。AI活用もうたわれる昨今にあって何ともいえないモヤモヤ感……自動ベルマーク仕分け機なんてものはないの……と他の親も思ったはず。
とはいえ、視聴覚室用のエアコンの購入を目指しているとかで、子どものためにも機械のごとく数えます!(和)
医師の学会で「あはきアピール」 日本プライマリ・ ケア連合学会でセッション多数実施

医師の学会で「あはきアピール」 日本プライマリ・ ケア連合学会でセッション多数実施
2023.05.25
「こんなにエビデンスあったの」との声
5月12日から3日間、名古屋市内の会場などで開催された『第14回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会』で、あはき関連のセッションが多数開かれた。当日、医師や薬剤師、その他医療従事者ら3500人を超える参加があった中、鍼灸マッサージ師が「インタラクティブセッション」(ワークショップ含む)で演者を務めたり、施術体験ブースが設けられたり、多職種連携に向けてこれ以上ないアピールの場となった。
日本プライマリ・ケア連合学会は、会員数1万1740人(令和5年2月時点)で、患者の疾患・健康面などを総合的に診て、あらゆる医療従事者と連携しその解決に当たる総合診療医・家庭医を中心に構成。今回、多数のあはきセッションの実現に尽力したのが、医師で鍼灸師でもある寺澤佳洋氏(医療法人弘池会口之津病院、同大会準備委員)。プライマリ・ケアを行う医師とあはき師は親和性が高く、最近では (さらに…)
『医療は国民のために』367 施術管理者研修修了証の有効期限切れの事前連絡を財団は行うべきでは?

『医療は国民のために』367 施術管理者研修修了証の有効期限切れの事前連絡を財団は行うべきでは?
2023.05.25
柔整療養費の受領委任を取り扱う上で、義務化された「施術管理者研修」が始まったのは、平成30年7月からである。「随分に前だな」と思っていたら、研修修了の有効期限となる「5年」に迫っているではないか。つまり今後、有効期間が切れる柔整師が順次に現れてくるということだ。 (さらに…)
福島県鍼灸師会春季学術講習会 コロナ患者来院増の見込み 鍼治療最大のメリットは

福島県鍼灸師会春季学術講習会 コロナ患者来院増の見込み 鍼治療最大のメリットは
2023.05.25
福島県鍼灸師会の令和5年度春季学術講習会が4月23日に福島県郡山市内の会場とオンラインのハイブリッドで開催。講師の福島県立医科大学会津医療センター漢方医学講座教授の鈴木雅雄氏は『COVID-19の鍼灸に関する最新知見と後遺症治療の可能性について』と題し、これまでの対応とこれからの対策について解説した。
(さらに…)
令和5年 春の叙勲・褒章

令和5年 春の叙勲・褒章
2023.05.25
あはき・柔整業界からは以下の11名。(敬称略)
◇瑞宝中綬章
矢野 忠(元明治国際医療大学学長)
◇旭日双光章
池田良一(元社団法人長野県針灸師会会長)
伊藤和夫(元公益社団法人三重県柔道整復師会会長)
中野義雄(元公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会副会長)
吉田隆一(元社団法人福井県鍼灸師会会長)
◇旭日単光章
菅野 徹(公益社団法人福島県鍼灸あん摩マッサージ指圧師会業務執行理事)
◇黄綬褒章
染井圭弘(染井はり灸療院院主・福岡県)
八山俔子(健友治療院院長・埼玉県)
◇藍綬褒章
一見隆彦(元一般社団法人三重県鍼灸師会会長)
大河原 晃(公益社団法人埼玉県柔道整復師会会長)
田代富夫(公益社団法人栃木県柔道整復師会代表理事会長)
連載『先人に学ぶ柔道整復』三十六 戦後の柔道整復師試験(前編)GHQ主導で柔整師教育が再構築

連載『先人に学ぶ柔道整復』三十六 戦後の柔道整復師試験(前編)GHQ主導で柔整師教育が再構築
2023.05.25
今回は、第二次世界大戦の日本の戦後処理において、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の公衆衛生福祉局が取った「衛生行政における柔整師への対応」について見てみたいと思います。 (さらに…)
運転免許お試し返納で施術料10%引き あはき滋賀社団所属の治療院が対象

運転免許お試し返納で施術料10%引き あはき滋賀社団所属の治療院が対象
2023.05.25
滋賀県警交通企画課が、高齢ドライバーを対象に5月上旬から始めた「運転免許お試し自主返納」キャンペーンでは、参加の高齢者が県内鍼灸マッサージ院にて施術料金10%割引で治療を受けられる特典を設けている。自費施術のみが割引の対象で、滋賀県鍼灸マッサージ師会と滋賀県鍼灸師会の計44院でサービスを受けられる。 (さらに…)
『治療院に介護予防事業をプラスした総合事業の展望』 第1回 なぜ総合事業参画を勧めるか?
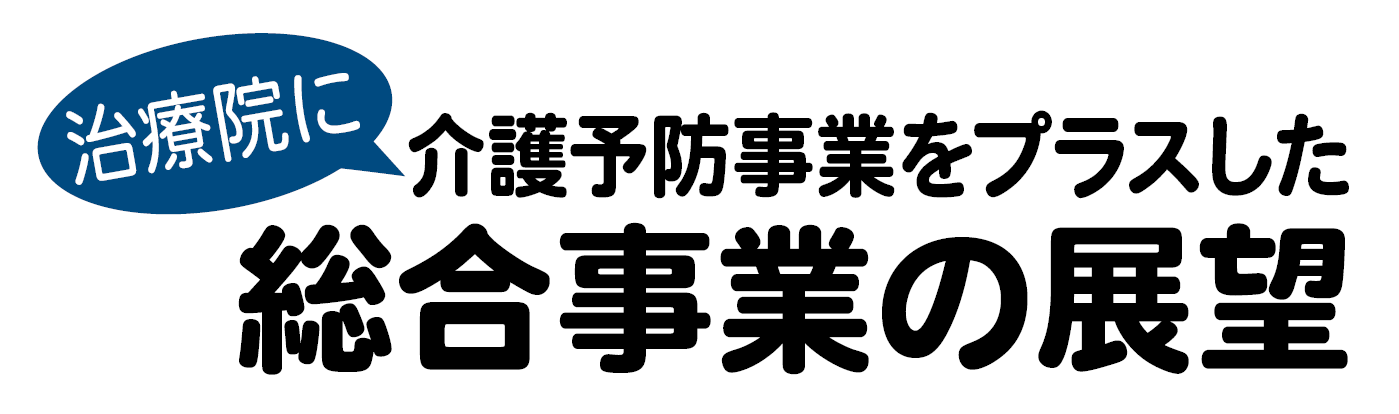
『治療院に介護予防事業をプラスした総合事業の展望』 第1回 なぜ総合事業参画を勧めるか?
2023.05.25
初めまして、NPO法人すこやか地域支援協会代表理事の鈴木と申します。私は京都と大阪で鍼灸整骨院を数院開業しているとともに、施術所併設の基準緩和型通所介護施設やケアプランセンター、機能訓練特化型通所介護施設(デイサービス)などを営んでいます。 (さらに…)
上田孝之氏の新刊予約受付中 療養費問題の最前線 令和4年度版
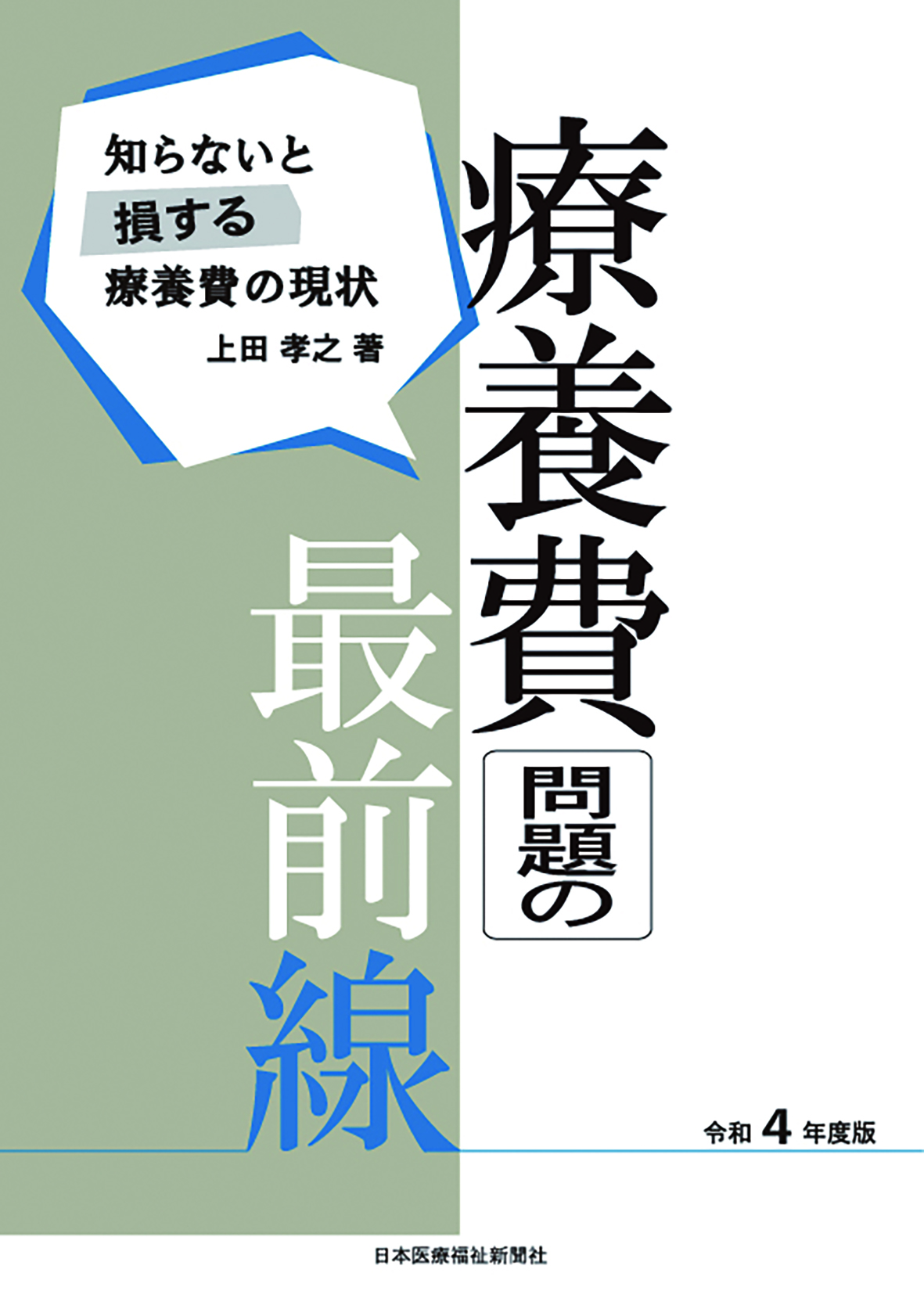
上田孝之氏の新刊予約受付中 療養費問題の最前線 令和4年度版
2023.05.25
本紙で連載執筆中の上田孝之氏(元厚労省療養指導専門官)の新刊『療養費問題の最前線 令和4年度版―知らないと損する療養費の現状』が5月31日に株式会社日本医療福祉新聞社から発行される。B5判210頁、本体価格1,650円。
全国柔整鍼灸協同組合専務理事として、保険者や行政との折衝などで全国を飛び回っている著者。その令和4年度の活動内容や本紙連載記事、業界への提言などをまとめた、「療養費のマニュアル」的事例集。
柔整師へ向けた『レセプトになぜカルテのコピーを添付しなければならないのか理解できない―添付しても不支給処分の理由付けにされるだけではないか!』のほか、柔整師・あはき師へ向けた2本の合わせて3本の書き下ろしを収録。オンライン請求やマイナ保険証との連携など、待ったなしで進むデジタル化についても業界に精通する著者ならではの確かな自論を展開する。
本書は右記QRコード(オンラインショッピングサイト「Amazon.co.jp」本書販売ページ)からご予約いただけます。 (さらに…)
『ちょっと、おじゃまします』 いつも使うもぐさに愛着を! 山正の工場見学 滋賀県長浜市<株式会社山正>

『ちょっと、おじゃまします』 いつも使うもぐさに愛着を! 山正の工場見学 滋賀県長浜市<株式会社山正>
2023.05.25
「もぐさの山正」の愛称で親しまれる株式会社山正は滋賀県長浜市にあります。明治28年にもぐさや美濃紙の行商からはじまり、現在は海外にも工場をもつ鍼灸材料製造会社となりました。近年オンラインのみとなっていた工場見学が、この4月から訪問でも可能に! もぐさ製造の装置や工程を実際に見せていただきました。 (さらに…)
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』211 救急相談アプリにトリアージ機能を搭載する時代にきている

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』211 救急相談アプリにトリアージ機能を搭載する時代にきている
2023.05.25
まだ5月にもかかわらず、東京は気温が30℃を超える日も多くなってきました。朝晩はとても気持ちの良い気候ですが、日中は日差しも強いので紫外線にはお気をつけください。
先日、某市民の会から、夜間往診サービスに関する意識調査のお願いが私のクリニックに届きました。スマホアプリで医師を呼ぶサービスの安全性や診療報酬の不適切請求問題視している団体のようで、調べても団体の正体がよく分からなかったのですが、調査の意図は理解できました。 (さらに…)
ナップから新刊 アスレティックケア リハビリテーションとコンディショニング第2版
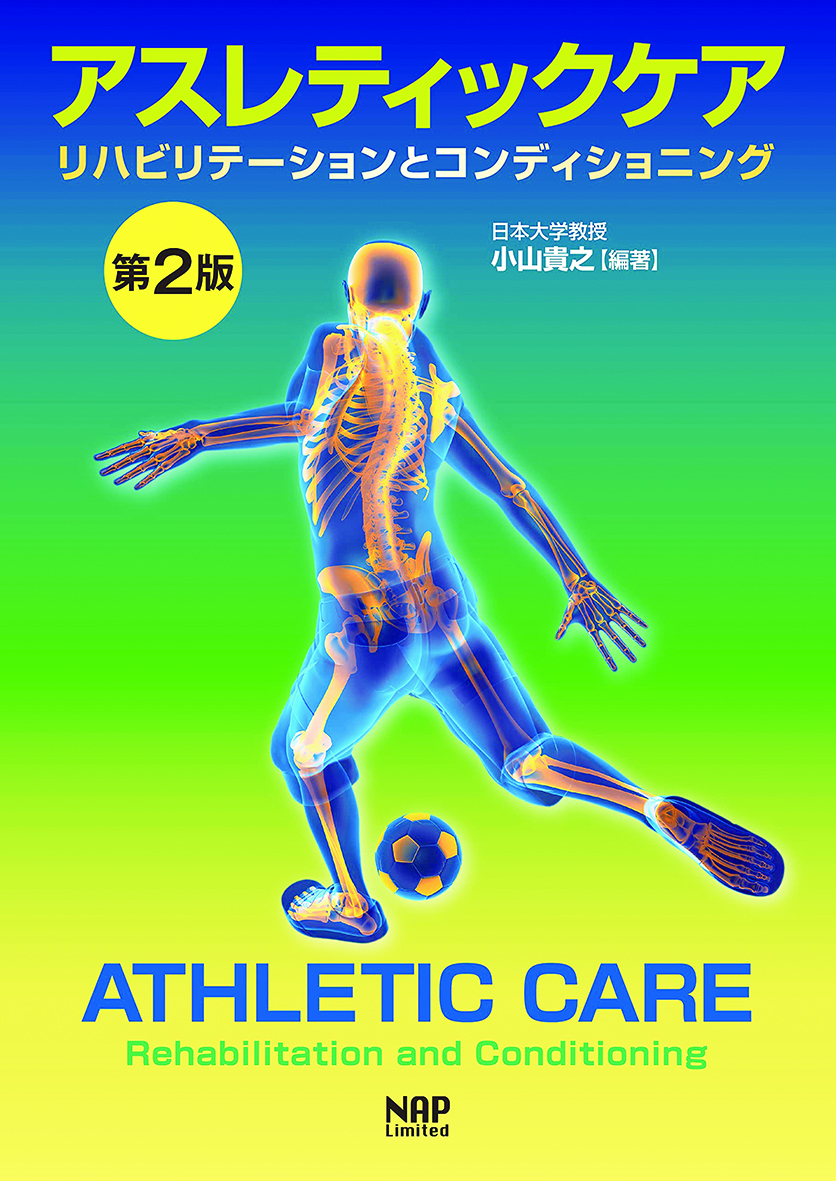
ナップから新刊 アスレティックケア リハビリテーションとコンディショニング第2版
2023.05.25
『アスレティックケア―リハビリテーションとコンディショニング第2版』が有限会社ナップより出版。編者は日本大学教授の小山貴之氏。B5判、280項、3,850円(税込)。
スポーツ医科学サポートを写真や図など交え分かりやすく解説する本書。発展するこの分野で、近年注目のトータルコンディショニングサポートに必要な知識や技術など先進的な内容を取り入れ初版から7年を経て刷新した。執筆陣には第一線で活躍中の理学療法士やアスレティックトレーナが名を連ねる。
基礎知識から、救急対応、部位別スポーツ外傷・障害のリハビリテーション、ストレッチング・マッサージ・リカバリーの実際、機能的スクリーニングとコレクティブエクササイズ、と展開。
新項目として「外傷の処置」「脳震盪の評価と管理」など盛り込んだ。「最終的に読者が普段接するスポーツ選手に内容が還元されることを期待する」と選手に関わる全ての人に託す一冊。
(さらに…)