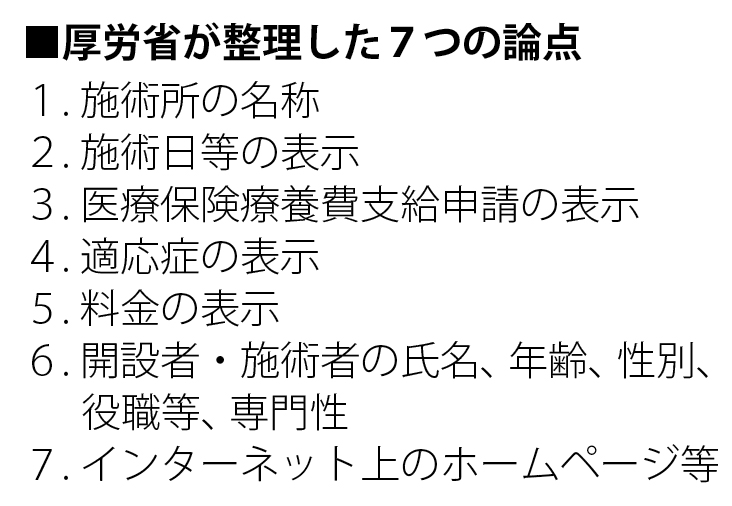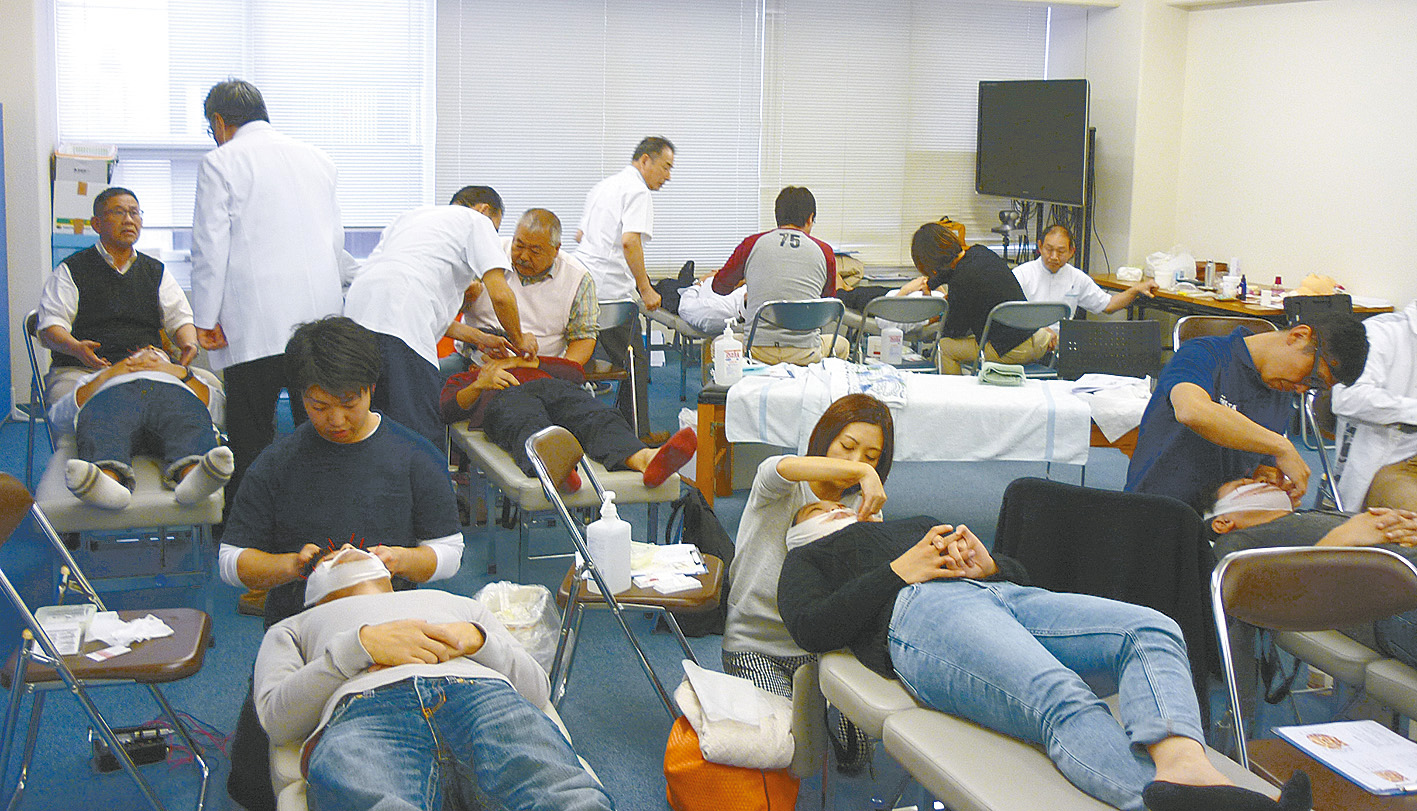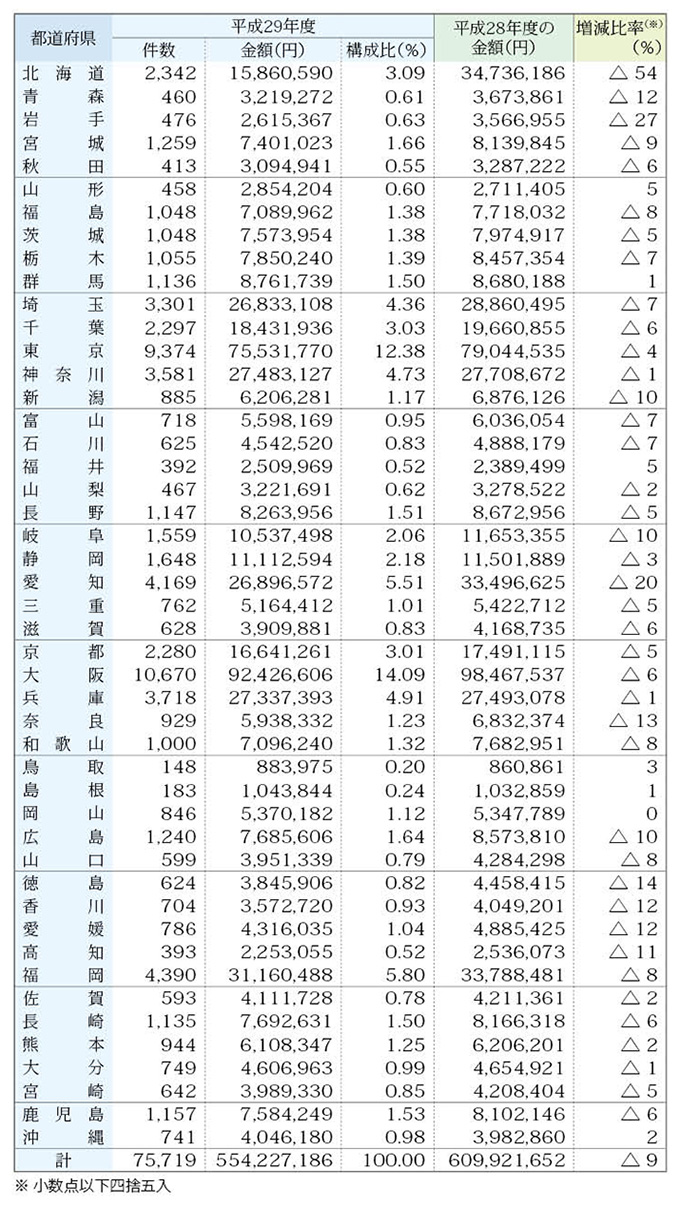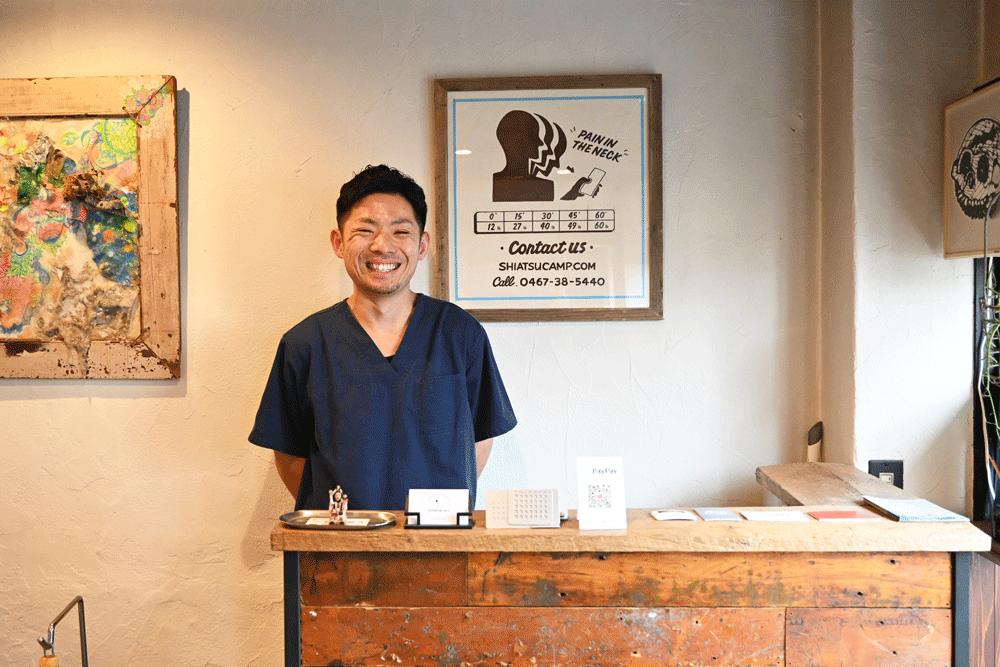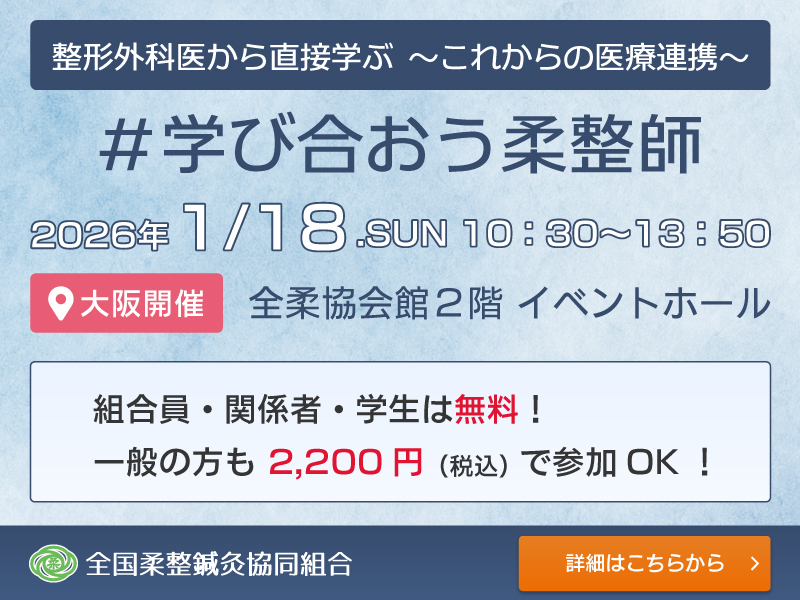あマ指師課程新設非認定処分取消裁判・大阪地裁 「藤井調査」、統計学的に全面否定
2018.11.25
1085号(2018年11月25日号)、あマ指師課程新設をめぐる裁判、紙面記事、
―「科学的信頼性が無い」と原告―
晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設申請を認めなかったとして、学校法人平成医療学園らが国を相手取って処分取消を求めている裁判で、11月9日、大阪地裁で口頭弁論があった。今回は、原告側から反論文書が出され、国が「あはき法19条は現在も正当性を有する」との主張の根拠に用いた、筑波技術大学教授・藤井亮輔氏らによる「あん摩業に関する実態調査」(以下、藤井調査)に対し、「科学的信頼性が無い」と否定するなど主張を展開した。
藤井調査は、平成28年秋に実施されたアンケート調査(回答数4,605人)。国は主張の中で、視覚障害者の「1カ月の患者数」や「平成27年分の年収」が、晴眼者と比べ低い水準にある(本紙1080号参照)といった調査結果から、あマ指師養成課程の自由化(新設・増設)をする合理的な理由が見いだせないとしていた。
今回提出された原告の文書は、これに対し、鑑定を依頼した統計学の専門家の意見を交えながら反論。主な指摘として、▽調査に利益相反のバイアスがかかっている、▽調査対象者の属性に偏りがある、等を挙げた。バイアスに関しては、研究代表者である藤井氏が基本的に「新設反対、19条支持」とのスタンスを取っており、その旨を表明している出版物も存在する上、調査自体が国の補助金による研究事業で、被告からの資金提供で実施されたものだと懸念を示した。調査の内容では、調査対象者のうち、あマ指師免許保有者以外が4割にも上回り、国勢調査(総務省が5年ごとに実施)の職業分類「あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師柔道整復師」と比較すると、男女比や年齢分布に大きな隔たりがあり、現状を反映していないと指摘した。また「患者数・年収」についても、藤井調査は「施術者」ではなく、「事業所」を対象に数値を調査しており、回答者の事業所規模も不明で、視覚障害者・晴眼者1人当たりの収入等の実態を正確に比較するのは不可能と強調。「調査の方法論並びに統計学について十分な訓練を受けていないと推測され、不十分な調査項目に関する標本比率の比較に終始しており、推論に無理があるため、納得的な結論が導出できていない」といった専門家の評価にも触れ、藤井調査を全面的に否定した。
台湾の例を19条廃止後の代替案に
また原告は、視覚障害者の職域の保護という目的を達成する手段として、「台湾」の事例に言及。2008年、あん摩業を視覚障害者の専業と規定する心身障害者保護法が違憲であると判断されたが、その後の各種行われた施策の結果、以前よりも視覚障害者のあん摩業が盛況になっていると説明した。その施策の中には、政府による営業費用の補助のほか、病院、駅、空港、公園、政府機関等の場所は視覚障害者しかあん摩業を行えないという規制なども設けられているとし、たとえ19条を廃止したとしても、この台湾の例が代替政策として具体的な案を提示していると主張した。
当日の口頭弁論では、原告から、視覚障害者の中にも19条に対する多様な意見があることから、証言に立ってもらうことを予定していると述べられた一方、被告は「必要があれば反論する」と話した。次回は、来年2月1日を予定。