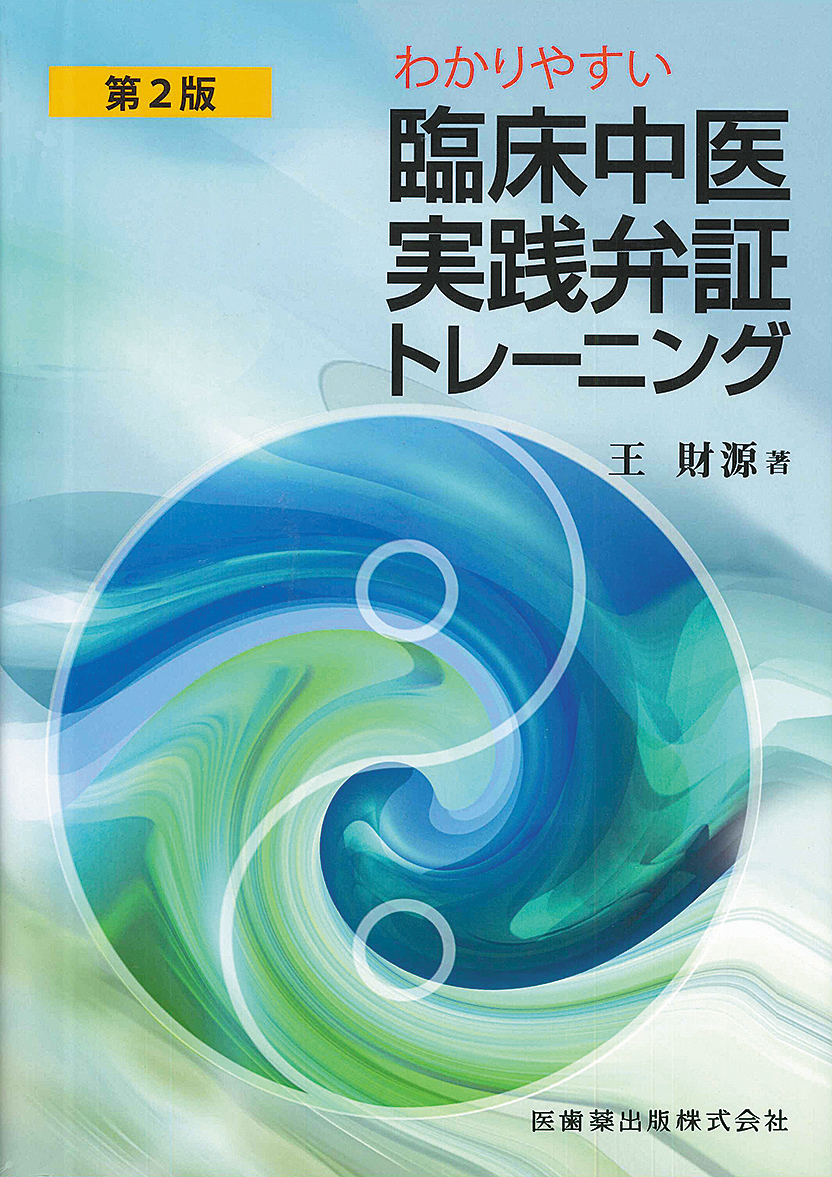連載『柔道整復と超音波画像観察装置』170 前距腓靭帯損傷の観察
2019.05.25
鈴木 孝行(筋・骨格画像研究会)
20代の男性。柔道の練習中に畳に足をとられて足関節が内返しになり受傷、その直後から足関節外側部に痛みが出現したため来院した。
患部を診察したところ、自発痛、運動痛はもちろんのこと、外果部の腫脹や前距腓靭帯付近の圧痛が確認でき、内返しのストレステストで疼痛が増強、患側での荷重負荷も困難で跛行がみられた。そのことを踏まえて「前距腓靭帯損傷」と判断したが、念のため腓骨下端部の骨折の有無を確認するため、超音波画像観察装置で患部を観察することにした。
まず健側画像中の組織の位置を確認する。①は「腓骨下端部」、②の高エコーラインは「距骨」、③の帯状のラインが「前距腓靭帯」である。全体的に組織間の境界が明確になっている。患側の画像は健側の画像と比較すると、まず確認できるのが前距腓靭帯部の黄色い実線の円で囲んでいる所の不整画像である。健側では靭帯組織の帯状のラインが鮮明に描出されていたが、患側では靭帯に損傷があるため出血や炎症物質が滲出、低エコー領域が増加して不整になっているのが認められた。また、点線の円で囲んでいる腓骨下端部の観察では、健側と変わらず鮮明な高エコーラインが描出されていたので、骨折は無いと判断できた。
今回のような足関節周辺の損傷では、靭帯組織の損傷だけではなく、腓骨下端部骨折を伴うこともあるので、見逃さぬように観察して判断を行わなければならない。超音波観察装置を使用して健側と患側とを比較観察することで多くの情報が得られ、患者にも実際に画像を確認してもらえば客観的な説明が可能になり、インフォームドコンセントをより明確に行うことができる。軟部組織損傷及び骨折に対する超音波画像観察の必要性は今後も高いと考えられる。