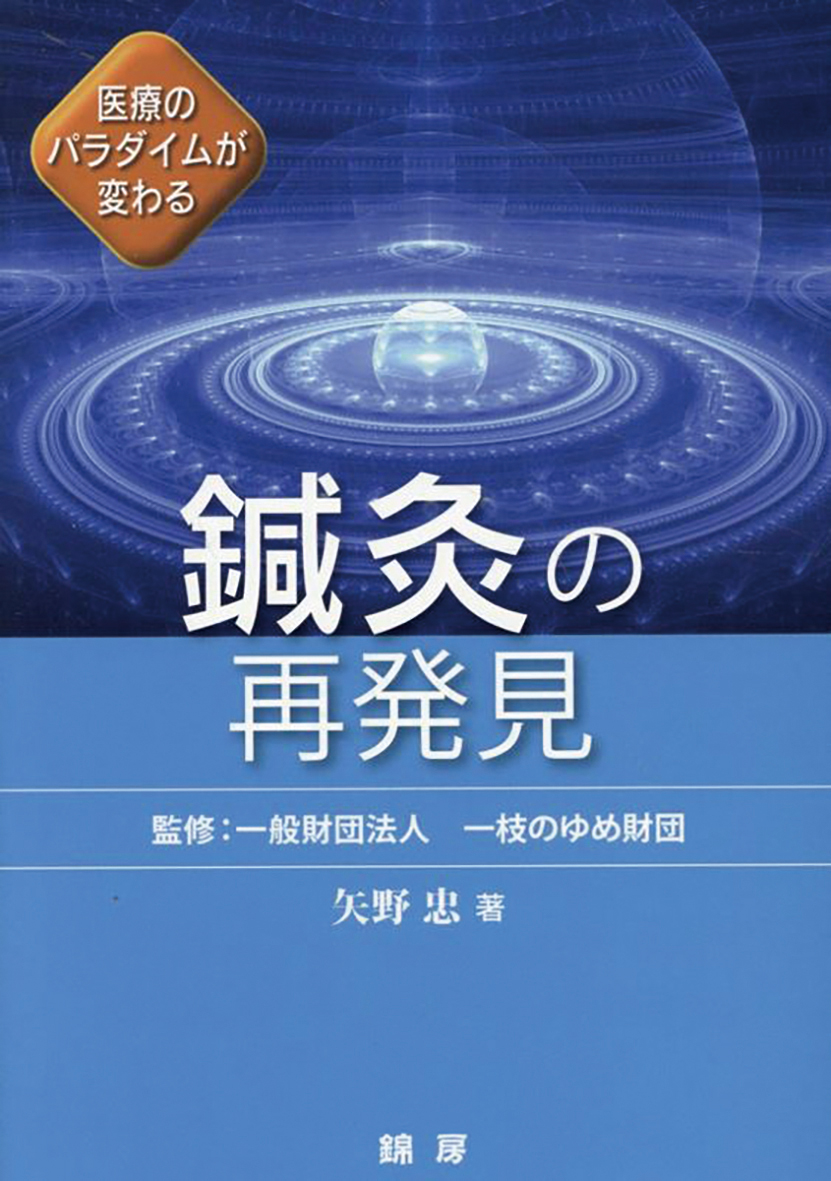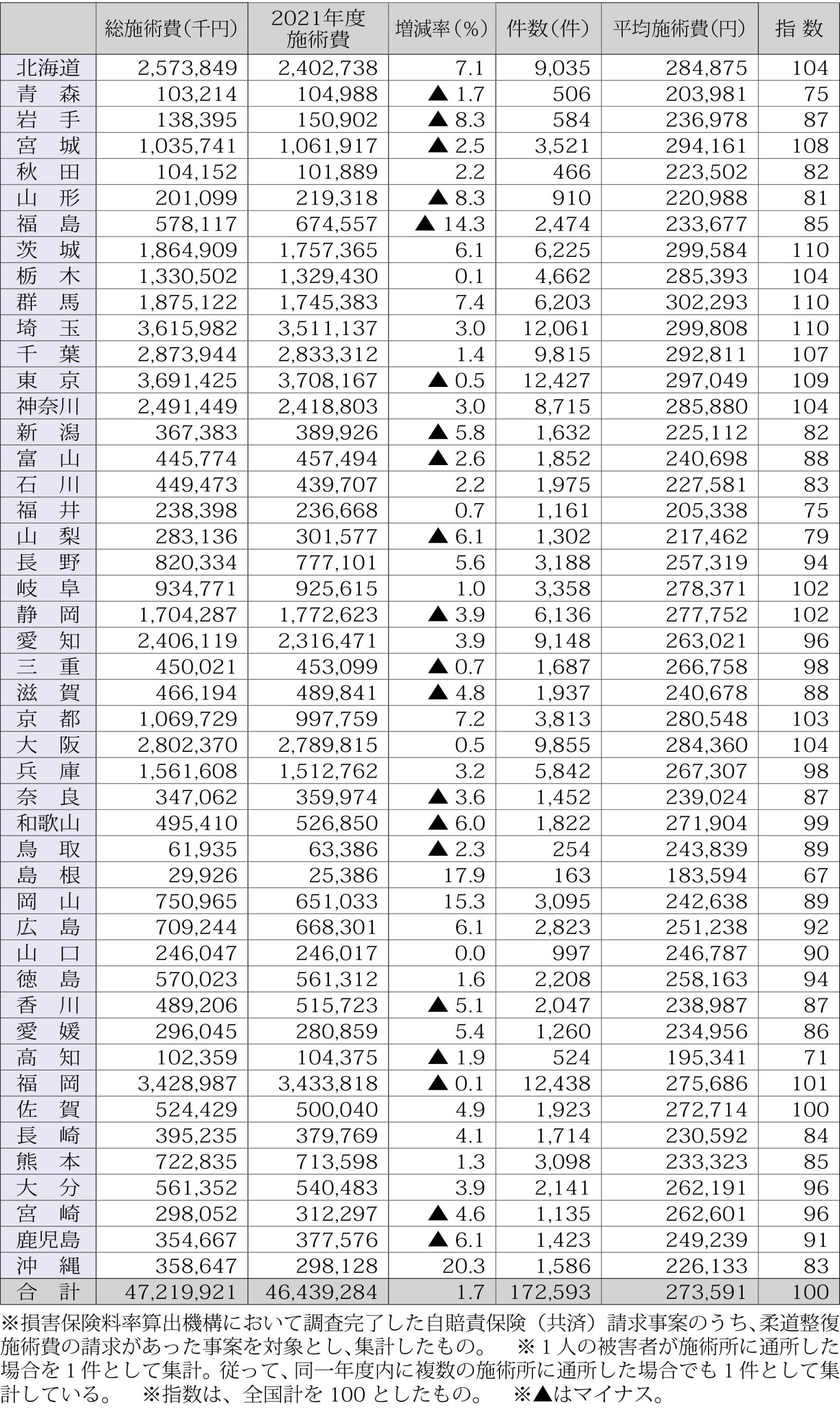ガイドライン案が最終合意 第11回 広告検討会
2024.07.25
整骨院は項目除外「これまで通りで」
7月12日、11回目となる「あはき師・柔整師等の広告に関する検討会」が開催され、違法広告の取り締まり強化などを目的とした広告ガイドライン(GL)の原案が合意された。新型コロナの影響で中断時期もあったが、6年以上に及ぶ議論がようやく終結した。最終盤になって再び持ち上がった「整骨院」の名称使用の可否については、GLに盛り込まないこととなり、結果的に「整骨院」を名乗っていくことは継続できることとなった。
柔整側、歴史・実態から再度訴え
今回の会議でも、5月下旬の前回と同様、柔整側メンバーである日本柔道整復師会(日整)の徳山健司氏が、「整骨院の名称を不可」とする意向で固まっていた同検討会の考えを今一度見直してほしいと強く訴えた。
柔整師と「整骨」の歴史的背景にも言及し、両者が切っても切り離せない関係にあると強調。古くは『養老律令』(757年)や『医心方』(984年)に骨損傷の治療に関する記述があり、時代が下った江戸期にも『整骨新書』(1810年)といった整骨専門書も多数出され、その著者・各務文献が「昔から日本に伝わり未だ精しく究められていない整骨術を研究して、もっと盛んにしたいと志して整骨医になった」と自序で述べていると紹介した。
また、日整と全国柔道整復師統合協議会(全整協)の所属会員に対して緊急で調査をしたところ、全28,617の施術所のうち、「整骨院を名乗っている」のが16,545カ所で、57.8%と半数を超えていたと報告。徳山氏は、柔整師の源流は「整骨術」にあると言っても過言ではなく、整骨院の使用実態から国民一般に広く浸透し、認識されているとして、従来通り整骨院の名称を使用できるよう求めた。
この要望を受け、厚労省が、①GLに広告可能な名称の例として記載する、②GLに広告不可な名称の例として記載する、③GLには記載しない、の3択を提示し、話し合いを促した。
(さらに…)