全柔協、大阪府警と安全・安心まちづくり協定結ぶ
2021.10.12
10月12日、全国柔整鍼灸協同組合(全柔協)と大阪府警察が「安全・安心なまちづくりに関する協定」を締結した。柔整団体が警察と協定を結ぶのは全国で初めてという。
今後、両者は同府内における特殊詐欺などの犯罪被害の防止に向け、協力・連携して取り組んでいく。
詳細は、10月25日発行の弊紙次号で伝える。
全柔協、大阪府警と安全・安心まちづくり協定結ぶ

全柔協、大阪府警と安全・安心まちづくり協定結ぶ
2021.10.12
10月12日、全国柔整鍼灸協同組合(全柔協)と大阪府警察が「安全・安心なまちづくりに関する協定」を締結した。柔整団体が警察と協定を結ぶのは全国で初めてという。
今後、両者は同府内における特殊詐欺などの犯罪被害の防止に向け、協力・連携して取り組んでいく。
詳細は、10月25日発行の弊紙次号で伝える。
あはきの2020年度受療率 鍼灸4.9%で低迷続く
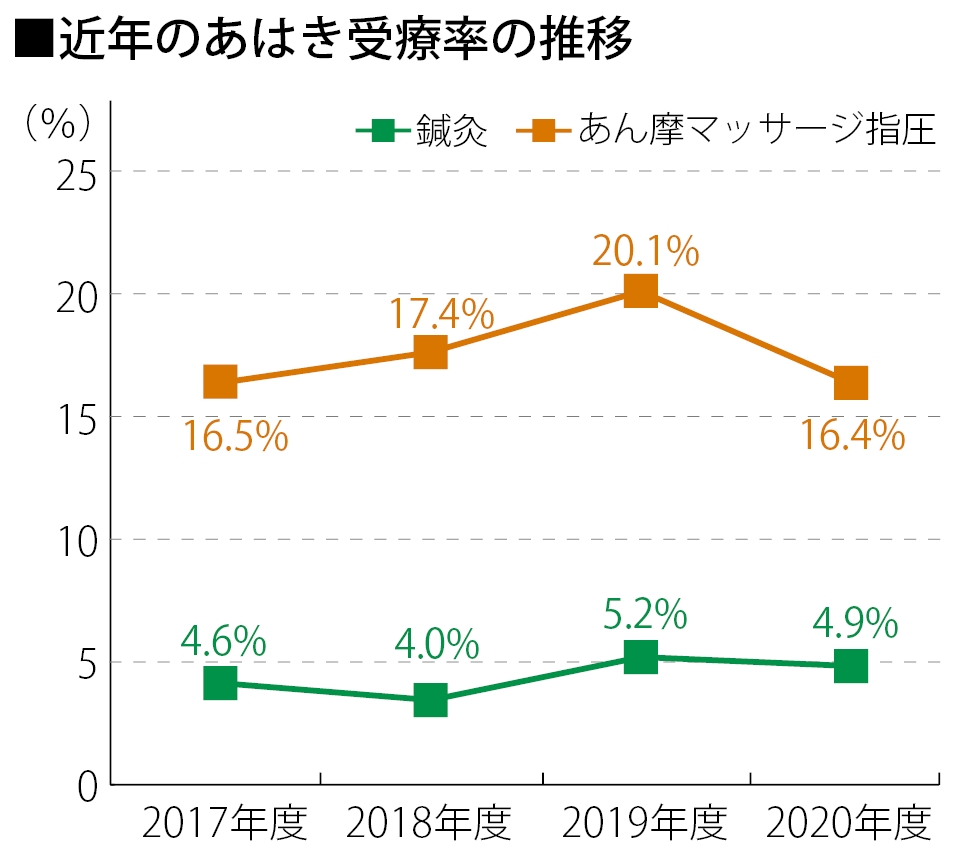
あはきの2020年度受療率 鍼灸4.9%で低迷続く
2021.10.10
あマ指は16.4%、コロナで減少転じる
2020年度における年間受療率が「鍼灸で4.9%、あん摩マッサージ指圧で16.4%」であることが分かった。毎年、明治国際医療大学学長・矢野忠氏を班長とする調査研究班があはき療法に関する受療率等を調査し、このたび報告書が公表された。鍼灸は2014年度以降の4~5%という落ち込み傾向が依然として続いている状況だ。
本調査は、公益財団法人東洋療法試験財団の2020年度鍼灸等調査研究として実施。2020年11月6日から15日までの間、20歳以上の者を対象に全国で調査を行い、回答者数は1,201人だった。男女比は「46.4%:53.6%」で、年齢は「70歳以上」が27.0%と最も多く、「40代」18.6%、「60代」16.9%などと続く。職業は「労務職」「無職の主婦」「事務職」の割合が多く、それぞれ2割強となっていた。
鍼灸の年間受療率は、「現在受けている」1.6%(19人)と、「1年以内に受けたことがある」3.3%(40人)の両者の回答を合わせて「4.9%」であった。前年度より0.3ポイント下がる微減。ここ最近の受療率4~5%の横ばい傾向は変わらず、過去7%前後で推移していた2010年代初頭以前と比べると低迷を抜け出せていない。受療しなかった理由としては、 (さらに…)
『医療は国民のために』328 亜急性負傷が廃止された今、自費メニューの「導入」が必要!

『医療は国民のために』328 亜急性負傷が廃止された今、自費メニューの「導入」が必要!
2021.10.10
平成30年6月以降、柔整療養費の支給対象から「亜急性」が削除され、柔整師にとって厳しい保険請求の実態となっているのは、改めて言うまでもないだろう。
保険者は負傷原因の確認に当たって、課長通知上の「外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すもの」をことさら振りかざし、こちらの主張する「反復性・蓄積性・オーバーユース(酷使、使い過ぎ)に起因する請求」の正当性もほとんど聞き入れなくなってきている。具体的には、「捻れがない」「関節可動域を超えたとは言えない」「外力の発生機序がない」「身体組織が損傷を受けたとは言えない」といったことで不支給処分または不備返戻とされてしまう。私としては「人は寝ている間でも頸椎捻挫する」も正当な主張だと思っているが、保険者からすれば、「人は単に寝ている間に捻挫などしない」と考えているようで、これも前述の「外傷性の定義」を論拠にしているのである。 (さらに…)
北里大学東洋医学総合研究所主催 養生シンポ、コロナ禍見据え

北里大学東洋医学総合研究所主催 養生シンポ、コロナ禍見据え
2021.10.10
「自分養生」と「他者養生」語る
北里大学東洋医学総合研究所主催シンポジウム「未病と養生」が8月22日、オンラインで開催された。
宮川浩也氏(日本内経医学会前会長)の講演では、養生を自身の健康を増進する「自分養生」と、大切な人や生き物の世話をし、慈しむ「他者養生」に分類。家族のために自分も元気でいないと……と考えるように、自分養生は他者養生のための資源となるもので、また、他者養生の実践が自然と自分養生につながるとした。一般にイメージされる、食事や運動、サプリメントなどでアンチエイジングを目指す行いは自分養生であり、ルーツは馬王堆医書や張家山医書に見える、神仙家が不老長寿を目指す修業術にあると説明。60代の宮川氏から見た親世代の平均寿命が、こうした「神仙養生」の習慣があまり定着していないにもかかわらず大きく伸びたのは、生活環境の改善や医療の充実だけでなく、子供を育てるため無心に働いてきたことが、自然と自分養生になったと推察した。
また、自分養生は健康増進、病気予防、病気治療に大別。健康増進には、努力家に向く神仙養生のほか、 (さらに…)
連載『不妊鍼灸は一日にして成らず』42 卵質と着床能の向上

連載『不妊鍼灸は一日にして成らず』42 卵質と着床能の向上
2021.10.10
1年間のラジオ番組「ハリある暮らし」が終わりました。放送原稿はA4で三百枚を超え、月に25枚以上書いたことになります。当初コロナの影響で少なくなった患者さんも徐々に戻り始め、今春以降は週に百数十人が来院される中、ひたすら原稿を書きまくりました。ラジオの経済効果は計り知れず、知人の鍼灸院だけでも何人も新患さんが足を運ばれたといい、当院も様々な愁訴での来院が多数。初診でお話すると「あ、ラジオの声!」とおっしゃる患者さんもいました。鍼灸師が公共のメディアで冠番組を持ったのは史上初でしょうから、今後の動向も注視したいと思います。音源も全て放送局から頂いたので、それを使って動画を作ろうかと頭に浮かび、アドビのアフターイフェクトやプレミアムプロを勉強したいとも思っています。
さて、8月のレーザーリプロダクション学会、10月の不妊カウンセリング学会の配信に続いて、11月28日には岐阜県鍼灸師会主催の講演があります。 (さらに…)
レポート 日本プライマリ・ケア連合学会主催セミナーで2度目となる鍼灸セッション開催

レポート 日本プライマリ・ケア連合学会主催セミナーで2度目となる鍼灸セッション開催
2021.10.10
医療法人弘池会 口之津病院/家庭医療専門医指導医・寺澤佳洋(医師、鍼灸師)
『シン・鍼灸治療の活用』と題し、少しマニアな世界を!
9月20日、一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会主催の「秋季生涯教育セミナー」の一つとして、鍼灸セッションがWeb形式で開催されました。昨年はコロナ禍で残念ながら中止となりましたが、リアル(対面)で実施した一昨年(2019年)以来、2年ぶりとなる開催でした。
筆者は、鍼灸師になった後に医師になった背景もあり、元より鍼灸の有用性を十分体感しています。また、海外ではガイドライン等でも鍼灸治療が上位に記載されているにもかかわらず、国内での活用は十分といえない状況にあり、日常診療のかたわらで『医はき師 てらぽん』を名乗り、医師、鍼灸師など医療人が正しく活躍でき、患者も含めた困っている人たちがHappyになれるようなことをデザイン・企画しています。そんな中、今回のワークショップ(WS)を医師中心で構成する同連合学会に申し込みました。
さて、今回開いたWSのテーマは、『シン・鍼灸治療の活用―少しマニアな世界も』。参加の医師やコメディカルに鍼灸の幅広い世界を見て知ってもらい、明日の臨床に生かせるTipsも随所に盛り込んだ企画としました。“マニア”という癖の強い言葉は筆者が勝手に付けたものですが、東洋医学や鍼灸の専門用語、またその独特の思考に少しでも接近してもらえるよう願いを込めました。 (さらに…)
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』171 若者のゴルフブームはコロナ禍の影響?

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』171 若者のゴルフブームはコロナ禍の影響?
2021.10.10
10月に入りました。永田町周辺の歩道は銀杏がたくさん落ちて、踏みつけられてネトネトしています。以前は落果する前に手作業で落として回収されていましたが、コロナ禍でそれどころではなかったのでしょうか。第5波もようやく落ち着いて、仕事終わりの街の景色も久しぶりに活気を取り戻しているようです。新政権も発足し、色々と始動する10月になりそうです。
スポーツの秋と言いますが、コロナの影響もあるのか最近はゴルフが再びブームだそうです。特に若者の間で人気を集めているようで、その背景には、スポーツの中では比較的「三密」を避けやすいことに加えて、リモートワークが一般的となり、時間的融通がつきやすくなったことが影響しているようです。 (さらに…)
連載『中国医学情報』199 妊娠期の鍼灸の安全性―英国の産婦人科専門誌掲載論文の内容と批評(上海鍼灸雑誌)ほか

連載『中国医学情報』199 妊娠期の鍼灸の安全性―英国の産婦人科専門誌掲載論文の内容と批評(上海鍼灸雑誌)ほか
2021.10.10
今回の内容
・妊娠期の鍼灸の安全性―英国の産婦人科専門誌掲載論文の内容と批評(上海鍼灸雑誌、21年7期)
・出産後の骨盤底筋機能に対する温灸の効果―骨盤底筋訓練とランダム化比較(中国鍼灸、21年8期)
☆妊娠期の鍼灸の安全性―英国の産婦人科専門誌掲載論文の内容と批評
北京の中国中医科学院鍼灸研究所・郝(かく)鳴昭らは、Moon(文)・Kim(金)・Hwang(黄)氏らが、韓国医療保険データベースを利用して妊娠期の鍼灸の安全性を調査し、英国の産婦人科雑誌に発表した論文(BJOG, 2020,127:79-86)とその批評とを紹介(上海鍼灸雑誌、21年7期)。
<論文の内容>
対象・方法=2003~2012年の20,799例(全員初めての妊娠)をレトロスペクティブ・コホート研究(後ろ向き要因対照研究)。このうち鍼灸治療を受けたのは1,030例(4.95%。以下、鍼灸群)、受けなかったのは19,749例※原文ママ(以下、対照群)。両群の年齢・収入に差なし。
結果= (さらに…)
読書日和から新刊 「あまねく届け! 光」
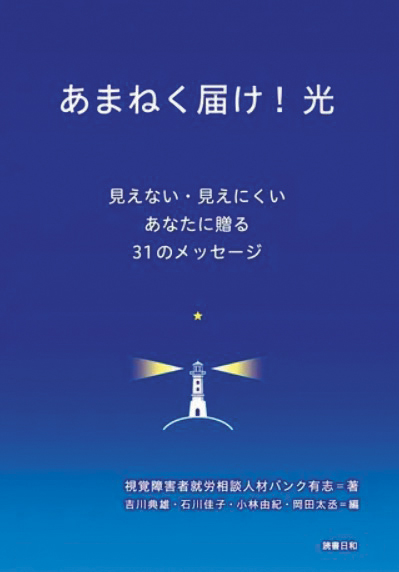
読書日和から新刊 「あまねく届け! 光」
2021.10.10
あまねく届け! 光
見えない・見えにくいあなたに贈る31のメッセージ
視覚障害者就労相談人材バンク有志による新刊「あまねく届け! 光」が、読書日和から上梓された。A5判400頁、2,750円(税込)。
事務職、生活支援員、数学教員、研究職、司法書士、銀行員、精神科医、そして鍼灸マッサージ師――。ある人は生まれつき、ある人は突然視界に異常が……それぞれの事情で視覚障害を持ちながら様々な道を歩む人々の、31篇の手記を収録。「なぜ『視覚障害=三療』なんだ、好きでもやりたいわけでもないのに」「理療の世界は今までとはまったく別世界です。目に障害があるからこそ、新しい世界へ飛び込もうと考えることができました。そしてこれから、新たな人生に踏み出すことができるのです」――。31の物語、その全てに込められた、苦悩と希望のメッセージを追う。
視覚障害やその他の理由で本が読めない方のための、郵送でのテキストデータ引換券付き。
(さらに…)
柔整支給件数、109万件減少 あはきはいずれも約10%増 協会けんぽ 令和2年度報告

柔整支給件数、109万件減少 あはきはいずれも約10%増 協会けんぽ 令和2年度報告
2021.10.10
このほど、全国健康保険協会(協会けんぽ)が公表した「令和2年度事業報告書」の中で、療養費の支給額等の状況が示された。柔整療養費は約1,416万件で、前年度から109万3千件減、支給額は30億円減少と、減少幅が大きくなった。1件当たりの支給額については4,413円で、117円増加している。あはき療養費の支給決定件数は、マッサージが約7万8千件、はり・きゅうが約55万7千件で、いずれも前年度より10%あまり増加していた。
同報告書では適正化の推進にも触れられており、柔整では文書による施術内容の確認や啓発活動によって「施術療養費の申請に占める、施術箇所3部位以上、かつ月15日以上の施術の申請の割合」を前年度以下に抑えるとのKPI(重要業績評価指標)を達成したものとした。また、加入者が増加する中でも柔整療養費の支給件数・支給決定金額が共に減少していることを「適正化が図られている」と評価している。
以下に、過去5年の柔整療養費の推移(件数、支給額、1件当たりの支給額)、あはき療養費の受領委任制度導入前後(平成29年度以降)の支給決定件数のグラフを掲載する。 (さらに…)
レポート 宮城柔整社団の「第6回はればれ健康フェスタ」開催

レポート 宮城柔整社団の「第6回はればれ健康フェスタ」開催
2021.10.10
宮城県柔道整復師会 介護企画推進室 中川裕章
9月12日、当会・公益社団法人宮城県柔道整復師会主催で『第6回はればれ健康フェスタ』をオンライン開催しました。仙台市薬剤師会や宮城県看護協会、宮城県栄養士会等の多くの共催・後援をいただき、フレイル予防の健康講和や実演セミナーなどを行いました。
まず基調講演では、東北大学大学院の辻一郎教授を講師に、「公衆衛生学から見たフレイル予防」のお話をいただきました。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 申請書内の申請欄氏名の機械印字に押印は必要なの?

Q&A『上田がお答えいたします』 申請書内の申請欄氏名の機械印字に押印は必要なの?
2021.10.10
Q.
市役所の国保給付係からあはき療養費支給申請書が不備返戻されました。返戻理由は押印がないことで、「申請欄の申請者氏名(被保険者・世帯主)が機械印字の場合は患者から押印をもらってください」となっています。代理人欄は患者さんが署名して押印はしていません。申請欄の機械印字の氏名に患者さんの押印は必要なのでしょうか。
A.
いまだにこのような返戻をする保険者がいるのですね。結論から述べますと、ご質問のケースで患者さんの押印は「不要」です。
令和3年3月24日付保発0324第2号で示された厚労省保険局長通知は押印の省略を認める運用通知であることから、レセコンからの機械印字の記入に係る押印は「不要」であることを徹底する趣旨で発出されています。
まず、申請欄は施術者による機械印字でOKで、その場合、押印も不要となります。なぜなら申請欄の氏名は「署名欄」ではなく、 (さらに…)
連載『汗とウンコとオシッコと…』206 振拉摧拔(しんらつさいばつ)

連載『汗とウンコとオシッコと…』206 振拉摧拔(しんらつさいばつ)
2021.10.10
秋分の日に、愛らしい甘い香りの金木犀が咲いた。血が噴き出るような彼岸花の開花と同時にお目にかかるとは、季節の循行が実に早いものだ。
今年の歳周りの在泉は太陽寒水だけあって、冬の到来が早まる気配がある。川の水に光が反射したり、夏のように水蒸気が蒸し上げられることもないので、川底が遠目でもはっきり分かるような収斂、粛殺の気の到来を候わせる。このような時期は肝気が肺の抑制を受け、少陽胆経に病が現れる。つまり呼吸が深くなり、酸素過剰で冷やされた肝臓は代謝が低下し、熱量が胆経から奪われるのだ。気短、右肩痛、仙腸関節痛、腓骨の弛緩で膝の内側が痛んだりすることも多い。あるいは、気温の低下で細動脈側が収縮して背面や四肢、とりわけ肘周囲に痺の病を形成する。今回はそれにまつわるお話だ。
「先生、私大丈夫でしょうか? 先日、エクステに行った時から眩暈がして丸一日寝込んだんですよ。自分でネットでも調べてみたら、熱や耳鳴もないし、突発性難聴でもなく……まさか脳? って思うと怖くなって……」
訴えるのは40代半ばのキリっとしたセミロングの馬場さんという女性だ。 (さらに…)
連載『鍼灸師・柔整師のためのIT活用講座』8 XaaS(Anything as a Service)モデル
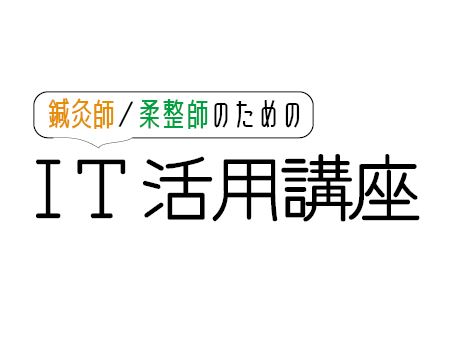
連載『鍼灸師・柔整師のためのIT活用講座』8 XaaS(Anything as a Service)モデル
2021.10.10
「XaaS(Anything as a Service、ザース)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。情報システムの構築や運用に必要な様々な資源(ソフトウェアやハードウェア)を、インターネットなどを通じて提供・利用するサービスの総称です。「X」の部分には様々な用語が当てはめられ、たとえば「Mobility as a Service」なら「MaaS(マース)」と称されます。バスや電車、タクシーからライドシェア、シェアサイクルといった交通機関を、ITを用いてシームレスに結びつけて、人々が効率よく、かつ便利に使えるようにするシステムのことです。このように、ザースとはオンサイトのローカルソフトウェアではなく、クラウドコンピューティングを駆使して様々なものをつなげ、サービスを提供したり、顧客を獲得するものです。また、得られたデータを解析して、他領域のデータと結合できれば、今まで別々に行われていたサービスを一つにまとめ、新しいビジネスを創造でき、以前取り上げたデジタルトランスフォーメーション(DX)、人々の生活をより良い方向へと変革させることにもつながっていくのです。
さて、鍼灸業界でも、インターネット経由の電子カルテが販売されるようになってきていますね。 (さらに…)
今日の一冊 福島の甲状腺検査と過剰診断―子どもたちのために何ができるか

今日の一冊 福島の甲状腺検査と過剰診断―子どもたちのために何ができるか
2021.10.10
福島の甲状腺検査と過剰診断 子どもたちのために何ができるか
髙野徹/児玉一八ら 著
あけび書房 2,200円
福島第一原発事故から10年。当時18歳以下だった福島県の子どもたちには現在も定期的な甲状腺がんのスクリーニング検査が行われており、これまで300人以上ががんと診断を受けた。だが、この割合は正常なもので、事故の影響はないとの見方が一般的だ。増悪リスクが低い若年型甲状腺がんの検査には近年、過剰診断……治療が必要ない疾患を発見し、逆に不利益を生むリスクが指摘されてきた。著者らはエビデンスを基に、検査中止を強く訴える。今なお続く不要な治療。子どもたちを守るため本当に必要なことは――。
編集後記

編集後記
2021.10.10
▽はじめまして。このたび「鍼灸柔整新聞」でお仕事をさせていただくことになりました。これまでライターとして日本文化や地方創生などのweb記事の取材・執筆を中心に活動してきました。紙媒体も経験はありますが、新聞は今回が初めてです。経験を活かしつつゼロからのスタートという気持ちで頑張ります。編集部の中では新人ですが、年齢はすでに四十台半ば。個人的にも長年のデスクワークからくる身体の軋みは悩みどころでした。業界のことについてはこれから勉強させてもらうとして、そのぶん患者さんの目線で取材ができればと考えています。生まれも育ちも大阪の人間なので、会話の端々にコテコテのナニワ色がにじむこともあるかと思いますが、何とぞよろしくお願い致します。(貝)
柔整・管理者研修、年明け開催分の申込み10月15日から

柔整・管理者研修、年明け開催分の申込み10月15日から
2021.10.07
柔整療養費の受領委任を取り扱う上で、義務化されている「施術管理者研修」の来年1月~3月の開催分の受講申込みが10月15日(金)14時から受付開始。
全3回ともオンライン研修(300名定員)で実施される。ただ、オンライン受講できない参加者限定で、2月19日(土)、20日(日)に大阪市内、3月19日(土)、20日(日)に東京都内でそれぞれ15名ほどの対面受講が行われる。
柔道整復研修試験財団「施術管理者研修ページ」
全整協 22の個人契約団体集め、不適切な患者照会で意見交換

全整協 22の個人契約団体集め、不適切な患者照会で意見交換
2021.09.24
厚労省「機械的に行う健保組合は改善を」
個人契約の柔整師団体で構成する「全国柔道整復師統合協議会」(全整協)が9月8日、柔整療養費に関する意見交換会を行った。22の団体が都内の会場及びオンラインを通じて参加。当日は、厚労省保険局保険課の健康保険組合指導調整官を招き、依然として不適切な内容が目に余る健保組合の患者照会について意見を交わした。
全整協は、日本個人契約柔整師連盟(岸野雅方会長、日個連)と全国柔道整復師連合会(田中威勢夫代表理事、全整連)が結集し、昨年4月に発足。岸野氏と田中氏が共同代表を務める。
今回の開催に当たっては、柔整団体から「不適切と思われる事例」が聴取され、▽月に1回の通院で照会を実施、▽保険医療機関に受診しなかった理由を求める設問がある、▽施術所に相談してはならないとの記載がある、など10を超える事例が集まった。事前にこれらの情報提供を受けていた厚労省の健康保険組合指導調整官は「早急に対応しないといけないと思っている。中でも、請求の中身も見ず、単に機械的に照会をかけている場合は改善が必要だ」と見解を示した。また、事例それぞれの健保組合に対し、厚労省から問い合わせをしたようで、 (さらに…)
『医療は国民のために』327 あまりにもハードルが高い支払基金の療養費参入

『医療は国民のために』327 あまりにもハードルが高い支払基金の療養費参入
2021.09.24
8月6日の柔整療養費検討専門委員会では、復委任を認めないとする主張が影を潜め、「療養費を施術管理者に確実に支払うための仕組み」と言い方を変えた議題が出された。国が「協定と契約に差を設けるつもりはない」との方針では、個人契約団体の縮小を狙っていた日本柔道整復師会も自分たちに不利益が及ぶ恐れがあると感じたのか、論難の矛を収めて行政側の意見を受け入れたものと私は考えている。
さて、この議論では「法的な関与の下に、請求・審査・支払が行われる仕組み」が今後検討されるとあるが、これは「社会保険診療報酬支払基金」と「国民健康保険団体連合会」の関与・参画を指しているに違いないだろう。国保保険者や後期高齢者医療広域連合では、業務委託の形で審査及び支払い事務を国保連が実施している。一方、被用者保険の協会けんぽと健保組合のため、同等・同様の受け皿として都道府県社会保険診療報酬支払基金が考えられるが、どうやら支払基金自体が積極的に受け入れる考えはなさそうだ。 (さらに…)
病鍼連携連絡協議会 戦略的卒後研修 うつ病治療と鍼灸テーマに
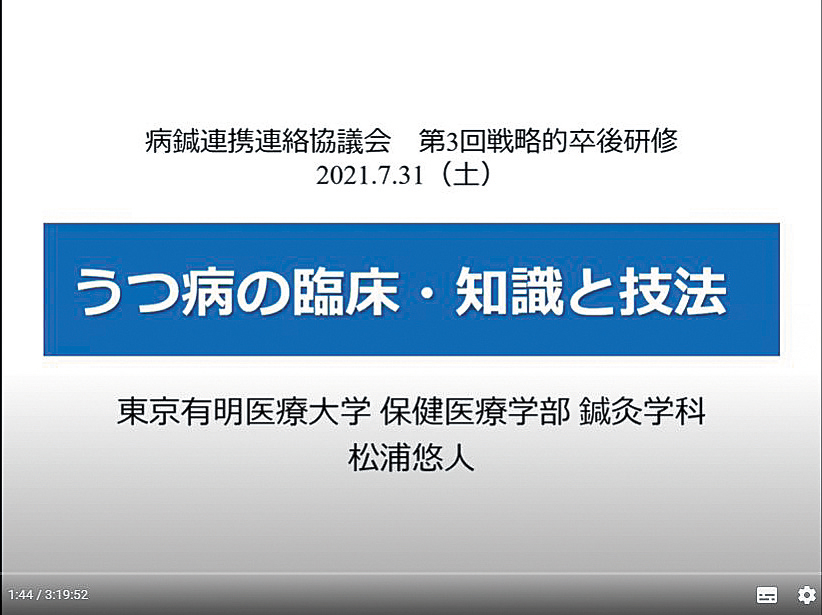
病鍼連携連絡協議会 戦略的卒後研修 うつ病治療と鍼灸テーマに
2021.09.24
鍼灸師向け教育プログラム、近日予定
病鍼連携連絡協議会の戦略的卒後研修第3回「うつ病の臨床・知識と技法」が7月31日、オンラインで開催された。講師は東京有明医療大学保健医療学部鍼灸学科助教の松浦悠人氏。
松浦氏は、うつ病の病態と標準治療について解説の上で、鍼灸の治療は、あくまで通常の医療面接、病態把握の上で適否を判断すると説明。注意の必要がある症例は鍼灸施術の適応とせず医療機関に紹介するとして、その例に▽自殺念慮・自傷行為のあるもの、▽他の医学的疾患による抑うつ障害、▽不安性の苦痛を伴うもの、▽混合性の特徴を伴うもの、▽精神病性の特徴を伴うものを挙げた。
また、鍼灸がうつ病に伴う筋骨格系の局所的な病態だけでなく、中枢の機能異常による病態の改善にも (さらに…)