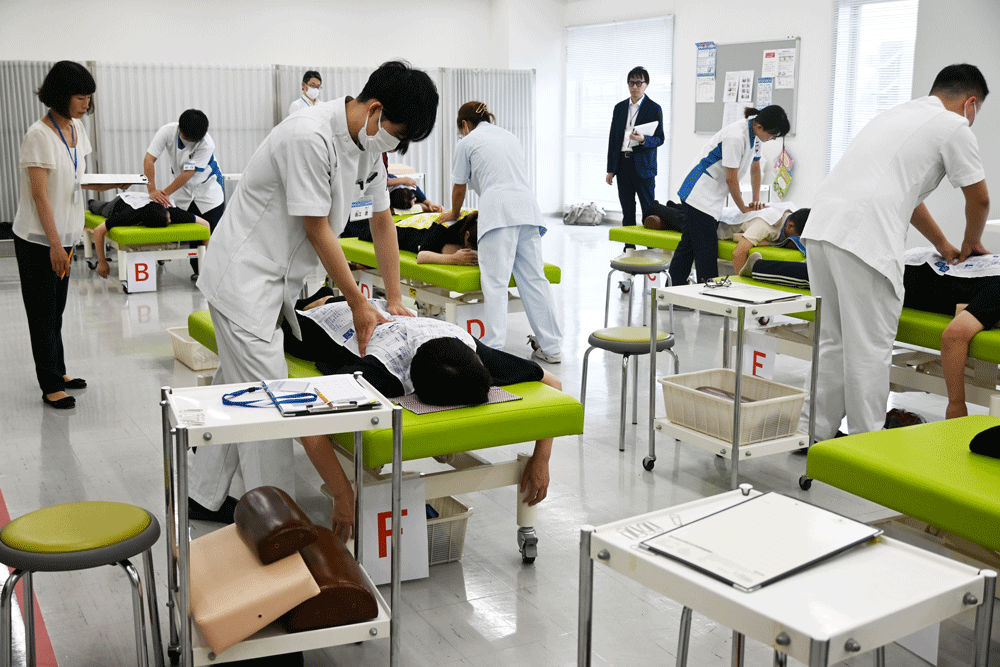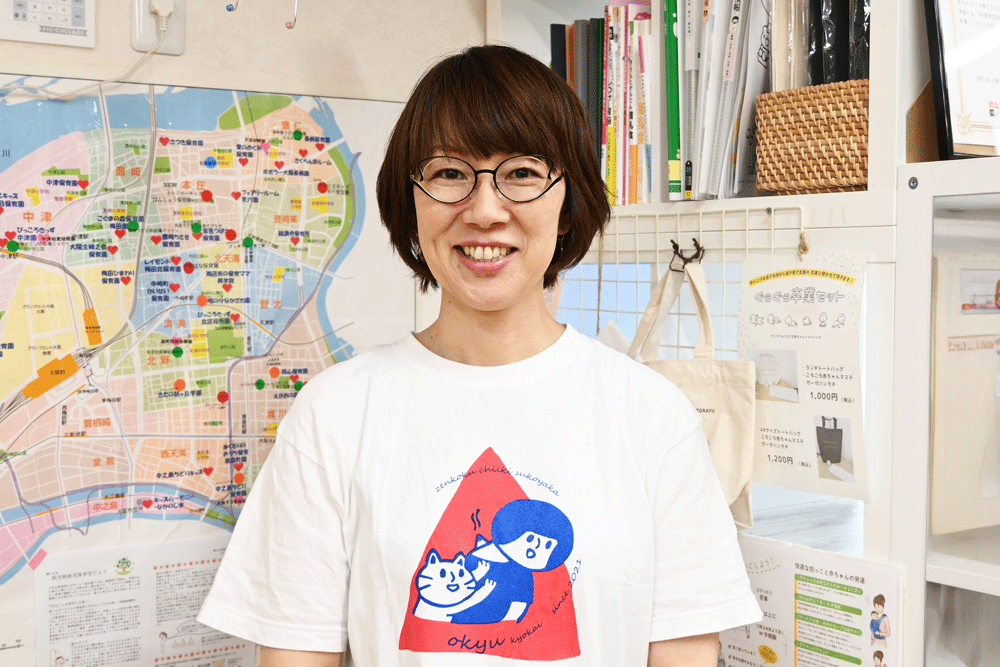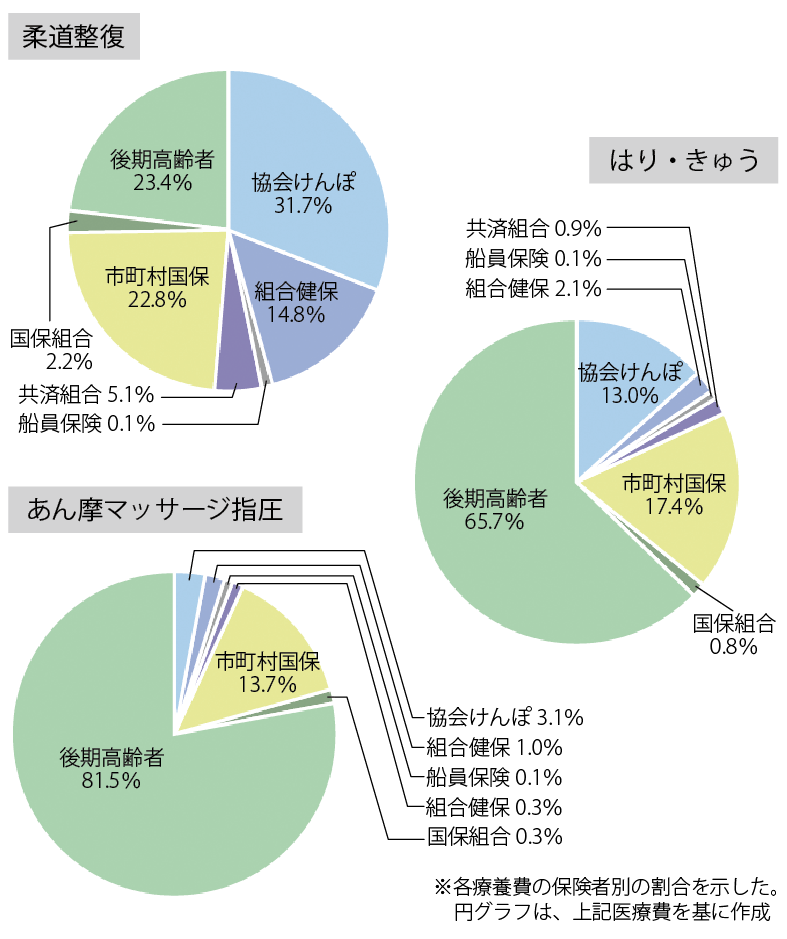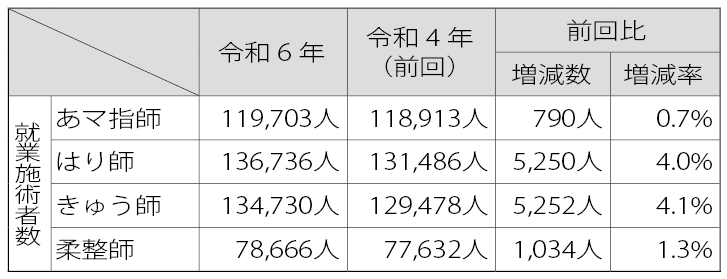「鍼灸師のキャリアに関する調査」への協力募る、履正社鍼灸学科
2025.09.18
現状把握し、若手・学生へのキャリア支援のあり方等を考えたい
履正社国際医療スポーツ専門学校鍼灸学科が、鍼灸師免許の取得者に向けた「キャリアに関する調査」を実施しており、アンケートへの回答の協力を求めている。
アンケート対象者は、現在就業中(もしくは休業中)で鍼灸関連業務に従事しているかの有無は問わない。※既に引退しており、今後働く予定のない方は対象外
近年、鍼灸師の働き方は臨床にとどまらず、教育、研究、地域活動など兼業を含め多様化しており、こうした現状を踏まえ、鍼灸師の「志向性」や「キャリア選択」の背景を明らかにしようと調査研究に取り組んでいるという。
また、同調査から鍼灸師のライフステージや価値観の違い、労働環境などの背景・働き方を把握することで、若手や学生に向けたキャリア支援のあり方を検討し、さらには現在の働き方を見直したいと考える鍼灸師にとっても有意義な知見を提供していきたいとしている。
回答方法は無記名式のWebアンケートで、所要時間は5~10分程度。研究代表者は同校鍼灸学科の桑原理恵氏。
回答はこちらから↓
「鍼灸師のキャリア形成に関する調査」アンケートフォーム