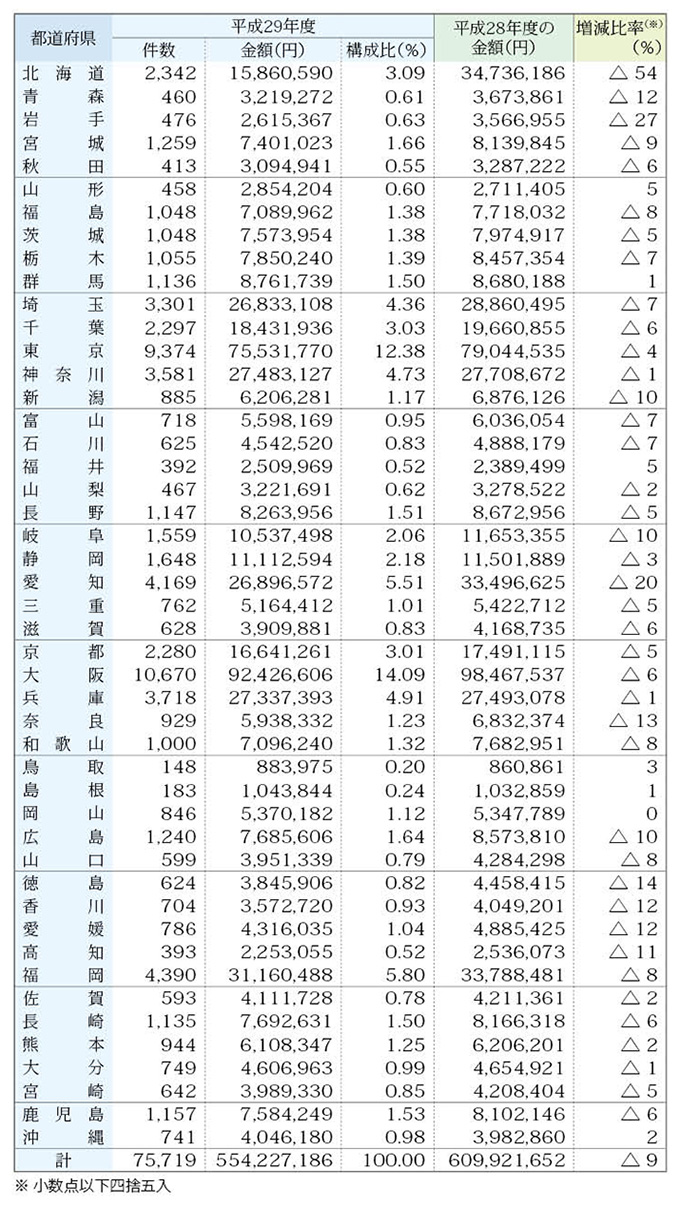連載『織田聡の日本型統合医療“考”』104 医療の破壊的イノベーション再び
2018.11.25
中国・深センのホテルでこの原稿を書いています。先日、中国で「1分間診療所」という無人クリニックが発表されました。『平安健康医療科技』による発表で、人工知能が、患者の声や画像を通じて初期診断し、実在の医師が確認して正式な診断を下すという仕組みで、診断から処方までを数分で完了するというものです。しかも、併設する自動販売機で、薬をすぐに入手することもできます。私たち「MedQuery(メドクエリ)株式会社」が、先日発表した事業計画の一部に非常に似ているモデルです。
日本では「このような無人クリニックで質の高い診療ができるのか」、「皆保険制度の日本は中国とは違い、すぐには不可能だろう」といった声も聞こえますが、破壊的イノベーションとはこんなものです。最初はおもちゃみたいだったものが、既存の市場を凌駕する。医療にもそういう流れが来そうです。MedQueryでは日本の医療は次の診療報酬改定で行き詰まるのではないかという仮定の下に事業開発を進めています。医療は5年後にはずいぶん変わっているのではないでしょうか。鍼灸マッサージ・柔整業界の変化はもっと早いかもしれません。
さて、近い将来、ウェルネスやセルフケアと言われる領域と急性軽症の疾患の診療との境界がなくなると見ています。私自身、鍼灸治療院と医療機関をつなげることで、それを引き起こそうとしてきました。そして同時に、ライセンスによる業界の〝くくり〟が消失すると思います。つまり、多職種連携です。宮崎大学の吉村学教授の言う「ごちゃまぜ師」というような新たなくくりでサービスは提供され、ライセンスが必要ない代替サービスが生まれてきます。一例として、肩こりという愁訴に対し、国家資格が必要のないリラクゼーション業が生まれました。さらに、医師が行っていたことを医師以外がやれるようになる。場合によっては機械が代替するかもしれません。このような世界が本当に来るのかと思うかもしれませんが、こういった流れは医療以外では既に先行して起きています。今まで守られていた業界は縮小し、新しい業界が生まれるということです。
これはもう必然で、鍼灸マッサージ師や柔整師も同様でしょう。「AIによって無くなる仕事」とあおる記事も見られますが、その前に職域の壁の崩壊が起きて「資格制度の事実上の崩壊」が生じると思います。医療は公益性が高く保守的で、こういった流れが起きにくい業界でしたが、逼迫した財政などの環境により変わらざるを得ないところにきています。それは多分、2020年の東京オリンピックまでに起きるでしょう。
【連載執筆者】
織田 聡(おだ・さとし)
日本統合医療支援センター代表理事、一般社団法人健康情報連携機構代表理事
医師・薬剤師・医学博士
富山医科薬科大学医学部・薬学部を卒業後、富山県立中央病院などで研修。アメリカ・アリゾナ大学統合医療フェローシッププログラムの修了者であり、中和鍼灸専門学校にも在籍(中退)していた。「日本型統合医療」を提唱し、西洋医学と種々の補完医療との連携構築を目指して活動中。