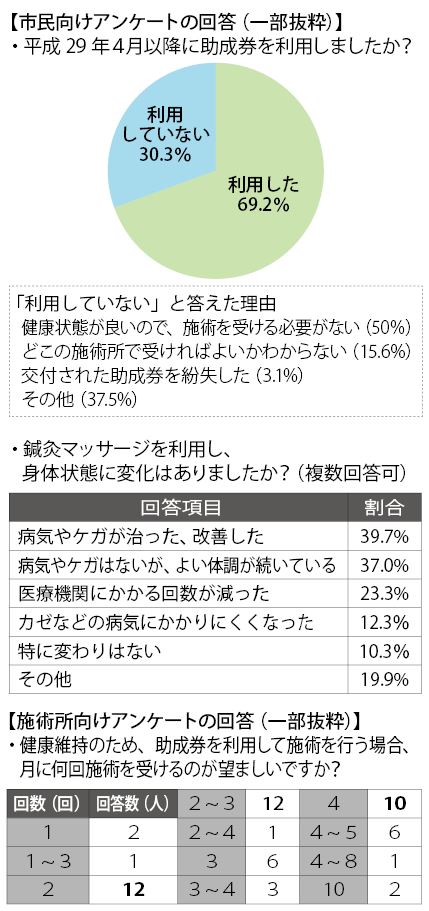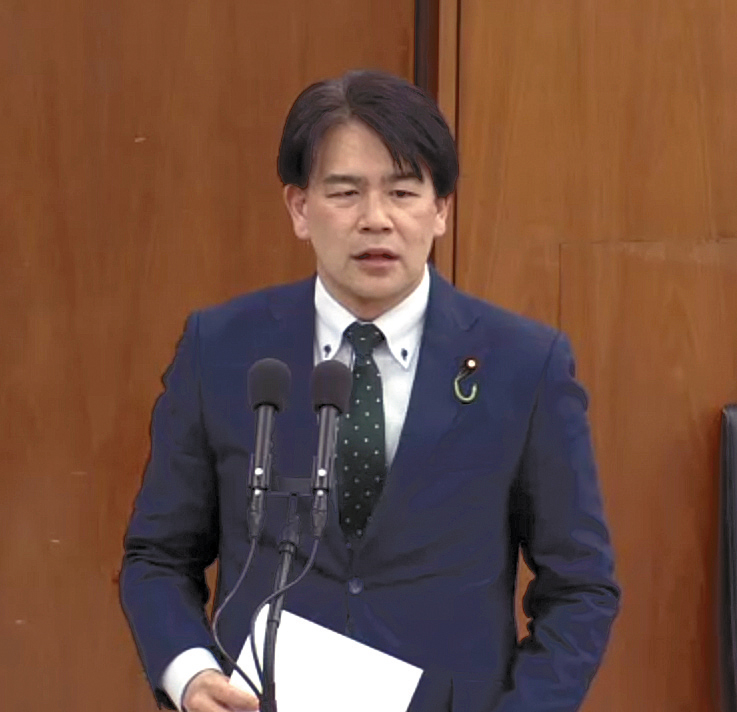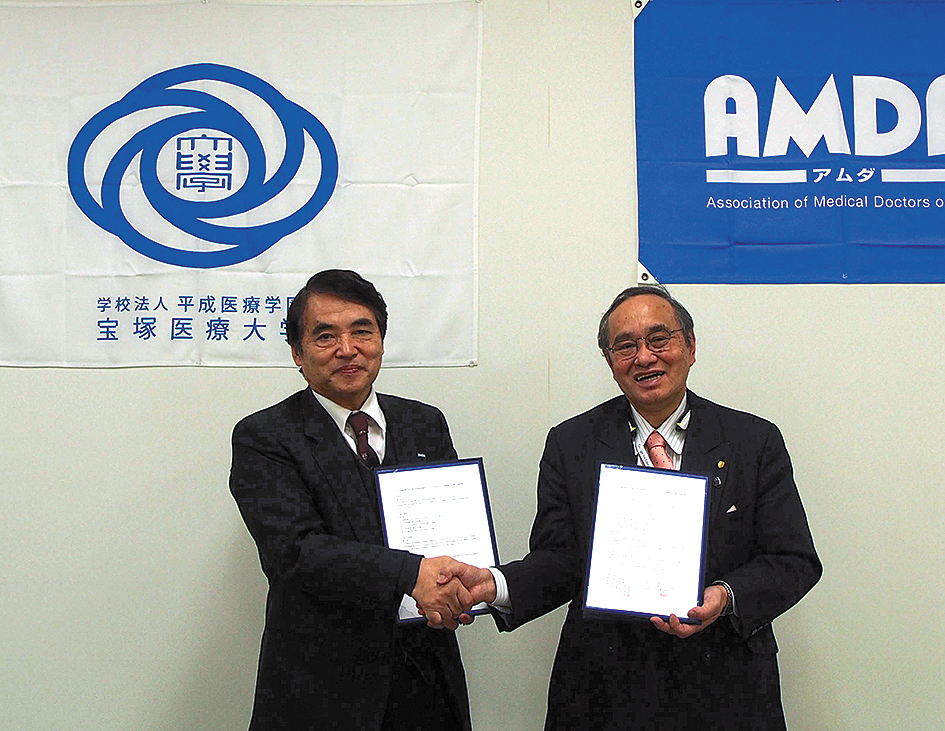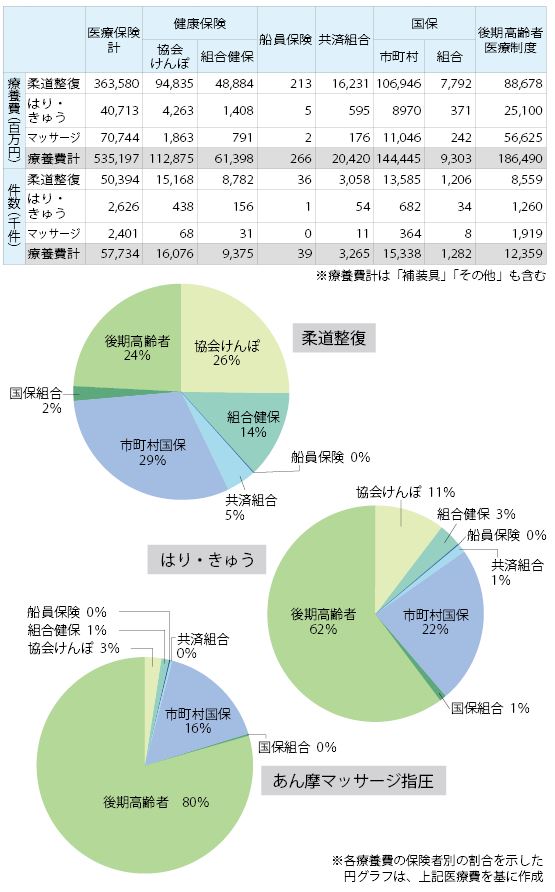連載『食養生の物語』72 茶は養生の仙薬
2019.05.25
「夏も近づく八十八夜」と唄われる茶摘みの季節。立春から八十八日目、ゴールデンウイーク頃に茂ってきた茶葉を摘み取ったものが、柔らかく甘味があって上質な「一番茶」。期間とともに出てくる新たな芽を摘み取る度に、二番茶・三番茶と、だんだんと品質は下がるとされています。特に高級とされる「玉露」は、一番茶を収穫する前に覆い、一定期間日光を遮断してから摘み取ります。日を遮ると、アミノ酸の一種のテアニンが豊富でうま味の強いお茶になるのです。日光を遮断せず、光合成が進めば、渋み成分であるカテキンが増加していき、スッキリとした味わいの「煎茶」として出回ります。収穫時期が夏から秋へと遅くまで成長した茶葉から製茶されるものは「晩茶」「番茶」と呼ぶようになっていったようです。摘まれた茶葉は、蒸した後、揉んで針の様な形に整えて乾燥させます。その後に焙煎したものが「ほうじ茶(焙じ茶)」。元は一部の地域で「ほうじ茶」を「番茶」と呼んでいたのが広まっていき、最近では「番茶」と「焙じ茶」は同一視されることが多いようです。食養生では「三年番茶」といって、収穫時期を遅らせ秋以降まで育成した茎を刈り取り、ゆっくりと時間をかけて焙じた後、倉庫で熟成させたお茶を飲用することを勧めています。足掛け三年にわたる時間と丁寧な製法とで独特の甘みと味わいがあり、体を冷やさないお茶でもあります。
紅茶や烏龍茶も緑茶と同じツバキ科のチャノキ(学名カメリアシネンシス)から作られ、違いは発酵の度合いです。茶葉には酵素があり、手を加えなければ発酵は進んでいきます。最も発酵を促進させるのが紅茶。茶葉を揉み込んでから十分に発酵させ、乾燥させたものです。インドやスリランカといった、気温が高く発酵を促しやすい国が産地なのも納得です。烏龍茶はこの酵素の働きを途中で止めた半発酵状態のもの。竹などでできた特有の筒状の入れ物に茶葉を入れて回転させ葉に傷をつけて発酵を促します。発酵の度合いをみて、炒って酵素の働きを止め、製茶します。その土地の料理に合うよう、それぞれの食文化と結びついてきた歴史があるのですね。
茶の渋み成分カテキンは、1980年代後半から、殺菌、抗ウイルス、抗酸化、血圧上昇抑制、血中コレステロール調節、血糖値調節、免疫増強など多くの作用が確認されてきました。病原性大腸菌O-157を通常飲まれる濃度の緑茶エキスに加えたら3時間後には千分の1に減少、5時間後には完全に死滅したとの報告もあります。カテキンだけに「勝て菌」とも言えそうです。近年では「体脂肪が気になる方に」という茶カテキンを有効成分とした特定保健用食品まで販売されています。茶を日本に広めた鎌倉時代の禅僧・栄西禅師は『喫茶養生記』で、「茶は養生の仙薬なり」と著しています。ここまで健康に良いと評価されることを8百年も前に見抜いていたのでしょうか。
【連載執筆者】
西下圭一(にしした・けいいち)
圭鍼灸院(兵庫県明石市)院長
鍼灸師
半世紀以上マクロビオティックの普及を続ける正食協会で自然医術講座の講師を務める。