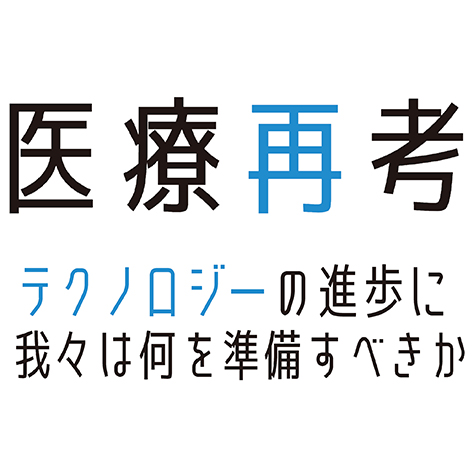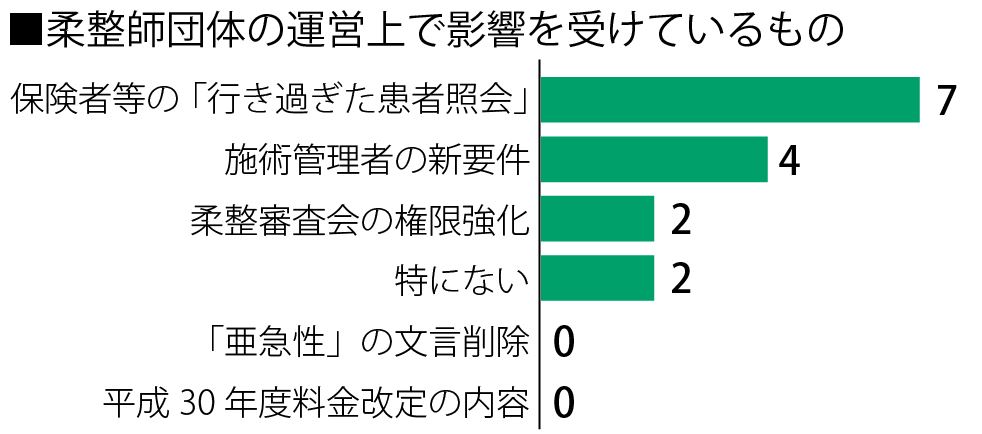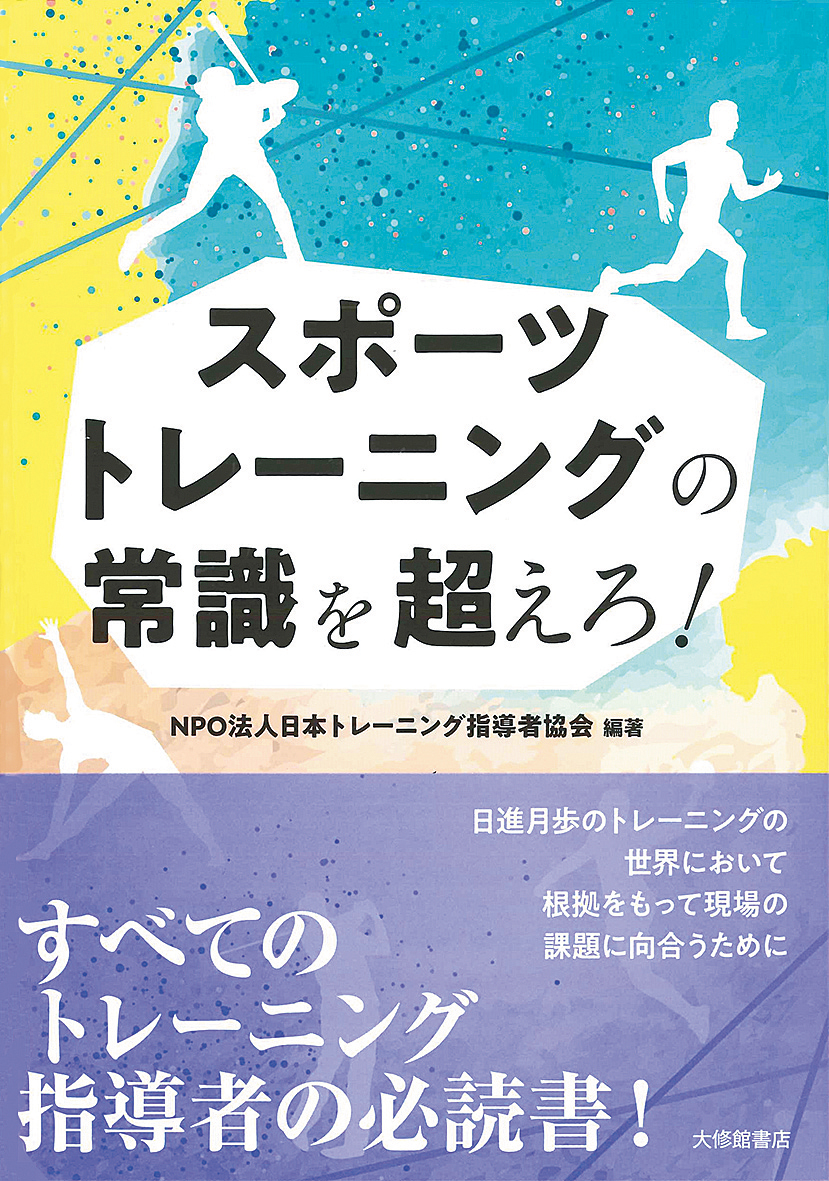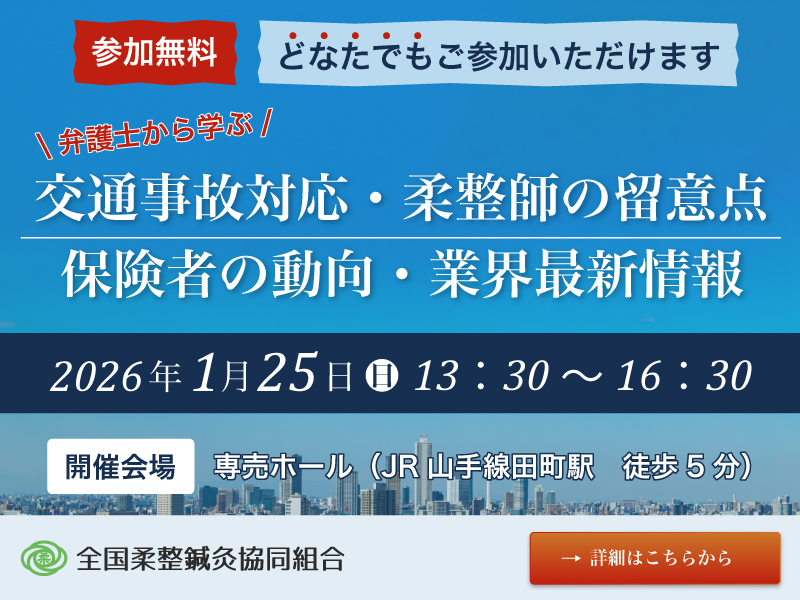連載『医療再考』4 情報を制するものが医療を制する ~情報を提供するか、提供されるか~
2019.06.10
世の中にあふれる情報は玉石混交です。これからの時代は様々な情報を正しく把握・分析し、活用する能力が求められます。これは情報という一つの財産を中心とした「コミュニティー」とも言え、情報を提供する側とされる側の2者で築き上げる世界です。
情報が一つの財産であることは、世界的成長を続け、それぞれが独自のコミュニティー(経済圏)を提供しているGAFA(Google Apple Facebook Amazon)を見ても明らかです。これからは何らかの情報でつながったコミュニティーが主流になる時代です。しかし、情報はやみくもに集めればいいというわけではなく、何に活用するのかという目的意識を持った上で魅力的な情報を集めなければ有益なものにはなりません。また、情報は正しくなければ意味はなく、正しさを担保するためにはたくさんの情報を集めること、いわゆるビッグデータ化が必要なのです。このようにどのような情報を収集するかというデザインをプラットフォームと呼び、プラットフォームの設計こそが情報コミュニティーの設計です。
現在、この情報コミュニティーで注目されている技術が、IoT(Internet of Things)です。IoTとは、コンピュータなどの情報・通信機器だけではなく、世の中に存在する様々な物体(モノ)に通信機能を持たせ、インターネットに接続・相互通信することで、自動認識や自動制御、さらには遠隔計測などを行う技術のことを指します。具体的には、自動車の位置情報をリアルタイムで集約することで最適な道を選ぶ技術や、電力メーターから得られた情報を基に、故障箇所を早期に発見したり無駄な電力を抑制したりすることで最適な環境をアシストしてくれる技術などです。このようにモノがインターネットを介して情報をもたらし、その情報を基に生活を便利にするという「モノによるコミュニティー」により、我々の生活は格段に便利になっているのです。5Gと呼ばれる新たな通信技術が普及すれば、大量の情報を素早くやり取りすることができるようになり、さらに便利な環境を実現してくれるようになります。
この次に起こるのはIoH(Internet of Human)でしょう。ウエアラブルデバイスから得られた生体情報を基に人の行動に介入することで健康を保つ、具体的には「運動不足であることが分かれば自家用車が動かない」といった技術が、これからの健康経営には重要になると思われます。その際、我々鍼灸師は情報を提供する側なのか、提供される側なのかで、コミュニティーの中心にいるのか、一部になるのかが決まります。これが健康経営におけるプラットフォームです。しかし、我々自身が何らかの情報をコミュニティーに提供しなければプラットフォームに接続することはできません。また、何を提供するかで役割や立場も異なってきます。我々が持つ情報の中で、一体何が医療や健康に役立つ情報なのか。そして、その情報は正しいデータで、きちんと蓄積されているのかが私たちの未来を決めることになるでしょう。
【連載執筆者】
伊藤和憲(いとう・かずのり)
明治国際医療大学鍼灸学部長
鍼灸師
2002年に明治鍼灸大学大学院博士課程を修了後、同大学鍼灸学部で准教授などのほか、大阪大学医学部生体機能補完医学講座特任助手、University of Toronto,Research Fellowを経て現職。専門領域は筋骨格系の痛みに対する鍼灸治療で、「痛みの専門家」として知られ、多くの論文を発表する一方、近年は予防中心の新たな医療体系の構築を目指し活動を続けている。